

地方創生現場を徹底取材「IT風土記」
【佐賀発】美味しい海苔をいつまでも。産官学連携×ITで次世代型海苔養殖に挑む
有明海での海苔養殖が盛んな佐賀県は海苔の生産枚数、販売額ともに日本一を誇る。多くの河川が流れ込み、日本で最も大きい干満差のある有明海独特の生育環境がおいしい海苔を育むという。海苔のさらなる品質向上と収量アップにつなげようと、昨年3月、産官学が連携し、海苔養殖に最新のAI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)技術を活用するプロジェクトが動き出した。AIやIoTが漁業をどう変えていくのだろうか。

SUMMARY サマリー
有明海を舞う固定翼型ドローン
深いところでも水深20メートルの遠浅の海が広がる有明海。大小100以上の河川が流入し、陸上からリンや窒素などの豊富な栄養素を注ぎ込む。河川の水は有明海の表層を真水にするほど塩分濃度が低くなることもある。また、大潮の時の干満差は最大7メートル近くにも達するという。「口どけがよく、うまみ広がる」という佐賀・有明海の海苔は、そんな有明海の稀有な環境が生み出したものだ。
14年連続で海苔生産全国一を守り続けている佐賀県では昨年3月、佐賀市に本店を持つAIやIoT開発を行うベンチャー大手、オプティムを中心に佐賀県や海苔養殖漁業者で組織する佐賀県有明海漁業協同組合、佐賀大学、農林中央金庫、NTTドコモの産官学6者でAIやIoTなどの最新技術の活用を目指す協定が締結された。海苔養殖漁場の海面を撮影できるドローンや、海面の水温や比重(塩分濃度)を測定するICTブイを活用し、収集された情報をIoTプラットフォーム「OPTiM Cloud IoT OS」上でAIを用いて解析して、海苔の生育に悪影響を与える病害や赤潮の発生を早期に検知しようという取り組みだ。

「海苔の養殖漁場はエリアが広く、管理が大変なんです。養殖する区画まで何キロも船を進めなくてはならない漁業者もいます。ドローンを飛ばして区画の状況を確認ができれば負担の軽減につながります。空撮画像から病害や赤潮の発生を早期に発見できれば、事前に収穫するなど早期に対応をとることで被害を最小限に食い止めることもできます。そうしたことができないか。可能性を探ろうというものです」。オプティム・インダストリー事業本部の速水一仁サブマネージャーは6者間連携協定のねらいをこう説明した。

病害、赤潮の早期発見を目指す
海苔の養殖では、アカグサレ病などの深刻な病気が発生する懸念がある。アカグサレ病は、海苔に菌が付着して海苔の葉体に穴が開いたり、色が赤くなったりして著しく品質低下を招いてしまう病気だ。感染力が強く、一度発生するとあっという間に周辺に拡大し、海苔の収穫に大打撃を与えてしまう。2015年には生産量が半分近くまで落ち込むほどの被害があったという。赤潮も海苔に必要な養分や酸素を奪い、色落ちなどの品質低下につながるが、現状では、漁業者による定期的な見回りや県の海苔養殖の研究機関である佐賀県有明水産振興センターによる監視によって対応している状況だ。
しかし、有明海の佐賀県沖には、実に約30万枚の養殖用の海苔網が設置されている。1枚の海苔網は幅1.5メートル、長さ18メートル。漁場の広さは単純計算でも山手線内側の面積の1.3倍に当たる9000ヘクタールにも上り、漁場の見回りは漁業者たちの大きな負担になっていた。

オプティムはもともと2015年から佐賀県、佐賀大学と連携し、ドローンを活用した次世代型農業の実証実験に取り組んできた。ドローンを用いて撮影を行った画像を、「OPTiM Cloud IoT OS」に蓄積し、「OPTiM Cloud IoT OS」上でAIを用いて解析することで、害虫被害を受けている農地を検知し、害虫被害がある場所だけにピンポイントで農薬を散布することができる新たな減農薬農法を確立。この農法による生産物は農家の負担を減らしつつコストを削減し、付加価値を向上することで販売価格がブランド野菜と同等に設定できるなどの効果を上げている。こうした取り組みに着目した農林中央金庫が漁業での応用を提案し、新たなチャレンジがスタートした。
今回の実証実験に向けて固定翼型のドローンを開発。ドローンといえば、3つ以上のローター(プロペラ)があるマルチコプター型が主流だが、「広範囲で長時間の飛行を可能にするため固定翼型にした」(オプティム・速水サブマネージャー)という。マルチコプター型のドローンは30分程度だが、固定翼にしたことで、1時間以上の航続が可能だという。ドローンにはNTTドコモが提供するセルラー通信機能を搭載し、飛行中のドローンへのリアルタイムの通信や固定翼ドローンの実用性の検証が行われている。
ドローンを活用した今回の実証実験では、アカグサレ病が発生しやすい気候条件など佐賀県有明水産振興センターが長年積み重ねてきた知見やノウハウを提供。さらに佐賀大学は今回の実験を通じた新たな技術開発にも取り組む。また、佐賀県有明海漁業協同組合は、実験フィールドの提供や漁業者への情報提供などのサポートを行うという。
さらにNTTドコモは今回の実証実験の大きなカギを握る重要なツールを提供している。
それが「ICTブイ」だ。海水の温度と比重(塩分濃度)を測定するセンサーと通信機能を備えたもので、海上に浮かべることで海水のデータを定期的に測定。携帯電話回線を通じて、その情報を送信する。測定された海水の温度や比重の情報はドコモのクラウドサーバーに蓄積され、漁業者のスマートフォンや携帯電話を通じて情報を確認できる。将来的には、それらの情報はドコモのクラウドサーバーを経由して、オプティムが提供するIoTプラットフォーム「OPTiM Cloud IoT OS」上に蓄積され、ドローンが収集した画像と組み合わせてAIを用いて解析し、クラウドサーバーを経由して、漁業者のスマートフォンや携帯電話を通じて情報を確認できるようになる。
「漁業者の問題解決にわれわれのICT技術が応用できるなら意義は大きい」(NTTドコモ九州支社法人営業部の淵上豊崇・ICTビジネスデザイン担当課長)と判断し、協定に加わったという。
広がる期待
しかし、農地での病虫害の検知とは異なり、海での病害検知には難しい課題も立ちはだかる。「アカグサレ病の場合、目に見えるくらいになるともう感染が広がっており、手遅れになっているケースが多い」と佐賀県有明水産振興センターの荒巻裕副所長は語る。センターでは、養殖の最盛期に、船を出して漁場を定期的にパトロールし、顕微鏡を使って採取した海苔にアカグサレ病の原因菌がないかチェックし、発生が懸念される時は漁業者に早期に対応するよう注意を喚起してきた。上空からの定期的な監視という従来の漁業にはなかった新しい取り組みの中で、どんな成果が表れるのかは今後の取り組み次第ともいえる。

一方で、ドローンやICTブイの活用によって、今まで目が行き届かなかった海水面の細やかな変化を察知し、品質の高い海苔の生産につなげられる可能性が秘められている。佐賀大学農学部の田中宗浩教授は「赤潮がどういったプロセスで発生するのか未解明なことが多い。定期的なドローンでの海水面の調査というのはあまり例がなく、解明につながるヒントが得られるかもしれません」と話していた。

また、佐賀県有明海漁業協同組合の徳永重昭代表理事組合長と江頭忠則専務理事はこんな期待を寄せる。
「海苔は手をかければ、かけるほど品質もよくなる。漁業者の中には毎日のように漁場に行って水温や比重をチェックしたり、海苔網をメンテナンスしたりする人もいる。労力もコストもかかる。ドローンで漁場を監視できれば、船を出す回数が減り、効率的に作業ができるようになる。最先端の技術を活用することで、若い人たちにも魅力的な仕事と思われるようになってほしい」。昭和46年に2700人いた海苔養殖の漁業者は現在820人にまで減少している。農林水産業全体にいえることだが、御多分に漏れず、後継者不足は深刻だ。それだけにIoTの活用が新たな活路になることを願っている。

オプティムの速水サブマネージャーは今回の取り組みについて「できれば2、3年かけて具体的な成果につなげていきたい」と語る。その一方で、2015年にスタートした農業分野でのIoTの活用は2年足らずで実用化にこぎつけている。農業分野の実証実験にも参画していた佐賀大学の田中教授は「2年といわず、早い段階で成果が出ることを期待している」と話す。
現在、ドローンの飛行は航空法で、「操縦者の『目の届く』範囲内」に限定され、目の届かない範囲(目視外飛行)まで飛行させるには国土交通大臣の事前承認が求められる。現状では広い有明海の沖合までドローンを飛ばすには船を出して飛行の様子を見届けるなどの対応が必要だ。
また、固定翼型ドローンへの搭載を実験中のセルラー通信機能は「目視外飛行」には欠かせないツールだ。上空におけるドローンでのセルラー通信利用は規制の対象になっている。上空でのドローンにおけるセルラー通信利用については、総務省及び各通信会社が2016年度受信環境調査を実施した。その中で総務省は引き続き課題解決にむけた検証を行うことを考えている。近い将来、上空におけるドローンでのセルラー通信利用も可能となるだろう。海苔養殖の実証実験はまさにスタートラインに立ったばかりだが、IoTを活用した次世代型の水産業が当たり前になる日は、そう遠くない未来なのかもしれない。

(産経デジタル SankeiBiz編集部)
NECおススメITソリューション|佐賀篇
海苔は、日本でずいぶん昔から食べられてきました。
しかし、江戸時代に入って養殖が行われるまでは、気軽に食べられる人は限られていたそうです。
天然海苔は貴重で、大変に人手がかかるので、とても高価だったのですね。
みなさんは、「海苔」ときいてどのような食べ方を思い浮かべますか?
オフィスできいてみたら、その答えに人それぞれの暮らしがみえて、これが実におもしろいんです。
おにぎり、海苔巻き、ざる蕎麦と答える男子は、コンビニ通いかな。
ごはんのお供の佃煮、お寿司の軍艦巻き、おもちと一緒に磯部巻き。
子どものキャラ弁づくりが大変で、という話をはじめる人も。
今や、日本人みんなの毎日の暮らしと切っても切れない存在です。
今回は、海苔が工場から出荷される時に、お役に立ちそうな「物体識別システム」はいかがでしょう。
これはNECが独自に開発した画像認識アルゴリズムにより、高速・高精度に画像解析を行う物体認識エンジンを活用し、予め対象物の画像の特徴を登録・学習しておき、撮影画像の特徴と比較することにより物品を識別します。
このエンジンを用いることで、商品パッケージ別の物品の種類や個数を識別することができ、検品・梱包・出荷作業の効率化を図ったり、陳列商品数・欠品数の把握・管理や棚卸しなどでも効率を高めることが可能です。
また、農作物など個体差がある物品でもリアルタイムに種類や個数を識別することもできます。
■画像認識による種類・個数の物品選別システムの導入効果
人手で行う対象物の識別を自動化し、生産・出荷プロセスの最適化・効率化を実現します。
- 作業効率の向上
- 判断基準の定量化
- リアルタイムに状況把握
- 低コスト・省スペースで生産ライン拡張を実現
私が思い浮かべたメニューは、アツアツの海苔茶漬けでした。寒い日は特においしいですよね。
冬の海から、美味しい海の恵みを届けてくださる作り手さんたちに感謝です。
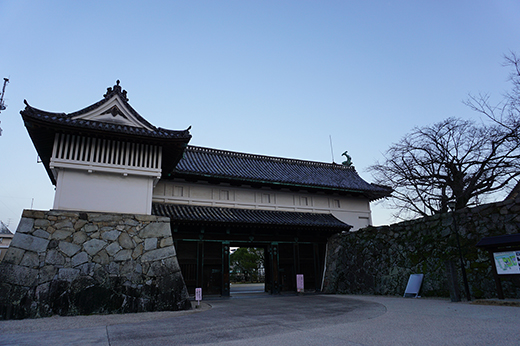
(By NEC IT風土記編纂室 R)

SankeiBiz 産経デジタル SankeiBiz編集部
(株)産経デジタルが運営するSankeiBiz(サンケイビズ)は、経済紙「フジサンケイビジネスアイ」をはじめ、産経新聞グループが持つ経済分野の取材網を融合させた総合経済情報サイト。さまざまなビジネスシーンを刺激するニュースが、即時無料で手に入るサイトです。