

自宅にいながら病院のような医療サービスが受けられる!
ICTが実現する未来の医療サービス

湘南慶育病院 院長 松本 純夫 氏
患者や地域住民が健康で生き生きと暮らせること、そのために医療サービスの質を向上させること──。そのようなビジョンを実現させるために積極的にICT活用を進めているのが、昨年11月に開院した湘南慶育病院だ。医療分野におけるICT活用の第一人者でもある同病院の松本純夫院長に、わが国が目指すべき未来の医療の形と現在の取り組みについて聞いた。
ICTの恩恵を医療サービスにも
「昨今、ICTの利便性は社会のあらゆる領域に広がっています。医療の世界もその利便性を享受すべきです。医療では、ICTを活用して医療機関と患者の新しいコミュニケーションが実現できる。そう私は考えています」
そう語るのは、これからの日本を支える「次世代型医療」の実現を目指す湘南慶育病院の松本院長だ。同院は、2017年11月に、環境共生型都市の形成を目指して藤沢市が策定したプラン「健康と文化の森構想」の中核病院として、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)と連携して開設された。
SFCは同病院開院にあたって、「湘南慶育病院連携・ラボ」という研究施設を新設した。代表を務めるのは、日本のインターネット研究の第一人者である環境情報学部の村井純教授だ。一方の湘南慶育病院内にもSFCとの共同研究施設が設置されている。ICTをベースとした大学側のシーズと、医療現場や患者が抱えるニーズ。その二つを組み合わせて新たな医療ソリューションを創出していくことがこのコラボレーションの狙いである。民間病院が大学とここまで緊密な連携体制を構築するのは、日本初のことだという。
自宅でも病院と同等の医療サービスを
湘南慶育病院は在宅時でも患者を見守る「Hospital in the home」コンセプトの実現に向けて、ICTを活用して、遠隔診療を含む新たな地域包括ケアサービスの研究開発及び導入を目指している。同病院長であり、厚生労働省のデータヘルス改革推進本部顧問、内閣官房の次世代ICT基盤協議会委員や官民データ活用推進基本計画実行委員会委員などの要職にある松本純夫氏は、こう説明する。
「身体の調子が悪いと感じた人が、自宅から病院のホームページにアクセスし、症状を具体的に入力する。そうすると、すぐに病院に行くべきか、数日様子を見るべきかをアドバイスしてくれる。そんなシステムの実現を目指していきます」
患者にとって、病院に受診に行くのは楽なことではない。1時間をかけて病院に着き、受付をしてさらに1時間待つ。診察が終わったら、処方箋が出るのを数十分待ち、薬局でさらに30分待つ。結果、ほぼ半日がつぶれてしまう──。誰もが体験しているこのような患者の苦労を解消してくれるのが遠隔診療の仕組みであると松本氏は言う。
「自宅でアドバイスを聞いて、受診の必要なしと患者さんが自ら判断し、病院に行かずにしばらく安静にすることで回復する。今後そんなケースが想定されます。受診する場合も、自宅で症状を入力してから病院に行くことで待ち時間を短くすることができるでしょう。小さなお子さんの不調時に病院に行くべきかどうかを判断する際にも、この仕組みは大いに役立つはずです。さらに、家庭用の心電計や血圧計、高解像度の映像システム、画像認識ソフト、音声認識ソフトなどを組み合わせれば、自宅にいながら医師の診察を受けることも可能になるでしょう。」
自宅にいながら病院と同等の医療サービスを受ける──。そのコンセプトを松本氏は「Hospital in the Home」と呼ぶ。2018年度診療報酬改定では、「オンライン診療料・オンライン医学管理料の新設」が予定されており、法律の見直しも進んでいる。人々の豊かな生活を支える「Hospital in the Home」の実現に向けて、様々な関係機関と相談・協力しながら、取り組みを進めていますと松本氏は言う。
同病院が研究開発を進めているこの遠隔診療の仕組みには、NECが開発したクラウド型問診サービスが使われる予定だ。
「AIをはじめとする先端技術を活用した同種のシステムがいくつかある中でNECを選んだのは、様子見をすべきかすぐに病院に行くべきかのリコメンドが技術的に可能であるエンジンを搭載しているからです。このエンジンは将来的に深層学習によってどんどん進化し、精度を上げていくと聞いています」
迅速かつ質の高い診察を実現する
現在、NECのクラウド型問診サービスは、病院受付における問診情報の入力と医師の診療記事作成支援にすでに使われている。来院した初診患者にタブレット端末を渡し、診察前に症状やアレルギー、既往歴などの問診情報を入力してもらう。そのデータをもとに、医師は電子カルテ端末にて患者の健康状態を詳細に把握して、診察を行う。結果、迅速かつ質の高い診察が実現する──。それが現在の活用法である。
「患者さんは、待ち時間を活用して、症状や不安なことを事前にしっかりと伝えることができ安心です。加えて、医師としては、患者が診察室に入る前に患者さんの症状を詳細に把握でき、すぐに会話や診察が始められることがこのシステムの大きなメリットだと思います。スマートフォンやタブレット端末に不慣れな患者さんには、看護師が傍に寄り添い入力のお手伝いをしています。結果として、今まで以上に患者さんとの親密な関係を築けるようになりました。」
そう話すのは、看護部長の片岡亮子氏だ。
将来的には、クラウド型問診サービスの適用範囲を院外まで広げ、遠隔診療を実現、患者に大きなメリットをもたらすことを目指している。

医師や看護師の「働き方改革」に向けて
遠隔診療の仕組みは、患者だけではなく、医療現場にもメリットをもたらすことが期待されている。現在、医療現場では医師や看護師の働き方の見直しが議論されている。受診件数が適正化され、かつインターネットを通じての診療が可能になれば、医師や看護師の労働時間を減らすことができる。さらに、社会問題となりつつある医療費の最適化も実現するだろう。
電子カルテに医師がどこからでもアクセスできる仕組みや、医療専用SNSを使って医師と患者とその家族が日常的に情報共有できる仕組み。それらのソリューションとクラウド型問診サービスを組み合わせることによって、患者に対する医療サービスの質を上げながら、医療現場の働き方を改革し、医療費を適正化すること──。それが、松本院長が掲げるビジョンだ。湘南慶育病院では、患者の同意を得て、遠隔診療の実証実験の取り組みを始める。
さまざまな医療課題を解決するソリューション
遠隔診療には、さらに広範な医療課題を解決できる可能性があると松本氏は話す。例えば、松本氏が以前院長を務めたこともある国立病院機構東京医療センターでは、救命救急センターにおける「ノンエマージェンシー」、つまり緊急性のない症状の患者の対応が課題になっているという。
「医師の数には限りがあるので、患者さんの数が増えれば増えるほど、早急な治療を要する重症患者への対応が手薄になってしまいます。たとえば、緊急でない症状の場合、遠隔診療システムから“すぐに病院に行かなくても大丈夫”といったアドバイスを受けられるようになれば、本当に緊急の患者さんの治療に集中することができるでしょう」
また、専門医の地域格差の解消にもこの仕組みが役立つ可能性がある。
「日本の地方には、専門医の数が少ないところがたくさんあります。例えば、クラウド型問診サービスと電子カルテ、カメラ映像を組み合わせれば、自宅にいながら都市部の大病院にいる医師の診察を受けることが可能になります。このシステムはまた、海外に輸出することもできるでしょう。世界には医師が足りないために十分な医療サービスを提供できない国がたくさんあります。」
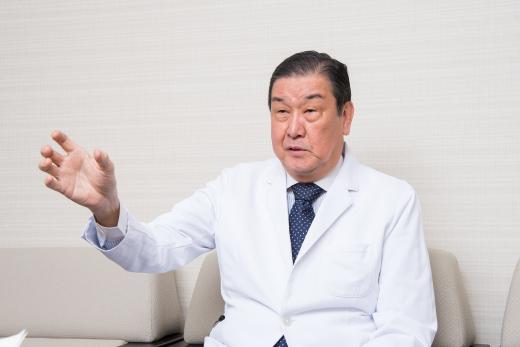
この病院で取り組んでいるようなICTと医療を組み合わせは、世界を対象にした社会貢献の可能性を秘めている──。松本氏はそう熱く語る。
大学との緊密な連携を進めながら、厚生労働省、総務省、内閣府などとも歩調を合わせてICT活用の取り組みを推進し、「医療×ICT」の最先端のモデルケースを世の中に提示していくこと、そして、患者や地域の人々が健康寿命を延ばし、健康で豊かに暮らしていける社会を実現することが、湘南慶育病院と松本院長のこれからのビジョンだ。
「NECは社会課題解決への貢献に真摯に取り組んでおり、高く評価しています。力強いパートナーとして私たちの取り組みを支えてほしい。そして日本の医療の発展に貢献してほしい。そう期待しています」
