産学の垣根を越えた共創で新しい防災システムをつくる!
──AIによる水害対策の実証実験
2017年11月28日
AIを防災分野で活用し、自治体の水害対策を有効に支援するシステムをつくることはできるか──。そんなテーマを掲げて茨城大学とNECがタッグを組んだ。防災、土木、映像、通信、そしてAIによる機械学習。産学の垣根を越え、さまざまな専門分野を結びつけて行われた実証実験から見えてきたものとは?
大学と民間企業の技術力を融合させる
狭いエリアに短時間で大量の雨が降る、いわゆる集中豪雨が全国的に増えている。豪雨による河川氾濫の被害を最小限に食い止めるには、増水の推移などを的確に見極めて、迅速な避難指示を出せる仕組みをつくらなければならない。では、どうすればそのような仕組みを実現させられるのだろうか──。
そのひとつの答えを出すための取り組みを茨城大学とNECが始めたのは、2017年6月だった。取り組みのきっかけをつくった茨城大学の齋藤修特命教授は話す。

ICTグローカル教育研究センター特命教授
齋藤 修氏
「茨城大学は、現学長が気候変動研究の第一人者でもあり、以前から環境分野の研究に力を入れてきました。防災セキュリティ教育研究センターという学内の機関で防災の研究などをしてきた私は、民間企業とともに防災システムの共同研究ができないかと以前から考えていたのですが、たまたま茨城県の新しい防災システムをNECが提供するという話を聞いて、この機会にぜひ一緒に研究ができないかと私からNECにアプローチしたのです。今年の3月のことでした」

NECにとってもそれは非常にありがたい申し出だった。そう話すのは、NEC未来都市づくり推進本部の小林真人だ。
「大学には、環境、土木、情報工学などに関する知識と技術があります。一方、NECには監視用のハードウェアだけでなく、通信やAIの技術があります。それらを組み合わせて防災の仕組みをつくるのはたいへん意義深い取り組みであり、社会課題を解決する新しいソリューションを生み出すチャンスであると思いました」

社会公共ビジネスユニット未来都市づくり推進本部
小林真人
そうして、実証実験に向けた体制づくりが早々にスタートしたのである。
河川氾濫の危険レベルをAIが判断する
カメラで河川の様子を24時間撮影し、その映像をネットワークによって大学のセンターに送り、NECのAI技術群「NEC the WISE」のひとつ「RAPID機械学習」によって分析する──。その仕組みをつくることが実験の目的となった。土木工学や測量の専門家であり、齋藤氏とともに大学側で実験を中心で進めた桑原祐史教授はこう説明する。

広域水圏環境科学教育研究センター教授
桑原 祐史氏
「実験は、計測、解析、検証の3つのステップで進められることになりました。まず、以前から私たちが調査をしてきた水戸市を流れる沢渡川の3カ所にカメラを設置して、ネットワークで映像を取得する。それが計測のステップです。次のステップとして、その映像をNECのRAPID機械学習で解析する。そしてその結果を検証し、実用的なモデルをつくっていくのが3つめのステップです」
この実験で、画像解析の判別対象としたのは「水位」と「水色」だった。水位は低い順にレベル1からレベル3まで、水色は「無色」「濁色」「土砂色」の3段階をAIが判別し、氾濫の危険レベルを判断するというモデルだ。カメラと通信環境を整備して実験がいよいよ始まったのは、7月に入ってからだった。

画像を拡大する
いかにシステムのコストを下げることができるか
この実験で特筆すべきは、結果を社会に迅速に還元していくためには「コスト」を重視する必要があるという認識が共有されていた点である。
「優れたシステムをつくることができても、コストが高すぎれば、自治体などへの導入のハードルになります。いかにコストを抑えて必要な要件を満たすことができるか。それが実験の狙いのひとつでした」
齋藤氏はそう話す。高性能カメラを設置し、高解像度の映像データを取得すれば、分析の精度は高まるかもしれないが、ハードウェアと通信の費用がかさんで実用性はむしろ下がる。十分な分析精度が確保できるぎりぎりのレベルまで画像の解像度を落とし、コストを下げられれば、設置するカメラの台数を増やすことも可能になる。そう齋藤氏らは考えたという。
この実験が続発する災害による被害を防ぐことを目的としている以上、実験の成果は、できるだけ早い段階で、できるだけ広い範囲に利用されることが望ましい。そのためには実用可能性がはじめから考慮されなければならない。それがこの実験のひとつのコンセプトだった。
「ソリューションをつくる際には、それを誰がどう買ってくれるのかを合わせて考えなければなりません。国立大学といえども、“営業”の視点が求められる時代なのです」(齋藤氏)
災害の危険性を数値化する画期的なモデル
8月までのおよそ2カ月間にわたった実験の結果は、極めて有意義なものだった。AIの学習モデルをつくり、画像判別の精度を検証したところ、かなりの高精度での判定が可能であることがわかった。つまり、ステップの2まではほぼ問題なく進んだということである。実験は現在、ステップ3の検証の段階にある。

画像を拡大する
「今回の実験では、水位と水色に分析対象を絞りましたが、この対象をどう増やしていくのが有効か、水位計データなどほかの指標とどう組み合わせていくかといったことが検討されています。また、AIの機械学習の精度を上げるには、多くのデータを覚え込ませる必要があるのですが、増水時の画像データがまだまだ少ないという課題もあります。それらをクリアするための取り組みを継続的に続けていきたいと考えています」(桑原氏)
その先のビジョンも見えてきている。齋藤氏が熱く語る。
「今回の共同実験の中で、防災に活用できるさまざまな技術をNECが持っていることがわかりました。それらを活用すれば、自然現象を数式化してデジタル処理するというこれまで世界のどの国にもなかった防災システムをつくることができるかもしれません。そのいわば“近未来型制御システム”は、あらゆる防災分野に応用できるはずです」
AIをはじめとする先端技術によって災害の危険性が数値化されれば、それは客観的指標となり、自治体の判断を手助けすることになる。結果、迅速かつ的確な避難指示が実現し、人々の命を守ることができる。つまり、最先端の防災システムは、まさに住民一人一人のためのシステムとなるということだ。
桑原氏はまた、この実証実験に大学の学生が参加できた点にも大きな意義があると話す。
「新しい仕組みをつくるためには、技術だけではなく人材の力が必要です。NECが次世代の育成につながる共同研究の体制をつくってくださったことに非常に感謝しています」
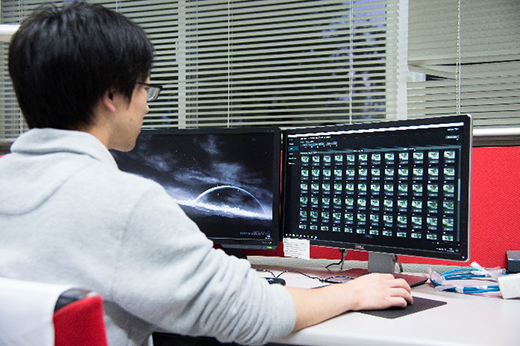
異なったものの結合で新しい活路が見えてくる
この産学共同による共創の取り組みには今後もおおいに発展の可能性があると、齋藤氏と桑原氏は口を揃える。まず、「防災」という研究テーマで学内のほかの研究室、さらには他大学の研究機関と結びつくことができる。また、このシステムの直接的なユーザーである「官」、つまり自治体との緊密な連携も今後は必要になっていくだろう。
そればかりではない。AIにより危険度判定の精度を上げていくには、画像データだけではなく、気象情報をはじめとするさまざまな外部データのインプットも必要となる。
「昔から災害の多い地域には、ちょっとした兆候から災害を予兆する知見が歴史的に蓄積されています。そういったいわば、“人々の知恵”などもデータとして活用しながら、モデルをつくっていくことができれば理想的だと思います」(桑原氏)
異なったものを結びつけることによって新しい活路が見えてくる──。それが実感できたことが、この実験の大きな成果であると齋藤氏は言う。社会の安全・安心を守るための垣根を越えた取り組みが、これからも続いていく。
