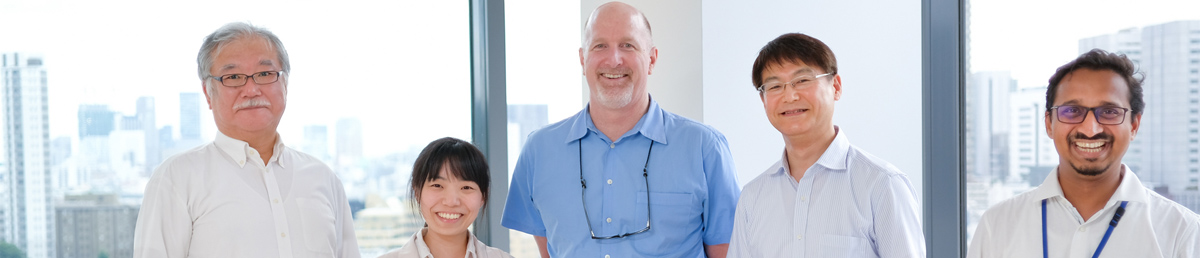
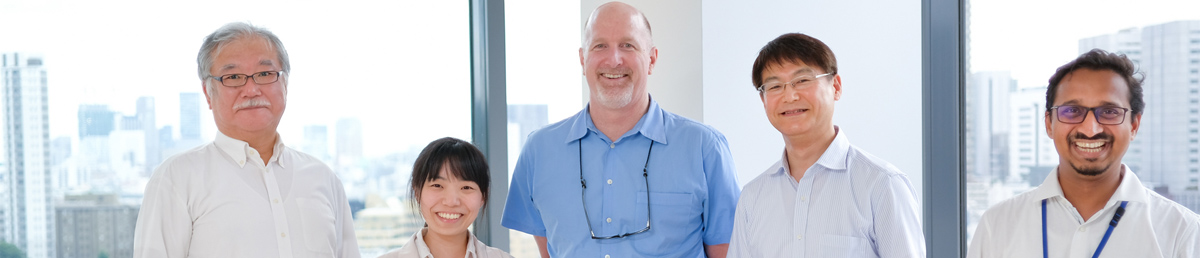
NECとGEがチャレンジする
共創によるサプライチェーン革新
SUMMARY サマリー
効果が大きかった、異文化からの刺激
Predixをインド、インドネシアの設置工事管理への導入を検討してから6カ月が経過した。福本は、これまで人に依存し、コントロールが難しかったプロセスの改善に役立てられると予感。PASOLINKでの成果を他事業へ横展開できる可能性も感じている。
「GEスタッフによるワークアウトがとても新鮮だったこともあり、現地スタッフに改革が受け入れられた。現場の意見も吸い上げられるようになりつつあり、NEC側スタッフのマインドセットが良い方向に変わった」(福本)
この変化に対してGEのマンダール氏は「GEが欧米的なアプローチを採ったことで、良い化学反応が起きた。多かれ少なかれ、企業には組織間のパワーバランスやしがらみがつきものだが、GEが第三者的な立場から議論をファシリテートしたことで突破できたと思う。GEは、デジタルツールの導入効果を最大化するためには、現在のプロセスをデジタル化するのではなく、時にはプロセスそのものを見直すことも必要だと考えている。一方、NEC側には、従来のやり方の中にも尊重すべき部分があるという声もあった。良い意味でのハレーションが起き、やがては双方のフュージョン(融合)によって、より理想的な形になるはずだ」と話す。
大嶽はこうした変化によって、NECのスタッフが以前よりも自立したと感じている。
「われわれが長く変えられなかったことに対して、GEは異文化の経験で、沢山の違和感を口にしてくれた。彼らには世界を変えてきた実績がある。最初は恐る恐る接していたNECのスタッフが、コミュニケーションを重ねるうちに変化していったので、私はこの機に異文化集団の力を大いに活用させてもらおうと考えた。しかしいつまでもGE頼みでは、真の改革を達成できない。『実際にやり遂げるのは自分たちだ』と気付いたNECの若いスタッフたちが、自らの改革を模索し始めた。今はそういう時点と言えるだろう」(大嶽)

現地ともTV会議でコミュニケーションをリアルタイムに取って議論を進めていった。
(写真提供:GEジャパン株式会社/GE Reports Japan)
真の"共創"には「経営に対する全員参加」の一体感が重要
大嶽は、デジタル・トランスフォーメーションのキーポイントとして、下記の3つをあげる。
- 事実を数値化して理解する
- 課題を共有して変化の行動を起こす
- 経営から現場までの各層の行動を評価する
従来の方法では、数値化できない事象は工場長以下のスタッフが現場の感覚でそれを捉え、処理してきた。
「しかし私のように、その上のレイヤーにいるとその感覚は共有できず、工場マネジメントに経営の立場からの示唆が与えられないし、踏み込んだ改革も難しくなる。IoT化により、データでこれを見えるようにして、経営層が工場のスタッフと同じ情報を持ち、改革のための議論ができるようになる」(大嶽)

(写真提供:GEジャパン株式会社/GE Reports Japan)
大嶽の目指す最終的なゴールは品質経営だという。一般的には品質の対立概念とされる納期・機能・コストなどをすべて包含した"クオリティ"を軸にしたマネジメントだ。そこに向かって今後、海外現地法人と事業部の一体感を醸成し、それぞれのチームがお客さまをハッピーにしている状況が、他のチームにも波及していかなければならない。
「海外の現場では、ビジネスユニットと現地法人が一体になり切れない状態があった。今後は横軸を担う私たちが積極的に関わり、両者をしっかり繋ぐチェンジ・マネジメントをして、最終的な成果が得られるまで責任を負い続けなければならない。最終ゴールまではまだまだ遠い」(大嶽)
福本は「GE for GEという考え方同様、NECもPredixを活用して自身を変革すると共に、その経験を活かしながら自分たちの顧客の変革も支援していくべきなのだろう。デジタル・トランスフォーメーションの実現に向けて、これからの顧客がたどる道のりをすでにNECが体験しているということは、なによりも大きなアドバンテージになるはずだ」と話す。