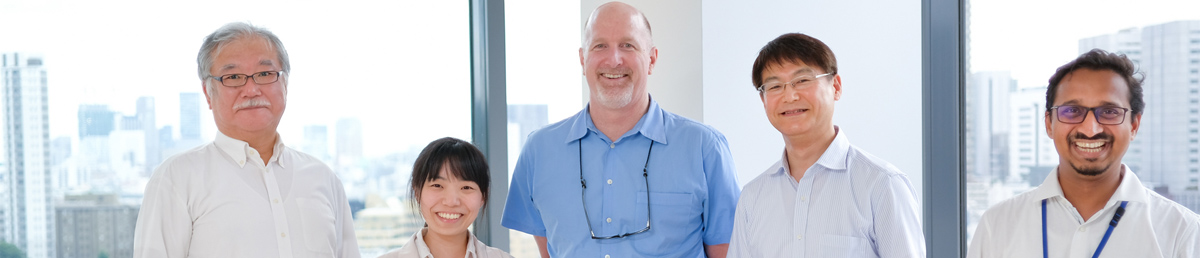
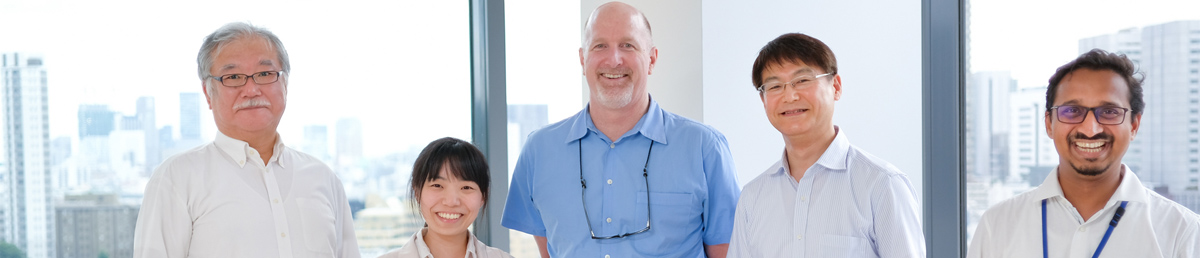
NECとGEがチャレンジする
共創によるサプライチェーン革新
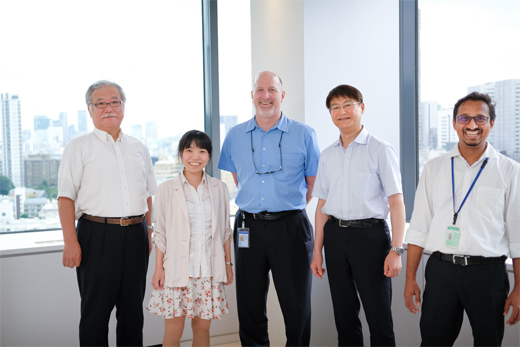
(写真提供:GEジャパン株式会社/GE Reports Japan)
NECとGEデジタルは、顧客企業のデジタル・トランスフォーメーションの促進に向けてIoT分野の包括的な提携を結んだ。最初のアクションとして、NECがグローバル展開する無線通信システム「PASOLINK(超小型マイクロ波無線通信システム)」のインド、インドネシアでの設置工事管理に、GEの産業向けIoTプラットフォーム「Predix」を導入。日米を代表するグローバル企業の協業は何を目指し、今後のIT業界にどんな革新をもたらすのか? 提携のキーマンらに話を聞いた。
SUMMARY サマリー
NECの経営、現場それぞれが抱えていた課題
今回、GEとの提携を決断したNECのサプライチェーン統括ユニット担当、大嶽充弘執行役員常務には、かねてから経営の立場からの懸案があった。「BtoBの場合、サプライチェーンの責任は営業プロポーザルから製品・サービスのエンドオブライフまで続き、調達・生産・物流のプロセスだけにとどまらない。NECのビジネス展開にはまだ十分とは言えない箇所がいくつもある。その象徴が、BtoBにおいて製品が出荷されてからお客様が使い始めるまでの期間におけるサプライチェーンマネージメントだった」と話す。
大嶽は2013年から、PASOLINKを対象としたサプライチェーンの改善に取り組んできた。しかし、150カ国に散らばる多様なプロセスをITで一括マネジメントすることは難しく、2015年に同社が「NEC Industrial IoT」を発表した後も、サプライチェーンの統合管理は課題であり続けた。「いくつかのSaaSベンダーとの協業も検討したが、彼らが提供する環境は製品中心のマネジメントであって、われわれの標榜する社会価値の提供という事業形態には合わなかった」(大嶽)
一方、お客様の運用環境を構築する現場でも、設置工事のマネジメントに同様な行き詰まりを感じていたと、NECトランスポートソリューション事業部の福本大蔵エグゼクティブエキスパートは話す。
「インドでの工事要員は管理スタッフだけで約300人、契約社員等の下請けを入れると約1000人になる。200以上に上るチームのそれぞれが、進捗管理などをExcel等による手作業で行っていた。ベテランのマネジャーが個別最適で管理していたが全体把握までは不可能で、共通課題への取り組みができる状況ではなかった。一方、事業のグローバル効率を高めるために、コストダウンを含めた全体最適の必要性が高まってきた。そのための有効な手段がデジタル・トランスフォーメーションであり、製造プロセスやリソースの抜本的な改革を図ることが求められていた」(福本)
GEのデータ化に対する執着心を感じて提携を決断
大嶽が最初にGEと接触を持ち、サプライチェーンに関する自身の考え方などを話し合ったのは2016年3月。その後「まずお互いの工場を見てみよう」という話になった。
「その年の7月、GEの日野工場を見学したときに、改革の権限を現場に持たせているだけでなく、Predixで工場内のすべての事象をデータ化しようというGEの執着心の強さを実感した。こうしたこだわりはNECのやり方とは異質だが、GEの手法を取り入れることで改革が加速するかもしれないと思い、提携に前向きになった」と大嶽は述懐する。
工場のデジタル化もひとつの選択肢ではあったが、一方で、NECは同社のバリューチェーン全体のうちROIを最大化できる投資場所を探る必要があった。
GEのマンダール・ワヴデ氏(GEデジタル・ジャパン コマーシャルリーダー)は「実際、NECの工場オペレーションはすでに非常に成熟したレベルにあった。100%に近い歩留率には、実際に見学したGEのメンバー一同、感動さえ覚えたほどだ。では、NECではどこにアプローチするとアウトカム(成果)が最も大きくなるのか。NECのメンバーと議論の末、海外におけるサプライチェーンだという結論に至った」と話す。

(写真提供:GEジャパン株式会社/GE Reports Japan)
大嶽も、改革の対象は最終的にはPASOLINKだけにとどまらないことを重視した。NECが社会ソリューション事業をグローバル展開すれば、マネジメント改革の必要性は多様なバリエーションで発生し、それを支えるIoTインフラは必ず必要となる。
「現場が『必要だ』と言いだすのを待っていては遅れをとってしまう。 全体最適を図るためには全社を統括する立場で方針を決め、組織を横軸で監督する自分たちの部門こそ一歩踏み出るべきだと思った」(大嶽)