2018年01月11日
シェアリングサービスが生み出す、住民や会員向けの新たな付加価値とは
さまざまな保有資産をうまく活かして、利用者の満足向上や住民サービス向上など、新たな付加価値を生み出すシェアリングサービス。業種の枠を越え、ビジネスの可能性を広げるシェアリングサービスは、今後も大きな伸長が見込まれている。この話題のビジネスモデルの魅力とは何か。サービス事業を行う時の留意点や成功するためのポイントは何か。シェアリングビジネス創出を支援する「シェアリングサービスプラットフォーム」を開発したNECの担当者が語る。

左:NECコーポレートマーケティング本部 戦略・企画チーム 主任 福田 浩一
いまある資産を活かし、新たなサービス創出を
──初めに、最近話題のシェアリングサービスについて、簡単に教えてください。
福田:
シェアリングサービスは、スペースやモノ、人材・スキルなどの資産を複数の人たちで共有したり、貸し借りしたりするサービスを指します。身近な例では民泊やサイクルシェアなどが知られていますが、いま日本では会議室や映画館などの空き時間をレンタルスペースとして提供する株式会社 スペースマーケット、Web上で登録した人材の知識・スキル・経験を時間単位で提供する株式会社 ココナラのほか、数多くのシェアリングサービスがあります。また、民泊サービスのAirbnbやライドシェアのUberは、グローバルで事業を展開しています。

新しいビジネスモデルとしてシェアリングサービス事業は、国内外で大きく広がりつつあります。野村総合研究所の「ITナビゲーター2018年版」の発表では、日本国内のシェアリングサービスの規模は2017年に2,660億円ですが、2023年には9,400億円に拡大すると予測しています。
──シェアリングサービスを提供する事業者の、ビジネスメリットとは何ですか。
柴田:
事業者がシェアリングサービスのために活用するモノや空間、スキルといったリソースは、遊休資産や余剰資産などを利用する場合が多いのです。つまり、新たな資産を持たずに、もともと保有している資産を活用するのがシェアリングサービスの大きな特長です。また、いまある資産や設備を利用するため、サービスをすばやく立ち上げることができるのも魅力のひとつです。固定費がかからず、マージナルコストも極めて低いので、シェアリングサービス事業者は、サービスを提供した分がそのまま収益につながるというビジネスメリットがあります。
住民や会員向けに、利用者視点での統合的なサービス事業を拡大
──シェアリングサービスに対する、NECの考え方を聞かせてください。
福田:
現在シェアリングサービスは、B to CやC to Cといった領域で多く展開されています。NECでは、今後B to B領域や公共・公益サービス分野におけるシェアリングサービス事業の拡大も支援していきます。たとえば、製造・プロセス業などの分野では工場の生産機器や検査機器、また医療分野においては高額な医療機器などのシェアリングなどが考えられます。また、公共・公益サービスでは、産業・地域・行政などの視点から、シェアリングによる住民へのサービス向上や地域の活性化に貢献したいと考えています。
インバウンドによる今後の需要拡大などを視野に入れ、2017年1月よりシェアリングエコノミー促進室を内閣官房に設置するなど、政府もシェアリングサービスを積極的に推進する姿勢を示しています。
NECは、こうした時代に対応するため先進のICTでサポートしていきます。
──B to B領域では、具体的にどんなシェアリングサービスが考えられますか。
柴田:
例えば、不動産デベロッパーで考えてみましょう。ビルのフロア賃貸や管理という従来の業務だけでなく、空いている会議室をシェアリングスペースとして提供したり、またレストランやフィットネスジムを運営している事業者と提携することで、ビルを利用する会員向けにさまざまなシェアリングサービスを提供することができます。

さらに、3階にある会社に籍を置くビジネスマンが、曜日や時間によって6階の別の会社でスキルを活かすといった人材マッチングなどのサービスも実現できます。複数のシェアリングサービスを連携して高付加価値を生み出すことで、本来の業務以外の収益アップやビル自体の魅力アップにもつながります。こうした新たなビジネスモデルは、不動産分野だけでなく、幅広いB to B分野に適用できます。
──公共分野では、どのようなシェアリングサービスが期待できますか。
福田:
日本のさまざまな自治体でも、実際にシェアリングサービスへの取り組みが進んでいます。地域住民同士による子育てシェアをはじめ、民泊サービス、個人の車に相乗りして高齢者の移動をサポートするライドシェアなどが、各地で行われています。また、自治体が地域の仕事と人材をクラウド上で募集して、マッチングさせるスキルシェアなどの事例もあります。子育て中の母親や高齢者などが空いている時間に仕事をすることで、地域の経済サイクルの活性化にもつながります。
──シェアリングサービス事業を行う上で、留意すべき点とは何ですか。
柴田:
シェアリングサービス事業は単一サービスではなく、既存の会員基盤をベースに魅力あるサービスを複数組み合わせて、その相乗効果で付加価値をさらに高めていくことがポイントです。たとえば地域に根ざしたスーパーマーケットや鉄道会社などでは、地場のロケーションや遊休スペースを活かしたイベント体験、宅配ボックスやコインランドリーの設置などを行うことで、ビジネスの可能性が大きく広がります。
自社にノウハウがなくてもさまざまなシェアリングサービス事業者との連携によって、既存のポイントサービス以外の、多様な付加価値を提供することが可能になるのです。そのため、複数のシェアリングサービスを柔軟に連携・統合できるプラットフォームの役割が重要になってきます。
福田:
シェアリングサービス事業を行う際には、2つの側面からの安全・安心の確保が大切です。1つは、子育てなどのスキルシェアや車に相乗りするライドシェアの場合、あらかじめマッチングした人ではない人がサービスを提供・利用する「なりすまし」を防ぐといった、利用者への安心の確保です。2つめは、前述したスキルシェアやライドシェア、さらには会議室や施設のシェアリングサービスを行う場合における、カメラやセンサーなどを活用し監視・評価するといった、サービス自体の安全の確保です。
例えば会議室の場合、社員以外の不特定多数の人が利用可能となるため、会員以外の入室制御や現場での不法行為を防止するなどの仕組みづくりが必要です。

柔軟で快適、安全・安心なNECのサービス基盤
──NECのシェアリングサービスプラットフォーム開発の背景を教えてください。
柴田:
スマートフォン、GPS、IoTの普及など、いつでもどこでもシェアリングサービスを利用できるインフラが整ってきたことが、まず挙げられます。また、グローバルなシェアリングサービスの台頭、日本政府によるシェアリングサービスの推進といった状況も背景にあります。そうした中、NECではこれまでリテール向けソリューションで培った会員管理の実績やIoT分野のさまざまな技術を活かし、今後ますます拡大するシェアリングサービスをサポートしていきたいという思いから、プラットフォームを開発しました。
──次に、シェアリングサービスプラットフォームの概要や特長を聞かせてください。
柴田:
シェアリングサービス事業に必要なさまざまな機能を、「2層構造」のプラットフォームに統合したことが大きな特長です。1層には、履歴や顧客情報、クーポン管理などの会員管理機能をまとめました。そして2層には、サービスメニュー、予約や決済などのシェアリングサービス管理機能を集約しました。これにより、複数のシェアリングサービスの連携が柔軟に行えるとともに、多様なサービスが一元的に管理できます。また、利用者の個人情報をまとめた会員管理機能とサービス管理機能を分離することで、セキュリティの向上を実現しています。

画像を拡大する
福田:
前段でも申し上げましたが、シェアリングサービス事業においては安全・安心の確保が利用者への満足度向上やサービスの普及に繋がります。NECでは世界No.1の精度を誇る顔認証技術をはじめ、指紋・掌紋、指静脈、虹彩、声、耳朶の形などによって本人を特定する、多彩な生体認証技術を保有しています。この生体認証を「Bio-IDiom(バイオイディオム)」と名づけ、皆さまに広くご利用いただけるよう取り組みます。なりすましを防ぐことや、部屋を貸し出す際のワンタイムパスワードとしての活用が可能です。
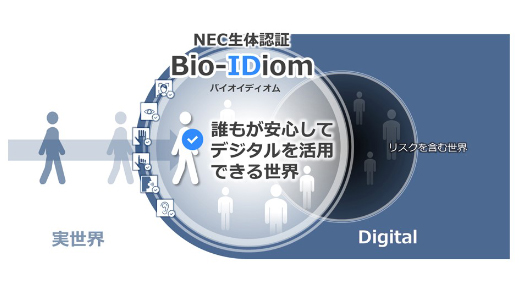
また、高度なAIを活用した人材マッチング技術やマイナンバーカードによる認証サービスも提供できます。これにより、安全・安心そして利便性の高いシェアリングサービスの実現をサポートします。
──シェアリングサービスプラットフォーム発表後の反響はいかがですか。
柴田:
NECシェアリングサービスプラットフォームは2017年10月に発表以来、電力会社や自治体、公共団体、金融機関、通信キャリア、旅行会社など、幅広い分野のお客様から多くのお問い合わせやご相談をいただいています。現在、実際に進行中のプロジェクトもあります。NECでは、新開発のサービスプラットフォームとこれまでの豊富な業種ソリューション実績やノウハウを融合して、シェアリングサービス事業の可能性を大きく広げていきます。
──最後に、シェアリングサービスに対するNECの思いを聞かせてください。
柴田:
今いる場所で誰もがスマートフォンを使って、希望するシェアリングサービスを自在に利用できる環境づくりをNECは支援していきたいと考えています。多くの企業や団体がNECのプラットフォームを活用して、魅力あるシェアリングサービスを連携することで、利用者には安全・安心そして便利なサービスを実現するとともに、事業者に対してはビジネスの拡大や新たな収益を生み出すサポートをしていきます。
福田:
NECでは、人・モノ・コトをデジタル化によって深いレベルでつなげることで、新しい価値を生み出し、暮らしやビジネスをよりよく変えていくデジタルトランスフォーメーションという考えのもと、さまざまな事業を展開しています。今回のシェアリングサービスプラットフォームも、その一環です。資産を有効に活かしながら、新たな価値や利便性を生み出すシェアリングサービスは、限りある地球の資源を無駄にすることなく環境にも配慮する、サステナブルな社会の実現に貢献できると期待しています。
※文中に記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。


