

地方創生現場を徹底取材「IT風土記」
島根発 「Edtech」が離島を活性化 全国が注目する海士町の地方創生戦略
SUMMARY サマリー
離島の高校の魅力を高める
隠岐國学習センターは2010年6月、廃校の危機にあった隠岐島前高校を活性化するため、海士町など隠岐島前地区の3町村などが取り組んだ「隠岐島前高校魅力化プログラム」の一環として設立された。
隠岐島前高校は、隠岐諸島の島前三島の一つ中ノ島にあり、全国的にも数少ない離島にある高校だ。島根半島の北約50キロ、松江市の境港や七類港からフェリーで3時間、高速船でも2時間近くかかる距離にある。入学生の大半は島の子供たちで、2008年度には入学者数が28人と、統廃合の基準(21人)にぎりぎりの水準に落ち込んでしまった。
「高校が廃校になれば、若者たちが島から離れ、人口が減り、島が衰退してしまう。高校の廃校だけは避けなくてはならない」。当時、海士町の財政課長だった吉元操総務課長は高校の廃校に強い危機感を覚えたという。高校がなくなれば、島の子供たちは島外に進学する。子供たちが島を出るなら、島外で働き口を探そうと、家族が島を出てしまう…。そんな悪循環に陥りかねない。吉元課長らは、島前の3町村の関係者に呼びかけ、高校の活性化支援に乗り出し、魅力化プロジェクトの取り組みをスタートさせた。
プロジェクトでは、島外の全国から高校への入学生を募集する「島留学」制度をスタートされた。また、教育教員が不足しがちな離島の高校のハンディを克服するため、公立の学習塾「隠岐國学習センター」の開設にも踏み切った。「一般的に高校と塾というと関係は希薄ですが、ここでは高校とセンターが密接に連携し、生徒の指導も含めて高校の先生と一緒に相談しながら進めています」と隠岐國学習センターの中山隆(りゅう)副センター長は説明する。

高校とセンターが一体となって進めている学習プログラムでは、島が抱える課題に生徒たちが取り組んだり、外部から講師を招いて生徒たちの進路指導を行ったりと独自性の高い教育を展開。やがて全国的にも注目を集めるようになり、島留学の希望者も増加。今では留学定員の2倍以上の応募があるほどの人気となっている。廃校寸前と言われた08年に約90人だった生徒数は180人と2倍にまで増加した。


さらに隠岐島では、SmoothSpaceに留まらず、様々なICTが学力向上に貢献している。
当初、島前3島の中学生を対象に遠隔授業を行う事を目的にiPadを導入した。センターでは島の中学生を対象に3島をめぐって授業をしてきたが、天候不順で島と島をつなぐ内航船が欠航して授業ができないケースも少なくなかった。iPadを活用することで天候に左右されず、授業を受けられるようにした。
遠隔授業はどこからでも配信することができるため、本土や他県の講師にも講義を依頼することで生徒の講師の選択肢を増やしたり、他地域の価値観や考え方に触れたりする機会を生徒に与えることができる。もともとは中学生を対象にしたiPad活用だったが、高校生の探究活動にも使えるようにも設定をしたことで、生徒たちが独自の使い方をするようになったと中山副センター長は振り返る。
その一例が「遠隔兄さん、遠隔姉さん」という取り組みだ。島前地区には大学や専門学校がないことから、高校生が大学生や専門学校生に勉強を教わる機会が少なかった。そこで、高校の卒業生に協力してもらい、iPadを通じて"遠隔家庭教師"として学習をサポートするというものだ。今では、パソコンを使って生徒の顏だけではなく、ノートが見える書画カメラを接続して、画面の向こうにいる先輩たちが親切丁寧に勉強をみたり、進路相談に乗ったりできるようになってきたという。
では、ICTを活用した授業は生徒たちにどんな効果を与えているのだろうか。中山副センター長はこんな風に語る。
「例えば、飯野高校の生徒たちとのディスカッションでは、島前の友達同士で通じることが相手には通じないことがあります。自分の中の当たり前のことがそうではない。そのことに疑問を感じ、その疑問を埋める。そのことによって地域や人によって考え方が違うことを感じてもらう機会になっています」
島の子供たちは、離島で限られた人間関係の中で成長するため、考え方が固定化しがちで、競争も生まれにくくなる傾向にあるという。インターネットを通じて、島外にあるさまざまな人と交流し、議論をすることで、固定化しがちな人間関係や価値観を打ち砕き、柔軟な思考力を養い、幅広い見識を持つ窓口になっている。
インターネットを活用すれば、日本だけでなく世界の高校生たちとの交流も容易だ。隠岐島前高校は2015年度に国際的に活躍できる人材の育成を目指した「スーパーグローバルハイスクール(SGH)」の指定を受けた。欧州にあるエストニアの高校生たちとの交流では、双方の生徒たちが両国を訪問。ICTを活用した活動も行われているという。
新しい価値観から生まれる地方創生
隠岐島前高校や隠岐國学習センターが目指すのは、グローバル(世界的)なセンスとローカル(地域的)なセンスを兼ね備えたグローカル人材の育成だ。
島での高校生活で、地域と連携し、地域の課題に取り組みながらローカルなセンスを学び、海外での研修授業やインターネットを活用した海外との交流などでグローバルな感覚を養う。そんな教育方針に触発され、「海外で活躍できる建築家になりたい」(青山さん)、「多文化の人たちと接する仕事に就きたい」(加藤さん)と、生徒たちの夢も世界に広がっている。
高校の存続問題を町の大きな課題ととらえ、魅力化プロジェクトの策定に奔走してきた海士町の吉元課長は「プロジェクトの最大の目的は島の人口の維持です。そして、島独自の歴史や文化を未来に引き継ぐことにあります。単純に経済合理性で非効率なことはやめようというのでは、地方に生き残りの道はありません。非効率なところに価値がある。われわれの取り組みの中から、そのことにも気づいてもらっている」と語る。
海士町が進める教育に関心を持つ高校や大学との交流も広がり、多くの学生や生徒が研修に訪れている。海外からの訪問者も少なくない。島外に生活の拠点を求める人も増えている。隠岐國学習センターのスタッフの多くもIターン組だ。大手企業のサラリーマン、元大学入試センターの職員、アフリカに派遣されていた元海外青年協力隊員…。新たな教育の取り組みをきっかけに島外から多彩な人材が集まっている。約2400人いる町の人口の約1割はIターン移住者だという。
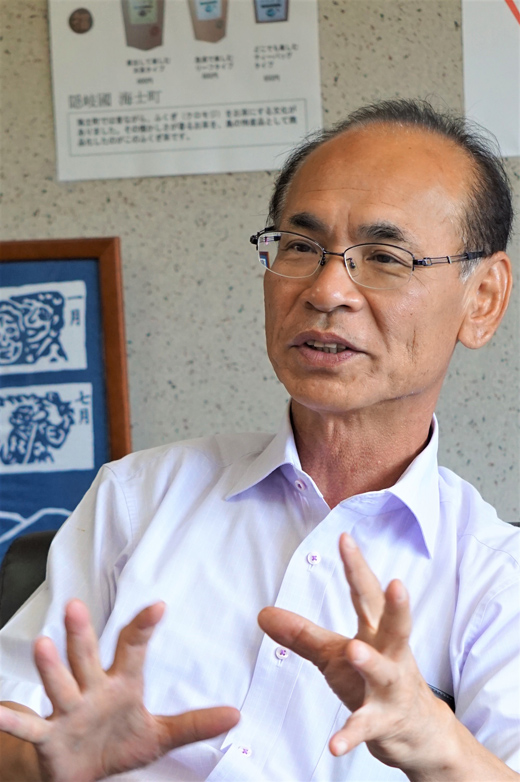
ICTの普及は海士町と日本、世界との距離を縮め、海士町の取り組みを発信。単に高校だけでなく、島そのものの魅力化にもつながっている。「東京に引っ張られ、島根県に引っ張られ、最後尾にいた海士町が最先端の課題解決をする。地域のモデルケースになって、日本を引っ張るタグボートになりたいですね」と中山副センター長。教育を通じた小さな島のチャレンジは、東京一極集中ではない新しい価値観を生み、地方創生の大きな牽引役となっている。

関連リンク