

第2回NEC未来創造会議・公開セッションレポート
「そもそも」を問う文化人類学者・松村圭一郎が、
NEC未来創造会議をアップデートする
SUMMARY サマリー
文化人類学からテクノロジーを問う
NECが2017年からスタートした、新たな社会を構想するためのプロジェクト「NEC未来創造会議」。まずは国内外の有識者を招いて議論することから始まったこのプロジェクトは、2018年から有識者とNEC社内のプロジェクトメンバーによる公開セッションを実施している。
SF作家の長谷敏司氏を招いて行なわれた第1回の公開セッションにつづき、第2回は文化人類学者の松村圭一郎氏が登場。AIに精通する長谷氏とは打って変わって、松村氏はエチオピアの農村や中東の都市におけるフィールドワークをベースに研究を行なってきた文化人類学者であり、いわゆる「テクノロジー」を専門としているわけではない。
しかし、人の能力をAI(人工知能)が超えるシンギュラリティ以後の社会を考えることは、テクノロジーの未来を考えることではない。むしろ狭義のテクノロジーにとらわれないことこそが、多様な社会のあり方を考えるうえでは重要となるだろう。松村氏が「わたしのいる世界とみなさんのいる世界がちょっとズレているから面白くみえるんだと思うんです」と語るとおり、同氏の見てきたさまざまな世界はついテクノロジーから未来を考えがちなわたしたちに多くの示唆を与えてくれる。
今回の公開セッションでは、前回と同様にまずプロジェクトメンバーからわたしたちが豊かに生きられる世界のあり方を提案。「人間」「社会」「環境」「未来」という4つのテーマに即して行なわれたメンバーの提案に対して松村氏が応答しながら、議論が深められていく。松村氏の指摘によりプロジェクトメンバーの提案が常に「そもそも」の部分から問われつづけた結果、第2回の公開セッションは第1回とはまた異なるビジョンを提示するものとなった。

「共鳴できる」人だけでいいのか?
たとえば「人間」と「社会」というテーマにおいて提示されたのは、どんな境遇にある人もテクノロジーを活用することでさまざまな夢にチャレンジできる世界だ。そのうえで、地域や文化の枠を超えて共鳴する仲間とともに夢を叶えていく仕組みをつくっていきたいとプロジェクトメンバーは語る。このビジョンに対して松村氏が指摘したのは、「テクノロジー」の限界と「共鳴」という言葉のもつ危うさだ。
「テクノロジーを考えるうえでは、デジタルデバイドが問題になりますよね」と松村氏は語る。たとえテクノロジーが豊かな生活を可能にするとしても、国によってはアクセスが規制されていることもあれば、障害をもつ人や貧しい人がテクノロジーの恩恵にあずかれないこともある。さらに松村氏は、テクノロジーを取り組みの前提とすることの限界を指摘する。
「テクノロジーを使うと新たな体験ができるように思えるけれど、実際のところはただ与えられたプログラムに乗っかっているだけだったりする。いまやテクノロジーはインフラのようになっていて、もちろんそれは重要なのですが、テクノロジーに“使われる”のではない関係が可能なのか気になっているんです。プログラムに乗っかるだけでは、どうしてもそこにアクセスできるかできないかが問題になってしまいますから」
続けて松村氏は、プロジェクトメンバーの提示したビジョンを理解しつつも、「じゃあ共鳴しない人とはどう生きていくんですか?」と問いかけた。この社会には極めて多様な人びとが生きている。もちろん共鳴する仲間とともに新たなチャレンジを加速させるのは重要だが、むしろ共鳴できない人びとの方が世界には多いのも事実だろう。
「インターネットは地理的に離れた人をつなげたけれど、人と人が関係することは常に意見が合わない人と生きるということですよね」と松村氏は語る。単に共鳴する人同士をつなげるだけでは、ときに攻撃的で排他的なコミュニティが生まれてしまう。「だから、共鳴できない人とどう相互に信頼できる関係をつくっていくかを考えていくべきなのかもしれません」

まずは「会社」のことから
公開セッションが後半に入ると、次第に議論のテーマは未来創造会議が考えていくべきことの「スケール」に移っていった。もとより未来創造会議はシンギュラリティ以後の世界について考えていくこともありスケールの大きな話になることが多かったが、果たしてそれが妥当なのかさえも問いなおされていったのである。
議論の発端となったのは、プロジェクトメンバーが「未来」というテーマを語る際に出てきた「地球よし、未来よし」という言葉。今後はテクノロジーによってこれまで見えなかった影響関係が可視化されることで、もっと広くエコシステムを捉えながら自分よし、相手よし、世間よしの「三方よし」を超えて未来を考えなければいけないとプロジェクトメンバーは語る。
たしかに、可視化は重要だ。わたしたちの行動や取り組みに問題があったとしても、それが可視化されなければわたしたちは問題を問題として認識できないのだから。問題が目に見えるようになってはじめて、わたしたちは解決に向かって議論を始められるようになるはずだ。
ただし、そこから一足飛びに「地球」や「未来」を考えることに危険が潜んでいるのもたしかだろう。松村氏は「話が地球というスケールになることで、自分よし、相手よし、世間よしをあっさり超えてしまっていますが、実際はそこが結構大変なんですよね」と優しく語りかける。「まずはもっと身近なところを考えることが大事だと思うんです。企業って、ひとつの小さな社会ですから。共鳴する人もしない人もいっぱいいますし、実際、部署が違うとまったくコミュニケーションがとれていないこともよくありますよね」
大きな世界を変えていくためには、まずは企業という小さな世界を変えていく必要があるのだ。事実、部署間のコミュニケーションを活性化させることや、すべての社員が企業のビジョンに寄り添える状況をつくることは、日本のみならず世界中の企業が頭を悩ませている問題でもある。こうした問題を解決することは、異なる文化に属する他者と豊かに生きられる世界をつくることと相似の関係にあるはずだ。
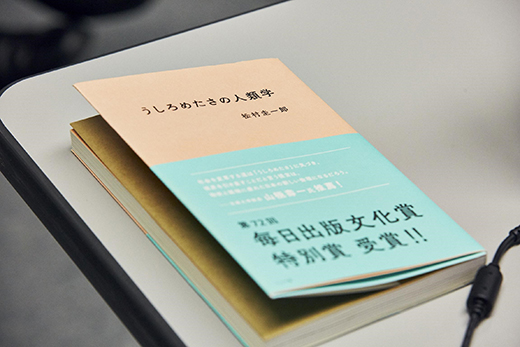
「そもそも」を問いなおすこと
もちろん、NECをはじめ多くの企業はすでにこうした問題に取り組んでいる。部署の垣根を超えた取り組みの実施や、新しいことに挑戦しやすい環境をつくるなど、その対応策はさまざま。しかし一方では、企業を巨大化しシステマティックな組織をつくろうとすることが組織に分断をもたらしてきたのも事実だろう。
たとえば少なからぬ人びとは仕事において「効率」を上げることを重視するが、効率を上げることで失われるものもあることに忘れてはいけない。テレビ会議のシステムを使えば実際に会わずとも会議はできる。でも、実際に会って話すのと画面を交わして会話することは大きく異なっているというように。ただし、仕事に追われたわたしたちはしばしばこの差異を無視してしまう。
松村氏が「わたしたちは意外と身近にある社会に触れずに生きてしまっているんです」と語るように、マスコミが流すニュースやインターネットで見かける話題にも一つひとつ「現場」があり、そこでは等身大の人間が生きている。「一人ひとりの生きている人間がいることを理解し、わたしたちも等身大で社会に出ていかなければ、社会が抱えているリアルな問題に触れられないのではないでしょうか」。そしてそれこそが、文化人類学なる学問がフィールドワークという行為を通じて実践しつづけてきたことでもある。
「ビッグデータや統計を通じて社会を俯瞰的に捉えるだけでは抜け落ちてしまうことがある。実際に現場に行くことで、社会の感覚に気づける可能性は増えていくんです。だからオフィスにいるだけではわからない世界の見方を知れる機会があったらいいのになと思っています」
わたしたちは自らが想像している以上に、自分が属している組織や社会、文化の考え方に縛られてしまっている。そこから抜け出すためには、「そもそも」を問いなおさなければいけない。「日本の教育システムってそもそもを問わせないから、みんな組織のルールや常識を簡単に内面化してしまう。でも、それは結局日本の狭い常識でしかないことはちょっと外の世界を見れば気づけるんですよね」と松村氏は語った。
だからこそ、NEC未来創造会議も「そもそも」を問いつづける必要があるのかもしれない。そもそもなぜ「テクノロジー」なのか? そもそも「未来」とは何なのか? そもそもこの活動はどんな意味をもっているのか? 文化人類学は、複数の社会や文化を横断しつづけることでわたしたちの「常識」が所与のものではないことを教えてくれる。その文化人類学的な問いなおしこそが、これからNEC未来創造会議が提示するビジョンの強度を高めていくのだろう。




