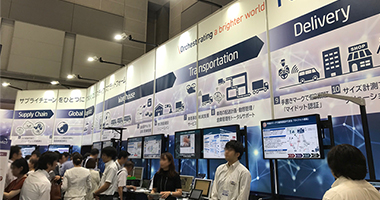MaaSによる物流革新!
エコシステム × モビリティで激変する物流の未来
人手不足をはじめとした課題が山積する物流業界で、100年に一度の革新が進行しつつある。高速道路におけるトラックの隊列走行やフォークリフトの自動化など、IoT、AI、ロボティクスといったデジタル技術の活用によって、より省力化・効率化した物流が整備されようとしているのだ。2030年に向けて物流革新はどのように進んでいくのか、実現に向けたカギはどこにあるのか。日本通運とNECのキーパーソンたちが、モビリティと物流の未来について語り合った(本文敬称略)。
SPEAKER 話し手
NEC

武藤 裕美
交通・物流ソリューション事業部
ソリューション推進部 部長

加藤 学
モビリティソリューション事業部
シニアマネージャー
日本通運株式会社

髙橋 啓 氏
ロジスティクスエンジニアリング戦略室長

松本 直樹 氏
ロジスティクスエンジニアリング戦略室
課長

牧 信吾 氏
ロジスティクスエンジニアリング戦略室
係長
「人の移動」と「モノの移動」が連動していくMaaS
──タクシーの配車アプリやカーシェアリング、ライドシェアなど、次世代型の交通サービス「MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)」の発展が世界的に期待されています。MaaSは物流業界にどのような影響を与えているのでしょうか。
NEC 武藤:MaaSは配車サービス「Uber」に代表されるように「人の移動」の領域を中心に発展してきましたが、今後は「モノの移動」と連動していくことになると思います。例えば、旅行に出発する際、空港のチェックインカウンターで荷物を預けたら、ホテルの部屋についた時には荷物が届いている。あるいは体験農園で採った新鮮な野菜や果物を、その日のうちに家族や友人に届けることができる。そんなサービスも出てくるのではないでしょうか。
日本通運 髙橋氏:MaaSに限らず、デジタル化によって、「移動」あるいは「輸送」の概念が大きく変わりつつあります。自動車業界は現在100年に一度の変革期にあるといわれていますが、物流業界も大きく変わろうとしているのです。これまで物流事業者は物流事業のことだけを考えていればよかった。しかし今後は、武藤さんがおっしゃったように、物流が新しいサービスに溶け込んでいく世界が当たり前になってくるかもしれない。そうなれば、さまざまなデータ連携やAI活用も含めた新たな運用に取り組んでいかなければなりません。
日本通運 牧氏:デジタル化によって変わるのはシステムだけではありません。企業間のパートナーシップのあり方も大きく変わろうとしています。単に輸送の部分を物流事業者が代行するといったことではなく、新しいサービスを生み出すために、業界を超えた結びつきも非常に重要になっていると感じます。
──最新デジタル技術を物流事業の中でどのように活用しているのか、具体的な取り組みをお聞かせください。
日本通運 松本氏:現在の物流業界の課題の1つにドライバー不足があるのはご存知のとおりですが、足りないのはドライバーだけではありません。フォークリフトの運転手やピッキングスタッフをはじめとした物流施設で働く人員の不足も深刻になっています。その課題を解決する方法の一つとして、私たちは荷物をピックアップするフォークリフトの自動化に取り組んでおり、2019年の7月より札幌の倉庫においてその実運用を始めています。
また、倉庫内で荷物を運搬するロールボックスと呼ばれる台車を、フォークリフトや人力で動かすのではなく、リモコン操作による搬送機器での運搬も実現しつつあります。ロールボックスは荷物を積むと数百キロの重さになることから、これまでは女性や高齢の従業員が運ぶことは困難で、事故の危険性もありました。これを機械操作にすることで、作業現場のダイバーシティが進み、人手不足が解消され、さらに安全度も高まることになります。

──トラックの隊列走行の取り組みも大きな話題になっていますね。
日本通運 髙橋氏:現在、トラックメーカーや物流事業者が参加する国家プロジェクトが進んでおり、私たちもそれに参画しています。
日本通運 松本氏:先頭車両のみを人が運転し、そこにCACC(コーペラティブ・アダプティブ・クルーズ・コントロール)という車車間通信の技術やLKA(レーン・キープ・アシスト)という車線に従って走行する技術等を使って無人の自動運転トラックを複数台連結させる。それが隊列走行の実現イメージです。技術面、法整備などいくつかのハードルがありますが、これが現実化すれば、ドライバー不足の解消、貨物運送の効率化につながると期待されています。
NEC 加藤:NECも、自動運転やコネクテッドカーの実用化に向け、国内外の自動車メーカーや自動車部品メーカーなどと共創の上、実証実験や開発を続けています。例えば、危険予測はその1つ。これは、AIやセンシング技術を用いて自動車の位置や周辺の情報をリアルタイムに収集・処理し、運転手が見落としてしまうような道路からの飛び出しや、他車の急な割り込みといったリスクをあらかじめ通知し、安全で効率的な運行を支援するものです。
また、車の異常の検知として、万が一の故障を素早く検知するだけでなく故障の予兆を検知する取り組みや、サイバーセキュリティへの対策として、未知の異常を素早く検知し、その原因を特定・対処を実施し影響範囲を極小化したりと、安心安全に向けた取り組みも進めています。

NECではAIやセンシング技術を用いて危険予測を行い、安全な運航を支援している
NEC 武藤:倉庫での作業の自動化、運転の自動化といっても、すべてを機械に任せるということにはなりません。基本的な考え方は、人と機械の協調によって人手不足の解消を図るということだと思います。人と機械が一緒に安全に働ける環境をどうつくっていくか。そこにデジタル技術を活用していく素地がまだまだたくさんあるはずです。

NECはセンシングやネットワーク技術を活用し、人とAI・IoT・ロボットが協調した物流現場の実現を支援している
日本通運 牧氏:おっしゃる通りです。当社でも最新技術を一方的に押し付けるのではなく、現場の人が活き活きと働ける環境の整備を念頭に置いて、技術の導入を進めています。
必要なのは、企業間の「競争と共創」
──最新技術を活用してビジネスの効果を上げていくに当たって、どのような課題があると考えていますか。
日本通運 牧氏:冒頭の話にあったように、業種間、企業間のコラボレーションが今後一層進んでいくはずです。同業界の企業であっても、競争領域と非競争領域があり、非競争領域での協業は十分可能です。それをどのようにダイナミックに進めていくか。それが現在の大きな課題だと思います。
NEC 武藤:まさに「競争と共創」ということですよね。
日本通運 松本:例えば、当社では、競合メーカー2社の家電量販店向け配送業務の共同化をお手伝いさせていただいております。これはまさに非競争領域での共創といえます。
NEC 加藤:今後そのような協業を広げていくには、お互いのモノ(商品・車)・人・お金・情報などさまざまなリソースをつなぐためのプラットフォームが不可欠となります。プラットフォームの動力の1つとなるのはAIであり、その精度を上げていくのに必要なのがデータです。プラットフォームに参加する企業が増えれば増えるほど、各領域のデータが蓄積され、AIの性能が上がり、よりよいサービス実現につながる。そんな流れをつくっていければ理想的です。
NEC 武藤:「競争と共創」の関係の中でプラットフォームを運営していくためには、データのセキュアな取り扱いも必須になります。それぞれの企業が保有するデータのどこまでを開示し、どこまでをクローズにするのか。そのセキュリティの仕組みを提供するのも私たちNECの使命だと考えています。
半導体・電子部品に特化した物流プラットフォームを共創
──既に日本通運とNECはさまざまな領域で共創の実績があるそうですね。
日本通運 松本氏:はい。その一例がRACS(レイルウェイコントロールシステム)です。私たちがお客様の荷物をコンテナで運んで鉄道に乗せ、到着したところで、再びコンテナを受け取りお届け先まで運ぶ。JR貨物様の運行管理システムとも連携しており、そのサービスのオーダー管理などにNECのシステムを使っています。
NEC 加藤:これは、一種のシェアリングプラットフォームといえます。車による運送と鉄道による運送を同じシステム上で管理することで効率を上げることができるのがこのプラットフォームの特長で、これも今後多くの事業者にお使いいただける可能性があります。
NEC 武藤:ほかにも、NEC、日本通運、さらに両社の合弁会社である日通NECロジスティクスの協業によって半導体や電子デバイスに特化した物流プラットフォームの構築を進めています。これは、製品の開発段階から、原材料の調達、製造、輸送、保管、販売、さらに電機や自動車といった川下産業の動向までを把握し、荷物の動きからサプライチェーンの最適化をトータルに行うことを目的としたプラットフォームで、日本通運の物流のノウハウとNECがメーカーとして取り組んできたサプライチェーン改革の知見をフルに活用しています。
──このプラットフォームを企業が利用するとどのようなメリットが得られるのでしょうか。
NEC 武藤:例えば、半導体や電子部品のサプライチェーンはステークホルダーが多く複雑であるため、リードタイムが長くなったり、需要変動に応じるため在庫を多めに保持せざるを得ないといった課題を耳にすることがあります。
このプラットフォームにより、棚卸資産の削減を実現することで、キャッシュフローが改善されます。
また、在庫の最適化により納品までのリードタイムを短縮することができれば、結果としてコストダウンにもつながります。
さらには、納品先や納品日が同じであれば、共同保管や共同配送により、さらなる効率化を図ることも可能です。
日本通運 髙橋氏:NECには高度なICT技術があり、日本通運はワールドワイドな物流網をもっています。それらを融合させた、グローバルなネットワークを活用できるのはサプライチェーンや物流を最適化する上で非常にメリットがあると思います。
日本通運 牧氏:将来的にはこのプラットフォームと連携する物流倉庫にNECが得意とする画像認識技術を組み込み、検品の自動化を行うことも視野に入れています。周辺業務の自動化とセットで検討する必要があり、研究すべき内容が多分にありますが、それによって人員削減と品質向上も実現できる可能性があります。またAIを活用してマーケットニーズの需要を予測しながら、販売計画や生産計画の支援に繋げられる可能性もありますね。

「すでに起こった未来」を社会実装へ
──この先、2030年に向けた見通しをお聞かせください。
NEC 加藤:2030年には、AIで需要を予測して、それに対して最適なモビリティを配備する。そんなモデルが当たり前のものになっていると思います。また生産と物流をモビリティがつなぎ、ICTによって川上から川下までのサプライチェーン全体を一元的に管理する仕組みをあらゆる製造業者が活用するようになっているのではないでしょうか。
NEC 武藤:モノの動きやお金の動きがすべて可視化されることによって、さまざまな企業や業種間のマッチングやシェアリングが進むと考えています。その仕組みは、人手不足や車両不足の解消につながることはもちろん、物流インフラが止まったり、滞ったりするリスクをなくすことにもつながるはずです。その仕組みの上で、さらに高度なサービスを実現できればいいですよね。
日本通運 髙橋氏:そうした高度なサービスの実現に向け、クリアすべきキーワードは6つあると考えています。それは(1)会社間、業界間、あるいは国と民間の間の「システム統合」、(2)「交通と物流の融合」、(3)「自動運転」、(4)「輸送のユニット化」、(5)「安全性の実現と環境への配慮」、そして(6)「よりよい働き方の実現」です。
「すでに起こった未来」というピーター・ドラッカーの著書があります。「未来」は少なくともコンセプトのレベルでは既に「起こっている」といえます。それを共創の力で社会実装の段階まで進めていく。それが2030年までの目標になると考えています。
──「物流危機」という言葉をしばしば耳にしますが、その危機をテクノロジーの力で乗り越えていくことによって、その先の未来が見えてくるといえそうですね。本日はありがとうございました。