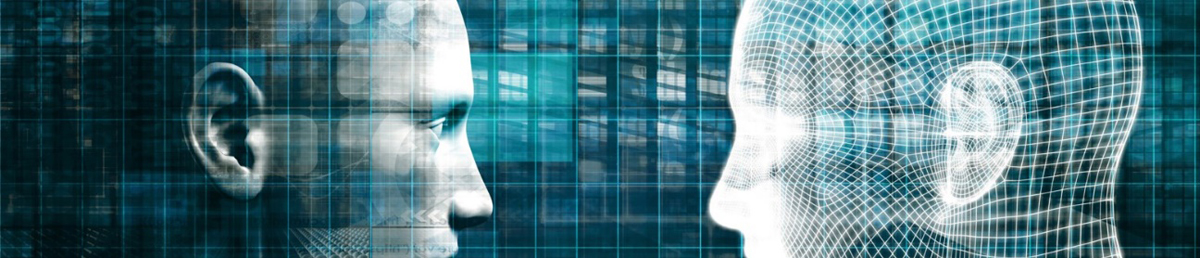
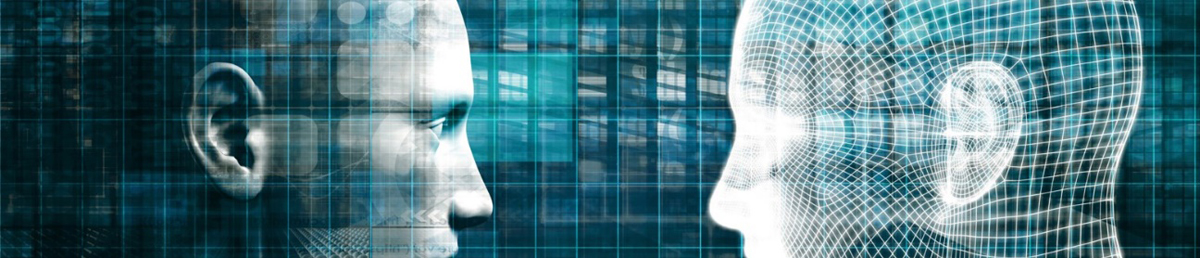
「AIが変革する未来」C&Cユーザーフォーラム & iEXPO 2018より
続々と生まれるAI活用モデル
次の進化を導く技術、人材とは
本格的な実用の段階に入ったAI(人工知能)。さまざまな事例が生まれているが、さらに大きな価値を創出するには、何が必要になるのか──。NECが開催したC&Cフォーラム & iEXPO 2018では、NECのデータサイエンティスト 本橋 洋介と滋賀大学教授の河本 薫氏が、AI活用のために必要な技術や考え方、組織、人材などについて語った。
大きく広がるAIの適用領域
この数年、メディアで「AI」の文字を見ない日はない。現在進んでいる技術革新の中心であり、未来を創出するカギとなるテクノロジー。それがAIだ。
しかし、AIをビジネスに活用する方法論は、現時点では完全には確立しておらず、まだまだ大きな可能性がある。AIによっていかにビジネスモデルを変革し、企業の成長に結びつけるか、ひいては社会の発展に貢献していくのか──。NECが開催したC&Cユーザーフォーラム & iEXPO 2018では「AIが変革する未来 ~先進事例と組織づくり~」と題した講演を通して、それに対する1つの解を示した。
最初に登壇したのは、NECの本橋 洋介である。

シニアデータアナリスト
本橋 洋介
「日本でもAIを活用した事例がすでに出始めています。AIが個人の信用力などを診断するAIスコアサービス、AIで需要を予測して価格を柔軟に変えていくダイナミックプライシング、あるいはタクシー配車サービスなどもあります」(本橋)
最近では、AIが自動的に画像を加工する「GAN」やAIが画像の隠れている部分を推測する「GQN」など、新しい技術も登場し、AIはよりクリエイティブな方向にも進化している。
NECもさまざまな技術開発を進めている。独自技術では、顔、指紋、虹彩などをAIが認証して本人識別を行う生体認証「Bio-IDiom」などの代表例がある。
「NECのAI技術には3つの強みがあります。視覚・数学・文章解析を中心としたコア技術があること、AI活用のリファレンスモデルを持っていること、そして、本当に使えるAIを実現するエンジニア力があることです」と本橋は話す。
中でも、企業からの期待が大きいのが「AI活用のリファレンスモデル」だ。
現在、NECはフランスのバイオテクノロジー企業・トランスジーンとともに、AIを活用したがん治療法の開発に着手するなどの取り組みを進めているが、工場の製品検査工程の自動化、AIとドローンの組み合わせによる農作業の省力化、店舗のレジレス・キャッシュレス化、地域の防犯・防災・誘導を支援するためのシステム、海中を泳ぐ魚の魚影で生育状況を可視化するシステムなど、すでに具現化しているさまざまな事例もある。
「NECは、これらの多数の事例を基に、リファレンスモデルをテンプレート化して提供し、お客様がすぐにAI活用を始められる環境を実現しています」と本橋は説明する。
AI活用を次のステージに進めるには
このようにすでにさまざまな事例が登場し、AIが人々の生活の中に組み込まれた未来は、技術的にはほぼ実現可能になりつつある。あとは、それをどうやって生活の中に落とし込むか。それが本格化すれば、AI活用は次のステージへと進み、社会のあり方もさらに大きく変化する。
「今後、必要になるのはAIの活用方法に応じて『伝え方』を変えていくことではないかと考えています。例えば、空間上に浮かぶディスプレイのような技術が具現化すれば、活用シーンはさらに広がる。メッセージに合わせてアウトプットの方法を最適化することでAIの活用は大きく進展するでしょう」(本橋)
また、ビジネスに利用するには、AIが導いた結論に根拠が必要。したがって、中身がわからないAIではなく、AIの解釈、結論の理由が明らかな「ホワイトボックス型AI」であることが重要だが、今後はAIがなぜその結論を出したのかを理解した上で、人の意見や疑問を再びAIに伝え、別の可能性を導くような対話型のAI活用に対するニーズも高まるだろう。
さらにAIを未来創造に役立てるには、さまざまなプレーヤー間のコラボレーションも重要となる。なぜなら、AIを実用化するためには、調査、企画、検証、導入、活用といったサイクルを回していかなければならない。そのそれぞれのプロセスは、業務専門家、コンサルタント、データサイエンティスト、アプリケーション開発者、ユーザー、運用管理者といったプレーヤーが担うことになるからだ。「今後は、そのプレーヤー同士の協働がより重要になる“みんなで創るAI”だけが『本当に使えるAI』となるのではないでしょうか」と本橋は強調する。NECは、この検証から活用までのフェーズをシームレスに接続し、さまざまなプロフェッショナルの協働による迅速な価値実現を支援する「NEC Advanced Analytics Platform」も用意している(図1)。

AI活用において、さまざまな役割を担うプレーヤー間のコラボレーションを支え “みんなで創るAI”の実現を支援。迅速な価値実現に貢献する
最終的には、専門技術者だけでなく、一般の社員がAIを活用したデータ解析をしながら仕事をするような時代が来る。企業には、その時代に備えた人材育成や研修プログラムも求められるようになる。多くの人がAIを使いこなし、そこから価値を生み出していけるよう、NECは人材教育に注力していくという。「社員教育で培った教育プログラムなどを、お客様にも提供していく計画です」と本橋は語った。
個性の異なる人材がそれぞれ異なる役割を果たす
続いて登壇したのは、前職で大阪ガスのビジネスアナリシスセンター所長を勤め、現在は滋賀大学データサイエンス学部の教授を務める河本 薫氏だ。河本氏は「人材」という切り口から、企業におけるAI活用について語った。

兼 データサイエンス教育研究センター副センター長
河本 薫 氏
経営者は「とにかくAIを導入しなさい」とミドルマネジメントに指示する。ミドルマネジメントは何をしていいかわからず、コンサルタントに相談したり、工場のデータを収集したり、機械学習ツールを導入したりする。しかし、結果が出せずに行き詰ってしまい、経営者からの不信を招く──。それが現在の多くの日本企業の実態であると河本氏は指摘する。「そのような“負の連鎖”を防ぐためには、経営層、ミドル層、エキスパート層それぞれの役割を明確に定義する必要があります」。
その上で河本氏は、エキスパート層に求められる人材を「フォワード型分析人材」、ミドル層に求められる人材を「映画監督型人材」と定義した。
以前、大阪ガスでは、河本氏が中心となって、データ分析力によってビジネスの付加価値を上げる取り組みを行ったが、その時に力を発揮したのが、フォワード型分析人材だったという。
「現場とのコミュニケーションの中で、ビジネスに役立つ分析課題を発掘し、ビジネスを意識したデータ分析を行い、実行を支援し見届ける──。そんな役割を彼らは果たしました。彼らが生み出した付加価値は、顧客訪問時に携行する交換部品選択の最適化、その結果としてのトラブルの即日解決です。データ分析の前に現場業務を徹底的に知った上で問題設定し、AIを使って現場の信頼を得られるソリューションを考え出し、それが有効利用できるように業務プロセスの見直しまで手掛ける。そして、それによってAIの有効活用を実現する。それがフォワード型分析人材の役割です」と河本氏は説明する(図2)。

現場とのコミュニケーションの中で、ビジネスに役立つ分析課題を発掘し、ビジネスを意識したデータ分析を行い、実行を支援し見届ける。ビジネスに新しい付加価値をもたらす上で大きな役割は果たす
経営層がやるべきことは「破壊と創造」
一方、映画監督型人材たるミドル層に求められるのは、AIやIoTについての知識をひと通り抑えながら、映画監督が俳優を動かして作品を作るように、部下や組織を動かし、担当者レベルだけでは為せないような組織横断的な業務改革を実現していくことである(図3)。

映画監督が俳優を動かして作品を作るように、部下や組織を動かし、技術活用を実現していく。過去の慣習にとらわれず、コミュニケーション力を駆使しながら、組織を全体最適の視点で変革する役割を果たす。 画像を拡大する
「全社的な視点からAIを活用した新しいやり方を構想し、組織の壁を越えて実行。それを定着させていくところまでがミドル層の仕事です。そのためには過去の慣習にとらわれず、全体最適な視点から変革を発想し、コミュニケーションの力で経営者からデータサイエンティスト、現場の人までを動かしてものごとを推進しなければなりません」(河本氏)
では、経営層に求められるのはどのような人材だろうか。
「経営層にしかできない役割があります。それは『破壊と創造』です。ビジネスモデルそのものを抜本的に改革することができるのは経営層だけ。そのためには、経営環境を根底から変えるドライバーであるAIやIoTの力を自ら理解しなければなりません。これからのビジネスには正解がないばかりでなく、どのような選択肢があるかも明確ではありません。部下から提示されたものを単に選択するのではなく、自らビジョンを考え、自ら社員に語り、自ら会社を変えていかなければならないのです」と河本氏は強調する。
プロジェクト・ベースド・ラーニングで人材を育成する
河本氏は現在、滋賀大学において「映画監督型人材」と「フォワード型分析人材」を育成するための教育を行っている。用いているのが「プロジェクト・ベースド・ラーニング(問題解決型学習)」と呼ばれる方法論だ。
学生はまず、講義と演習によって分析手法とプログラミングを学ぶ。次に、企業から課題とデータを提供してもらい、企業の担当者や教員からのアドバイスを得ながら課題解決にはデータから何を解明すれば良いかを整理し、学んだ分析手法によってデータから解決策を導出する。そうして、その解決策を企業にプレゼンする。それが、河本氏が実践する「AI人材」育成プログラムの一連の流れである。公表できるだけでも40近い企業がこれまでこのプログラムに協力しており、今後も協力企業を募っていく予定だという。
「企業や自治体側に必ずしも成果をご提供できる取り組みではありません。にもかかわらず、多くの団体がリアルな課題と実データを提供してくださっています。日本のAI人材を育成したい。その使命感だけで協力してくださっているわけです。そのような思いに応えるべく、これからも多くの人材を育て、日本の産業の発展に寄与していきたいと思います」と河本氏は最後に展望を述べた。
基礎となる技術はすでにある。後はそれをどう社会に当てはめていくのか。そして、それを担う人材をどう育成していくか。2人の話からは、AI活用は、その段階まで来ていることがわかる。
NECが「異種混合学習」「ホワイトボックス型AI」といったAI技術はもちろん、「AI人材育成サービス」といった周辺サービスに力を入れたり、「AI活用のリファレンスモデル」に対する期待が高まったりしていることもそれを証明しているといえよう。
他の変化がそうだったように、どんな変化も人はいずれそれを当たり前に感じるようになる。AIが私たちの暮らしに、どんな当たり前をもたらすのか。ワクワクしながら、それを待ちたい。


