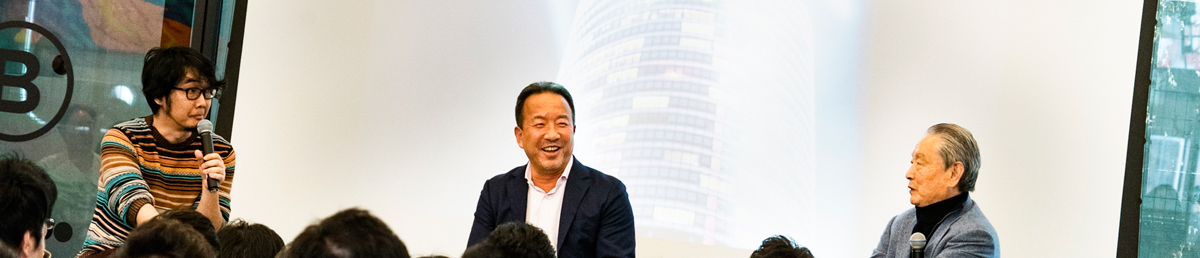
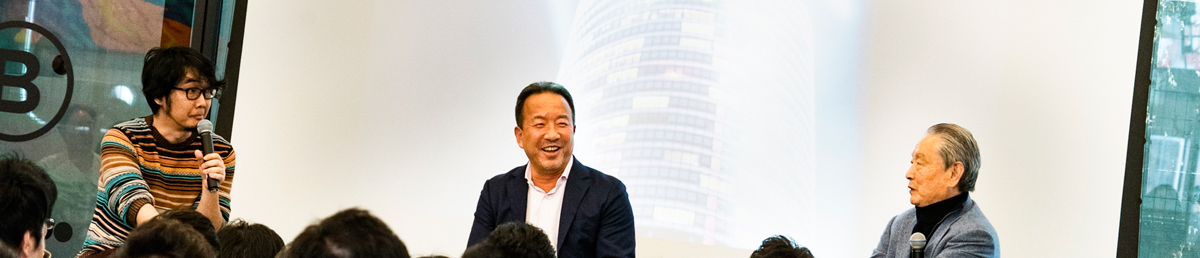
Next Generation Bank and Beyond Event Report
お金の変化からみる未来の社会の設計図、そして個人の幸福を探求する
お金は、生活に欠かせない存在だ。そのお金が変化することは、社会が変革することを意味する。では、どのような未来が待ち受けているのか。これからの社会の設計図について議論するイベント「Next Generation Bank and Beyond」が、2月23日、東京・原宿にあるコワーキングスペースWeWork Icebergで開催された。
イベントの下敷きとなったのは、黒鳥社の若林 恵氏が責任編集を務めたムック「Next Generation Bank 〜次世代銀行は世界をこう変える〜」。現在のお金、金融の基本となっている銀行という存在の進化と、既に中国を中心に起きている銀行に代わって巨大な影響力を持っている新しい存在、また官民一丸となって急速に環境が整備されているインドの事例から、我々の未来の生活を想起していこう。
SUMMARY サマリー
中国のアリペイを深く理解する
イベントではまず、アント フィナンシャル ジャパンの執行役員、小滝 浩哉氏が、アリババグループとアントフィナンシャルの現状、アリペイの役割について紹介した。既に日本でも、コンビニをはじめとする多くの小売店で、QRコードを用いたアリペイが利用できるようになった。中国でのアリペイの利用者は七億人以上、第三者が推定した2017年の決済額は500兆円以上は、日本の電子決済総額の8倍にも迫る。

もともと、中国の巨大ECサイトに成長したTaobao.comの一部門として出発し、円滑にオンラインショッピングを楽しめるようにするための「決済インフラ」として、アリペイはスタートした。日本では未だに請求書払い、すなわちサービスを提供してからお金を支払う性善説に基づいた取引が続いているが、その前提がなく、銀行の振り込みを待ってからサービスや商品を提供する中国において、ECサイト成長を加速させるために欠かせない決済インフラだった。
こうしてスタートしたアリペイの歴史と現在の姿を比べると、そこには非線形の発展があったように思われる。決済インフラ以上の意味合いを色濃く持っているからだ。
現在アリペイのユーザーには、芝麻信用(ジーマクレジット)と言われるスコアが付与され、いつでもスコアを確認できるという。資産やアリペイ決済の利用、投資、送金の情報などから信用指数を数値化する仕組み。日本のクレジットヒストリーと異なり、ユーザーは自分のスコアをいつでも確認することができる。
そして、このスコアは中国での生活において重要だ。デポジット社会におけるデポジットの免除や、シンガポール、ルクセンブルグといった国でのビザ審査の簡素化などのメリットが得られるからだ。そのため、アリペイを通じた決済額を多くして、スコアキープに努めるようになっている。裏を返せば、この点数が低い場合、円滑な生活に支障が出ることを意味する。そこまで、アリペイは影響力を持っていることの表れだ。
中国の銀行以上に人々の生活や消費行動に影響力を持つようになったアリペイの扱いについて、中国政府や当局も無碍にできない存在となっている点で注目していく必要がある。
アリババは既存ビジネスを壊さなかった
アリペイの現状を受けて交わされたディスカッションは、黒鳥社の若林 恵氏をモデレーターに、アリババの日本法人でCEOを務める香山 誠氏、そしてクオンタムリープ株式会社ファウンダー・CEOの出井 伸之氏が登場した。この議論の中で、興味深かったのは、これだけ破壊的な変革を起こしているように見えるアリババやアリペイが、必ずしも既存ビジネスを壊していない点だ。香山氏はアリババの戦略に秘密があるという。

アリババは、地元の商店が大規模資本に淘汰される前に、インターネットの購買力を取り込めるよう「デジタルラッピング」を行った。その結果、不動産王などが経営するショッピングモールは大打撃を受けたが、依然としてデジタルの勢いが強く、そちらもデジタルラッピングが進行していき、結果として顧客体験全体が向上してきた。いわば中国の購買のデジタル化を担ったのがアリババであり、そのインフラとなったのがアリペイだったのだ。
出井氏は、アリババができてから20年で、中国の金融や銀行そのもの、個人やベンチャーの生き様を変えたところに注目した。
「日本では中小企業はお金が借りられないが、アリババが展開し始めた金融ビジネスによって、日本にほとんど存在しないリスクマネーが回るようになった点が大きい。信用のポイントによって、みんなのビジネスが楽になっていった。個人やベンチャーが生きやすい世界に変化させたという、本質的なことをやってのけ、それは絶対日本にはなかったことだった」(出井氏)
ネット以来、米国ではGoogle、Amazon、Facebook、Appleのいわゆる「GAFA」が成立したが、アリババは1社でGAFAの役割以上のことを演じていると出井氏は指摘する。同時に、日本社会の既存システムが不要になることから、日本はアリババを歓迎しないとみている。金融機関としてみると、日本の銀行は口座を作らせない、お金は貸さない、という状態になっており、アリババと真逆の環境であることを認識した方が良い、と強調した。
順風満帆に見える中国のデジタルイノベーションによる社会変革、金融改革だが、危険性はないのだろうか。香山氏はアリババの現場から、次のようにみている。
「沿岸部に住む6億人の人たちは豊かになり、それ以外の8億人の人たちは依然として1人あたりのGDPが数千ドルのレベルです。サプライチェーンの問題で、なかなか内陸部へと経済が波及していかない点も問題です。成長はいろいろなものに蓋をします。まだ成長余地はあります。ただし、今後順調にいくかは分かりませんし、成長の罠にはまったとき、予想外のことが起きうるでしょう」(香山氏)
出井氏は政治やアジアの展望についても指摘した。
「若者が急成長している裏で、長年共産党に尽くしてきた人たちが冷遇されつつある。中国は広大で、いろいろな言語を喋っている人たちもいる。国内をどのようにまとめていくのか。また、イスラム系の6割の人たちがアジアにいます。今後中国がアジアのいろいろな人種と宗教をまとめていかなけらばならない」(出井氏)

スコア化社会と個人の幸福
中国における芝麻信用の社会は果たして幸せなのか。若林 恵氏をモデレーターに、憲法学者である慶應義塾大学大学院法務研究科の山本 龍彦氏と、弁護士の佐藤 明夫氏がディスカッションを行った。
まず山本氏から、中国ですすむ個人のスコア化の現状について紹介された。芝麻信用はアリババによるスコアリングで、いつでも個人が自分のスコアを参照可能になっており、スコアの高い人は快適に生活できる。しかし低いと、厳しい生活が待っているかもしれないと指摘。佐藤氏はスコア化には基本的に賛成の立場だが、その性質を深く知る必要があるという。
「ポジティブな側面しては、さまざまデータが評価に用いられることで、その人の行動や努力が、『点』ではなく『線』で正当に評価される社会となること、より効率的で安全な社会の成立に役立つことなどを挙げられる。一方ネガティブな側面もある。過去の差別が再生産される点、また超監視社会の出現、低スコアが負のスパイラルを引き起こすバーチャルスラムの問題、そして生まれながらの差別の復活などが起きうる」(山本氏)

例えば、就職に失敗すると、低賃金の職に就かざるを得なくなり、それがまたスコア低下の要因になる。また予測のためにAIが介在することで、学習データにバイアスが含まれることもありうる。山本氏はスコアの利用範囲が融資などの場面に限定されれば、日本の現状とさほど変わらないとしながらも、スコアに対する自己のコントロールを認めると、スコアが高い人は自分のスコアをより広範に使いたくなり、結果的にスコア活用が拡がってしまうジレンマを指摘する。
弁護士である佐藤氏は、日本は民族的な難しさが比較的少なく、個人のプライバシーのレベルが比較的低い中でに社会が成立してきた歴史的経緯もあり、個人情報の保護や利活用について諸外国と比べてそれほど高い関心を集めていない現状を訴えた。
特にテロ対策ではスコアやプロファイリングに期待を寄せている一方で、プライバシーを配慮し匿名性を高めると、その匿名性を理解し活用した人が圧勝することにつながる。その上で、スコア化は、全てが良くなるわけではなく、何かが犠牲になっていることを考えなければならない、と指摘した。
日本の社会で起きえなかった金融改革は、中国社会と人々の生活、行動を大きく変えている。出井氏が指摘するように、日本で享受できないデジタルイノベーションを、中国はまさに謳歌している様子が浮かび上がる。その一方で、個人のスコアリングがはらむ格差や階級、差別の固定化の問題を目の当たりにすると、既存の先進国の人々が二の足を踏むだけの「恐れ」があることも分かってきた。
山本氏は、今現在、個人の情報が各所で大量取得され、知らないうちにスコアリングされている状態を踏まえ、日本に問題意識や危機感が薄いことに警鐘を鳴らす。アリババと中国の事例の深い理解は、日本を含む先進国でこれから起きることを予想し、社会として情報技術をいかに有効活用するかを考える、重要なヒントになるのだ。
中国とは異なる道を選んでいる巨大国家に、インドがある。アリババは中国国内にある企業が巨大な影響力を発揮するようになった結果だが、インドでは「India Stack」と呼ばれる政府主導のオープンな取り組みが進んでいる。こちらの議論についても、続編となるレポートを掲載する

Text by 松村太郎 @taromatsumura
Photographs by YURI MANABE


