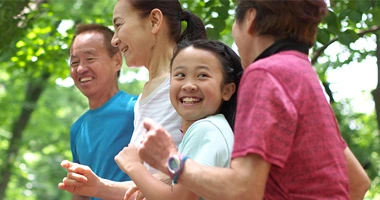顔認証AIでがんの「顔つき」を判別、早期発見や見逃がし予防に貢献したい
日本で最も患者数が多い大腸がん。その多くは大腸腺腫などの前がん病変(ポリープ)から移行したものといわれる。この前がん病変を早期に発見し、がん化の芽を摘み取る役割を担うのが内視鏡検査だが、この検査は肉眼で行われることなどに起因して、見逃しのリスクが指摘されている。
こうした中、NECでは国立がん研究センター中央病院と連携して、大腸内視鏡用のAI診断支援ソフトウェア(内視鏡画像解析AI)を開発。研究・事業開発に携わったキーパーソンたちに、開発に至るまでの苦労や懸ける思いについて話を聞いた。
内視鏡の画像をAIで解析し、大腸がんの早期発見に貢献へ
大腸がんは、前がん病変、いわゆる大腸ポリープから移行して発生することが多いことはよく知られている。
「大腸がんとは、内視鏡検査を一生に一度でも行えば、がんの罹患率のみならず死亡率も減少することが証明されている、数少ないがんの1つ。内視鏡検査によりポリープの段階で発見・切除すれば、大腸がんへの進行を未然に防ぐことができます」と国立がん研究センター中央病院の斎藤 豊氏は説明する。
とはいえ、ポリープのサイズや形状、場所によっては判別が難しいものもあり、医師による診断技術の格差も大きい。このため、大腸腺腫性ポリープの見逃し率は24%に及ぶ(※1)という報告もあり、内視鏡検査で病変が発見されないまま、大腸がんに進行してしまうケースも少なくない。

内視鏡センター長 内視鏡科 科長
斎藤 豊 氏
そこで、NECでは、顔認証技術を活用して、大腸ポリープをAIで検知する画像診断支援ソフトウェアを開発。これは、内視鏡検査時に撮影される画像から内視鏡検査中にAIで病変が疑われる部位を自動検知し、病変の検出を支援するソフトウェアだ。
- (※1) Rex DK, Cutler CS, Lemmel GT, Rahmani EY, Clark DW, Helper DJ, Lehman GA, Mark DG. Colonoscopic miss rates of adenomas determined by back-to-back colonoscopies. Gastroenterology. 1997 Jan;112(1):24-8.
顔認証で がんの“顔つき”を見分けられないか
内視鏡画像解析AIのアイデアが生まれたのは、2015年1月。
タイ・バンコクの国際空港でのふとした会話が発端だった。当時、NECは、国立がん研究センター中央病院と協力して、病理画像解析の研究を進めていた。出張先のバンコクの空港で雑談中、あるNECの社員が、同行の内視鏡医にこう話しかけた。
「今、空港の出入国ゲートで、NECの技術が広がり始めているんです。NECの顔認証技術は世界一なんですよ(※2)」。すると、内視鏡医は思わぬことを言った。「そうですか。実は、腫瘍にも“顔つき”があるんです。顔認証で、顔つきの悪い悪性腫瘍(がん)を見つけられないかな」。
帰国後、社員が相談を持ちかけたのが、顔認証研究の第一人者である今岡 仁(現・NECフェロー)だった。顔認証でがんを見つける――奇想天外ともいえるアイデアに今岡は戸惑ったが、ともかくも、提供された8枚の画像を加工して数十枚まで増やし、画像の病変が「がんか否か」を識別しようと試みた。
「『がんか、そうでないか』という2択であれば、確率的に5割は当たるわけです。ところが、実際にやってみたら、正解率は7割に上った。これはもしかすると可能性があるかもしれない。当時、世の中に出始めたディープラーニング技術(深層学習)を医療に適用すれば、新しい可能性が広がるのではないか――そんな思いから、この研究を始めることにしたのです」と、今岡は振り返る。
-
(※2)
米国国立標準技術研究所(NIST)による顔認証技術の精度評価で5回第1位を獲得
NISTによる評価結果は米国政府による特定のシステム、製品、サービス、企業を推奨するものではありません
https://jpn.nec.com/press/201910/20191003_01.html

フェロー
今岡 仁
翌2016年、国立がん研究センター中央病院との共同研究が正式にスタート。ついに、「顔認証AIを用いて、前がん病変である大腸ポリープや早期がんを見つけ出す」という、前代未聞のプロジェクトが始動したのである。
とはいえ、人間の顔ではないものを顔認証で判別しようというのだから、その難しさは想定を超えていた。
「私は2002年以来、20年にわたって顔認証を研究してきました。人間の顔とちがい、がんは非定型のものなので、特徴をとらえるのは容易ではありません。この問題を克服することが、今回最大の技術的課題でした」(今岡)
病変のタイプはさまざまで、隆起しているものもあれば平坦なものもある。どこに病変があるのか、どのようなものがポリープもしくは早期がんなのか。専門家でなければ見極めがつかないことばかりだった。
そこで、プロジェクトでは国立がん研究センター中央病院に協力を求めた。
当初は小さくスタートしたプロジェクトだったが、国立がん研究センター研究所の浜本隆二氏の支援のもと、内視鏡科から山田真善氏らを中心メンバーに加え、国立がん研究センター全体とNECを巻き込む大きなプロジェクトへと発展していった。
その中で内視鏡医の所見がつけられた5000例30万件の内視鏡画像を入手。これを、ディープラーニングの“正解”に当たる教師データとして蓄積し、顔認証AIに学習させていったのである。
「ひと口に腫瘍といっても、さまざまなタイプのものがあります。認識が極めて困難な表面型腫瘍(前がん病変)や極めて小さな陥凹型大腸がんなど含め、幅広くAIに学習させることで、あらゆる病変の検出を支援できるようにしたい。そんな思いから、学習させる病変の種類を多く確保することにこだわりました」と斎藤氏は振り返る。
技術的課題として立ちはだかったのは「がんの判定」だけではない。「検査中に解析できること」も大きなポイントとなった。内視鏡検査では、内視鏡を人体に挿入している間に、カメラの画像でポリープの有無を判断し、ポリープ切除などの処置を行わなければならない。そのためには、画像解析を高速化し、検査と並行して解析を実現する必要があったのだ。
「ところが、高速に解析を行うには、ディープラーニングのモデルが大きすぎる。そこで、顔認証で蓄積したノウハウを活用して、モデルのサイズを減らすなどの工夫を重ね、解析の高速化を図りました」(今岡)
こうして研究チームは、ディープラーニングを活用したAI技術と、独自の高速処理アルゴリズム、画像処理装置(GPU)を搭載したプロトタイプPCを開発。臨床現場で検査中に解析結果をフィードバックできる仕組みをつくり上げていった。
さらに、「未検知と過検知の両方をいかに減らすか」も大きな課題となった。「未検知」とは要するに病気の見逃しのこと、「過検知」とは「病気ではないのに、病気だと間違って判断してしまうこと」を指す。
「過検知が多発すると、内視鏡を大腸に挿入しただけで、1分間に何回もアラートが鳴ってしまう。そうなると、病変の見逃しは防げるかもしれませんが、アラートの信頼性が失われて使い物にならなくなります。今回は過検知を減らす仕組みに徹底的にこだわりましたが、かといって、未検知が増えてしまっては元も子もありません。『未検知を減らしつつ、過検知も減らす』というのが非常に難しかった」と今岡は振り返る。
当初、過検知の発生率は数10%に上ったが、試行錯誤の末、1%未満まで減らすことに成功。それと同時に未検知も減らし、最終的には高い発見率を達成した。この「未検知・過検知・リアルタイム性」という3つの課題をクリアしたことで、内視鏡画像解析AIは、実用化に向けた大きな一歩を踏み出したのである。
すべては「NEC方式」を否定することから始まった
プロジェクトが直面したのは、技術的課題だけではない。医療機器を世に出すための体制づくりでも、さまざまな壁に突き当たった。そんな中、プロジェクト推進の立役者となったのが、医療機器メーカー出身で、2018年6月にNECに転職してきた池田 仁(デジタルヘルスケア事業開発室 ディレクター)だった。

デジタルヘルスケア事業開発室
ディレクター
池田 仁
医療機器は人体への影響度が高いため、誰にでも製造や販売ができるというわけではない。国から医療機器を製造・販売する許可を受けない限り、医療機器を扱うことは許されていないのが実情だ。ところが、当時のNECには医療機器の開発経験がなく、臨床試験への対応など、厳格なルールに則った開発体制が整っているとはいいがたい状況にあった。
「そこで、私が入社してまず着手したのが、体制づくりでした。医療機器を開発するためには、国の業許可を取り、医療機器品質マネジメントシステムをつくらなければならない。その体制を立ち上げることが急務で、開発手法から品質管理、組織設計に至るまで、すべてをやり直しました。今までのNECのやり方とは全くちがうので、メンバーも暗中模索の状態でしたが、モチベーションは高かった。変革を進めるため、要所要所で外部のリソースも補充し、体制をつくり上げていきました」(池田)
社外からは、薬事のエキスパートや医療機器開発経験者、内視鏡業界の経験があるメンバーなどが参加。また、ソフトウェア開発の新戦力として、複数名の社員も社内公募制度を利用してプロジェクトに加わっていった。
2019年4月、NECは「医療機器製造販売業」の業許可を取得。会社の定款も変更し、同社が創薬も含めた医療分野に本格参入していくことを高らかに宣言した。メディカルで新たな社会価値を創造したいという、経営陣の思い。それが、プロジェクトに大きな力を与えたことは想像に難くない。
内視鏡画像解析AIの開発に当たって、池田がこだわったもう1つのポイントがある。それは「デザインと安全性のバランス」だ。「プロジェクト発足当初から社内のデザイン室と連携して開発を進めてきたが、意見が衝突することもしばしばだった」と池田は言う。
「デザイナーが考えるのは、使いやすくてモダンなデザイン。でも、医療機器は何よりも安全でなくてはならない。 “かっこいいデザイン”は、時にユーザをミスリードすることがあるので、事故につながる可能性のあるデザインは排除しなければなりません。それで、デザイナーと喧々諤々やりあいながら、デザインを詰めていきました」
臨床現場を知ってもらうため、国立がん研究センターにもデザイナーを同行。ユーザビリティを磨く上で貴重な経験となった。
「このソフトでは、病変を見つけた時に鳴らす通知音の音量や音色、マーキングの色を変えられるように設計しています。例えば、内視鏡室が暗くてマーキングが見えにくい、周囲が騒がしくて通知音が聞きづらい、といった場合には、環境に合わせて自由に設定を変えることができる。デザイナーが実際に内視鏡室を見学したことが、このデザインに結実したわけです」(池田)
画像解析AIは、医療DXの実現に向けた第一歩
こうして、プロジェクトは終盤に入り、最大の関門ともいえる臨床試験を迎えた。だが、当初は机上の計算通りの結果がなかなか出ず、途方に暮れることも多かった、と池田は振り返る。
医師たちとも真剣に議論を重ねながら、試行錯誤を繰り返した末に、ようやく目標値をクリア。
「がんになる前に病変を発見し、処置することを支援する。それが最終的なゴールです。悪性腫瘍になる可能性のある病変を早期発見し、早期治療につなげれば、がんの死亡率を下げることができる。それを最終的な成果とする意味でも、がんの発見率を定量効果として出していきたいと考えています」(池田)
内視鏡AIに期待される効果は、それだけではない。AIがサポートすることで、検査における医療格差を是正する効果も目指す、と池田は言う。
「内視鏡検査を行っているのは、大学病院や専門病院だけではありません。このAIを使うことで、熟練医の知見を踏まえた内視鏡検査の支援を得ることができます。このソフトウェアを通じて、検査の均てん化による医療格差の是正に貢献していきたいと思います」
また、国立がん研究センターの斎藤氏も、内視鏡画像診断AIへの期待をこう語る。
「今回期待するのは、ヒューマンエラーを防ぐ安全装置としての役割です。例えば、自動車運転がうまいドライバーの車にも安全装置がついているように、内視鏡の専門医にとっても、AIのサポートは心強い。現在の性能改善に加え、機能拡張を目的とした国際的な共同研究も進めているので、今後もAIがサポートできる範囲は広がっていくと考えています」

NECはこれからどのような方向性を目指すのか。
「今後は、食道や胃など、大腸以外の内視鏡検査にも対象を広げていきたい。それから、病変の検出だけでなく腫瘍性の判定もするというように、検査の支援機能を強化していきたいと考えています」と池田は語る。とはいえ、NECの強みを活かせる分野は、それだけではない。NECが世の中に提供できる最大の付加価値とは、「医療とITとの連携」だという。
「今後は、画像解析を入り口として、院内オペレーションとも連携することで、院内のデジタル化を進めるお手伝いをしたい。顔認証AIによる診断支援を機能強化しながら、電子カルテなど他事業とも連携して、多様な院内ソリューションをご提供していきたいと考えています。医療機器を軸としてDXを起こせるというのは、NECならではの重要な視点。今回のプロジェクトも、すべてが融合していくDXを起こすための第一歩だと位置付けています」(池田)
一方、「自分の役目は『飛び地を見つけてくる』こと」と語るのは今岡だ。「医療の領域では、AIを使ってできる部分がまだまだある。社外と連携しながら、しっかりと“飛び地”を見つけ、顔認証やAIの可能性をどんどん広げていきたい」と、その思いを語る。
「IT企業」から、医療現場の課題を解決し「医療DXを支援する企業」へ。今回のプロジェクトは、新しい挑戦へのきっかけになったようだ。