

地方創生現場を徹底取材「IT風土記」
熊本発 プロジェクションマッピングやVRを観光や教育に活用
Text:産経デジタル SankeiBiz編集部
まるでその場にいるように全方位の映像をみることができるVR(バーチャルリアリティー)や建造物などに映像を投影してさまざまな幻想的な映像を表現するプロジェクションマッピング。ゲームやエンターテインメントの世界で利用が広がる最新の映像技術を、観光や地域教育に活用する取り組みが熊本県で進行中だ。県や公益財団法人阿蘇火山博物館が阿蘇山をテーマにしたVR映像やプロジェクションマッピングを制作。郷土のシンボルである阿蘇山への理解を深めてもらう“教材”として活用する考えだ。

SankeiBiz 産経デジタル SankeiBiz編集部
(株)産経デジタルが運営するSankeiBiz(サンケイビズ)は、経済紙「フジサンケイビジネスアイ」をはじめ、産経新聞グループが持つ経済分野の取材網を融合させた総合経済情報サイト。さまざまなビジネスシーンを刺激するニュースが、即時無料で手に入るサイトです。
「火の国」でもあり、「水の国」でもある熊本
熊本県は阿蘇山からさまざまな恩恵を受けている。雄大な景観や温泉は多くの観光客を呼び込み、肥沃な農地は多様な農産物を育む。全国生産トップのスイカやトマトをはじめ、数多くの特産品が出荷されているほか、広大な草原で育成された肉用牛の生産も盛んで、ブランド牛の「あか牛」は、無駄な脂肪分が少ないヘルシーな肉質が人気を集めている。もともとは火山性の土壌で酸性が強く、農業には向かない土質だったそうだが、長年にわたる土地改良の努力の結果、肥沃な土地に生まれ変わったという。
阿蘇から受けている恩恵の中でも最も大きなものは「水」だ
阿蘇山ろくから染み込んだ雨水は、水はけのいい火山灰土壌の大地に浸透し、豊富な地下水となって蓄えられている。阿蘇のふもとには、清澄な地下水が湧き出す水源地が数多く点在する。そして、実に県内の水道水の80%は地下水で賄われている。清澄な水を求め、飲料メーカーや精密機器メーカーをはじめ多くの企業が熊本に工場を立地しており、まさに県民の生活の支えになっている。熊本県は、「火の国」であると同時に「水の国」でもある。

「阿蘇山の魅力は草原ですが、その維持には多くの人々が携わっています。そこには阿蘇山独特の自然の循環システムが成り立っています。野焼きをして草原を維持することで、さまざまな生き物を育み、水源のかん用にも役立っています。なぜ阿蘇の自然が保たれているのかを多くの方々に知ってもらおうと、阿蘇の水資源をテーマにしたVRコンテンツの制作を企画しました」。こう語るのは、熊本県 商工観光労働部 観光経済交流局観光物産課の松岡 和美主幹だ。
県が阿蘇火山博物館と連携し、NECの協力を得て今回制作したVRコンテンツは、「恵みの水を巡る」「壮大な自然を空中散歩」の2編。「恵みの水を巡る」では、阿蘇の水源地である白川水源(南阿蘇村)や池山水源(産山村)などを巡っている。
白川水源は毎分60トンもの地下水が湧き出す県内屈指の水源地だ。実際に足を運んでみたが、水源は圧倒的な透明度の湧水を満々とたたえ、水底の砂を巻き上げながら、地下水が沸き上がっている。水源の水は煮沸しなくても飲めるほどだ。VR映像では、こうした水源地を巡るのだが、水源の中に水中カメラを沈め、地下から水が沸き立つ様子を間近に撮影した映像が眼前に映し出されるなど通常ではみることができない迫力ある映像を体験できる。

一方、「壮大な自然を空中散歩」は阿蘇カルデラ誕生の解説とあわせてドローンで撮影した火口を体感できる。前後、左右、上下に首を動かせば、その風景に映像が動き、阿蘇カルデラに広がる青々とした草原の上空をまるで鳥のように飛んでいる感覚だ。
これらのコンテンツは阿蘇山中腹にある阿蘇火山博物館で視聴できる。博物館には12台のヘッドマウントディスプレーが用意されており、博物館に来館すれば無料で体験することが可能だ。県と博物館は阿蘇市の観光促進を目指して2018年10月に委託契約を締結し、AIやIoTなどの先進技術などを活用した観光振興の強化に取り組んでおり、昨春には観光の目玉である阿蘇中岳火口の空中散歩ができるコンテンツを制作している。今回、新たなコンテンツが加わった形になる。
阿蘇中岳の噴火を再現
こうした取り組みと同時に博物館を運営する公益財団法人阿蘇火山博物館久木文化財団も独自に最新の映像技術を駆使した新たな展示物の制作に乗り出した。
博物館は、火山研究や防災のため、阿蘇中岳の火口に高精細カメラを設置し、火口の様子を撮影し続けている。これまで蓄積してきた映像を活用し、阿蘇中岳の火口を模したジオラマを作製。さらに、火口の映像をプロジェクションマッピングの手法で投影することで、火口の様子を体感してもらう展示物だ。
ジオラマの大きさは直径約3メートル。国土交通省の地形図や航空写真などを参考に精密に再現した。実際の中岳火口の大きさは約600メートルあるが、リアルに再現されたジオラマは、上空から火口を見下ろしているようだ。天井に設置したプロジェクターから火口に溜まった湯だまりや噴火の際に火口から沸き上がる噴煙の映像、噴火の際に火口から火が立ちのぼる映像などが映し出される。

火口に溜まった青色の湯だまりは昨年4月の噴火までに消失してしまったそうで、どれも通常ではみることができない貴重な映像だ。火口のジオラマに投影されているため、まるで目の前で中岳の火山活動を体感しているようで、プロジェクションマッピングならではの臨場感豊かな映像をみることができる。
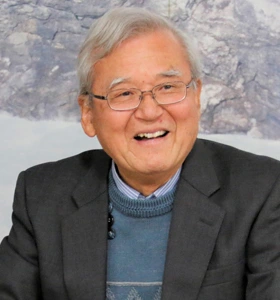
「阿蘇山上に来ても、天候が悪かったり、火山ガスの発生量が多すぎたりして中岳火口の見学ができないケースが多いのですが、そんな時でも見学したときと同じような体験ができる展示物を作ろうと考えていました」と、阿蘇火山博物館学術専門委員長で、新たな展示物の選定にあたった展示物刷新委員会の矢加 部和幸委員長は語る。当初、4プランの提案があったが、委員の要望や4プランの長所をミックスしながら今回の展示物を完成させた。
「これまでは火山の映像をスクリーンに映していたのですが、映像が高精細できれいになりました。また、ジオラマに立体的に映し出すようにしたことで臨場感が増してきました」と矢加部委員長は評価している。プロジェクションマッピングの映像については今後、さらに磨きをかける予定で、火山の成り立ちを紹介する映像などの製作が検討されている。
県や阿蘇火山博物館がコンテンツの制作に力を入れるのは、阿蘇観光に新たな魅力をつくるためだ。
阿蘇観光の大きな目玉は、火口の目前まで見学できる阿蘇中岳観光だが、昨年4月以降、中岳の火山活動が活発になり、火口周辺1キロ以内の立ち入りが厳しく制限されている。規制が解除されても火口付近のガスの状況や天候によっては立ち入れないことが多い。せっかく阿蘇山上に観光に訪れても、何も見えず帰途につかざるを得ないケースも多い。実物はみることはできないものの博物館に立ち寄って、プロジェクションマッピングの映像を見てもらえば、疑似的ではあるものの火口見学の醍醐味を味わうことはできる。
2016年に発生した熊本地震や阿蘇中岳噴火の影響で阿蘇観光は大きく落ち込んでいる。震災前の阿蘇地域の延べ宿泊客数は200万人近くにのぼっていたが、噴火翌年には3割近くも減少。2018年も154万人にとどまり、なかなか回復していないのが実情だ。県としても「阿蘇観光の回復に寄与したい」(松岡主幹)とVR映像の作成に力を入れているのだ。
博物館の企画・教育などを担当する阿蘇火山博物館主任・副ガイドセンター長の豊村 克則学芸員によると、「水源を巡るVRのコンテンツは、見た方の評判がよく、『ここに行きたい』と尋ねられることが多く、ここから水源に向かう観光客も増えています。阿蘇全体の滞在時間を増やすいい効果が出ています」と指摘していた。

教育への活用に期待
VRコンテンツの充実化や新たな展示物の作成で阿蘇火山博物館が特に期待を寄せているのが、教育への活用だ。
博物館には県内を中心に全国の多くの小中学生が校外学習や修学旅行で訪れているが、熊本地震以前の水準には戻っていない状況だ。
阿蘇は、ユネスコの世界ジオパークに認定され、活発な火山の活動をはじめ、地球が生み出したダイナミックな地形や地質を目の当たりにできる。古くから信仰の対象としてあがめられ、親しまれてきた歴史もある。また、県民が守ってきた持続可能な循環システムに加え、火山との共生、防災など「生の教材」がちりばめられている。
「映像は文字でみるだけではわからないことを感じ取ることができます。実際にみられなくてもVRやプロジェクションマッピングによって理解が深まります。ぜひ一度、体験して、何かを感じとってほしいですね」と豊村学芸員。熊本県でのVRやプロジェクションマッピングの活用をみると、娯楽としてのコンテンツだけでなく、教育や学習への興味をそそらせる新しい形の活用法がみえてくる。


