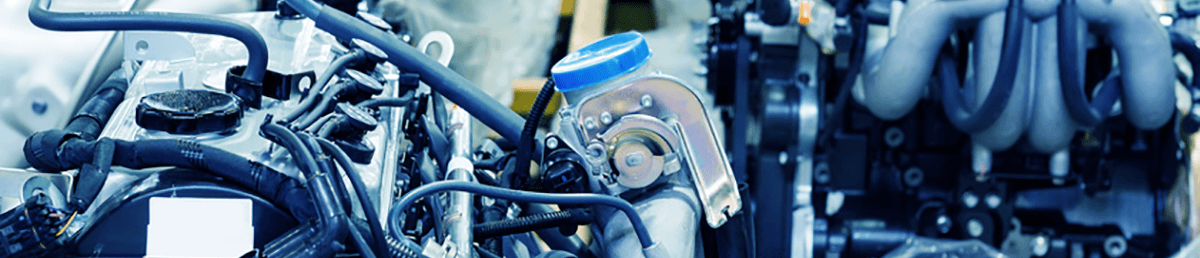2016年01月29日
インダストリー4.0最新動向、日本・ドイツ・アメリカが目指す未来とは
インダストリー4.0の最新動向、日独米それぞれの取り組みを比較・考察する
2016年インダストリー4.0最新動向
「IoT(Internet of Things:モノのインターネット)」や「インダストリー4.0」という言葉については、既に知らない人がいないほど一般的になりました。
こうした取り組みは、2020年には世界で250兆円以上、国内でも20兆円以上の経済効果を生むという予測もあり、大きなビジネスチャンスにつながると言われています。

ドイツが産官学で取り組むインダストリー4.0や、米国でゼネラル・エレクトリック(GE)など企業連合が取り組む「インダストリアルインターネット/IIC(インダストリアル・インターネット・コンソーシアム)」を睨みながら、2015年は日本でも政府や企業などがこれに取り組み始めました。
日本政府は、ロボット革命イニシアティブ協議会(RRI)やIoT推進コンソーシアム(スマートIoT推進フォーラム/IoT推進ラボ)、学術系では日本機械学会から派生したインダストリアル・バリューチェーン・イニシアチブ(IVI)などを設立しています。
また、企業がそれぞれ独自にグループを組織してIoTに取り組みはじめています。特に自動車や産業機械など日本の製造業は、こうしたドイツや米国の動きに強い危機感を抱いており、製造業(ものづくり)とICT技術の融合という、これまで想定していなかった取り組みには戸惑いも見られます。
しかし、ドイツや米国の取り組みや活動を調べて比較分析した結果、ドイツと米国ではその取り組みに違いがあることがわかってきました。

ドイツが目指しているのは、「ドイツの製造業を世界標準にすること」です。欧州経済が停滞し、ドイツ以外の欧州諸国が財政赤字に苦しむなか、ドイツ政府は中国やアジア市場などに目を向けてドイツ経済の成長を維持してきました。
しかし、日本企業や米国企業との競争も激しく、自動車や産業機械などでは米国企業や日本企業のみならず、新興勢力の中国・アジア企業が存在感を増しています。
ドイツでは、中堅中小企業が製造業を支える構造となっているため、中国やアジアが生産の中心になると、ドイツの中堅中小企業では日米の大手企業に対抗できないと危機感を抱いていました。
そこで、ドイツが新しいものづくり「インダストリー4.0:第四次産業革命」を起こし、これを世界標準『デジュールスタンダード』としてドイツが主導すれば勝てると考えたのです。ドイツが提唱するインダストリー4.0では、「Smart Factory(つながる工場)」というコンセプトで工場間、製造ライン間をネットワーク化して情報共有するコンセプトを掲げています。
一方、米国が目指しているのは、「米国がデジタル化(CPS:サイバーフィジカルシステム)とオープン・イノベーション(前述のIIC)で世界をリードすること」です。
これは、ドイツが掲げるインダストリー4.0に似ていますが、製造業だけを対象としているのではなく、ヘルスケアや運輸、エネルギー、インフラ、資源開発など幅広い産業を対象としています。
また、米国政府が主導するのではなく、GEやシスコ、インテルなど企業連合(IIC設立は2014年3月にGE、インテル、シスコ、AT&T、IBMの5社が創設、その後200社超に拡大)を組んで活動しています。
エンジンや車両など、機械(マシン)にセンサーを搭載してネットワーク化し、マシンのデータを収集分析して効率化やムダを減らし、コンピュータ側でマシンを制御、遠隔操作して自動化、省人化を実現しようとしています。
こうした技術が、実質的な世界標準(=デファクトスタンダード)となって世界市場を握ることが狙いです。
そのなかでもGEは、事業ポートフォリオを大きく組み替えて、巨額の資金と製造業の強みをベースに、米国が圧倒的な強みを持つICT技術を融合した新しい製造業のビジネスモデル構築を実現しつつあります。
その存在感は圧倒的で、GEグループのソフトウェア部門(GEソフトウェア)が提供する産業用基本システム“Predix(プレディクス)”を武器に、IT企業トップ10入りも時間の問題と言われています。
ちなみに、2015年のGEグループソフトウェア事業の売上高は50億ドル(約6000億円)ですが、2020年には、その3倍の150億ドル(約1.8兆円:IT第3位の独SAPと同等規模)に引き上げるとしています。