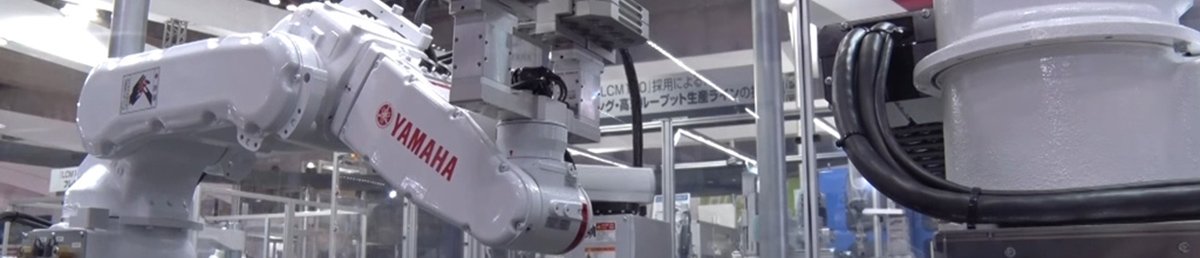2016年12月15日
インダストリー4.0最新動向、日本・ドイツ・アメリカが目指す未来とは
ヤマハ発動機ロボットビジネスのキーマンが語るIoT戦略「競争の軸は規格ではない」
ロボットをシステムとして完成させるシステムインテグレーター不足が問題
──このシステムが生まれた背景として、日本の工場にはどのような課題があると感じますか?
村松氏:
ファクトリーオートメーション(FA)におけるロボットの主戦場は、10年以上前から塗装と溶接で、FA用のロボットの出荷金額の約40%を占めています。
なぜこの分野かというと、全工程におけるロボットが占める割合が9割以上なのが溶接と塗装だからです。つまり、ロボットの仕事時間が長い領域はロボット化しやすいのです。
一方、我々のカバーする領域は自動組み立てです。これは、組み立て作業そのものよりも、その周辺にある部品のピックアップや、運搬などの作業時間が長く、そこを効率化しない限り、ロボット化の恩恵が十分に受けられません。このシステムの課題は、周辺作業の高速化が要求され、システム全体の効率化が求められます。

──周辺作業というのをもう少し詳しく教えてください。
村松氏:
自動化ラインでは、ネジ締めや接着剤の塗布は時間にして2秒くらいです。この作業は人がやってもロボットがやってもそれほど時間は変わりません。しかし、モノを第1工程から第2工程に流すのは、従来であればコンベアーに乗せて、流して、セットする流れで、時間にして3秒から5秒ほどかかります。そうすると組み立てにおけるロボットの実作業時間は、50%を切ってしまうわけです。
これに対して、モノの移動を高速化するロボットがあれば、実作業の時間は同じでも、周辺の作業時間を1秒に短縮できます。これにより、作業効率は高まり、ロボットの稼働率が上がります。
──お客さまのFAへのニーズについてはどう捉えていますか。
村松氏:
我々の業界には大きく3つのプレイヤーがいます。我々のようなロボットメーカーとそれを使うお客さま(スマホメーカーや自動車メーカーなど)、そして、その両者の間で重要な役割を担う自動化設備メーカー、すなわち「システムインテグレーター」がいます。
ロボットは売って終わりではありません。製造現場におけるお客さまのニーズに応じて、ロボットをシステムとして完成させて初めて自動化が実現できるわけです。現在の日本の製造業が抱える最大の懸念事項は、ロボットを出荷しても、システムのセットアップが追いつかず、メーカーであるお客さまに届かないという問題です。大手のメーカーはそれでも社内にこうした人員を抱えていますが、特に深刻なのは中堅・中小のメーカーです。
──システムインテグレーターのキャパ不足はなぜ起こっているのでしょうか。
村松氏:
システムインテグレーターは極めて広い総合技術力が必要とされます。ロボットの知識だけではなく、製造ラインについての知識や、どういうソフトで制御するかの知識。そうしたノウハウやスキルのある人材を確保することも大変ですし、会社を経営しながら脈々と人材を育成していくのは時間もお金もかかることです。
一方で、資金繰りは厳しくなりがちです。というのも、お客さまとの商談がはじまり、ロボットを購入し、組み立てて調整して、納品、検収と入金までに短くて半年、長くて2年かかることもあります。高額なロボットの費用も含め早めに資金を回収する必要があります。
それに耐えられるだけの体力がないと、ビジネスを継続していくことが難しくなるのです。実際、リーマンショックの時も数多くのシステムインテグレーターが倒産しています。日本のものづくりを支えているのは中堅・中小企業であり、それを支えるシステムインテグレーター不足は早急に解消するべき重要な課題だと考えています。
我々の新システムはこうしたロボットのセットアップにかかる人、カネ、時間を従来よりも圧倒的に圧縮することを可能にします。システムによっても異なりますが、当社の推奨環境であれば、コストと工数を最大で約50%削減できる可能性があります。
競争の軸は規格ではなく規格の上に流す「データ」。独自規格にはこだわらない
──業界における規格の標準化の動きについては、どのように見ていますか。
村松氏:
個人的には、正しい手段、正しい方向を選ぶことが大事だと考えています。規格の中身を精査して、将来の主導権を握ると判断すれば、それに乗る方が現実的です。私は、規格は競争の軸にならないと思っています。
競争の軸は、あくまで規格の上に流すデータで、データをどうモノに展開するか、そのユーティリティの部分です。規格はあくまでプロトコル変換のためのもので、本来はそれ自体に価値はありません。それどころか、独自規格にこだわれば、そこにプロトコル変換が生まれ、それが積み重なると膨大なコストになるわけです。
──今後、工場のIoT化を進めていくために大事なことは何でしょうか。
村松氏:
一番大事なのは「それによって何がしたいのか?」という目的の部分です。たとえば、工場のコストを30%削減したい、そのために何のコストを下げ、ベストな手段は何なのか、それを考えていくのが大事です。

もう一つはセグメンテーションです。自動化に最適なガバナンスの単位というのがあります。たとえば、工場のありとあらゆるモノを全てEtherCATで繋いで一元管理するという話を聞くこともあります。しかし、あるレイヤーから上はEtherCATでつなぎ、それより下のレイヤーはローカルな規格で構成したほうが効率的という場合もあります。
大事なのは、どのくらいの大きさを制御の一つのパッケージとするか、それをどういうネットワーク単位で繋ぐか、その設計が自動化には大事になってきます。
ロボット関連事業の売上を2020年度までに約200億円に倍増させる
──村松さんはIoTをどのように捉えているのでしょうか。
村松氏:
インターネットにより、時間と距離の制約がなくなりました。IoTは、データを含む「コト」といわれる領域が、インターネットで交換可能になり、距離や時間といったコスト要因を圧縮することだと感覚的には捉えています。
では、距離と時間の圧縮が可能になったことで、何が必要とされるかというと、モノは直接的にはケーブルで送ることができないのでから、モノをデータ(コト)に変換する必要があるわけです。そこで、従来のモノも、今まで以上に、インテリジェンスが必要とされるように変わっていくのだと思います。
──今後、ものづくりはどう変わっていくと思いますか。
村松氏:
ものづくりは積み重ねです。その意味で、一気に飛躍することはなく、長年のコア技術の積み重ねが大事だと思っています。今後はますます「人が作るべきもの」と「そうでないもの」の2極化が進んでいくと見ています。
たとえば、伝統的な職人さんの世界は、今後も高度な技が伝承されるべきであり、ロボットへの置換は困難。一方で、「そうではいもの」の領域では、さらに自動化が進んでいきます。というより、自動化せざるを得ない状況です。
──中国などの新興国もロボット分野に力を入れていますが、どのように見ていますか。
村松氏:
脅威ですね。彼らとは技術レベルでは拮抗しているものの、ノウハウの部分はまだ我々に一日の長があります。
そして、もう一つ、新興国との最大の差はインフラの部分です。ここでいうインフラとは、ものづくりを支える部品サプライヤーの製造能力、品質の高さです。日本の大手製造業が成り立っているのは、中小のサプライヤーの水準が、海外に比べて極めて高い点にあることを忘れてはいけません。
──IM事業としての今後のビジョンをお聞かせください。
村松氏:
IM事業部のうち、ロボット事業の売上は現状で約100億円ですが、これを2020年度までに、200億円に成長させたいと考えます。今年はEU離脱等もあり、円高の影響を受けていますので、今後の世界情勢の変化などを踏まえ、平均成長率を120%くらいに設定しています。そして、このペースを維持できれば2020年にちょうど2倍になります。
新商品のリリースと合わせて、新たなプラットフォームのコンセプトに含まれる商品を来年以降、拡充していく予定です。
──本日は、貴重なお話をありがとうございました。
(インタビュー=ビジネス+IT 編集部 松尾慎司)