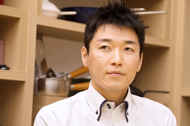2017年03月09日
AI対談:料理家×データアナリスト
”おもてなし”の心が、料理のベース 「AI」との協調は、おいしさの隠し味
料理の楽しさをサポートするAIに期待
──料理をAIと一緒に作るようになれば、料理とは何なのかが改めて問われそうです。
栗原氏:
料理は食べるだけが目的ではなくて、作る楽しさもある。そのプロセスや時間はかけがえのないものだと思います。私が出演している「男子ごはん」でも、そのことを大切にしています。出張なども多いため、訪れたご当地での新しい発見や、使ったことのない食材なども取り入れて、レシピを考え、おいしい料理を紹介する。その番組を見て共感してくれた人が、今度はレシピをもとに家族や大切な人と楽しみながら料理してくれたらいい。
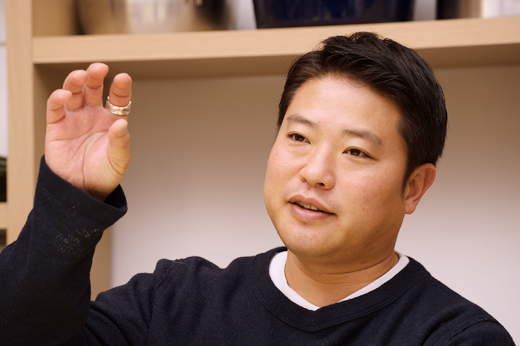
山本:
同感ですね。経験や体験としての料理は大切にしたい。子どもと一緒に作ったり、友だちと料理を持ち寄って味比べする時間は何にも代えがたい。料理の世界でのAI活用は、先ほどお話が出たように、体調管理や健康バランスを考えることが、人と協調していく形の1つかも知れませんね。
──今後チャレンジしてみたいことを聞かせてください。
栗原氏:
「ゆとりの空間」では料理やそれを食べるシーンまで提供できるように心がけています。今後は食材に関してもポリシーを打ち出したい。私たちが求めるものを安定的に供給してくれる生産者の方と協力して、全国の野菜や肉、魚などを提供していくことを考えています。レシピを活かして加工品を作ったりして販売することを目指したいです。
山本:
今お話をされたビジネスについては、農産物の生産管理の自動化や出荷予測、物流の最適化などにAIの出番がありそうです。旬の食材を切らさず供給するには、いつ・どこから・どれだけの量を・どうやって調達するかが重要です。AIを使えば、そういうことを無駄なく、効率的に行えます。実際に、NECでは農業や物流へのAIの活用も進めています。また、店舗での顧客の動線の分析も行っていますので、「ゆとりの空間」が経営するショップで、商品の配置やインテリアのレイアウトなどもサポートできるかもしれません。

栗原氏:
今回お話を伺って、AIが思った以上に進化していることがわかりました。レシピ作りにAIを活用すれば、新しいアイデアも生まれるかもしれない。味覚センサーや食感センサーをうまく使っていけば、おいしさも追求していける。その一方で、料理の醍醐味は誰かのために作ってあげたいというおもてなしの気持ちであり、作る過程の楽しさにある。食べる相手を思いながら、AIと協力して料理を楽しむ。そんな未来が実現するといいですね。