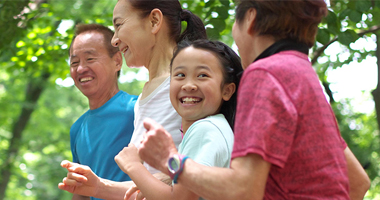楽しみながら健康になる!大田区で始まった新しい健康事業とは?
いかに健康な状態で長生きするか。これは多くの人にとって共通の願いだといえるだろう。現在、日本では、認知症や生活習慣病、関節疾患などのために介護を必要とする人が増えており、単に長生きをするだけでなく、いかに「健康寿命」を伸ばすかが大きな課題となっているのだ。こうした課題に対して、デジタルツールを活用して、「健康なまちづくり」を進めているのが大田区だ。どんな背景のもと、どのような施策を行っているのか。区政13年目を迎えた松原 忠義区長に話を伺った。

松原 忠義 氏
東京・大田区で始まったユニークな健康ポイント事業とは
──松原区長はご就任以来、区民の健康増進のための施策に力を注いで来られました。どのような思いで、「健康なまちづくり」を推進されているのでしょうか。
大田区は今、大きな変化の時を迎えています。2020年の世界的なスポーツイベント開催を控え、現在、羽田空港に隣接する羽田空港跡地第1ゾーンでは開発が進められ、2020年には第一期事業のまち開きも予定されています。
一方で、区民の価値観や生活様式は多様化し、地域課題も複雑化の一途をたどっています。また、人口構造の変化やグローバル化など、社会情勢の変化も加速しており、大きな時代の波を捉えた取り組みをしっかりと進めていく必要があります。
これからは、従来の取り組みの成果をしっかり検証した上で、健康・福祉・子育て・教育・産業・環境など、各分野で切れ目のない施策を展開していきたいと考えています。とりわけ「生涯を健康に過ごす」ことは、すべての区民の願いです。その願いを実現するためには、一人ひとりの主体的な健康づくりを促すだけでなく、健康に暮らせる社会環境を整えることが大切です。したがって、行政と地域が連携して、区民の誰もが健康づくりに励める社会環境を整えることが、今後は大変重要になってくると思います。
──昨年、大田区では「おおた健康プラン(第三次)」を策定されました。その中で、①区民一人ひとりの健康づくりを推進、②地域や企業と連携した取組の推進、③地域の特性に応じた取組の推進、の3点を挙げています。
このプランを策定するに当たり、大田区では区民に対してアンケート調査を行いました。その結果、「健康寿命が男女とも東京都の平均以下」、「国保被保険者の生活習慣病の有病率が23区で一番高い」、「若年層に運動習慣のない人が多い」、「がん検診の受診率が、国の目標である50%を下回っている」など、さまざまな健康課題を抱えていることがわかったのです。
そこで、大田区では課題解決に向けて、「キラリ☆健康おおた」というプロジェクトを発足させました。そして、「適度な運動」「適切な食事」「休養」「喫煙・飲酒のリスクと理解と行動」という4つのアクションと、健康診断・がん検診の受診を推進することになったのです。
2019年12月には、「おおた健康プラン(第三次)」の中核的な事業として、「はねぴょん健康ポイント」事業がスタートしました。これは、18歳以上の区内在住・在勤の方を対象にしたもので、ポイントを貯めながら、楽しく健康づくりをしてもらおうという取り組みです。

──はねぴょん健康ポイント事業を考案されたきっかけは何だったのでしょうか。
健康ポイント事業については先行する自治体もあり、さまざまな成果が認められています。区民が健康になれば、自治体の医療費の適正化が進み、区の経済が活性化して、まちが元気になる効果もある。その意味で、「まちづくり施策」の観点からも、健康ポイント事業には大変関心を持っていました。
大田区は、地域特性に合った健康施策を展開したいと考えています。そのためには、データに基づく分析が必要です。それも、単に既存の行政データを活用するだけでなく、若い世代も含めた区民の”生の声”を集めて、施策に反映できるようなサービスが必要だと考えました。
はねぴょん健康ポイント事業では、スマートフォンのアプリを通じて、自治体と区民が直接つながることができます。この仕組みを活用して、区内の大学や企業と連携し、参加者の健康状況や健康課題を科学的に分析しながら、より効果的な施策を展開していきたいと考えています。これは昨今注目を集めているEBPM(Evidence Based Policy Making:科学的根拠に基づいた政策立案)の推進にもつながっています。
区内の観光を楽しみながら、ゲーム感覚で健康増進
──大田区ならではの健康ポイント事業をつくるに当たって、工夫された点をお聞かせください。
この事業では、気軽に楽しく、「区の魅力」を感じていただきながら、継続的な健康づくりに取り組んでいただくための工夫を凝らしました。
その1つとして、今回整備したのが区内を巡る25のウォーキングコースです。例えば、池上本門寺や平和島の旧東海道を通って浜辺を散策するコース、馬込文士村を巡って文士や芸術家の作品を堪能するコース、9月に開館した勝海舟記念館にも立ち寄ることができる洗足池周辺コースなど、区内の観光や文化を体験しながらウォーキングが楽しめる25のコースをアプリに搭載しました。
また、多くの方に楽しんでいただけるように、区内300カ所にスタンプ・スポットも設けました。その中には、スポーツや観光・文化・産業・高齢福祉・障がい福祉・銭湯など、さまざまな店舗や施設が含まれています。スポットに行くとポイントが貯まり、そこに隠れているさまざまな「はねぴょん」を集めることができます。歩いたり、大田のまちにでかけていただいて貯めたポイントで応募すると、抽選で景品が当たる仕組みになっています。景品には、「お土産100選」の品や伝統工芸品、「はねぴょんグッズ」の詰め合わせ、区内共通商品券や入浴券など、大田区ならではのものを用意し、ポイントをたくさん貯めれば、便利家電などが当たるチャンスもあります。
運動したり、歩いたりすることは大事ですが、こちらの一方的な“押し付け”や“楽しめないもの”であっては、一過性のものにとどまり、長く続けることは難しい。そこで、はねぴょん健康ポイント事業は、高齢の方や障がいがある方、親子連れなど、幅広い方々に楽しんでいただけるものになっています。
今年度の参加目標は1万人。はねぴょん健康ポイント事業がスタートして1カ月がたちますが、ダウンロード数は3,000を突破しました。
このアプリでは、自分の歩数や消費カロリー、歩行時間・距離、目標達成率を見ることができるので、それがよい動機付けになるのではないでしょうか。ランキングの機能もあるので、「自分の歩数は区内で何位」ということもわかります。目標やランキングは性別、地域、年代別に設定されており、無理なく続けられるようになっています。区の職員も積極的に活用しているのですが、世代を超えて「今日は何歩歩いた?」と会話が弾み、よいコミュニケーションツールになっています。
大田区ならではの事業に楽しく参加しながら、区民が健康になって、まちの活性化につながれば──そんな思いで、大田区らしい健康まちづくり事業を推進していきたいと考えています。

──区民の健康づくりのため、企業や地域と連携する意義について、どのようにお考えでしょうか。
「人生100年時代」といわれますが、大田区にも、100歳超の方が426名おられます(2019年)。生涯の多くの時間を地域や職場で過ごすわけですから、健康施策も「地域」や「企業」と連携して考えていく必要があります。
まず、地域との連携についてお話ししましょう。
広い大田区では、区内を「大森地域」「調布地域」「蒲田地域」「糀谷・羽田地域」の4地域に分けて管轄しています。今回、「おおた健康プラン(第三次)」の策定にあたって区民にアンケート調査をしたところ、地域ごとに健康特性が異なっていることがわかりました。
例えば、蒲田地域は平坦で、自転車の利用が多く、下町の気風が残る庶民的な土地柄です。飲食店も多く、区民同士が交流する場には事欠かないのですが、健康に対する意識は高いとはいえないのが実情です。
一方、健康の指標となる数値が、比較的よかったのが調布地域です。隣近所の付き合いもあり、山坂が多い地形なので、自然に足腰が鍛えられているわけです。健康施策を実効性の高いものにするためには、こうした地域特性を、きめ細かく施策に活かしていくことが大切です。
現在、大田区では、区内全域に対して均一的な健康施策を行っていますが、今後は地域と連携しながら、地域特性を反映した施策を行う必要があると考えています。今回のアプリでは、健康にかかわるデータが取得できるので、それも更なる健康増進施策に活用できるはずです。
──一方、企業との連携はいかがでしょうか。
昨今の複雑かつ高度化した行政課題に対応するためには、企業の協力が不可欠だと考えています。このため、区の企画部門には公民連携部署を設け、民間企業の強みを活かした行政サービスの効率化や強化に取り組んでいます。
企業のCSRによる支援をいただくことで、行政施策の可能性は大きく広がります。SDGs(持続可能な開発目標)という観点からも、両者が現場レベルで目標を共有し、連携・協力していくことが、今後はより一層必要になると考えています。
2020年、HANEDA INNOVATION CITYが誕生
──大田区における公民連携の好例が、「HANEDA INNOVATION CITY」です。この開発事業においては、健康に対してどのような取り組みを計画されているのでしょうか。
HANEDA INNOVATION CITYは、羽田空港に隣接し、天空橋駅に直結した5.9ヘクタールのエリアです。これは、羽田空港跡地の第1ゾーンに複合施設を整備する事業で、「新産業創造・発信拠点」の形成を掲げ、公民連携によるまちづくりが進められています。
今後のスケジュールとしては、2020年にまち開きをし、2022年には全施設の開業を目指します。2022年に開業する先端医療研究センターでは、臨床機能を活かしたスマートヘルスケアに取り組み、ビッグデータの利活用による予防医療などを展開する予定です。また、まちに集まるさまざまな企業や、区内ものづくり企業との交流を促進し、医工連携にもつなげていきたいと考えています。


2020年夏にオープンするHANEDA INNOVATION CITYは「文化産業」と「先端産業」の融合がテーマ。グルメ、日本文化、ライブイベントといった体験を提供するほか、研究開発施設、先端医療研究センター、会議・研修施設なども整備される
──HANEDA INNOVETION CITYの流れをふまえ、区内産業の可能性についてはいかがお考えでしょうか。
今、大田区では、町工場や中小企業が横の連携をつくり、医療機器や福祉機器などの開発製造を行っています。最先端医療の分野では、数多くのハイテク技術が必要とされるので、今後は、区内の中小企業がその技術力を活かせるチャンスも大きく広がるでしょう。その意味で、大田区が蓄積してきた技術と医療が結びつき、医工連携が加速すると期待しています。
もちろん、健康や医療だけでなく、観光や福祉も充実した、お年寄りや障がい者に優しいまちをつくっていきたいと考えています。
──最後の質問です。今回、はねぴょん健康ポイントで業務を委託されたNECについて、感想をお聞かせください。
NECさんとは、以前から行政系システムなどの分野で関わりがあり、そのネットワーク技術やコンピューティング技術は高く評価しています。はねぴょん健康ポイントの開発も短期間であったにもかかわらず、区の考えを十分に具現化した、親しみやすく使いやすいアプリをつくっていただきました。他自治体の類似アプリと比べても、その内容や機能において大変良いものができたと感じています。
PR活動でも特色を発揮され、12月に区役所で開かれたオープニングイベントでは、歩行姿勢測定システムや健診結果予測シミュレーションをご提供いただきました。また、昨年11月には大田区総合体育館にて女子バレーボール部「NECレッドロケッツ」のホームゲームを開催、今年の2月にはNEC府中・玉川吹奏楽団によるコンサート開催など、区民の方が楽しめるイベントを通したPR活動も企画されています。
これらに加え、IoT、AI、ビックデータ、ロボットなどの最新技術を活用して、今後も新しいまちづくりやイノベーション創出のためにご協力いただけるよう期待しています。