2016年05月30日
地方創生現場を徹底取材「IT風土記」
佐賀発、職人芸継ぐ「デジタル技術」、 有田焼の逆襲はじまる
試行錯誤で生み出す革新
2001年には、まだラピッドプロトタイピング(高速試作)積層造形法などと呼ばれていた初期の3Dプリンターの導入に踏み切った。この3Dプリンターを使えば、3次元データを元にスライスして出力した紙を一層ずつ重ね合わせることができ、これに石膏を流して型をつくることができる。
しかし、紙製なので防水処理をしていても石膏を流すと多少変形してしまうという問題が浮上した。焼き物は陶土を焼くと30%ほど体積が小さくなるのであらかじめ縮み方を計算した大きさをデータ入力できるが、出来上がった石膏型の表面にはどうしても紙を重ね合わせた段差が残る。傾斜面を手作業で磨く手間もかかった。
それなら「コンピューターの数値制御(NC)で石膏の塊から直接型を切り出してはどうか」。液状の石膏を型に流し込むのではなく、まず四角いブロック状の塊をつくり、乾燥させて削るという発想の転換だ。精度も上がるし表面の粗さという欠点も克服できる。3Dデータのソフトウェアには米国製のを見つけた。価格が10万円前後なので、零細業者でも手が届く。
国や佐賀県からの資金援助を得て2003年、センターに機械が入った。新方式で作った石膏型は、デザインデータとの誤差がわずか0.02ミリ前後だった。

2年後には組合や地元企業の一部も機械を購入し始め、産地に復活の兆しが見え始めた。しかし、3Dデータをつくったり、NC切削機を扱える人はまだ少なかった。「従来の型屋さんがやっていた仕事をセンターがカバーしているのが実情。機械を買えば何とかなるではなく、使いこなせるようになるのが大事」と副島さんはオペレーター不足を痛感した。佐賀県陶磁器工業協同組合の原田元理事長も、「単にデータを打ち込むだけでなくて、焼成の収縮率や型から抜ける形状かどうかの判断ができる、焼き物の基礎知識も要る。両方ないとうまくいかない」という。
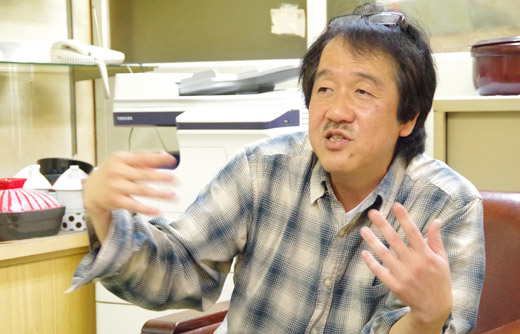
そうした課題を乗り越えるのは若い世代だ。ソフトの使い方を独学してデジタルデザインの陶磁器ビジネスに乗り出す若手経営者も出てきている。磁器ブランドを展開する224porcelain(佐賀県嬉野市、ニーニーヨンポーセリン)は昨年、約50万円を投じて小型のNC切削機を購入した。辻諭社長は「工程のスピードが速まり、コストも製品ひとつにつき2~3割カットできるので、3ヶ月くらいで元がとれました」と胸を張る。屋根や煙突が取り外せて箸置きになる小さ家などユニークなデザインの陶磁器が特徴だ。2012年に創業したばかりだが、昨年の売り上げはすでに3000万円に達したという。

