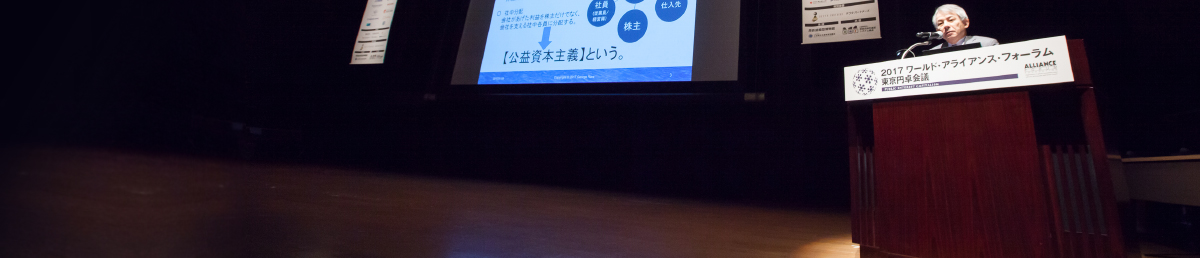
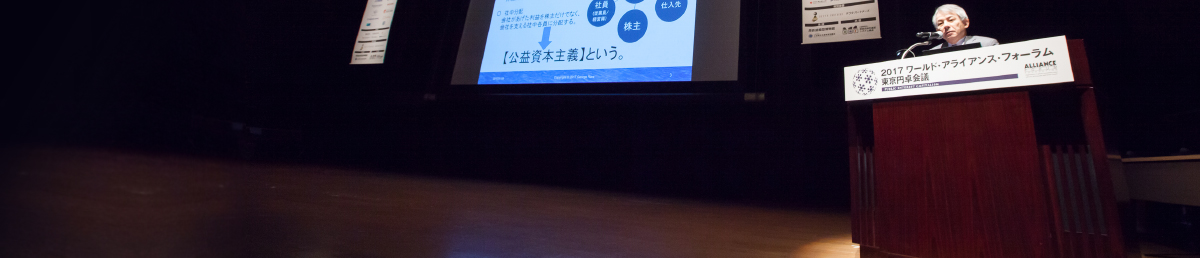
企業はいかにしてイノベーションを創出すべきか
──持続的成長に向けた「公益資本主義」の取り組み
2015年に国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」において、2030年までに貧困を撲滅し、持続可能な社会を実現するための指針としてSDGs(持続可能な開発目標)が設定された。SDGsにもとづき、各国政府、企業、団体は、さまざまな取り組みや仕組み作りを進めている。持続可能な社会構築への重要性が増すなか、企業が成長し続けるために必要なものは何か。
「公益」と「イノベーション」の関係性
企業は、経済的、社会的に持続可能な発展を遂げるために、まず何よりも絶え間のないイノベーションを続けていかなければならない。そして、企業がイノベーションを続けるためには、短期的な視点にとらわれた経営ではなく、中長期経営・投資を視野に入れた取り組みが必要になる。
「企業は商品の改良だけをやっていても尻すぼみになるので、次々と新しい事業を作っていく必要があります。しかし新しい事業は、どうしても中長期的にしか成果を出せないものが多くなります。このため、短期的には利益が出なくても『リスクを取ってチャレンジする』という企業家精神を鼓舞する仕組みを作ることが重要です」と話すのは、『公益資本主義』の提唱者でありアライアンス・フォーラム財団代表理事で内閣府参与の原丈人(はら・じょうじ)氏だ。

「公益資本主義」とは、”企業は社会の「公器」であり、その目的は事業を通じて「公益」に貢献することである”という考え方。
原氏は、2017年11月9日に日本橋三井ホール(東京都中央区)で開催された「2017ワールド・アライアンス・フォーラム(WAF)東京円卓会議」において、会社の持続的発展における中長期投資の重要性を指摘。長期的経営・投資を促す環境を作ることで、企業が果敢に新しい事業に挑戦し、イノベーションを創出できると話した。
また同会議では、イノベーション創出における「公益資本主義」の役割や具体的な活動などについても報告した。
企業に公益性が求められる背景とは
アライアンス・フォーラム財団によると、公益に貢献する上で、企業が果たす役割が近年飛躍的に増加しているという。
同財団の報告によると、国家の歳入よりも大きな売上高の企業が増加傾向にある。国・地域の歳入、企業の売上の世界トップ100を集計すると、1960年代ぐらいまでは圧倒的に国・地域の歳入のほうが大きかったが、2000年になると「国・地域:企業=49:51」、2015年時点では「国・地域:企業=31:69」になったという。
例えば米国ウォルマート社の売上高はスペインの歳入より大きく、同様にトヨタ自動車はインドを、サムスン電子はトルコを上回っている。また欧米の企業を中心に株主への利益の還元率が増加傾向にあるというデータも報告された。
このように、大企業を中心に企業の存在感と役割が増すなかで、短期的利益ばかりを追求するような投資は投機的バブルを誘発しかねない。その結果、富裕層が富を総取りするような”Winner takes all”につながり、貧富の差が激しくなることが懸念される。
原氏は、過度な株主資本主義の問題点を指摘しつつ、「経営陣と従業員が協力し合って会社を成長させる」という企業文化を持ち、公益資本主義を実践する土壌がすでにある日本が主導的立場を取り、世界の経済を変えていくべきだという。
「技術の蓄積」でイノベーションを生む
原氏は、公益資本主義の理念を日本が主体となって実現するために、内閣府参与の立場で、政府の未来投資会議構造改革徹底推進会合において、「中長期にわたって企業が無から有を作る制度」を提言している。企業の公益への貢献と、さらなるイノベーション創出が促進される基盤作りに力を入れている。
「会社は社会の公器であり、事業を通じて社会に貢献するべきです。会社が事業を通じて社中(社員、株主、仕入れ先、顧客、地球、地域社会)全体に利益をもたらしたり貢献したりすることによって会社の付加価値を上げ、その結果として株主にも利益がもたらされるのでなければなりません」(原氏)
社中に対して持続的に利益を分配するためには、企業が十分な利益を上げることが前提で、そのためにもイノベーションが必要であると付け加える。
WAF東京円卓会議では、企業経営者、経済団体代表などが登壇し、活動報告やディスカッションが行われた。そこでは様々な業界の企業関係者からも、イノベーションの創出には研究開発分野などへの中長期的な投資が必要だという意見が出た。
「お客様にとって有益で、世の中に貢献できるような製品を作るためには、どうしても長い時間をかけながら研究開発に取り組む必要があります。当社は短期的なものではなく、中長期的な目線を持って経営しています。ステークホルダー(社中)に対して『笑顔の総和』をどれだけ拡大していけるかが、世の中から受け入れていただける重要な価値観なのだと認識しています」(自動車メーカー関係者)
また大手化学メーカーの関係者は、「世の中で必要とされている新しい価値を提供するために、当社は企業文化として、『技術の蓄積』を心がけています。経営者は長期視点に立った経営を行い、現場の技術者も、2年や3年の短期ではなく、長期的な視点で技術を蓄積して事業に取り組む必要があります」と、製造業におけるイノベーション創出に必要な要件として、「技術の蓄積」を挙げた。 株主偏重では、2年や3年も利益が出ないと、「そんな金があるなら配当に回してくれ」、と株主から言われるかもしれない。

「短期主義」是正のための具体策とは
さらに、WAF東京円卓会議では、イノベーションを阻む「短期主義」の是正策として、「四半期決算開示義務の廃止」などが示された。
すでに、アライアンス・フォーラム財団の働きかけで、「四半期決算短信での業績予想欄記載義務」が廃止されているが、日本の企業は横並び意識が強いため、いまだにほとんどの企業が財務部門などの人的リソースを投入して、業績予想を記載しているという。
原氏が訴える四半期決算そのものの開示義務をなくすことには、さらなる人的負荷軽減や中長期的な経営を押し進める狙いがある。ディスカッションでは「なかには小売業など、月ごと、あるいは景気動向によって頻繁に売上高が変わるような業種では、四半期よりも高い頻度で業績の開示が求められるケースもある」という話や、「通期予想を開示するなかで、今年あるいは今現在取り組んでいる活動など、投資家とコミュニケーションが図れる面もある」という現行の制度下での工夫も見られた。「四半期開示を廃止する際に必要なのは企業の説明責任の拡充かと思います」という大手インフラ企業関係者の意見にもある通り、単なる定量的な情報開示の廃止ではなく、中長期経営を進めるために、定性的な情報をより活用した株主とのさらなるコミュニケ―ションが必要となるだろう。
日本を世界最高の「難病医療先進国」に
原氏は、公益資本主義の国づくりへの応用として、医療分野での国家戦略的イノベーションの推進を政府に提案している。
それは「2050年までに、日本国民として生まれた人は、天寿を全うする直前まで健康でいられるような社会を構築する」というものだ。
現在、先進国を中心に、従来の医療では治療や回復が不可能だった難病や重度の障害を対象に、革新的技術を使った治療法の開発を目指そうという気運がある。日本でも再生医療の分野で、iPS細胞を使った心不全の治療法などの目覚ましい発展があり、こうした流れを他の医療分野にまで拡大して、日本を世界最高の「難病医療先進国」にしようという狙いだ。
原氏は「この分野は日本に十分な勝ち目があります。薬事法が改正され、再生医療分野においては『安全性が確認された段階で新しい治療法を患者に適用してもよい』という早期承認の方針が決まりました。この流れを再生医療だけでなく、他の難病治療分野にも拡大していくことで2030年までに、他国では治療できない難病でも日本なら治る可能性があるという国際的な評価を確立するのが当面の目標です」と説明。実現すれば、少なくとも毎年3.3兆円ほどの経済効果が期待できると試算している。
原氏は「こうした変化を通じて、若い人たちが日本や自分の将来を不安に思わなくてもいいような、誇りを持てる国づくりが進められるはずです」と語っており、中長期投資が活発に行われる仕組み作りや、イノベーションを通じた革新的技術と新たな基幹産業の創出を実現する方向性を示した。
企業のSDGsに対する取り組みについては、下記の記事をご覧ください。

2021年08月30日