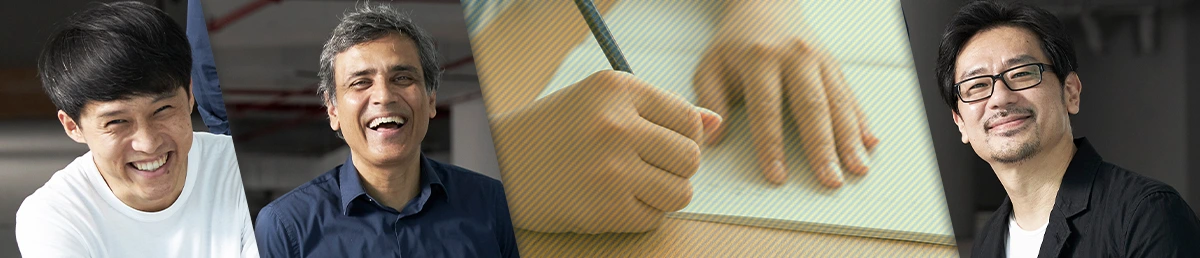
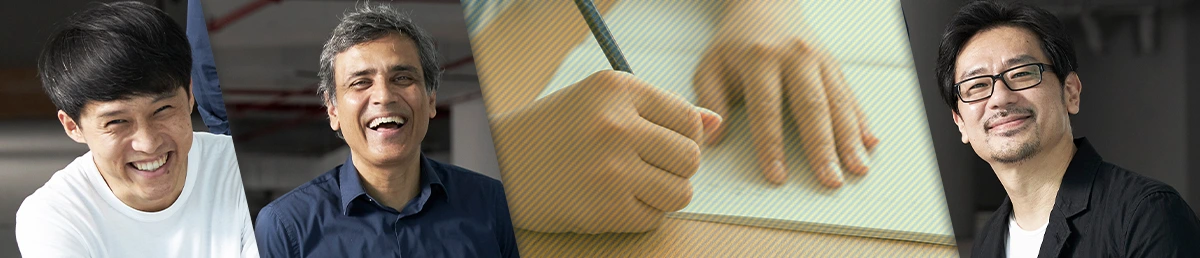
多重知覚理論が教育の物差しのスタンダードを変える
所属する外資系広告会社「マッキャンエリクソン」でイノベーションとグローバルのネットワークを創造し、自らのキャリアを切り開いた松坂俊。現在はマレーシアと東京の2拠点生活をしながら、エドテックベンチャーTOY EIGHT(トイエイト)のCCOとしても多忙な日々を送る。松坂に起業に至るまでの軌跡や、マレーシアの魅力、海外で働く醍醐味などを語ってもらった。

松坂 俊(まつざか しゅん)氏
「TOY EIGHT(トイエイト)」創業者/CCO
マッキャンマレーシア クリエイティブ ディレクター
1984年、東京都生まれ。イギリスのファルマス造形芸術大学(現ファルマス大学)グラフィックデザイン科イラストレーション専攻を卒業後、2008年、外資系広告会社マッキャンエリクソンに入社、媒体本部に配属。2013年に制作本部に転籍。2015年、マッキャン・ワールドグループ国内外の1980年~2000年代前半生まれのメンバーで構成されるユニット「マッキャン・ミレニアルズ」を立ち上げる。2017年よりマレーシアと日本の2拠点生活を開始。2018年よりエドテックベンチャーTOY EIGHT(トイエイト)を創業。
"未来のエジソン"発掘のために
2018年、「すべての子どもが才能を発揮できる世界をつくる」をミッションに、エドテックベンチャー「TOY EIGHT(トイエイト)」をマレーシアにて創業しました。民間の教育市場規模が約28兆円と、今後も急速に成長が期待される東南アジアを中心に、独自のセンシング技術やAIを用いて遊んでいる子どもの才能を分析し、それぞれの才能や資質にあった教材を提供します。
具体的には以下のふたつを合わせたサブスクリプション型サービスを予定しています。
(1) TOY8(トイエイト)
ショッピングモール内にプレイグラウンド(遊び場)をつくり、遊んでいる子どもをセンシングして「多重知能理論(The theory of multiple intelligences)」に基づき才能の傾向を分析。分析結果に応じて最適な遊びを提案する。
(2)TOY8 BOX(トイエイトボックス)
工作キットやアプリ連動型の知育ゲームなど、上述の分析に基づき個々人の才能に最適化された教材や知育キットなどが毎月届く。
ベースとなるプレイグラウンドは、ハーバード大教授のハワード・ガードナー氏が1983年に提唱した、人間の知能を8つに分類する「多重知能理論」をもとに設計されています。
これは「人間は誰しも単一ではなく複数(現在は8つ)の知能を持っている」という考え方で、現在、世界各国の教育現場やビジネスの世界で取り入れられています。
トイエイトでも、「すべての子どもは生まれながらに天から授かったGIFT(才能)をもっている」という前提に立ち、開発している「GIFT(Gifted Intelligence Finding Technology)」という知能を可視化する技術を使って、その才能をテクノロジーで可視化することに挑戦しています。例えば、「あなたの子どもは音楽とロジカルシンキングが高い傾向があるから、このおもちゃやこのコンテンツで遊ぶと、より学びを広げたり深められたりします」というように。
子どもは、本質的には学ぶことが好きなはずです。しかし、得意な学びかたというのが個々によって違う。プログラミングを習うにしても、動画で見せた方がいい子と、教科書で学んだ方がいい子と、会話をしながら学んだ方がいい子がいる。もしくはグループワークが向いている子もいれば、ひとりが適した子もいる。そのような能力の傾向値を見ながら、楽しく、挫折なく、没頭できる環境をつくり出していくというのが、トイエイトの基本の事業内容です。

実は僕自身、子どものころは勉強が得意ではありませんでした。後年、イギリスの美術大学に通っていたときに軽度のディスクレシア(識字障害)であることがわかり、腑に落ちました。要するに文字で学ぶのが苦手な人間だったんです。社会人になってから脳波のプロジェクトを担当したときも「情報処理の仕方は視覚と聴覚の体を動かすことの組み合わせ」という考え方を知り、測定してもらったら耳と体を動かすことによる処理が断然優位でした。そんな僕のようなタイプの人間に「教科書と板書だけで学べ」というのは、身長が低いのに「バスケットをやれ」と言われているようなもの(笑)。いま現在、読書は移動中などにオーディオブックや電子書籍の読み上げ機能を使っていますが、摂取量も増え、内容も以前よりずっとよく記憶できるようになりました。
現在、子どもの未来を大きく左右する学校の試験やIQテストなどの評価システムは、多重知能理論で考えると知能の20〜30%ほどしか評価できないそうです。もちろん、学校の試験やIQテストで優秀な成績を収められるというのも、素晴らしい才能のひとつです。ただ、そこでスコアが悪ければ「劣等生」というのは違うのではないかと。いまの学んでいるすべての子どもたちは、未来のエジソンやレディーガガ、スティーブ・ジョブズ、マイケル・ジョーダンかもしれない。単一な教育の評価のスタンダードをテクノロジーで多様なものさしに変えることで、その子どもたちの才能と可能性を発掘し、最大化すること──それがトイエイトのビジョンなのです。
マレーシアを選んだ理由とは?
マレーシアで起業することになったのは、現在も所属している外資系広告会社「マッキャンエリクソン」で「McCANN MILLENNIALS (マッキャン・ミレニアルズ)」を同僚2名と立ち上げたことが大きいです。
マッキャン・ミレニアルズとは、マッキャン・ワールドグループの国内外・グループ会社間の枠を超えて、ミレニアル世代(1980〜2000年代前半生まれ)が所属する集まり。広告制作にとらわれないプロジェクトの企画と実施が主な活動で、日本では現在約90名が、アジア太平洋地域の若手社員と連携しながら活動しています。
マッキャン・ミレニアルズを立ち上げてからは、僕自身の仕事は広告案件が減り、大企業の新規事業のクリエイティブディレクションに携わることが多くなりました。その中で大企業とベンチャーのそれぞれのメリットやデメリットを間近にし、起業への興味を膨らませていたことと、2017年7月に家族とともにマレーシアに移住をして東京との2拠点生活を始め、マレーシア政府の仕事を通じて石橋正樹(トイエイトCEO)と知り合ったこと。この2つのタイミングが重なり、石橋からトイエイト設立に声をかけてもらったとき、子どもが生まれたばかりだったのもあって、「教育だったら人生をかけてコミットできる!」と創業メンバーに加わりました。

住む場所としてマレーシアを選んだ理由は、大学時代のイギリス生活で、狩猟民族である欧米人とゲームを戦うのは自分には不向きと判断したから(笑)。それで親日国も多く、世界の成長センターである「東南アジア」を視野に入れ、英語が通じ、リビングコストが安く、安全性が担保され、教育のオプションが多数あるマレーシアに決めました。
マレーシアは、日本の半分ほどの費用で質の高い教育を受けられるインターナショナルスクールが多数あります。また、いわゆる欧米の名門校の分校もあれば、起業家マインドをもった子どもを育てるアントレプレナースクールもあります。そのアントレプレナースクールでは、子どもの脳波や能力傾向をある程度診断し、その子の適性を先生が理解するという努力がされています。教室の後ろにはクッションが積み上げられ、座っているのが辛くなったら、クッションに座って本を読んでもよいとのことでした。テストではある程度の点数を取るという「義務」と、自分に合った勉強方法が許されるという「権利」のバランスが大事なのだそうで、こんな学校が自分の子ども時代にあったらなあ……と本気で思いました(笑)。
また、マレーシアはマレー系67%、中国系24%、インド系8%の人口比で3つの民族が共生している他民族共生国家であり、言語や文化が多種多様です。彼らのお互いに対する気の遣い方や融和の仕方は、無理やり努力している感がないんです。煙草の分煙のように、分けるところは分ける。一方でオフィス環境など物理的に共有するところは、それぞれのルールを尊重する。見ていて非常に気持ちがいいですし、日本人として学ぶことが多いです。
会社軸、社会軸、個人軸が重なるスイートスポット
マッキャン・ミレニアルズを立ち上げたころは、「ビジネスパーソンとして日本の市場にだけしか対応できない人材でいいのか」という不安や焦りがずっとありました。マレーシアに住んでから3年、大きな成果を出していないので偉そうなことは言えませんが、アフターコロナ後のグローバルという観点から言えば、日本と海外での2拠点生活が増えるのではないでしょうか。
日本でもテレワークやリモートワークがここまで一般化されましたし、これからは転職をするように住む国を変えてもいいと思うんです。自分の経験から言えば、それほどおおごとではないし、いままでと変わりなく生活できます。もし、海外に対して少しでも意識があるなら、これを機に身軽に動いたほうが活躍の幅がグッと広がるのではないかと思いますね。
よく「ミレニアル世代は社会意識が高い」と言われますが、濃淡はあれど、実際優秀な人たちは社会貢献意識も高い気がします。また優秀な同世代は利益だけを探求する企業を選ばなくなっているとも感じます。マッキャンでも数年前、グループのミッションを「WE HELP BRANDS PLAY A MEANINGFUL ROLE IN PEOPLE’S LIVES(私たちはブランドが人々の生活の中で、意味のある役割を果たせるようお手伝いをする)」とあらためて発表がありました。このミッションの「MEANINGFUL ROLE=社会に意味のある役割」に若い社員が共感していて、仕事における重要な視座としてもつようになったのは、非常によいアップデートだと思います。
僕の中にも、会社軸、社会軸、個人軸というのがあります。それぞれ、所属する企業に対する貢献、社会に対する貢献、自己の成長なのですが、その3つの軸のメリットが重なるところ──スイートスポットを僕は常に探してきました。マレーシア2拠点生活と起業はその探索の結果ですし、これからもその3つの軸を意識して、所属している会社に利益をもたらし、社会に対するインパクトを出し、これまで以上に自己成長しようと思っています。
取材・構成:堀 香織
編集:ORIGINAL Inc.



