

ヘルスケアの最前線で活躍する有識者が語る
2030年のあるべき医療のカタチとは?
超高齢社会を迎えた日本では、医療への期待と重要性がますます高まっている。これまでの常識にとらわれず、いかに患者中心の医療を実現していくか――。これは医療業界のみならず、社会的に重要なテーマだといえるだろう。そのヒントを探るべく開催されたのが、「NECヘルスケア・ライフサイエンス有識者会議」だ。2021年12月より3回にわたって開催された「Medical Care WG(ワーキング・グループ)」では、医療の現場を知る有識者たちが今後の医療やヘルスケアについてディスカッションを行った。そこから見えてきた2030年の近未来医療の青写真について紹介したい。
誰もが意識せずに健康でいられる社会に
日本で暮らす約3人に1人が65歳以上の高齢者になるという2030年に向けて、医療変革の機運が高まりつつある。
その根幹にあるのは、家族を含めた「患者中心の医療」だ。「自分では判断が付かず、どの病院や診療科に行けばいいかわからない」「通院は大変だし、待ち時間も長い」「自分の病気を理解した上で、納得した治療を受けたい」――。これまでの不安や不満を解消しつつ、新しい期待にも応えていく医療である。

産学連携研究センター 特任教授
藤本 康二氏
これまでの医療と近未来医療の違いについて、東京医科歯科大学 特任教授の藤本 康二氏は、鉄道を例に次のように述べる。
「昭和30年代の鉄道会社は『運ぶ』ことが使命であり、乗客は乗車率200%でギュウギュウ詰めにされても『乗れる』ことを良しとし、今の価値とは全然違っていました。医療においても、がんになったから何とか手術してもらいたいとの要望から、今後は個人別の三次予防が切っても切れない話になると思います」
それでは2030年では、どのような新しい医療が可能となるのか。その1つが「健康を意識した生活が、きわめて容易におくれる」状態だ。デジタル技術を上手く活用すれば、これまでと異なるアプローチが可能となる。
例えば、検査結果や診断結果、治療内容などのすべての医療データをデジタルで保存すれば、地域の医療機関で横断的にそれを活用できるようになる。さらに生活者がウェアラブルデバイスを身に付けることで、脈拍や血圧などのバイタルデータをリアルタイムに把握できる。
もちろん、このようなデータの診療活用の仕組みづくりや法整備などクリアすべき課題もあるが、実現すればICTツールによって不調の兆しを早期に発見でき、より正確な医師の診断に役立つ。例えば「今日は血圧が高いから、入浴は暖かいうちにするか、止めた方がいい」「脈拍が頻繁に乱れるから、かかりつけ医に連絡してください」といったアドバイスも可能になる。つまり、自分では気付かないことをフォローして健康に留意することができるようになるわけだ。
ウェアラブルデバイスを身に着けるだけなので、生活者の負担も少ない。デジタルの仕組みが生活者を常に見守りしてくれるわけだ。
データは医療の質を高め、医師の教育にもつながる
治療は患者の病気を治したり生活の質を高めたりすることが目的だが、そのデータは患者個人の治療だけでなく、医療全体の発展にも貢献する。
例えば、こんな症状のときはこういう治療法の効果が高い。この薬を飲んだらこんな副反応が出た。電子カルテに記録される多くの診療データを収集・集約し、分析していくことは、同じ病に苦しむ誰かにとって貴重な情報になる。
「医療機関はセキュリティ専門家による高度なデータ管理を実施し、未来の日本人、あるいは世界の人のためにデータをもっと活用していく必要があるのではないでしょうか」と国立国際医療研究センター 医療情報基盤センター長 の美代 賢吾氏は訴える。 現在の治療は過去の誰かのデータのおかげで成り立っている。同じように現在のデータが未来の医療を創り出すとの考えだ。
もちろん、データ管理のルールづくりが必要不可欠になるが、将来的には遺伝子情報の活用による創薬支援や個人の疾病リスク解析の可能性も広がる。「データを単なる診療支援ではなく、創薬や生活者のライフスタイル変革につながるものに発展させていくことが大切です」と美代氏は続ける。

医療情報基盤センターセンター長
美代 賢吾氏

橋本 千香氏
治療の映像も有用な医療データである。ガラサス代表の橋本 千香氏が提案するのが、バーチャルトレーニングの活用だ。「その分野で一流といわれる医師の手術を撮影し、見たい角度から画像が見えるようにすれば、医療従事者は自分の職場で一流の技術を追体験できます」。
最近はコロナ禍により、医学生や研修生が臨床に立ち合う機会が減っているという。最新のデジタル技術を駆使したトレーニングはこうした経験不足を補い、休職中の医療従事者の復職にも有効な手立てとなるだろう。
そこではAI活用の期待も大きい。検査の実施や判読には、知識や経験によって大きな差が出てくることがある。そこをAIがサポートできるようになれば、見落としや見間違いを減らし、医師の経験値も上がる。藤本氏は「AI支援は医療行為の高位平準化に寄与します」という。
患者負担のない医療を実現する
こうした変革が進むと「それぞれの患者に最適な医療が受けられる」社会の実現が近づいてくる。その未来予想イメージは次の通りだ。
まず患者が予約時間に病院玄関へ到着する。すると生体認証カメラで自動的に受付が完了し、診察室番号と現在地からのルートが自身のウェアラブルデバイスに音声と画像で伝えられる。患者側の手続きは一切不要だ。医療機関は予約時のオンライン問診によって患者ごとの検査や医師の診察時間をスケジューリングしているため、病院内では待つことなく診療が始まる。医師の説明は診察後に動画で家族にも提供され、繰り返し確認できる。処方箋データは登録済みの薬局に送られ、支払いは電子決済されるので、患者は診察が終わり次第すぐに帰宅できる。帰宅後は指定の時間・場所に処方薬が配達される。「体調の悪い方であれば、病院内の移動も一苦労です。そんな時、患者は院内を歩き回ることなくさまざまな検査が受けられ、ストレスフリーな治療を受けられる。そんな世界を思い描いています」と藤本氏や美代氏は話す。
AIの活用によって医師と患者の最適なマッチングも進む。「治療先を探したくても、現在はインターネット上の医療機関情報が限定的で乏しいため、口コミに頼らざるを得ないのが現状です。ネット上の情報を充実させ、マッチングアプリなども整備した上でAIを活用すれば、身近なデバイスに問いかけるだけで、自分が求める条件に合った医療機関や医師がリストアップされ、診療予約も可能になるでしょう。さらに、患者に寄り添う医療も広がります。例えば、がん患者の場合、遺伝子の変異は一人ひとり異なるし、個人の体質によって治療効果や薬の副作用にも差が生じます。こうした際にAIが情報を補い医師をサポートすれば、個の患者をより深く知り、医師と患者のコミュニケーションでその人に合った治療や投薬が可能になります。そうなれば担当医が仮に300人の患者を診ていたとしても、一人ひとりの患者にとってはその医師は自分だけの先生になる。患者に優しい、個人を大切にする素晴らしい医療を実現できるでしょう」と橋本氏は期待を込める。
データの標準化、医師の診療業務の負担軽減が課題
ここまで2030年の近未来医療の可能性を見てきたが、その実現には解決すべき課題も多い。例えば、電子カルテは病院内の利用に閉じていることが多い。患者中心の医療を実現するためには、地域の医療機関や介護施設との緊密な連携が欠かせない。そのためにはデータの標準化も必要になる。
長い待ち時間の後に診察を受けても、医師はPCを見ているだけで患者と殆ど目を合わせない――。診療の不満としてよく聞かれるエピソードだ。原因の1つに医師の忙しさがある。診療結果を正確に記録し、症状も正確に把握しなければならない。その結果、電子カルテと向き合うことに終始してしまう。この記録や情報取得にAIを活用すれば、医師の負担を減らせる。音声のテキスト化技術は既に実用段階にある。これを活用すれば、入力・記録の手間を大幅に軽減できる。
「医師が診察に十分時間をかけて一人ひとりの患者に向き合ってくれることで、患者は『この医師は信頼できる』と感じられる。医者と患者の協力的な関係という本来の医療の在り方は丁寧な説明と対話によって築かれるのです」と橋本氏は指摘する。
「医療の最前線にいる医療スタッフが『私が医療者になったのは、こういうことがやりかったからだ』と思えることも大切です」と藤本氏は訴える。
課題解決と新しい医療の実現にはICTの活用が不可欠
医療現場の課題を解決し、現実とのギャップを埋めていく――。NECは、この課題解決に主体的に取り組み始めている。2030年に目指す姿を定義した「NEC 2030VISION」の中で、ヘルスケア・ライフサイエンス事業を成長戦略の柱の1つと位置付けた。2019年には定款を変更し、創薬事業にも本格的に参入した。

北瀬 聖光
このヘルスケア・ライフサイエンス事業のコンセプトとして、NECは「live as you。あなたを知り、あなたらしく選ぶ」を掲げる。「ここには『あなたらしく生きてほしい。そのために、あなた自身が健康を管理し、あなた自身の状態を知り、あなた自身が治療の方法を選べる未来を実現したい』という想いが込められています」とNECの北瀬 聖光は語る。先に触れた近未来医療はNECが目指す姿でもあるわけだ。
既に次々と取り組みも行っている。世界トップクラスの顔認証技術を応用し、がんの診断を支援する「内視鏡画像解析AI」を開発したのはその一例だ。2021年には日本と欧州で、大腸がんを対象とした内視鏡画像解析AIの販売も開始している。
「医療、予防、介護は密接に関連しています。健全な情報が医療にきちんと伝わり、それが介護にも予防にも伝わっていく。3つの領域をしっかりつなげることもNECの務めと考えています」と北瀬は話す。その土台となるのはNEC自身の長年にわたった取り組みである。NECの50年以上にわたる医療事務システムの開発に加えて、電子カルテシステムなどの提供を通じて病院業務の効率化にかかわってきた。さらに2019年からは、創薬事業にも本格的に参入するなど、社会課題の解決への貢献へとその軸足を向けている。ここで得られた知見が大きな役割を果たすことになるだろう。
ただし、ビジョンの達成はNECだけで成し遂げることはできない。大学・研究機関やベンチャー、医療機関、民間企業、省庁・自治体など多様なパートナーとの連携を深め、業界・業種の垣根を越えた価値づくりを加速させていく考えだ。特に、これからの医療は電子ネットワーク産業、ICT産業の協力が欠かせなくなる。美代氏は「今の医療の延長線上で考えるのではなく、ICTが新しい医療を創っていくとの気概を持って欲しい」と期待を寄せる。
適切な医療で病気を克服し、患者や家族が、より快適に暮らせるように生活の質を高めていく。同時に医療従事者の負担を減らし、医療の質の向上も目指す。自分らしく生きることのできる社会は誰もが願うことだ。この実現に向けたチャレンジは力強く歩み始めている。
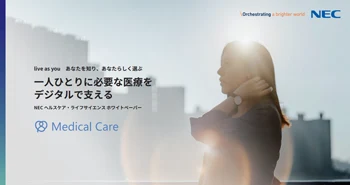
NECヘルスケア・ライフサイエンス ホワイトペーパー
「一人ひとりに必要な医療をデジタルで支える」
藤本 康二氏
国立大学法人 東京医科歯科大学 産学連携研究センター 特任教授
【略歴】
2003年 経済産業省商務情報政策局医療福祉機器産業室長
2008年 商務情報政策局ヘルスケア産業課長(サービス産業課から組織変更)
2011年 内閣審議官 内閣官房健康・医療戦略室 次長
美代 賢吾氏
国立研究開発法人国立国際医療研究センター 医療情報基盤センター センター長
【略歴】
1998年 東京大学医学部附属病院 中央医療情報部
2013年 東京大学医学部附属病院 企画情報運営部 部長、東京大学大学院医学系研究科 准教授
2015年 国立国際医療研究センター 医療情報管理部門 部門長
2018年 国立国際医療研究センター 医療情報基盤センター センター長
2020年 国立高度専門医療研究センター医療研究連携推進本部
データ基盤課 課長(併任)
橋本 千香氏
ガラサス合同会社 代表
【略歴】
2001年 米国にてGallasus.Inc, 設立
2019年 日本にてガラサス合同会社設立



