

日本の製造業や職人にも再興の光、今注目のビジネスモデル「D2C」が求められる理由
業界が変わるビジネストレンド
日経トレンディが毎年発表しているヒット予測特集の2021年版「ヒット予測ランキング」で、「マイクロD2C」が10位にランクインした。メーカーが顧客にダイレクト販売するビジネスモデルを意味する「D2C(Direct to Consumer)」は、なぜ注目を集めているのか。日本のD2C市場の先端を進む企業へのインタビューから、時代が求める新しいリテールの姿が見えてくる。
D2Cの加速がブランドやメーカーの二極化構造をつくる?
D2Cは、ECサイトやアパレル業界を席巻するSPA(製造小売業)と混同されることが多いが、実態は大きく異なるものだ。ECは自社製品に限らず仕入れたものを販売するモール型であり、SPAは実店舗を中心に販売しているのに対して、D2Cは自社のオリジナルブランドを自ら企画・生産し、Webやテクノロジーを活用して販売することである。販売だけに限らず、商品企画からマーチャンダイジング、マーケティングなどにもテクノロジーを駆使して、顧客起点の経営・業務体制を構築することもD2Cの特徴だ。マイクロD2Cは、個人など小規模で展開するD2Cビジネスを指す。
「D2C企業は2020年から急激に増えてきました。スタートアップが次々と立ち上がり、大企業もD2Cをビジネスに取り入れようと動いています。この流れは止まらないでしょう。今後、マイクロD2Cで小さなブランドが世の中に大量に出回ると、中規模の企業が苦しくなり、大規模と小規模の二極化構造が加速すると考えています」と、日本におけるD2Cの先駆けであるFABRIC TOKYOの取締役執行役員CFOの三嶋 憲一郎氏は語る。

取締役執行役員CFO
三嶋 憲一郎 氏
2014年に設立されたFABRIC TOKYOは、オーダーメイドのビジネスウェアを提供している。サービスをリリース後、大都市圏に実店舗を展開。採寸を店舗で行い、体型データをクラウドに保存すれば、オンラインでオーダーできる。新ブランド「STAMP」では、無人店舗での3Dスキャンによる採寸サービスの実証実験も進めている。
同社はオンラインと店舗のオフラインを融合したOMO(Online Merges with Offline)を取り入れたサプライチェーン垂直統合型D2Cであり、他のD2Cとは一線を画す。すでに10万人以上の体型データを蓄積し、順調に拡大中だ。

「D2Cは販売も小売や卸に依存せず、あらゆるバリューチェンを統合できるため、それを実現できれば競争優位性を獲得できます。例えば、アップルはいち早く世界でD2Cを実践してきた企業だと考えられます。ハードはアップルストアだけでなくあらゆる店舗やオンラインストアで購入できます。ユーザーはアップルIDに紐付けされるため顧客データを直接取得でき、その上でさまざまなコンテンツ、アプリをオンラインで販売し続けます。クラウドサービスやコンテンツプラットホームを持ち、ハードからOSまですべて独自に持つ垂直統合型の典型です。当社もアップルを1つの目標としています」と三嶋氏はいう。
D2Cに最も重要な指標はLTV
顧客から見たD2Cのメリットについて三嶋氏は「ブランドと直接コミュニケーションを取るので、自らのニーズや課題をとらえてくれますし、LTV型なので、さまざまな利用シーンが快適になるはずです」と語る。
顧客が長期にわたって商品やサービスを使い続け、どれだけ利益をもたらしてくれたか総額を算出するLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)は、D2Cにおいて重要な指標だ。従来のビジネスでは売上というある時点での指標と向き合ってきたが、LTVはどれだけ長く顧客とブランドの関係性を構築できるかを問う。
「売上を目標にすると、例えば店舗スタッフはなるべく多く売ろうとしてLTVが落ちていきます。LTVを指標とする場合、各業務に合わせて要素分解する必要があります。店舗では顧客の体験満足度の向上を指標にするなどの工夫が求められます」
LTVを指標とするためには、業務や組織のあり方から顧客起点に変える必要がある。例えば商品やサービス開発は顧客ニーズをとらえて、その課題を解決するため「マーケットイン」の考え方に徹しなければならない。仮説を立てて短期間で開発し、実際に使ってもらいながら改善を続けていく「アジャイル開発」的な手法を取り入れるわけだ。いいものをつくれば買ってくれるという発想は通用せず、高速でPDCAサイクルを回すことがD2Cのカギである。
「D2C最大のボトルネックが組織です。縦割り組織は通用せず、顧客の不満の元になります。そこで、多種多様な人材をフラットに連携してマネジメントしなければなりませんが、それは至難の業です。FABRIC TOKYOにおいても組織運営は試行錯誤の繰り返しです。部署やグループでそれぞれの力学が違うので、常にずれることを前提にLTVを要素分解しながら、各現場で修正していくことが経営サイドに求められます。そのために、組織のサーベイは必須です」
国内でも大手企業がD2C企業を買収したり、出資したりするケースが増えているが、大手自身がD2C化することは、組織やカルチャー、既存の流通などの問題から難しいという。しかし、コロナ禍の影響もあり、市場のD2C化は加速している。それに従い、店舗のあり方や出店方法も見直しが進むだろう。「世界的にもOMO型のD2Cが主流になっています。ただし、やみくもに出店するのではなく、店舗の楽しさや顧客体験価値を提供する本質的な役割が再認識されるでしょう」と三嶋氏は今後を占う。
D2Cでメガネ業界を牽引
D2Cによって、既成概念を打ち破った企業もある。2012年にメガネ専門のECサイトを立ち上げたオーマイグラスだ。従来、メガネのオンライン販売は難しいといわれていた。なぜなら、視力矯正のためのメガネはレンズの度合わせ(検眼)が必要となるからだ。検眼した後、実際に試着して掛け心地を確かめてから購入するメガネには店舗がどうしても不可欠だった。
「D2Cというビジネスモデルを採用したのは、優れた日本のメガネを世界に向けて売りたいと考えたからです。もちろん、ネットだけでは完結しないし、難しさがあることも承知していましたが、逆に障害は参入障壁になるので戦いやすいと思いました」と、オーマイグラスの代表取締役社長を務める清川 忠康 氏は語る。

代表取締役社長 清川 忠康 氏
オーマイグラスは、直営店舗も併設するOMO を採用。D2Cでありながら、オンライン販売にこだわることなく顧客視点のマーケティングを展開したことで、いまや国内最大規模のメガネECサイトに成長している。9店舗を展開する直営店で検眼すれば、以降はサイトで選んだ商品を直接自宅に送ってもらえる。5本まで5日間試着することも可能で、もちろん店舗への取り寄せも可能だ。コロナ禍においても対前年比50%増の勢いで会員数を伸ばしており、また、リモートワークが増えた影響で、ブルーライトカットなど高付加価値のレンズを求める顧客が増えているようだ。
卸や小売店を介さない分、手頃な価格で提供できるが、清川氏は品質には絶対の自信を持っている。日本が世界に誇る眼鏡の産地である福井県鯖江市の職人とのコラボレーションで開発、製造しているメガネが同社の売りだ。オーマイグラスが展開する3つのブランドのうち、主力の「Oh My Glasses TOKYO」が売上の大半を占め、鯖江ブランドのメガネも提供する。「TYPE」はアメリカのクリエイティブ・エージェンシーと組んで立ち上げたブランドで、書体から着想したデザイン性が特徴である。「PAGE」はサッカー選手の本田圭佑氏とのコラボで、サングラス中心のブランド。売上の2%は世界の恵まれない子供達に寄付される。
本田氏はオーマイグラスのビジョンに共感し、出資もしている。そのビジョンとは、日本発のメガネブランドを確立すること。清川氏は日本のメガネにはそれだけの価値があるという。「世界に誇れる日本の製品のなかでも、高級メガネは日本に優位性があります。特にメタルフレームは高評価です。私たちはそれをブランド化し、世界にアピールしていきたいと思っています」
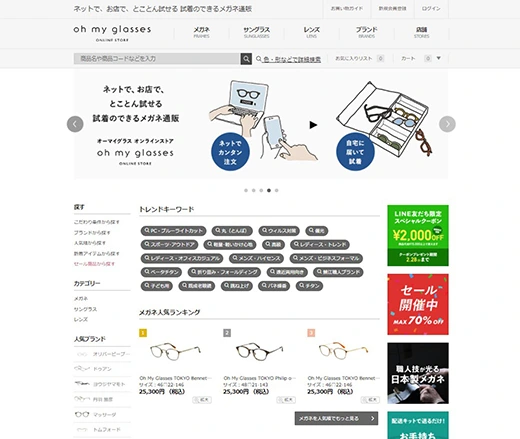
デジタルマーケティングで日本の屈指の職人技を活かす
清川氏が日本のメガネに対して強い思いを持つようになったのは、海外生活経験からだ。特に、3度目のアメリカ留学でスタンフォード大学ビジネススクールに入学したときのこと、自分の掛けているメガネがコミュニケーションのきっかけになったことが印象に残った。
「もともとメガネ好きではあったのですが、スタンフォード大のときに、メガネをオシャレだと褒めてもらいました。コミュニケーションのきっかけにもなりますし、その人のイメージを一瞬で変えるファッションアイテムになるので、ポテンシャルを感じました。しかし、時計などに比べるとおカネを使う人は少ないので、メガネを掛け替えて楽しむ文化や価値観を創り出したいと思いました」
MBAを取得後、帰国してオーマイグラスを設立。オンラインストアを開設するとともに、鯖江市の職人たちのもとを何度も訪ね、一緒に新しいメガネブランドを立ち上げようと訴えた。清川氏はデジタルによる職人技の活性化を狙っていた。日本経済の底力は中小製造業にあると考えているからだ。当初は誰も相手にしてくれなかったが、少しずつ理解者が増え、現在ではオーマイグラスが分析した顧客データをもとにメガネを企画・開発するようになった。「職人さんの多くはものづくりの技はあっても、お客さまの分析まではできていない場合が多いです。そこで、当社のデジタルマーケティングを使って商品企画することで、Win-Winの関係性を築くことができました」
D2Cのメリットは、顧客と直接つながれることだ。購買行動から趣味、嗜好が見えてくると、その顧客に合った商品を提案できる。「メガネは頻繁に買ってくれるものではないので、お客さまと長く継続的な関係性を築く必要があります。そのためにメルマガやSNSなど、接触するチャネルを持つことが重要です。それを通して細かくデータ分析し、地道にPDCAを回していきます。特別なコンテンツをつくる必要はなく、投稿頻度や内容、回数などを細かくチューニングしています。その運用の仕方がノウハウといえます」
現在、オーマイグラスは世界15ヵ国に販売しているが、まだ既存の流通経路を使っている。今後は日本のようなD2Cモデルを導入する予定だ。ブランドを世界に広げつつ、日本のメガネ業界の進化にも協力したいと清川氏は将来の展望を語る。「苦戦しているチェーン店も多いので、支援するソフトやノウハウを提供し、メガネ業界のDX化推進に貢献したいと考えています」
メガネのような成熟した業界でこそD2Cは活性化の核となり得る。清川氏は自社の国内シェア争いよりも海外でのブランド力を高め、デジタル化の遅れた業界を後押ししようとしている。経験や勘といった属人的なものではなく、データで顧客を知るD2Cは内需喚起のカギを握り、旧来の製造業や職人と連携することで、ものづくりの再興にもつながるだろう。
「デジタル世代を中心に、意味のある消費」志向が今後強まると三嶋氏は予測する。社会貢献も含めて企業のミッションやビジョンが問われるなかでD2Cは格好のモデルである。「ただし、インターネットビジネスとは違って、ものを売るD2Cは急激に拡大しません。中長期を見通し、地道に自らのビジネスモデルを磨き込む強い意志と努力が必要です」と最後に警告する。勃興するD2C企業に対して、既存のメーカーや大手ブランドはどのような戦略をとるのか。今後の動向に目が離せない市場である。

