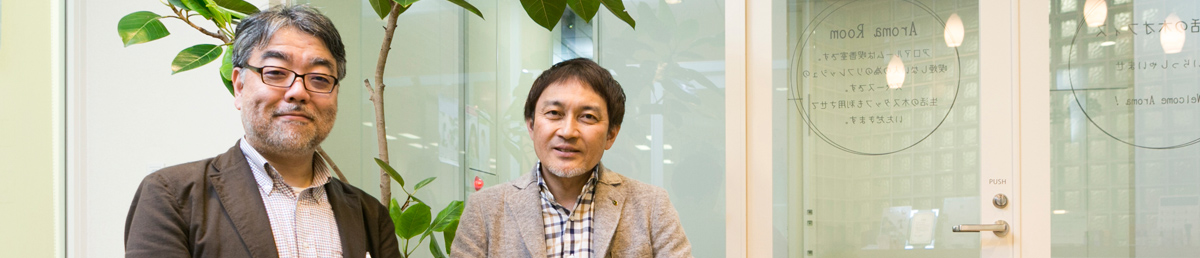2017年03月28日
三宅秀道のイノベーター巡礼 新しい問いのつくりかた
日本にアロマテラピー文化を普及させた「生活の木」の開発力
ポプリブームの火付け役となった少女漫画
重永氏:
きっかけは、佐藤まり子先生に少女漫画誌『なかよし』(講談社)で、ポプリ作りをする少女が主人公の『あこがれ♥二重唱』を連載してもらったこと。この作品が当たり、小学校の女の子たちの間でポプリ作りがブームになります。その時代にポプリの材料を買えるのはうちしかなかったもので、わざわざ東京に出てきて買いに来たり、あるいは当時から始めていた通信販売で注文したり。材料をブレンドすることによってオリジナルポプリが作れるという行為が、コトとして子どもたちに受け入れられました。「この商売はいけるな」と肌で感じた瞬間でした。
三宅氏:
材料は、どのように仕入れていたんですか? それまでとは、まったく別の事業ですよね。
重永氏:
調べてみると、世界にはハーブの流通があったんです。ただし、ポプリとしてではなく、食品として。ハーブティーはドイツでも飲まれていましたし、香辛料としても流通しています。ですから、はじめはハーブを食品として流通させている問屋に分けてもらっていたのですが、それを小分けするのは、うちでやらなければいけません。そのときに、瑞浪の存在が生きてくるわけです。最初はすべて手詰め小分けしてもらいました。だいたい販売価格が20グラムで250円~300円くらいだったでしょうか。子どもたちが、百円玉を握りしめて買いにきていました。
あとは、よくネクタイ族のお父様方が、娘さんに頼まれて買いにきていましたね。「東京に出張するんだったら、これを買ってきて」とメモを渡され、なにがなんだかわからないまま(笑)
三宅氏:
なぜ、『なかよし』にツテがあったんですか?
重永氏:
私と同い年か、少し上くらいの年齢だったでしょうか。当時、実践女子大学の子が4人くらいアルバイトにきていました。彼女たちが漫画研究会に所属していたので、キャラクターを作ってもらい、PRに活用していたんですね。そこで、漫画が持つ力に気がつきました。そして、彼女たちのツテを使い、『あこがれ♥二重唱』の連載にこぎつけたという流れだったと思います。

三宅氏:
タイアップ契約のようなものを結んだんですか?
重永氏:
いえ、単純に佐藤まり子先生がポプリ作りを面白がってくれて、価値を理解してくれたんです。女の子は、子どもでも香水に興味を持ちますが、香水をつけるのは、親が許してくれないですよね。でも、ポプリを作ることなら許してもらえるんですよ。そこが一つのポイントでした。その時、私たちと一緒にマーケットを作っていった女の子たちが、今は母親の世代になっています。ハーブやアロマの恵みを母と子が共有して、一緒に来店してくれる親子も多いんですよ。
物欲ではなく、学習欲に惹かれる顧客
重永氏:
さらに、『あこがれ♥二重唱』では、ポプリコンテストも実施しました。「自分のオリジナルポプリを作って、ネーミングをつけて応募してください」と呼びかけ、毎月大賞を選びました。私も、コンテストの品評をしていました。ハーブの世界は奥が深いといいますか、こだわり始めたらキリがないんです。「物欲」ではなく、「学習欲」に支えられている市場だと思っています。
三宅氏:
私の知人女性にも、エッセンシャルオイル(精油)のブレンドに凝っている人がいます。混ぜはじめたら深みにハマってしまったと喜んでました(笑)
重永氏:
アロマテラピーがなぜ日本でこれほどまでに根付いたのかというと、検定試験を作ったからです。検定試験を通して、アロマテラピーをもっと勉強したい、もっと知りたいという学習欲が醸成され、さらに検定でインストラクターやアドバイザーの資格を取った人は、アロマの魅力を人に伝えたいと思うようになる。だから、こんなにもアロマテラピーの人口が増えたんです。
これもお客さんと一緒にマーケットを作っていった一例になります。コンシューマーとしての顧客だけではなく、インストラクター、アドバイザーとしての顧客も存在するということです。購買する顧客と、広めていく顧客の両方がいて、マーケットが形成されていく。そのために、全国に18校のカルチャースクール「生活の木 Herbal Life College」を運営しています。
三宅氏:
まさにエバンジェリストですね。文化の伝道者が自分から学びに来て、育って、広げてくれる。
重永氏:
そのために必要な品揃えやサービスを、我々がプラットフォームとして用意する。さらに、文化の伝道者としての顧客が、買う、学ぶ、広げるだけではなくて、社員として入社してくれることもあります。これが大きいんですよ。好きなことを仕事にしているので、企業にとってはパワーになる。弊社には、「仕事だから」と嫌いなことを仕方なくやっている社員はいません。
三宅氏:
営利組織としての生活の木の基盤には、ハーブ、アロマを愛するトライブというか、部族というか、同じ文化を愛するコミュニティがしっかりと根付いているということですね。今、資格を持っている人はどれくらいですか?
重永氏:
アロマテラピー検定の受験者は、40万人くらいです。メディカルハーブ検定も2.5万人くらいだと思います。生活の中で使う人、教える人、お店を開く人、社員になってくれる人と、いろいろな広がり方をしています。
三宅氏:
それだけ支持者がいると、どこかの政党からお声がかかりそうですね(笑)
重永氏:
いや、政治はちょっと……(笑)。ただ、我々が考えているのは、日本の人口は約1億3000万人ですが、ハーブやアロマテラピーを生活の中で活用している人は、推測ではまだ3000万人くらいしかいない。残りの1億人は知らないか、なんだか敷居が高そうだと思っている人かでしょう。ですから、まだまだマーケットを拡大できる可能性は十分にあると考えています。
文化から作っていくという伝統
三宅氏:
お話をうかがい、ハーブやアロマの文化を土から作っていくような努力があったからこそ、生活の中で普通に使われるようになったという経緯がわかりました。コンシューマーとしての顧客だけではなく、インストラクター、アドバイザーとしての顧客も重要であり、さらにはその中から社員になってくれる人も出てくるといったようなエコシステムは、後から考えれば合理性があることがわかるのですが、ゼロから始めるときには勇気が必要だっただろうと思います。

重永氏:
普通は効率が悪いと考えますよね。実際、マーケットがほとんどなく、マニアックな趣味に過ぎなかった時代に、自社生産体制や世界から調達なんて言っても原料が余ってしまいますので、経済ロットに合わないわけです。トンで仕入れてグラムで売るのが、この商売の基本ですから。
三宅氏:
トンで仕入れてグラムで売るというのは他では聞いたことがないですね。ものすごい割り算です。
重永氏:
そこで考えたのは、製販がマッチングするまで店を出さなければいけないということです。店を出し、リアルな場で魅力を伝えながら文化を広めていくしかない。30店舗くらい出店したときに、ようやくSPAがスタートしました。ドトールコーヒーだって、あそこまで店舗を作ったから、豆を現地生産できるわけです。ただし、素材だけで売っていても、ちっとも付加価値がつかないので、「用途開発」に力を入れてきました。最初は香りのポプリから始めて、ハーブティー、アロマテラピー、それからマッサージオイル、入浴剤などに展開していきました。
はじめた当初によく言われたのが、「お前たちは、こんな枯れ草をなんであんなに高い値段で売っているんだ」ということです。たしかに、知らない人が見たら、ただの枯れ草ですよね(笑)。それにコトだったり、生活シーンだったり、ライフスタイルだったりの付加価値をつける。ハーブティーを飲むことが素敵だ、生活空間の中にアロマの香りがあると精神的に充実するといった価値観を広めていかなければいけません。つまり、スパイス問屋、原料屋になっては駄目だということですね。だから、2500のアイテムを開発し、オリジナル商品を売っているわけです。製販一体にしたことで、用途開発にも幅と柔軟性を持たせることができるようになりました。
三宅氏:
先ほど、ハーブティーの飲み方を提案するときに、陶器店ノウハウが生きたというお話がありました。陶器店の時代にも、リアルな店舗で消費者や生活者の声を吸い上げていた、と。そうすると、ものは違っても、生活シーンから用途開発を構想して実体化していく手法の原型は、お父様の時代からあったということですよね。お父様の代からあった文化開発的な手法をハーブ、アロマの業態に展開させたのが、3代目の重永社長だった、ということだと思います。
重永氏:
おそらく、写真もそうだったと思います。写真を撮って、納めるなんてことは、当時は一握りの人にしかできませんでした。となると、写真を撮るという文化から作らなければいけません。しかも、製販一体でやっていたわけですから、考え方の根底は変わっていないと思っています。
三宅氏:
対象は時代が進むにつれて変わっても、スタンスは共通しているということですね。