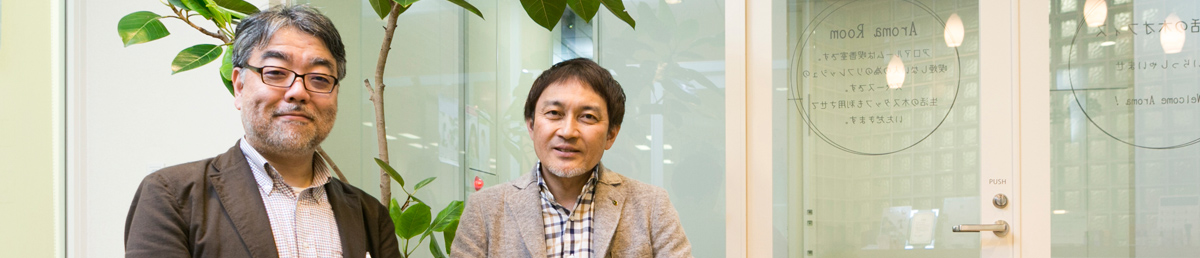2017年03月28日
三宅秀道のイノベーター巡礼 新しい問いのつくりかた
日本にアロマテラピー文化を普及させた「生活の木」の開発力
大切なのは「醍醐」という言葉
三宅氏:
生活の木らしい、用途開発の例にはどんなものがありますか?
重永氏:
お風呂に入れるバスハーブでしょうか。ハーブティーは、残ったお茶っ葉を捨てますよね。でも、そのお茶っ葉からは、まだ香りがするんですよ。そこで、お風呂に入れられないかと考えました。なにからヒントを得たかというと、ホッカイロです。あの袋の中に、ハーブを入れられないかと思ったんですね。そしたら、登戸の近くでホッカイロを作っている工場を見つけたんです。そこに頼んで、鉄粉の代わりにハーブを入れてもらったら、見事にバスハーブができあがりました。
しかし、問題が起こります。ある時にお客さんからクレームが入ってしまったんです。どんなクレームかというと、香りがしないというものではないんですよ。そうではなくて、白い浴槽がハーブの色に染まってしまったというものでした。すぐに飛んで行って確認したところ、洗ったらすぐに落ちたのですが、たしかに浴槽が茶色く染まってしまっている。私たちがそのクレームから得たものは、バスハーブを改良する必要性だけではなく、染まるということは染料にもなる、ということです。浴槽が染まるんだったら、布はもっと染まるだろうと気づいて開発したのが、ハーブ染めでした。
どうせやるなら、徹底的にやらなければ気が済まないので、染め織りの産地である群馬県桐生市に拠点を作り、染色家に頼んでハーブ染めをやってもらいました。5000色くらいテストして、データベースを作ったんですね。さらに、二子玉川にハーブ染めの実演をするお店を作ったり、ハーブ染めの教室を作ったり、桐生市でハーブ染めを体験するツアーを組んだり。ただ、時代が早すぎたのか、あまりヒットはしませんでした。今やれば、違ってくるとは思うのですが。
三宅氏:
ティー、バスハーブ、染めの三段跳びは面白いですね。アロマテラピーとの出会いは?
重永氏:
フランスのロクシタンという有名メーカーがあります。そこの商品を扱っていたのですが、当時は石鹸が人気で、エッセンシャルオイルは少ししかラインナップがありませんでした。しかし、用途をいろいろと研究して気づいたのが、アロマテラピーの奥深さです。1本のエッセンシャルオイルの瓶に、どれだけの効能効果や使えるシーンがあるのだろうと感動しました。
そこで自社生産に切り替え、オリジナル商品を横展開していきました。ところが、日本では芳香療法や治療というかたちで売ることはできません。ですので、芳香の「利用法」として広めていこうということになり、アロマを使えるさまざまなシーンを開発していったという流れです。
三宅氏:
文化開発を組織としてシステム化していくために、意図的に行っていることはありますでしょうか。
重永氏:
システム化ということは考えたことはありませんが、企業文化としてやった者勝ちという空気があります。陶器の時代もそうですが、社内でぶつぶつと考えているくらいなら、試作品を店に並べて、お客さんと語り合ってしまったほうが早い。そのうえで改良を重ねながら、本生産に結びつけていけばいいと思っています。
その根底にあるのは、社員がハーブやアロマを好きということです。店舗のマニュアルは最低限でいいと思っていて、それよりは社員が生活の中で得た実態感を伝えてほしい。また、商品開発部門の人間でなくても、企画を応募できる社内制度も設けています。
さらに、私たちは「T字」という考え方を大事にしています。ハーブやアロマの魅力を掘り下げていかなければならないのは当然ですが、それだけではマニアックになってしまうので、その応用範囲を広げていかなければいけません。広げながら深めていくといった感じでしょうか。
私は今年の言葉として「醍醐」を掲げています。今年は酉年じゃないですか。両方の漢字に酉へんがつくこの言葉には、「牛乳などを発酵、熟生していった過程の中で、最後にたどり着く最高の状態」という意味があるそうです。そして、そこに「味」をつけると、「醍醐味」になる。「なるほど。私たちのビジネスは醍醐味を伝えることにあるんだ」と腑に落ち、会議のたびにこの言葉を使っています。社内では、上司は部下にスキルばかり教えてしまいがちです。もちろん、それも大事なのですが、まずは仕事の醍醐味を教えなければいけないと思っています。

三宅氏:
「醍醐味」は、今回のインタビューのキーワードになりそうですね。商品のポテンシャルの中から、最上の価値を伝えるには、それをユーザーに届けるリレーランナー全員が深い理解を持たなければならない。そこではメーカー側も、購入する側も、魅力を広めていく側もハーブとアロマの醍醐味に魅せられているということが大事なんだと思います。3代続けてビジネスが変わってきたということですが、今後も変わる可能性はありますか?
重永氏:
いきなりまた写真館をやるというような大きな変化はたぶんないと思いますが、今の価値観の中からいろいろな枝葉が出てくるとは思っています。陶器からハーブという流れも大きな変換に見えて、実は生活シーンを豊かにするという意味では繋がっています。ハーブやアロマの醍醐味を追い求めていった先に、新しい価値が出てくるかもしれない。それに人生を賭けたいという気概ある社員が出てくれば、その経営を任せてもいいと考えています。
社内起業なのか、事業部制なのか。形はまだわからないですけど、誰もが経営者になれるチャンスのある会社にしたいです。
三宅氏:
アロマは、ビジネスメディアの主たる読者であるおじさんたちにとってあまり馴染みのない分野です。そのために、本来ならばもっともっと注目されてもいい生活の木の事例が、そこまで多くの人には知られていない。今日、重永社長から市場の創造者としての歴史をうかがえて、ますますそう思うようになりました。私は『新しい市場のつくりかた』(東洋経済新報社)という本で、「文化振興財団的企業」という概念を提唱しましたが、その時、生活の木の事例を紹介できていたら、もっとわかりやすくなったのにと悔しい思いです(笑)。
「文化振興財団的企業」の手法の特徴は、優れた園芸家が造園のために土壌から手がけるかのように、社会に提供しようとしている文化の価値を評価して、享受するためのエコシステムを丸ごと構想し、素地づくりから手がけるというものです。その手法を採用すると、事前にはわからない課題に次々ぶつかることになりますから、きっちりと計画を立ててからやるよりも、まず試作して社会の反応を試してみてすぐ改良する、というサイクルを早く回すやり方のほうがむしろ合理的になります。そこから次のアイデア、商品も創発的に産まれる。個々の打席で三振しても、投手の癖をだんだん学ぶ打線のようなものです。まさにマドルスルー(muddle through 「泥の中、手探り状態で出口を探し求めて進んで行く」こと)の発想です。
そしてそれに大きく貢献するのが、ハーブを介して生活の木と一緒に育った、アロマ文化のファンコミュニティです。草創期にアルバイトのツテから少女漫画の連載が始まり、ポプリのブームが起きたというのは、いわば御縁に恵まれた、好運でもあります。しかし、その縁をちゃんと長く繋いで育んで、エバンジェリストも社員もそこから輩出している。そのことこそが、アロマ文化の「家元」たるべく営々と努力されてきた証ではないでしょうか。
日本の産業史を見ると、ピアノ文化を振興したヤマハ、ケチャップ文化を振興したカゴメが、それぞれ聴覚、味覚分野の先例としてあります。嗅覚は生物の感覚でもいちばん古くからあるそうですから、この市場はまだまだ深くなると思います。
今日はとてもよい勉強をさせていただきました。ありがとうございました。
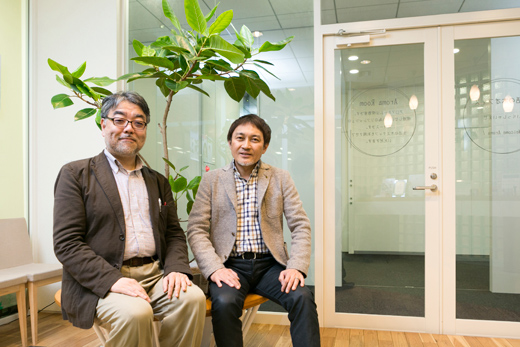
(文・構成=宮崎智之)