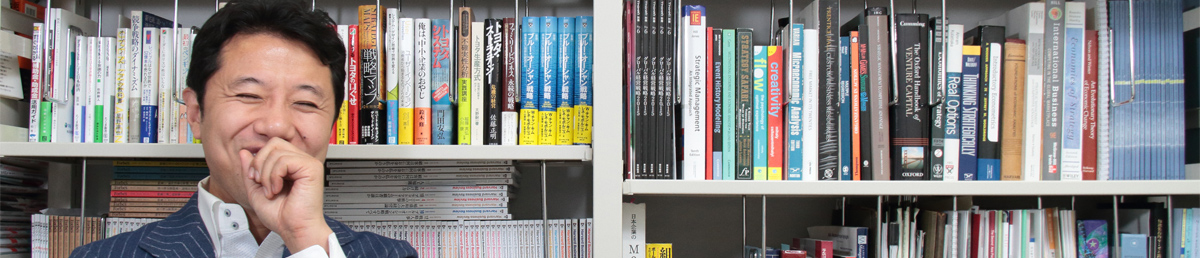2017年04月25日
なぜ、これからのイノベーションに「あなた自身の強いビジョン」が必要なのか
~「常識の枠」を出る組織と個人のあり方を考える~
人も組織もビジョンが必要
──学びということについて言うと、入山先生は経営学を学ぶことと共にその一つ一つを統合するものを学ぶ必要性を説いていらっしゃいます。その一つにデザイン思考の可能性を挙げています。デザイン思考は主に「観察(observation)、アイディアを出す(ideation)、試作(prototype)、テスト(test)」を繰り返し、できるだけ早く失敗をする(fail fast)というものかと思います。入山先生は間違えを改善していくことを繰り返しながらよいものは生まれてくるとおっしゃっていますね。
入山氏:
そうですね。これは経営学で言う、リアルオプション理論に近いです。リーンスタートアップ的な考え方ですよね。とりあえず始めてみて、PDCAを回すということ・小さく始めること・早めに失敗すること・どこで損切りするかを決めておくことがポイントです。
これは日本の大企業では一番苦手なのですよね。日本の大企業は綿密に計画をし、正確な需要予測を立て、正確な企画書を作り、場合によってはファイナンシャルシミュレーションをし、数字を作って積み上げていくわけです。それをやっていると1年とか、かかるわけですよ。結局はそれで終わっちゃうことも少なくない。
ただ、これも先の副業と人事の話と同じで、デザイン思考やフェイルファストだけをやってもうまくいかないのですよ。フェイルファストと共に重要なのは、人事が評価制度を見直すことなんです。今の評価というのは基本的に成功・失敗で判断するわけですよ。フェイルファストって失敗を前提にしているわけじゃないですか。だから、もともと矛盾しているんですよ。そのままだと誰も新しいことに取り組まない。
成功・失敗の評価の代わりとして、例えば、上司がひとりひとりと向き合って、かなりインテンシブに二人でインタビューとかディスカッションをして、今何考えているのとか、これ失敗だったけど、どうなのとかを聞き取っていくものや、同僚の「あの人この前のプロジェクト失敗しちゃったけど、あんな魅力的なことをしているならあの人とまたやりたい」というような声を拾っていくような、主観ベースの他者評価をするとかがあります。ただ、なかなか大変なことは確かです。
──そうすると、その人の人柄のようなものも重要になってくるということですか。
入山氏:
もちろん人柄もありますが、「この人は何をやりたいのか」がここでも重要になってくる。周りの人がその人のやりたいことに共感してくれたら難しいことも越えていけると思います。
だから会社もビジョンが必要なのですよね。ビジョンがあって、そこに賛同する人たちが集まって、そうすると共感し合っているから、失敗しても「とりあえずこっちですね」という方向に進んでいく。でも会社が大きくなればなるほど、それがなかなか伝わりづらいのですよね。だから、トップの仕事の半分以上は社員にビジョンを語ることなんですよ。社長や会長の仕事って本当はそれなんですよ。いかにそのビジョンに魅力があって、社会に貢献できて、ということをひたすら説く。そうしないとみんなついてこないですよ、これからの時代。

マインドセットは人と会わないと変わらない
──最後に、これからのビジネスパーソンが身に付ける力を教えていただけますか。
入山氏:
みんな力とかスキルとか能力とか言うのですが、一番足りないのは、やはりビジョンと言うか、自分はどういう人間で、何がしたいのかということ。やはりそこですね。それが一番重要で、日本人っていきなりスキルとか能力に走る方が多いですね。「俺って、今この仕事をしているんだけど、なんでこれをしているんだとか、20年後にどういう価値を生み出したいんだ」ということをあまり考えないでやっているんですよね。だから、好きな仕事ではなくてやらされている仕事をやっているみたいな状況になっている。そうすると結構厳しいのですよね。逆にやりたいことがあれば、それだけで前に進める。やっぱりそこが一番足りないんだと思います。その点で言うと、うちのビジネススクール(早稲田ビジネススクール)には幸いそういう人が結構いるので面白いですよ。今まで会ったことのない職種の人とか、全然違うバックグラウンドを持った人とか、ビジネススクールに来ないと出会えないような人がいたりする。教員にもそういう人がいっぱいいる。どっかの有名な会社の社長とか、海外で研究してきた人とか、そういうのがぐちゃぐちゃいて、そうすると視野が圧倒的に広がる。だから、その中でマインドセットが変わって、ビジョンがさらに明確になってきます。
残念ながら大企業には似たような人がいて、同じオペレーションで20年、30年と生きている人がいる。そうすると、マインドセットを変えられないんですよ。マインドセットは基本的に人と会わないと変えられないのですよね。だから、ものすごく多様な人とか、ものすごく自分の人生で影響を与えてくれる人とかに社内で出会うのはなかなか難しい。多様な人が入ってくればまた変わるのですけれど。とすると、外に目を向けて多様性のあるところに身を置くことが必要になってきますね。
──それは外見の多様性ではなく、考え方の多様性を求めていくということですよね。ありがとうございました。
(企画=有限会社ラウンドテーブルコム Active IP Media Labo、インタビュー・文章=尾澤知典、写真撮影=今井紀彰)