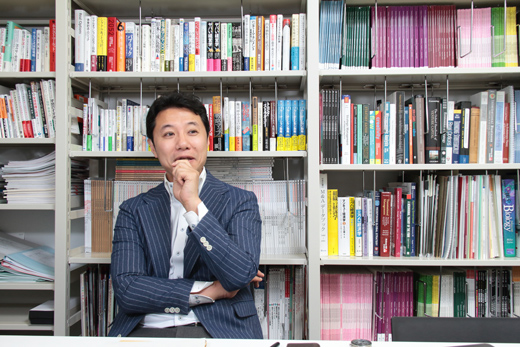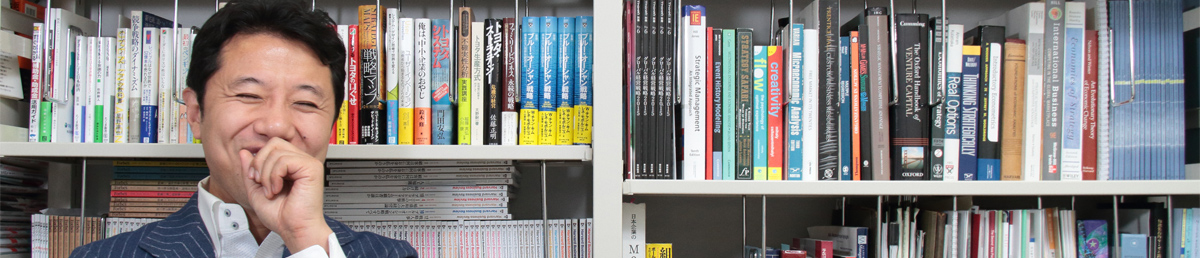2017年04月25日
なぜ、これからのイノベーションに「あなた自身の強いビジョン」が必要なのか
~「常識の枠」を出る組織と個人のあり方を考える~
大規模化・複雑化する現代社会の諸問題をどう解決できるか、そういう視点を持ち、実行していける人材が、生き残る企業には必要です。そういう人材、すなわちイノベーションを起こすチェンジメーカーが生まれる組織とは?早稲田大学大学院経営管理研究科で「世界標準の経営理論」を説く入山章栄准教授から、慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所の尾澤知典研究員が、今すぐ実践に活かせるビジネスの知恵を聞き出しました。

早稲田大学大学院経営管理研究科
准教授
「知の探求」からイノベーションが生まれる!
──入山先生の御著書「ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学」が昨年から話題になっています。この中に経営の研究理論を実際のビジネスの実践へ橋渡しするヒントがたくさん書かれています。この本が多くのビジネスパーソンに受け入れられているのはなぜですか。
入山氏:
まず、本に書かれている内容が、自分の知らないことだということ。また、これを読むと普段お仕事をされている中でのもやもやがすっきりしたという感想を持つ人が多いことが挙げられますね。例えば、組織内のダイバシティが大切だと言うけれど、それって本当なの?ということに対して、ダイバシティにはデモグラフィ型(性別・国籍など)とタスク型(職歴・経験など)の2種類があって、後者が重要だということや、イノベーションってみんな言っているけれど、イノベーションってそもそも何か?ということに対して、それは知と知の組み合わせで生まれる新しいアイディアだということを言っています。そして、組み合わせるときに、遠くのものの「知の探索」が必要なこと、と説明することで、なるほど自分が今までもやもやしていたイノベーションがこういう風に整理できるんだと思ってもらえるのですね。
──イノベーションを起こすために、遠くの知を探ること(知の探索)の必要性を主張されています。さらにそのために、社内でのハイブリッド的起業を勧めていらっしゃいますが、これはどういうことですか。
入山氏:
ハイブリッド的起業というのは、「会社勤めを続けながら、それと並行して起業すること」です。これを進めるためには、会社が起業副業を認めるかどうかがまず問題としてあります。これが会社にとってプラスかマイナスかを見定める必要があります。副業をすれば、今の自分たちのテリトリーから違うところに行けると僕は思っているのです。つまり、「知の探索」ができるとか、一つのネットワークともう一つのネットワークをつなぐ人材になったりできます。ただ、問題はそういう人材は会社をやめる可能性があるということなのです。企業は、そういう人材にやめてほしくないから副業を推奨しないわけです。問題はどうしたら副業してかつ、会社もよくなるかということを考える必要があります。理想的には、起業してもし失敗したら(失敗することの方が多い)、帰って来たときに、「いい経験したな」と戻ってきた人材を受け入れられるかが重要です。経緯は異なりますが、スティーブ・ジョブズだって「出もどり人材」ですしね。
──職種によっては会社から出て、戻ってくるというのを良く思わないところがありますよね。特に技術系とか。
入山氏:
そうですね。だけど、これからはそういう時代ではない。帰ってくる人材はとても重要だと思います。彼らは、「知の探索」をして、いろんな人脈を作ってきますから。確かに技術を持ち出したかもしれないけれど、逆に外の技術を持ってきているわけですよね。そう考えると、その方が知と知の新しい組み合わせになります。
日本って昔から、「会社」という箱があって、会社と外の境界線がはっきりしています。だけど、これからの時代というのは、イノベーションを起こすための「知の探索」が必要で、そのためにはそれをある程度取っ払ってやらないといけないと思います。それによって、出たり入ったりすることができます。また、完全な自前主義ではなくて、ほかの会社と連携してやっていくというようにしていかないとなかなか難しい。
ただ、副業というのはあくまで人事の一つの施策なので、副業だけ進めれば会社にとってプラスになるというわけではなく、出ていった人を受け入れるということも含めて考える必要があります。人事も含めた全部が一体化した問題だと思います。逆に言うと、出ていった人が起業で失敗したときに、「元の会社には戻りたくないな、他の会社に行っちゃおう」と思われるような会社ではなく、一度やめた会社でも、あの会社はすごくいい会社で、もう一回働いてみたいなと思われる会社になることが新しいイノベーションの機会を得るためにも重要です。そういったところまで含めてやる必要がある。
──企業は、これまでの考え方の枠を変える必要に迫られていると言えますね。

尾澤 知典(おざわ とものり)氏
慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所
研究員
入山氏:
そうですね。新しいことを成功させるには、何か一個やったらうまくいきますということはあり得ない。ものすごく色々な仕掛けを試してみるのですよね。その点で言うと、新卒一括採用もやめた方がいい。また、それをやめるためには定年制もやめる必要がありますね。なぜ新卒一括採用をやめるかと言うと、同じ人しか入ってこなくなるからです。新卒で入ってきて、その会社の色に染め上げていくことになる。20年くらいすると、A社とB社の人とは同じ業界なのに全然違ったような人になっていく。それだと同じ人しか育たない。イノベーションは「知と知の新しい組み合わせ」で決まるのだから、会社にはできるだけばらばらの人がいた方がいいのです。
そこで、新卒を採らないとなると中途をいっぱい採ることになりますよね。彼らは、いろんな経験や価値観、生活スタイルを持っているので、働き方も多様にならないといけない。だから、働き方改革が必要になってきます。ダイバシティとか働き方改革って実はワンセットで扱う必要があるのです。
日本の場合、ずっと新卒一括採用をしてきて、同じ人がずっといて、60の定年で皆やめていく。外との連携をせずに自前主義でやり、一度会社を出たら戻らない。これで90年代の初頭まではそのモデルが回っていたわけですが、それ以降の時代は新しいものを生み出す時代なので新しい時代には向いていません。
──日本は文化的に、帰属意識が強くて、出ていったものは戻らないとか、年功序列で一つ二つ上だと先輩として見るというのは、小さいときからの学校生活の中で培われてきた集大成のように感じられます。
入山氏:
そうです。これまでの教育システムはキャッチアップ型の経済には向いていました。これから必要な教育は、「自分はどういう人で、何をしたいのかという考えを持っている人を育てること」です。つまり、ビジョンというものがすごく重要だと思っています。先ほどの話で言うと、これからの時代は企業間を人がどんどん動くようになります。そうすると、多様な人同士はぶつかりますよね。意見が割れたときにもビジョンさえそろっていれば一つの方向へ進みます。
教育の問題で言うと、いい名前の大学に入って、なんとなくいい名前の会社に入って、何かをやりたくて入ったのではなくてその会社に入りたくて入ったという場合、ビジョンがはっきりしないので、イノベーションは起きにくいです。結局イノベーションを起こすときには、やりたいことがあって、「知の探索」をたくさんする。でも多くは失敗するので、失敗してもやり続けないといけない。そのときには自分はこれがやりたいから、失敗してもどんどんリスクをとって「知の探索をするんだ」というものが必要なんですね。だから、自分はいったいどういう人間で、何をしたいのかということがものすごく重要です。日本の学校教育にはここを育ててほしいと思います。