2016年08月05日
インダストリー4.0最新動向、日本・ドイツ・アメリカが目指す未来とは
インダストリー4.0に対するマイクロソフト流アプローチとは
日本企業に対するマイクロソフト流のアプローチ
──こうした中でマイクロソフトはどのような立ち位置を目指すのでしょうか?
武本氏:
ITがいろいろな業種業界でビジネスを支える中核技術に据えられて、ITが世界を変えていくことが当たり前になっていきます。すると、我々が提供するクラウドなどのIT基盤は、単なる道具ではなく、社会インフラになります。そして、社会インフラになるには、技術的に越えなければいけないさまざまなハードル、たとえばサイバー攻撃への対策等の最高レベルのセキュリティやスケーラビリティが必要になりますから、そこを世界最先端の技術と経験を持つマイクロソフトがしっかり対応して、安心して使っていただける基盤を世界中に提供していくということです。
──欧米企業は「まずやってみよう」から始まるのに対し、日本企業は「まず勉強してから」になりがちです。そういう日本企業に対して、日本マイクロソフトとしては、どういうアプローチをされていきますか。
武本氏:
たとえば、最近トレンドワードになっている「AI」も技術的な中身や利用形態は各社バラバラなのに、魔法の言葉としてイメージだけが先行しています。より具体的に「機械学習」に目を向けると、世の中に機械学習のツールはたくさんあります。しかしおおむね、高度なデータサイエンスの知識に加え、プログラミングスキルも必要とする難解なものであり、これが広い活用を阻んでいます。我々が社会インフラとしての機械学習サービスを提供するためには、専門的な複雑さを取り除いて使い勝手をガラリと変え、敷居を下げなければなりません。それによって、これまで使ったことのなかった幅広い層のユーザーがその威力を享受できるようになることが、イノベーションにつながると考えています。
これを伝えるため、たとえば電力の専門家であるお客さまからデータをいただき、ITベンダーである素人の我々がお客さまの目の前で電力需要を精度よく予測して、お客さまを「えっ」と驚かせてから、事業での活用シナリオをディスカッションさせていただく、といったことも1つのやり方です。
重要なことはITの力の可能性を「触発すること」だと思います。先ほどの電力需要予測の話であれば、「ここまでなら我々のやり方でも簡単にできます」というのを見ていただいて、お客さまに「だったら、我々が本気で取り組めば今までよりいいやり方ができるんじゃないか」と思っていただきたいのです。
──従来のマイクロソフトのビジネスとは大きく異なりますね。
武本氏:
はい。マイクロソフト自身も大きく変わろうとしています。世の中も変わっていますし、我々のビジネスモデルもモバイルとクラウドにシフトしています。我々がプラットフォームを提供し、その上で、お客さまが作った我々の名前の出ないさまざまなユーザー向けサービスがたくさん登場することになりますので、「そこで収集されたデータをどう管理し使えるようにするのか」、「そこで得られた利益をどう配分するのか」といったことも含めて、現在、弊社内でも、さまざまな検討が行われているところです。
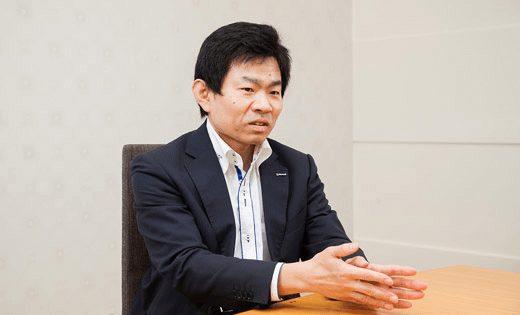
「データが生み出す価値」のほうが圧倒的に重要
──武本さんが注目しているメガトレンドはありますか。
武本氏:
2050年になったら、日本の生産年齢人口が約半分になるので、2倍の効率で働かなければならないのは、すでに見えている未来です。そうすると、今までの働き方の延長では絶対不可能なので、働き方を変えなければいけない。成果の考え方やコミュニケーション方法が変わり、今流行のAIも、間違いなく当たり前に使われるレベルになるでしょう。
製造業についても、省力から省人化、さらに無人化のニーズが広がる一方、品質をどう確保するかが課題になるでしょう。すでに、物流や製造の現場では人が雇えていない。優秀な人材を確保して教育するのが難しくなっています。新興国では人材の成長より経済の成長が遥かに速いため、課題はより深刻かも知れません。すると、人間と機械の役割を見直さざるをえないですし、優秀な人のノウハウをデジタル技術でサービス化する流れが起こるでしょうというのが、まさに直近のテーマです。
──日本マイクロソフトとしてはどの分野に注力していきたいとお考えでしょうか。
武本氏:
製造業に限らず、流通・小売業や医療分野などにも注力しています。ただ、他の分野にも言えることですが、データ流通に関する規制と「データの所有権」についての議論が少し心配です。
今年4月に、米国本社主催の「Envision」というカンファレンスが行われました。そこでスマート製造業に関するパネルディスカッションがあり、データの所有権について話し合われたのですが、ここではもう「データは誰のものか」と議論しているレベルではありませんでした。フィールドレベルの細かいデータからERPのデータ、さらに他社や外部のデータまで、とにかくデータをクラウドに上げて結びつけることで初めて新しい価値が生まれ、それによって産業や経済を活性化することを考えるのが重要で、「これは○○のデータだから外に出せない」と言っている場合ではもはやないと思います。先ほどのロールス・ロイスの例では、乗客や航空会社のメリットを目指して、航空会社、航空機メーカー、エンジンメーカーが会社を越えてデータを共有していましたしね。
デバイスのレイヤーからビジネスシステムのレイヤーまでをつなぎ、人のプロセス中心に価値を提供するITプラットフォームをすべて提供できるのは、マイクロソフトならではの強みです。また、OPC Foundationなどの業界団体による標準化活動に我々の知見や技術で貢献し、逆に弊社が提供するSDKやサービスにニーズを取り込むこともしています。また、日本では「IoTビジネス共創ラボ」というコミュニティを作り、5つのワーキンググループに分かれてIoTプロジェクトの共同検証を行っています。こうした活動を通じて、ノウハウを共有する取り組みも引き続き行っていきたいと思います。
──本日は、貴重なお話をありがとうございました。
(インタビュー=フロンティアワン 代表取締役 鍋野 敬一郎、ビジネス+IT 編集部 松尾慎司)
