2017年02月27日
MITテクノロジーレビュー
巨大銀行はなぜブロックチェーンを研究しているのか?
フィンテック以外のブロックチェーン
NECの岩田室長は、ブロックチェーンの価値は「本人確認と医療、保健を含む履歴確認、情報の所有権をユーザー側が握るプライバシー」にあるという。たとえば内戦で国民の財産や出生届(本籍)などを保管するデータセンターが失われれば、どこの誰でどんな教育を受け、どんな資産を持つのかは第三者に証明できなくなる。ブロックチェーンであれば、世界中のどこかにデータが残る可能性があり、生体認証と組み合わせれば、本人が生きてさえいれば自分のデータにアクセスできる。
実際、ケニヤのダダーブ難民キャンプで、住民が支援機関とのやりとりを通して経済上の身元を確立するのをブロックチェーンで支援するプロジェクトがある。また、WebサーバーApacheの開発に関わったブライアン・ベーレンドルフは現在、ブロックチェーンのオープンソース開発を支援する非営利団体「ハイパーレッジャー・プロジェクト」を率いている。ハイパーレッジャーは2016年10月、保健医療分野でプロジェクトを提案する作業グループを形成した。患者が自身の医療記録を医療提供者間で転送しやすくすることをテーマに掲げている。

ハイパーレッジャーはブロックチェーン型ソフトウェアの開発を加速するための組織であり、IBMやJ.P.モルガン、エアバス等、約100社が支援している。ベーレンドルフは、ブロックチェーンには大企業の事業領域以外にも用途があるという。政府に提出する書類をブロックチェーンでやり取りできるようにすれば、同じ申請なのに所管の省庁別に異なる書式の書類を用意するような無駄を排除したり、必要な情報だけを、申請者が指定した省庁にだけ転送したりする仕組みを構築し、行政を効率化できるかもしれない。
ブロックチェーンで、インターネットそのものを置き換える構想もある。今年1月、ベンチャーキャピタルから400万ドルの資金を調達したブロックスタック(Blockstack)は、ユーザーが自分のデータを管理できる新しいWebを作り出すオープンソース・ソフトウェアを開発している。
ブロックスタックの構想は自社を含むどの企業からも独立して構築されたIDシステムによって実現される。システムは、ブロックチェーンでユーザー情報を保持しており、グーグルやフェイスブック、アマゾンなど、巨大なインターネット企業に登録されたアカウントを使い回し、結局はどのユーザーがどこでどんな行動をしているか記録されている現在のインターネットへのアンチテーゼになっている。
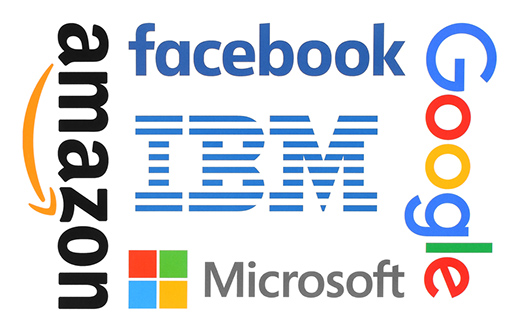
ブロックスタックは、既存のWebブラウザーから、新しいデジタル領域で構築されたサイトやアプリを閲覧できるソフトウェアを2017年下期にはリリースする予定だ。新しい世界でも、リンクをクリックしたり、アドレスを入力したりして、友だちとチャットしたり、買い物したりできる。ただし、グーグルやフェイスブックのように、各サイトで別のアカウントを作る必要はない。ブロックスタックのシステム上に構築されたサイトのユーザーは、自身で自分のアカウントを管理できる。ユーザーは、自分だけに管理権があるプロフィールへのアクセス権をサイトに許可することで、そのサイトにアカウント情報を提供するのだ。サービスの使用を中止するときは、プロフィールやデータへのアクセス権を取り消し、また別のサイトにアクセス許可を与える。個人データの完全な制御権をユーザー側に戻すのがブロックスタックの構想だ。
ブロックチェーンは、ビットコインを実現するために開発された分散データベースだ。しかし、その真の価値に気付いた人々は、デジタル通貨以外の用途に大きな構想を描いている。国内でもブロックチェーンとビットコインを切り離して理解する動きが今年に入ってようやく活発化した。
NECの岩田室長は「日本は便利なのでブロックチェーンの必要性を認識しづらい」としながら、パスポート申請のために役所から戸籍謄本を取り寄せたり、就職・転職で卒業証明書を大学に発行してもらったり、地元の両親の判断力が落ちてきたとき、後見人として財産を管理したりするなど、生体認証による本人確認とブロックチェーンの組み合わせが威力を発揮する場面があるという。役所や学校のコンピューターを接続し、ブロックチェーン型システムを構築すれば、災害や廃校で施設がなくなっても、データは保持され、自分の情報を誰に送るかを本人が指定できる。

お金を管理できる仕組みだからこそ、データを低コストかつ高セキュリティに扱えるのがブロックチェーンの魅力なのだ。フィンテックとは異なる文脈でブロックチェーンを活用する方法はまだまだ未開拓であり、日本企業も十分に活用できるチャンスがあるはずだ。
関連記事
