2016年11月25日
「先んずればビジネスを制す」マイナンバーカードで生まれるビジネスチャンスとは
2015年10月より、日本に住む一人ひとりの住民に12桁の個人番号を付与するマイナンバー制度が始まった。これに伴い、本人の申請によって無料で交付される「マイナンバーカード(個人番号カード)」に大きな期待が集まっている。これは企業や自治体のサービス、電子申請など、幅広いシーンで活用できるICカード(ICチップを搭載したカード)のこと。マイナンバーカードは、今後どのように発展し、私たちの生活利便性はどう変わるのか。さらに企業にはどんなビジネスチャンスをもたらすのか。マイナンバーの制度設計を担当し本制度推進のキーマンである向井治紀 内閣審議官に話を聞いた。

(左)聞き手:NEC 番号事業推進本部 マネージャー 山口桂子
2017年度中に3000万枚の普及をめざす
山口:
まずは、今、大きな注目を集めている「マイナンバーカード」ですが、何に使えるのかよく分からないという声を聞きます。どのようなものなのか、今一度説明していただけますか。
向井氏:
マイナンバーカードは、公的個人認証の電子証明書(電子署名・利用者証明)の機能が標準搭載されたICチップ付のカードのこと。これを使った公的個人認証サービスは民間企業にも開放されています。これによりネットショッピングなどでの個人認証がインターネット経由で簡単に行えるようになっています。また、ICチップの空きスペースにさまざまな機能を付加することで、幅広い用途に使えます。
特に注目していただきたいのは、セキュリティに対しても高度な対策を行っている点です。まず、マイナンバーカードのICチップには税や年金の情報、病歴などプライバシー性の高い情報は記録されません。
また、ICチップの利用にはパスワードが必要で、一定回数間違えると使えなくなるほか、ICチップの情報を不正に読み取ろうとするとICチップそのものが壊れてしまう仕様にしてあります。
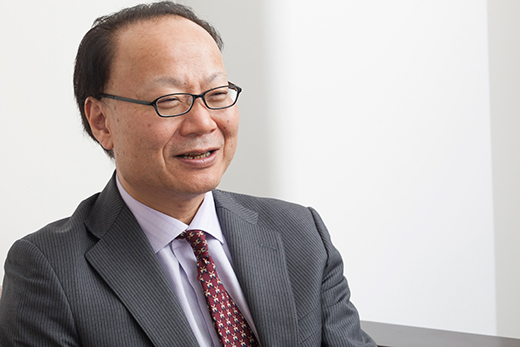
山口:
とてもセキュアで利便性も高いカードなんですね。
向井氏:
マイナンバーカードによるメリットが実感できるようになるには、やはりカードの普及がカギとなります。
そこで普及促進策の一環として、2018年からマイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせようと考えています。健康保険証はほぼすべての国民が持つものですし、併せて入院の際の煩雑な手続きや各種書類作成の手間も、電子署名や入力補助(※)の機能を利用することで大幅に軽減することもできます。
※予め登録した暗証番号を入力すれば、個人番号や住所・氏名・生年月日・性別といった情報が自動的に入力される仕組み
山口:
それは大きなトピックですね。病院側も保険者資格を正確にオンラインで確認できるようになるでしょうし、業務の効率化を実現する一方で、確実性・正確性の確保など、さまざまなメリットが期待できますね。
向井氏:
将来的には制度の趣旨や個人情報の保護などに配慮しながら、クレジットカードやキャッシュカード、ポイントカード、各種免許証、診察券など、皆さんが普段使っているさまざまな機能をマイナンバーカード1枚に集約していく「ワンカード化」の促進に力を入れていきたいと考えています。
山口:
たくさんのカードを財布に入れて持ち歩くのは非常に不便なものですし、ついつい忘れてしまいがちですが、それがマイナンバーカード1枚に収まれば、とても便利になりますね。カード発行や管理に係わる手間やコストが大幅に低減できるので、サービスを提供する企業にとっても嬉しいですね。
向井氏:
国民に対して官民横断的なワンストップサービスを提供するための基盤として2017年7月から本格的な運用を開始するのが、自宅のパソコンなどからアクセスできる国民一人ひとり向けのポータルサイト、「マイナポータル」です。
利用にあたっては、マイナンバーカードで認証を行い、パソコン、タブレット、スマートフォンなどからログインしていただきます。マイナポータルでは自分のマイナンバーを含むどんな個人情報について、「いつ」「誰が」「誰に」「どのような目的で」照会し、提供したのかという「情報提供等記録」を確認できるようにしてあり、行政手続きの透明性を担保しています。
こうした数々の施策を展開することで、2017年度中には3000万枚、2018年中には6000万枚のカード発行につなげていきたいと考えています。
