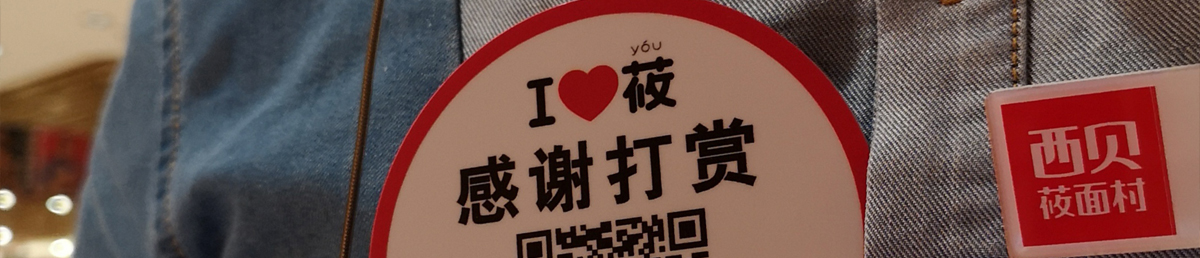
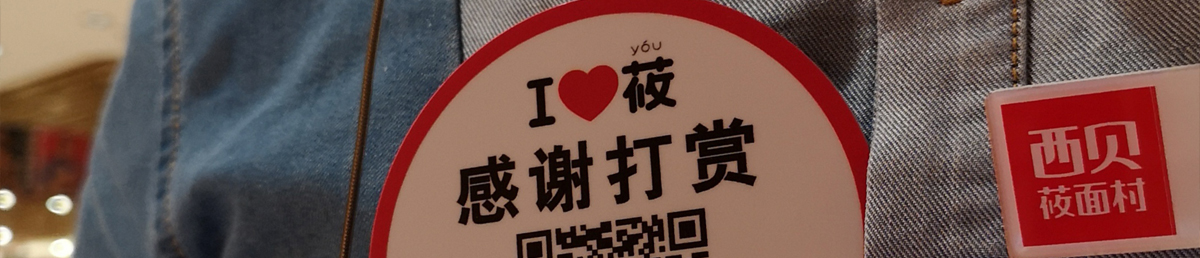
次世代中国 一歩先の大市場を読む
中国で広がる「投げ銭」文化~個人と個人の信頼感は社会を変えるか
農民が一夜にして資産家になる日
Text:田中 信彦
個人のコンテンツに直接お金を払う
ビジネス現場のモチベーションを高める目的で導入されている金銭支払いの仕組みとは別に、普通の個人の著作物や「考え方」「主張」などに対して、それを支持する人が気軽にお金を払って激励する仕組みも広がっている。その代表的なものが中国で10億人を超える利用者を擁し、いまや事実上、中国国民の通信手段のスタンダードとなっているSNSのウィチャット(WeChat、微信)の附属機能「微信公衆号(Wechat public account)」である。
日本では「ウィチャット公式アカウント」と訳されることが多いようだが、「公衆(パブリック)」のアカウントなので、「公式」はやや語感が違うような気がする。ここでは中国の通称「公衆微信」にならって「パブリック・ウィチャット」としておく。個人(企業)が自分のコンテンツを広く公開するブログのようなもので、さらに希望すれば、自分のファンから金銭的支援を受ける仕掛けを組み込むことができる。
それぞれのコンテンツの下部に「喜歓作者(この作者が好き)」というボタンが置かれ、読者が「この人を支援したい」と思えば、金額を指定してウィチャットで直接、現金を贈る。なにしろウィチャットは10億人超の国民が日常的に使うツールで、友人間や仕事関係のコミュニケーションだけでなく、日常的なニュースや話題もここから得ている人が少なくない。注目されれば反響は大きい。母数がとてつもなく大きいので、仮に少数派であっても「広く薄く」が成り立つ可能性があるのである。
「街の個人商店を救え」に賛同集まる
私の友人に俞菱(Yu Ling)さんという、このパブリック・ウィチャットを舞台に活躍している人がいる。彼女はある女性誌の編集者だったのだが、近年、上海の街角にある個人経営の小さな店が、家賃や人件費の高騰、大手チェーンの進出などで次々と閉店に追い込まれていくのに心を痛め、徒手空拳ながら小商店の支援運動を始めることを決意した。

2015年6月2日、この日をみずから「世界路地歩きデー」と名付け、「路地は世界最大のネットワークだ!」「家に籠もらず、外に出よう」を合い言葉に活動をスタート。パブリック・ウィチャット上に「俞菱と街を歩く(跟俞菱逛马路)」という画像と動画をふんだんに活用した文章を定期的に掲載し、上海を中心に、時には他の都市や海外の個人経営の店を訪ねてはその経営者と語り、励ましつつ、みんなで「小さな店を守ろう」という声を上げ続けた。私事ながら、筆者の妻も上海でシルク製品などを商う店を経営していたので、そのプロセスで彼女と知り合った。

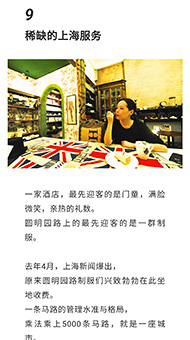
最初は賛同者も少なく、彼女も個人商店から広告を取る気はなかったので、自腹で店を回り、ご主人が動画を撮影し、夜なべ仕事で編集してアップロードするという傍からみてもたいへんな様子だった。しかし、次第に中国のメディアが彼女の主張を取り上げるようになり、昨今では上海市政府も大企業偏重から個人商店重視の方向に政策のカジを切り始めたこともあって、支援者が増えてきた。
1回の配信で7000元の「投げ銭」

彼女の「おひねり」「投げ銭」のシステムも当初はほとんどお金が入らず、1日に日本円で数十円、数百円のレベルが続いたが、昨年後半あたりから金額が増え始め、今年1月19日にアップロードした「上海の小さな店を救え!」という動画+文章は7000元を超えて過去最高を記録。その後も好調を維持している。
支援者は大半が5~20元で、多い人で200元。このパブリック・ウィチャットの「投げ銭」の仕組みは最大256元までしか贈れない。仕組みそのものが「広く薄く」が前提となっている。金額が上向いてきたとはいっても、7000元は日本円で11~12万円ほどで、仮に毎月数本のコンテンツをアップロードするとしても活動経費にはまったく足りない。日常の暮らしは広告制作などの仕事でまかない、活動部分は持ち出しが続いている。しかし彼女は意気軒昂である。「とにかく支援してくれる人が増えているのがうれしい。お金を出してくれた人には、たとえ5元でも10元でも必ず全員にお礼のメッセージを送っています。多い時には何百人もいるからもう大変」と笑う。
このようなパブリック・ウィチャットの数は2017年末現在で2100万を超え、年率15~20%の勢いで増加している。そのすべてが「投げ銭」の仕組みを取り入れているわけではないが、個人が自分のファンから直接、比較的容易に金銭の支援を受けられる仕組みが、着実に広がっていることは間違いない。
広がる「お金を通じた評価、支援」
ダンスや歌、バンドの演奏など、もしくは容姿端麗な男性もしくは女性が登場してお話をしたりする様子をアップロードし、ファンがそれに対して「投げ銭」を贈るという類のパフォーマンス系のアプリは、かなり以前から中国にもあるし、日本にもある。その種のアプリに登場する人物が日本円換算で数千万円、数億円のお金を儲けたとか、逆に、ファンの側が決して多くはない収入の中から度を越したお金を貢いで人生が破綻したとか、子供が親に無断で多額の金銭を贈ってしまったとか、その種の話題も両国共通にある。これはまさに典型的な「投げ銭文化」であって、独自の才能を持つさまざまなアーティストを発掘し、才能を伸ばすうえでとてもよい仕組みだと思う。おそらく今後さらに広まっていくだろう。
しかし中国の社会で面白いと思うのは、こうした「お金を稼ぐための投げ銭」とは別に、前段で挙げたいくつかの例のように、個人を対象に直接お金で評価、支援する動きが広まりつつある点だ。
その背景にアリペイやウィチャットペイに代表される決済アプリが日常に深く浸透し、手数料も事実上、無料で、どんな小銭でも即座に相手に届けられる利便性の高さがある。しかし、それ以上に大きいのは「個人」を軸に、価値観の共通する人と人がつながって物事を実現していく中国人の生き方である。
個人を通じて社会を変える期待感
中国人はたとえ自分がレストランで服務員をやっていても、「店は店」「自分は自分」だと考えているし、やや自己評価が高すぎるきらいはあるが、自分の果たした役割をそのままストレートに評価してもらいたいと思っている。お客のほうも自分とウマが合う従業員がいれば、その人、個人に好感を持ち、次回もサービスしてほしいと思う。「従業員と客」の関係から、個人的な友人関係になることも珍しくない。これはタクシーの運転者さんであっても、宅配便の配達員であっても基本的に変わらない。
また中国社会には、気持ちが通じる相手に対して「なんとかして力になりたい」という一種の義侠心を持つ人がたくさんいる。中国語で「義気(yiqi)」と表現するが、「義気のある人」は中国ではかなり強い褒め言葉である。
前述した俞菱さんがパブリック・ウィチャットを通じて目指していることは一種の社会運動であり、いわばクラウドファンディングに近い性質のものである。ただそれがプロジェクト単位ではなく、彼女個人に対する支援の形で集まっている。そこには政治に対する自由な意思表示が事実上不可能な社会で、人々が好感を持つ人物を通じて自分たちの思いを少しでも実現したいという期待感が込められている。日々閉塞感の強まる社会において、中国の人々は「個人対個人」の信頼感のなかにある種の希望を見出しているともいえる。
今後、中国社会でも日本社会でも、こうした個人に対する直接の「投げ銭」「おひねり」文化は徐々に拡大していくのではないかと思う。ただ、それが社会に対して持つ意味合いは、常に個人と個人の信頼感で問題を解決し、個人と個人の離合集散で世の中が変化していく中国社会のほうが、より大きなものがあるように思える。

次世代中国

