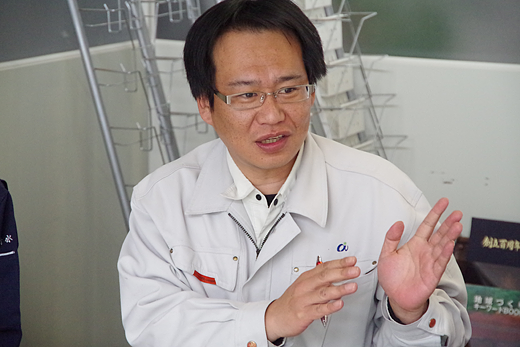2016年04月27日
地方創生現場を徹底取材「IT風土記」
愛媛発、ICTで水産業活性化、現場で使えるものこそ最新
愛媛県の南西部、太平洋の黒潮の恵み豊かな愛南町は古来から水産業の盛んな町だ。だが1982年に400億円あった漁業生産高は2009年には260億円に落ち込んだ。漁獲高だけではない。全国の水産業と同様、燃料や飼料の価格高騰や後継者不足など取り巻く環境は厳しい。そこでICTを導入し必要な情報を関係者が共有することで効率化を図った。その試みと成果は―。

〝ここにしかない産業〟を活性化
愛南町は2004年10月、南宇和郡内の5つの町村が合併して誕生した愛媛県最南端の自然豊かな町だ。だが、合併にともなう民間企業の撤退や少子高齢化の影響などで町の人口は約2万3000人。合併当初より約5700人減った。就労機会がなくては地域の経済が疲弊し過疎化が進んでしまう。
そこで愛南町は「昔からある、ここにしかない産業を活性化しよう」と考えた。水産業だ。カツオなどの1本釣り、漁船漁業、貝類・魚類養殖が3本柱で、なかでも海中に生け簀を設ける魚類養殖ではマダイが全国2位、カンパチは5位、ブリも7位の生産量を誇る。
2008年、総務省の市町村活性化施策の一環で町内に愛媛大学との連携で南予水産研究センターができた。研究チームから町に提案があった。「毎日、漁協から海水温などの水域情報をFAXで送ってもらっているが、紙のデータは整理が難しい。魚の病気の検査をしたくても、過去のデータを一部しか管理できていない。もったいない。ICTを活用すればもっと便利になるのでは」
愛南町水産課の浦崎慎太郎水産振興係長は「もっともだ」と思った。折しも、総務省の交付金プロジェクトの案内が届いた。そこで町の養殖業者が直面している赤潮や魚病の被害を軽減するため、海水の温度・塩分濃度などの水域情報や魚病の観測・診断結果をネットワークで配信し、さらに、ホームページを通じて消費者や小学生向けに魚の食育情報も発信するシステムを考えた。「愛南町次世代型水産業振興ネットワークシステム」と命名され2010年度に全体で約5000万円の交付金を得て、2011年度から本格的に運用されることとなった。水域情報可視化システム、魚健康カルテシステム、水産業振興ネットワークシステムの3本柱で構築される本システムは、2015年3月に地域情報化大賞奨励賞を受賞した。