

環境負荷の低減は最優先の経営課題 課題解決にレンゴーは、AI・データ活用で立ち向かう
製紙、段ボール、紙器、軟包装、重包装などの事業を展開するレンゴー。環境課題の解決を最優先の経営課題と位置付け、幅広い取り組みを進めている。その取り組みを加速させるものとして期待されているのがデータ活用だ。データは環境課題の解決に欠かせない。「データの民主化」を掲げ、現場主導のデータ活用に向けた挑戦を開始した。
データ活用は環境課題の解決に欠かせない
──環境負荷の低減を最優先で取り組むべき経営課題に設定するなど、持続可能な社会の実現への貢献を重視していますね。
西谷氏:レンゴーは、パッケージに関するあらゆるニーズにお応えする「ゼネラル・パッケ-ジング・インダストリー(GPI)」です。製紙、段ボール、紙器、軟包装、重包装など、さまざまな事業を展開しており、段ボール原紙生産の国内トップメーカー(※1)であり、段ボール生産(※2)では国内トップシェアを誇っています。
レンゴーを中心とするレンゴーグループの経営理念には「時勢の変遷に対応して最も優れたパッケージング(包装)を提供することにより、お客様の商品の価値を高め、社会に貢献しつづけていく」と明記しています。時勢の変遷、お客様の商品の価値、社会貢献、これらを考える上で環境負荷の低減は、絶対に欠かすことのできない視点です。「地球環境の保全に主体的に取り組むこと」を同じように経営理念の中に盛り込み、「レンゴーグループ環境憲章」を制定するなど、方針や目標を明確にしています。
- ※1 日本製紙連合会調べ
- ※2 矢野経済研究所調べ

情報システム本部 副本部長 兼
情報システム第一部長
西谷 卓也氏
──どのような取り組みを進めていますか。
西谷氏:事業活動を通じて最優先で取り組むべき環境課題として「脱炭素社会の形成」「エネルギー効率の向上」「循環型社会の形成」「環境問題や社会課題を解決する製品の創出」「水リスクの管理」「バリューチェーンマネジメント(下流)」の6つを挙げています。中でも脱炭素社会の形成は最重要の課題ととらえ、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロとするための挑戦を開始しています。
例えば、2027年までに国内製造拠点における石炭使用量をゼロにすることを目指し、石炭・重油ボイラの燃料転換を進めています。ほかにも環境問題や社会課題を解決する製品の創出にも取り組んでおり、資源循環や海洋プラスチック問題の解決につながる生分解性のあるセルロース関連製品を開発し、その普及に注力しています。
──多方面から取り組みを進めているのですね。データ活用にも取り組んでいると聞きました。
平田氏:より効果の高い施策を実行していくには、資源やエネルギーについて「何を」「いつ」「どこで」「どれくらい」使用したかを把握し、どのように改善すれば使用を抑えたり、ムダをなくしたりできるかを模索していかなければなりません。データは環境課題の解決に欠かせないものだと考えています。

情報システム本部
情報システム第一部 情報システム課
主任
平田 匡人氏
担当者の勘と経験にデータという新しい力を融合したい
──データ活用には、どのように取り組んでいますか。
西谷氏:受発注や生産管理、生産設備の情報、温度・湿度、振動などを計測するさまざまなセンサーのデータを集約するデータレイクの構築、そして、データ活用人材の育成という2つの柱を中心に取り組みを進めています。
──人材不足は多くの企業がデータ活用の障壁として挙げる課題です。人材育成は、どのように進めていますか。
松尾氏:環境問題を解決するためのデータ活用において、生産プロセスを無視することはできません。
段ボール原紙をつくるプロセスでは、原材料を繊維状にする、異物を除去する、ワイヤの上に原料を吹き付けて均一に広げて乾燥させる、原紙を所定の幅に切りながら巻き直す。段ボールシートをつくるプロセスでは、中しんと裏ライナの段ボール原紙を貼り合わせる、表ライナの段ボール原紙を貼り合わせる、切断し段ボールシートにする。段ボールケースをつくるプロセスでは、段ボールシートに印刷をする、箱状になるように糊付けし折りたたむ。生産プロセスには、さまざまな工程がありますが、これらは多様な知識やスキル、経験を持つ技術者など、専門性の高い担当者たちが支えています。データを分析して得た知見を実際の業務に落とし込むには、各担当者自身が分析結果を見て、それを理解し、どのように業務に反映させるかを考えなければなりません。担当者の勘と経験にデータという新しい力を融合したい。そう考えて現場主導のデータ活用、「データの民主化(※3)」を目指すことにしました。
- ※3 データの専門家だけではなく、従業員の誰もがデータを活用して価値を創出するという概念

情報システム本部
情報システム第二部 情報システム課
松尾 満里奈氏
平田氏:私たちがデータ分析ツールにNECの「dotData」を選び、ツール導入と同時にNECがデータ活用人材の育成を支援してくれる「DX人材育成サービス」も採用したのは、このデータの民主化のためです。
松尾氏:dotDataは、自動的に大量の特徴量を探索し、ユーザに提示してくれます。情報システム部門に配属になった際に、開発言語のPythonを使ったモデル開発を学んだことがあるのですが、それに比べるとはるかに簡単で、データ分析に関する高度な専門知識がなくても、思い込みに左右されず、客観的に分析モデルを評価することができると考えました。
平田氏:DX人材育成サービスは、dotDataの操作だけでなく、業務課題を見つけて、分析テーマを設定し、実際に分析を行いながら精度を上げて結果を導くというデータ分析プロジェクトの工程をほぼ網羅しています。さらに、私たちが持つ実際の実務データを使ったユースケースによるOJTが組み込まれているなど、実践性を評価しました。
ユースケースから新しい発見。操業への反映に期待
──現在の育成状況をお聞かせください。
平田氏:まずPoC(概念検証)と位置付けて情報システム部門のメンバーがDX人材育成サービスのプログラムに参加。「これならいける」と判断して、我々情報システム部門のメンバーはサポートに回り、本番である現場の担当者向けのプログラムを開始しました。
OJTで設定したユースケースや分析結果にも手応えを感じています。例えば、あるチームは、段ボールの「反り」に関する分析を行いました。先ほど松尾が紹介したように、段ボールは、原紙を貼り付けたり、印刷を行ったりする工程を経て製造されますが、その過程で段ボールシートに反りが発生することがあります。反った段ボールシートは蒸気などで矯正していますが、材料やエネルギーの節約という観点では、できるだけ反りが発生しない方が望ましい。そこで、どのような条件が反りに大きく影響を与えているかを分析しました。さまざまな条件下での反りの発生要因を定量化し、生産性・品質の向上、環境負荷の低減を実現するためです。
松尾氏:製紙工場のメンバーは、段ボール原紙を製造するために消費する原材料と電力について分析を行いました。分析の目的は、今回は原材料や電力をなぜ多く使用したのか、どうすれば消費を抑えられるのかを知り、効率的に製造を行うとともに、環境への負荷を低減することです。分析の結果、担当者の経験に近いものもあれば、相関があると考えた気温と降水量が実はほとんど影響していなかったなど、さまざまな発見がありました。現場の担当者からは「長年、生産量を記録してきたが、ただ蓄積し続けているだけだった。それをやっと有効活用することができた」と非常に前向きな声が上がっています。このユースケースは、今後も継続的に取り組み、最適な分析モデルを見つけ、実際に操業に反映することを検討しています。
平田氏:このような成果を導くために、NECは非常に手厚いサポートを行ってくれました。例えば、プログラム前半の内容は、当初はデータ分析の基礎などを学ぶ内容だったのですが、より実践的なものにしたいという私たちの要望を受けて、課題やユースケースの設定の仕方を学ぶワークショップに差し替えてくれました。それ以外にも、さまざまな要望を伝えたのですが、毎回、NECは「難しい」とは回答せず、どうすれば要望に応えられかを親身になって考えてくれました。いずれ情報システム部門がトレーニングを主導する内製にシフトしたいと考えていますが、そうした姿勢は、ぜひ受け継いでいきたいですね。
松尾氏:OJTにおけるきめ細かな対応も印象に残っています。十数人のメンバーが参加しているのにもかかわらず、一人ひとりの学習の進捗状況を丁寧に把握して、それに応じたフォローを行ってくれました。
──今後の展望をお聞かせください。
西谷氏:現場のノウハウの多くは、属人的であり、データによる裏付けまではできていないこともあります。根拠が明確になれば、そのノウハウをより多くの担当者が学びやすく、共有できるようになります。上層部も大きな期待を寄せています。最終的には、各部門に必ずデータ活用人材がいる。そういう状況に発展させ、事業の成長や環境課題の解決に役立てていきたいと考えています。
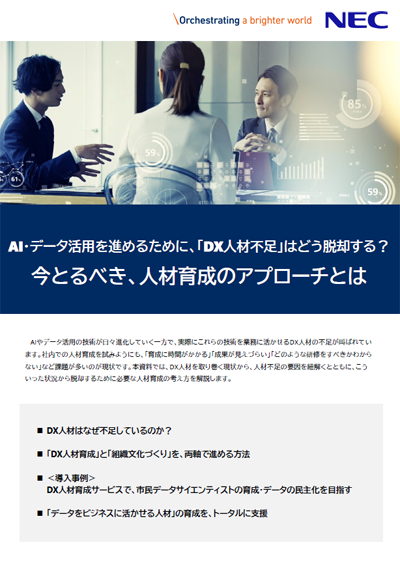
「DX人材育成サービス」関連のホワイトペーパー資料のご紹介
DX人材を取り巻く現状から、人材不足の要因・その状況から脱却するために、今とるべき人材育成のアプローチを解説しています。





