

価値創出のためのデータ活用は現場主導で
実践力重視の姿勢でのぞむ中部電力グループのDX
企業が事業活動を通じて社会的な価値と経済的な価値を両立させるCSV(Creating Shared Value)経営が注目されている。そのような企業の多くに共通するのがデータ活用への積極的な姿勢である。データ活用を単なる効率化にとどまらない変革の切り札と位置付け、さまざまな挑戦を行っている。その挑戦を成功させるポイントとは──。私たちの生活を支えるインフラの役割を確実に果たしつつ、新しい事業価値の創出にも積極的に取り組んでいる中部電力グループにデータ活用と「DX人財」育成の秘訣を聞いた。
SPEAKER 話し手
中部電力株式会社

澁谷 信幸 氏
DX推進部
DX推進グループ
課長

家喜 景子 氏
DX推進部
DX推進グループ(取材当時)
主任
中部電力パワーグリッド株式会社

柏樹(かしわぎ) 祐輔 氏
システム部
システム戦略グループ
主任
NEC
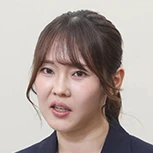
山田 実奈
データドリブンDX統括部
DX人材教育コンサルティンググループ
データサイエンティスト
データを活用し新しい事業価値を創出。その「実践」に必要なものとは
再生可能エネルギーの導入と安定供給、老朽化したインフラ設備の更新、人材不足と技術継承などの課題に取り組むエネルギー産業にもデータ活用による変革の波が訪れている。
例えば、中部電力グループは、データとAIを活用して水力発電の課題解決に道筋を付けた。渓流量の予測、最適な発電計画の策定などによって発電量の最大化、技術と知見の継承、業務の効率化を実現。脱炭素社会の実現に貢献しようとしている。ほかにも電力スマートメーターデータを活用し、電気の使用量からフレイル状態(※)の高齢者を抽出。自治体とも連携しながら介護予防を支援するといったプロジェクトなどを進めている。
このような新しい事業価値創出の挑戦に必要なものとは──。中部電力グループでは、自らデータを活用し、価値創出に向けた取り組みを実践できる「DX人財」が重要だと考えている。
その育成に向けて、同社は複数のプログラムを用意しているが、その中の1つに「データ分析スキル向上研修」がある。なにより実践力を重視し、現場の社員自身がデータを活用し、ビジネスに役立てられるようにすることを目的としている。この研修の企画や運営を担うキーパーソンに学びの内容や成果などを聞いた。
- ※ 加齢により心身の活力が低下し、日常生活に影響を及ぼしている状態
データ活用文化を早期かつ確実に現場に根付かせたい
──データ分析スキル向上研修とは、どのようなプログラムでしょうか。
澁谷氏:当社では、2020年より特徴量設計を自動化するAIデータ分析プラットフォーム「dotData」を導入しています。dotDataは、データ分析の知識を持たない人でもデータ分析を行えるようにし、現場主導のデータ活用を可能にするツールです。解決したい課題に関連するデータを投入すれば、ビジネスの課題解決に役立つインサイトを自動的に見つけてくれます。実際に使ってみると、人だけでは気付くことが難しいインサイトを抽出できる手応えがありました。
データ活用は、分析することが目的ではなく、あくまでもビジネスに役立ててこそ。ビジネスをよく知る現場が中心となることは、データ活用を成功させるポイントだと考えています。そこで、中部電力グループの社員を対象に、dotDataを活用してデータをビジネスに役立てるスキルを最短距離で習得するデータ分析スキル向上研修を立ち上げました。
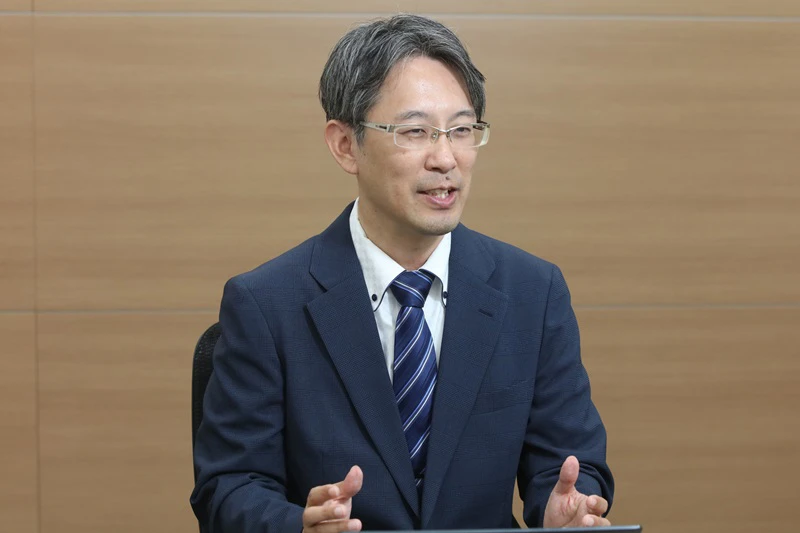
DX推進部
DX推進グループ
課長
澁谷 信幸 氏
──具体的には、どのようなことを学ぶのでしょうか。
家喜氏:研修は4つのステップに分かれており、段階的にスキルを学んでいく構成になっています。
- ステップ1 データ分析基礎研修
データ分析の必要性を知り、活用事例や分析プロセスなど、分析を行う上での基礎を学ぶ - ステップ2 分析ツールハンズオン研修
dotDataを実際に操作しながら、使い方やdotDataが得意とする分析手法について学ぶ - ステップ3 ユースケース策定ワークショップ
各部署が抱えるデータ分析課題を解決するための効果的な課題立案・ゴールの策定方法をワークショップ形式で学ぶ - ステップ4 データ分析OJT(On-the-Job Training)研修
各部署が抱えるデータ分析の課題をテーマに設定し、テーマごとにチーム編成。各チームにアサインされるNECのデータサイエンティストが支援をしながら、dotDataを用いて実際にデータ分析を実施。研修最終回では受講者間で成果を共有しあう
どのステップも重要な研修ですが、現場主導のデータ活用に直接結びつくのがステップ4のデータ分析OJTです。ステップ3までの座学やハンズオン、ワークショップなどとは根本的に違い、ステップ4は受講者自身の業務課題を解決するために、実際に業務で使用しているデータを用いて分析を行います。最終的には、ステップ4で得られた分析結果を通じて、実際に現場の業務が変わることを目指しています。

DX推進部
DX推進グループ(取材当時)
主任
家喜 景子 氏
業務活用につなげるために育成プログラムを再構築
──研修内容を設計する際には、どのようなことを意識しましたか。
澁谷氏:データ分析スキル向上研修は2年目を終え、3年目に向けた検討を開始したところですが、1年目を終了した時点で構成を大きく見直しました。実践力を重視してデータ分析OJT研修を採用していることは変わっていませんが、先ほど紹介した4つのステップはNECと相談しながら 2年目から採用したものです。1年目は、基礎研修とデータ分析OJT研修の2つの構成で研修を開催し、段階的なアプローチも採用していませんでした。
──なぜ見直したのでしょうか。
家喜氏:研修への期待値と実態に若干乖離があり、データ分析OJT研修に参加したもののついて行けなかったという社員が散見されたからです。またデータ分析OJT研修に参加した社員の中には、業務課題とゴールの設定でつまずく人も少なくありませんでした。
例えば、営業担当者なら誰もが「売上を上げたい」と考えますが、データ分析に慣れていない場合、どのデータをどのように分析すれば、その課題を解決できるのかわからないこともあります。まずは、業務課題をデータ分析の課題として再定義する知識やスキルが必要です。データ分析OJT研修の効果を高めるには、そのことを学んでからのぞむべき。そう考えて、2年目からは基礎的な学習であるステップ1から全員がスタートし、dotDataの操作法を学ぶハンズオン、業務課題をデータ分析課題に落とし込むワークショップを経て、データ分析OJT研修へと進む、より体系的な構成に変更しました。
──研修の内容を見直した後の反応や感触はいかがでしたか。
家喜氏:どこまでスキルをあげれば課題を解決できるのか。自身が持つ課題をデータ分析で解決するには、どんなデータをどの程度の量・粒度で用意すべきかなど、受講者自身がデータ分析のステップや価値を理解し、段階的にゴールに近づいていくプロセスが好評でした。
柏樹氏:受講者の期待と、実際に学ぶ内容のギャップを解消できたこともあり、何を学びたいか、どんなデータ分析に取り組みたいかなどの目標がより具体的になった印象です。
また、ステップ3にユースケース策定ワークショップを設けたことが、さらなる実践力の強化につながっています。業務課題をデータ分析課題に落とし込む過程で、これから取り組むデータ分析が業務にどれくらいのインパクトをもたらすか、あるいはもたらすべきかを事前に考える中で、データとビジネスをより結びつける意識が高まるからです。

システム部
システム戦略グループ
主任
柏樹(かしわぎ) 祐輔 氏
OJTで取り組んだデータ分析の一部を実際の業務で運用
──ほかにはどのようなことを意識していますか。
澁谷氏:私たち事務局の姿勢は、少なからず受講者の熱量や本気度に影響すると考えています。NECから支援を受けながら開発したデータ分析スキル向上研修は、NECのデータサイエンティストに研修の講師を行ってもらっていますが、受講者からの問い合わせ対応などはNECに任せるのではなく自分たちで行っています。質問が技術的な内容でNECに聞かなければ正確に答えられなかったとしても、事務局がNECの回答を聞き、咀嚼して、自分たちの言葉に変えて受講者に返しています。事務局を務める私たち自身のデータ分析スキルを高めるためにも、このことを徹底しています。また、グループ会社の事務局間でも密に情報連携をするなどコミュニケーションを取り、最善の活動ができるよう心掛けています。
山田:「自走」を強く意識している事務局の姿勢は、間違いなく受講者のモチベーション向上につながっています。特に2年目のデータ分析OJT研修は、課題意識も業務変革に向かう意欲も非常に旺盛で、その熱意に応えたいとNECの講師陣も自然に力が入っていきました。
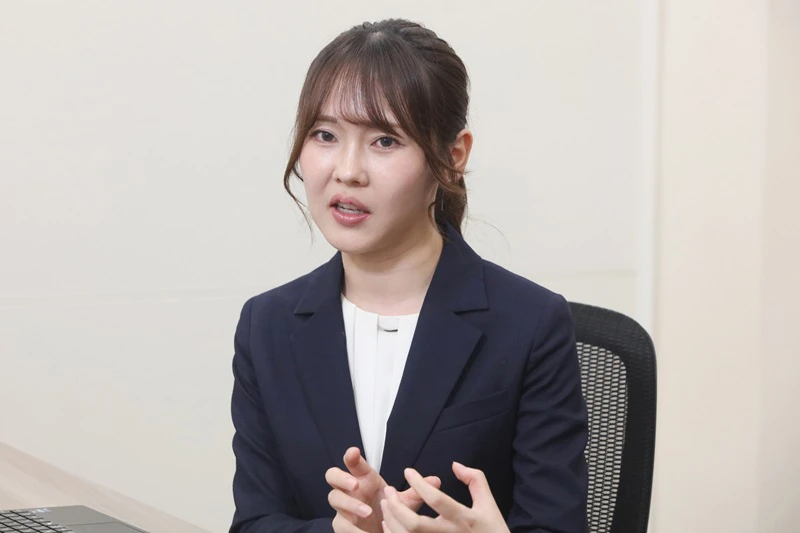
データドリブンDX統括部
DX人材教育コンサルティンググループ
データサイエンティスト
山田 実奈
──データ分析スキル向上研修は、どのような成果を上げていますか。
家喜氏:これまでの2年間の研修の中で、実際に現場の社員がデータを加工し、dotDataを利用して分析を行った結果、徐々に業務の効率化や高度化が見込める案件が生まれています。中には実際の業務で運用する段階に進んでいる事例もあります。
柏樹氏:中部電力グループにはさまざまな業務があり、それぞれ経験豊富な社員が中心となって日々業務を行っていますが、DXによる業務の変革が重要な課題となっています。現場の社員がdotDataを使って自らデータを分析し、自身の業務を変革していく必要があり、この取り組みを通じてデータ分析が本格化すれば、その力が身につくはずです。
──3年目に向けた展望をお聞かせください。
家喜氏:2年目から採用した段階的なアプローチは受講者に好評ですから維持する予定です。改善しようと考えているのはデータ分析OJT研修の最終回で行う報告会です。前回は受講者とその上司などの限られたメンバーで開催しましたが、3年目は全社に公開したいと考えています。受講者には大きなプレッシャーかもしれませんが、研修の意義や成果を多くの社員に伝え、データ分析の必要性を理解してもらうことで、次期の受講希望者数を増やしたり、さらに積極的な姿勢を引き出したりするのが狙いです。dotData のユーザ会に参加した際、ほかの企業の方のアイデアが非常に参考になり、自社でも展開を検討しています。
柏樹氏:ワークショップやデータ分析基礎研修で課題設定のためのスキルを学んでも、社員が各現場で抱えている業務課題をデータ分析課題に再定義するのは簡単ではありません。そこで、3年目を迎えるにあたり、中部電力パワーグリッドでは、データ分析OJT研修の前に社内のデータ分析事例を紹介する「データ分析事例共有会」を開催しています。過去の取り組みを共有し、現場の社員が自身の業務課題に置き換えてデータ分析のアイデアを検討することによりデータ分析OJT研修の参加者の拡大やdotDataの利用案件の増加などによる、社内のデータ分析の浸透を目指しています。
山田:NECからも研修内容の改善を提案しています。中部電力グループ様の受講者様は、姿勢が非常に前向きで、とても真剣です。ですから、動画の閲覧や問題を解く演習などの一部は事前課題にして、講義の時間は講師(データサイエンティスト)の経験を聞く、直接アドバイスをもらうなど、コミュニケーションを多く取れる時間とし、インタラクティブな時間になるよう設計しています。
澁谷氏:現場主導のデータ活用文化を醸成していく取り組みは、まだ続きます。今後も豊富な経験を持つNECの支援に期待しています。






