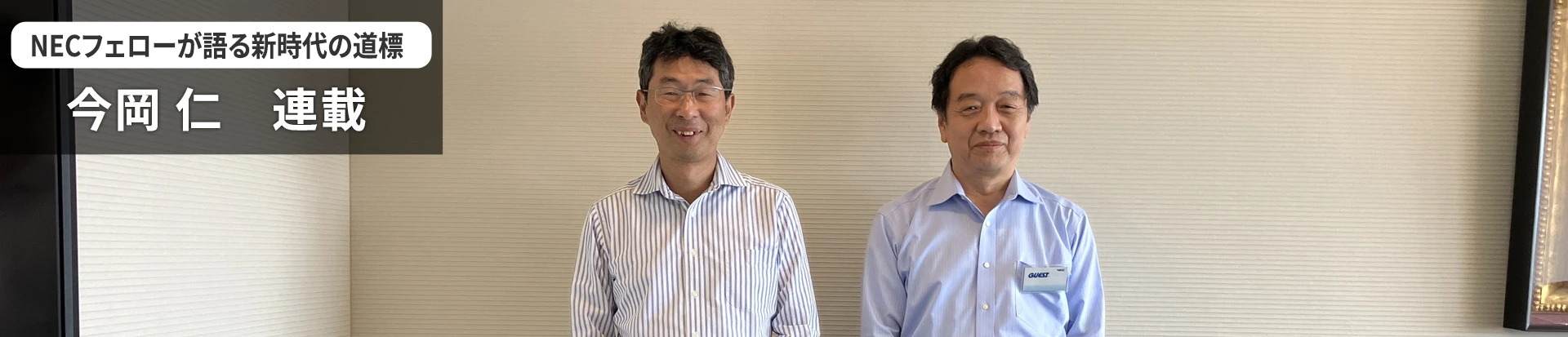
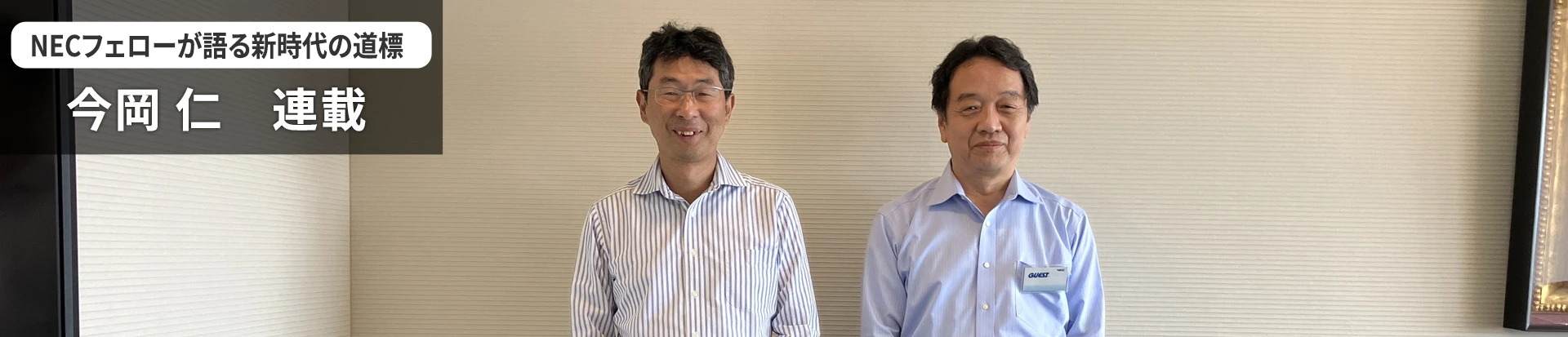
「1:N認証」で広がる生体認証の新時代
改札を顔認証で通過し、イベント会場でも手ぶらで本人確認をする――そんな未来が、いよいよ現実のものとなりつつあります。生体認証技術の発展により、「1:N認証(多人数の中から本人を特定する仕組み)」が実社会で実装されはじめています。しかし、技術の進歩だけでは乗り越えられない課題や、社会全体が納得して安全に使うための仕組み作りも欠かせません。本対談では、生体認証標準化の第一人者である新崎氏とNECフェロー今岡が、1:N認証がもたらす新たな価値、導入現場でのリアルな変化、そして普及への課題と展望について掘り下げます。
SUMMARY サマリー
SPEAKER 話し手
株式会社Cedar

新崎 卓氏
代表取締役
株式会社Cedar代表取締役。1988年に大手電機メーカーの研究所に入所し、生体認証技術及びシステムの研究開発に30年以上従事。指紋認証を搭載した世界初の量産型携帯電話(2003年)の開発に携わる。2022年6月にID・認証を中心に技術調査を行う株式会社Cedarを設立、最新の知見を活かしたアドバイスを提供している。ISO/IEC JTC1/SC 37(バイオメトリクス)の発足当初から20年以上にわたり国際標準化活動に従事し国内委員会委員長も務めた。令和5年度産業標準化事業表彰 経済産業大臣表彰受賞。
NEC

今岡 仁
NECフェロー
1997年NEC入社、2019年NECフェロー就任。入社後、脳視覚情報処理の研究開発に従事。2002年に顔認証技術の研究開発を開始。世界70カ国以上での生体認証製品の事業化に貢献するとともに、NIST(米国国立標準技術研究所)の顔認証ベンチマークテストで世界No.1評価を6回獲得。令和4年度科学技術分野の文部科学大臣表彰「科学技術賞(開発部門)」受賞。令和5年春の褒章「紫綬褒章」受章。東北大学特任教授(客員)、筑波大学客員教授。
なぜ「1:N認証」が求められているのか
今岡:前回の対談では、スマートフォンやパソコンで使われる「1:1認証(本人と端末が一対一で結びつく認証技術)」や、生体認証が私たちの生活にどう浸透してきたかを中心にお話ししました。今回は、さらに一歩進んで「1:N認証」について深く掘り下げていきたいと思います。これは、多人数の中から個人を特定できる生体認証技術です。たとえば将来、改札を顔認証で通過したり、イベント会場で長蛇の列に並ぶことなくサッと入場できたり──そんな未来が、現実になるかもしれません。今回は、その可能性や課題について、新崎さんと一緒に考えていきます。
新崎氏:生体認証の「本人確認」の便利さに期待している方は多いですが、実は皆さんが理想とする使い方は、端末に触れず、その場にいるだけで本人かどうかを瞬時に特定できる「1:N認証」なのではないかと思います。空港の出発ゲートで、荷物を両手に持ったまま、何も取り出さず顔認証でスムーズに通過できる――こんな光景もすぐイメージできますよね。ところが、私たちが普段よく使っているのは「1:1認証」、つまり自分のスマートフォンやパソコンに自分の指紋や顔を登録してロック解除する仕組み、いわゆる「端末と一対一」の認証です。意外に、この違いが一般的にはあまり知られていません。
今岡:たしかに今の1:1認証だと自分だけの端末が必要ですし、スマートフォンが盗まれたり誰かになりすましされたりするリスクも残っていますよね。逆に、1:N認証なら「その場に立つだけ」で本人確認ができるので、もっと簡単で、セキュリティが強くなる側面もあると感じます。
新崎氏:はい、実際に「手ぶら」で認証できることへの期待は高まってきています。たとえば買い物のレジでも、財布やスマートフォン、カードを出す必要がなく、顔認証で決済までできれば、これまで以上に便利になりますよね。
今岡:1:N認証がうまく機能すれば、改札やレジ、イベント会場なども、行列や待ち時間が解消されて、社会全体の効率化にもつながりそうです。
新崎氏:そうですね。加えて、「救急時の本人確認」など、より社会的な分野でも1:N認証の活用が期待されます。たとえば今年10月から全国で始まった「マイナ救急」の仕組みでは、急病や事故現場で本人確認が必要な場面で、今はマイナンバーカードが手元にないと使えないケースがあるのですが、もし生体情報の事前登録が可能なら、1:N認証を活用してその場で本人確認ができ、カード不携帯でも迅速に医療サービスを受けられる。これは大きなメリットです。また、精度をより高めるために、顔、虹彩や静脈など複数の生体情報を登録しておくという対策も考えられます。将来的には「マイナ救急」の仕組みと1:N認証を連動させることで、より安心かつ実効性の高い本人確認システムを実現できるのではないでしょうか。
ただ、「手ぶら」で便利になる一方で、本当に本人なのかを正確に判定できるのか、そしてセキュリティやプライバシーの問題にどう対応するかは、常に大きな課題です。1:1認証でも不正利用のリスクはありますが、1:N認証では多数の人の中から特定する仕組み上、万一起きた場合の影響範囲も大きくなる点は注意が必要です。特に、本人の同意なく生体情報が使われてしまうと、社会全体への不信感にもつながりかねません。ですので、利便性とともに、安全性・プライバシーにどう配慮するかが課題です。

今岡:確かに「便利さ」と「安心・安全」のバランスは非常に重要ですね。そもそもですが、こうした1:N認証がこれまであまり一般化しなかった理由はどんなところにあったのでしょう?
新崎氏:やはり大きかったのは、技術的な壁ではないでしょうか。1:N認証の場合、「本人を確実に見つけ出す」ための認証精度、それから大量の情報を一瞬で処理する速度、この2つにどうしても限界がありました。
今岡:「本人なのに認証されない」という本人拒否率の問題や、「本人と他人とを誤認してしまう」リスクも広く社会で導入するには越えなければならない課題でした。
新崎氏:しかしここ数年でAI技術やセンサーの精度などが上がり、同時に生体認証を日常で使う機会が増えたことで、技術的・心理的なハードルも下がってきたと感じます。また、生体認証の精度評価方法に関する国際標準のISO/IEC 19795シリーズやISO/IEC 5152がととのいましたi。加えて、顔認証については、NISTが随時ベンダーから提供されたアルゴリズムを評価してWebサイトで検証結果を公表しています。今岡さんもベンチマークテストを受けられたので良くご存じと思いますが、Face Technology Evaluations - FRTE/FATE iiというサイトです。ここで示されている結果は、どのくらいの人数で1:N認証を利用する事ができるかという目安にもなると思っています。さらに、NISTでは政府職員向けの認証ガイドライン(SP800-63-4)も発行しており、同ガイドラインでは生体認証単体では認証手段として推奨されていません。必ず他の認証要素と組み合わせて使うことが求められています。これはあくまで「政府職員向けの高いセキュリティレベル」を想定したルールなので、民間や日常利用では、目的やリスクに応じて柔軟に運用されているケースも多いです。少額決済と高額決済で求める認証方式が違うように、用途によって適切なルールが必要ということですね。
今岡:おっしゃる通り、技術の進歩やルール整備によって、社会全体の生体認証への受け入れが着実に進んでいると感じます。実際、顔認証もこれまでのような「特別な場面」から、最近ではスマートフォンのロック解除やオフィスの入室など、日常的に使う場面が広がっていますよね。その経験の積み重ねが1:N認証に対する社会全体のハードルや抵抗感を低くしているのかもしれません。同時に、こうした技術がより安心して使えるためには、やはり制度やルールづくりも欠かせない要素だと思います。
新崎氏:ええ。さらに大事なのが、まさに制度やルールづくりです。例えば個人情報の取扱いに厳しい欧州では生体認証の利用範囲や方法に厳しいルールを徹底し、利用目的を説明した上での本人同意の取得など、運用の透明性を高めることで社会的な信頼感を得ています。日本でも同様に、利用目的や安全管理の仕組みの整備が進みつつあり、今後ますます「安心して使える」環境が整っていくと思います。
-
i
ISO/IEC 19795-1:2021 Information technology — Biometric performance testing and reporting Part 1: Principles and framework, https://www.iso.org/standard/73515.html
(参照 2025-10-09)
-
ii
Face Technology Evaluations - FRTE/FATE, https://www.nist.gov/programs-projects/face-technology-evaluations-frtefate
(参照2025-10-09)
導入事例から見える1:N認証の可能性
今岡:実際の現場で、1:N認証が導入されたことでどのような変化がありますか?
新崎氏:まず、利用者の体験が大きく向上しているのではないかと思います。たとえば茨城県那珂市の図書館では、手のひらの静脈認証と生年月日を組み合わせた仕組みが導入されていて、手ぶらで本を借りられるという便利さが評価されています。このケースは厳密には1:1または1:少数の認証ですが、カードレスで手続きを簡単にするという点では1:N認証に近い発想です。この図書館では生体認証への抵抗感を考慮して、カードによる図書館利用登録も可能ですが、成長期のため手のひらの静脈登録を選択できない小学生以下を除いて8割を超える利用者がカードレスの静脈登録を選択するそうですiii。
今岡:生体認証をPINコードやスマートフォンのGPS情報などと組み合わせて多層的に使うことで、安全性と利便性のバランスも取れるということですね。たとえば子どもや高齢者など、カードやスマートフォンを持つのが難しい層にも有効な気がします。

新崎氏:おっしゃる通りです。すべてを1:N認証だけに切り替えるのではなく、既存の方法や状況に応じて段階的に複数の認証手段を併用することで、現場の使いやすさや安心感を高めることができます。
今岡:イベント会場の入場や、混み合うテーマパークでの顔認証入場などは、待ち時間の短縮やセキュリティ強化にもつながるので、体験価値が大きく変わりますよね。
新崎氏:そうですね。スポーツイベントやライブ会場などで事前登録した顔情報とチケットを紐付けておけば、ゲートで素早く本人確認ができて、チケットの転売や不正入場防止にも大きな効果が期待されます。主催者側にとっても運営がスムーズになり、人員コストの削減や安全性向上にもつながるでしょう。スポーツイベントやライブ会場では、短い休憩時間に飲み物やグッズを買いたいですよね。事前に生体認証で決済できるように登録できれば利用者の行列ストレスも減り店舗の売り上げも上がるというメリットしかありません。スマートフォン決済も取り出してアプリを起動するまで意外と時間がかかりますから。今後この流れは、さまざまな分野にさらに広がっていくと思います。
今岡:現場で得られたフィードバックや、実際のリアルな利用体験が、技術の改善や新たな課題発見にも役立ちそうですね。
新崎氏:はい。現場での試行錯誤から、より利用しやすく安全な社会インフラとしての1:N認証が育っていくのだと思います。同時に、実際に使ってみなければ見えてこない課題やニーズも必ずあります。そうした「現場の声」を丁寧に拾って、技術・運用・制度をバランスよく発展させることが何より重要です。
-
iii
小泉周司「いつでも気軽に立ち寄れる図書館を目指して ―那珂市立図書館におけるカードレスへの取り組み」, 情報管理 49 (11), 611-621, 2007 https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/49/11/49_11_611/_pdf
(参照2025-10-09)
安心して使うための課題と社会的な仕組み
今岡:やはり、どんなに技術が進化しても、現場のリアルな声や実際の使い勝手に耳を傾けながら改善していく姿勢が今後の普及には欠かせませんね。また、新しい技術が社会に根付くにはセキュリティやプライバシーに対する安心感をどう醸成していくのか、という点も重要だと感じます。
新崎氏:おっしゃる通りで、技術そのものの安全性だけでなく、「どのようにデータを管理しているか」「悪用や漏洩のリスクをどのように抑えているか」といった運用体制への透明性が不可欠です。信頼を高めるためには、仕組みや制度の細かな説明や、利用者が納得できる情報発信を継続していくことも大切ですね。たとえば海外の先進事例ですが、韓国のKFTC(韓国金融決済院)は生体認証のプラットフォームを金融機関や公共サービス向けに提供しています。ここでは、登録データを分割して別のデータベースに保存しておき仮に片方の認証要素が漏れても安全性が確保できる設計や、データの目的外利用を厳格に禁止する制度が敷かれているなど、透明性の高い運用が進んでいます。こうした姿勢が利用者の信頼につながり、生体認証社会の土台を築いているのだと思います。また、これらの内容はISO/TC68で策定された、金融サービスでの生体認証セキュリティを規定するISO 19092の改訂版(2023年)にも記載されています。
今岡:まさに、技術的な進化と同時に、制度面や文化面での「納得感づくり」が普及には欠かせないと感じます。特に日本では、セキュリティや個人情報保護に厳しい視線が向けられている分、透明性や説明責任がより問われるのかもしれませんね。
新崎氏:「納得感づくり」はじつに的を射た言葉だと思います。漠然とした不安や誤解をなくし、本当にできること・できないことを正しく伝えるべきです。たとえば「1:N認証を使えばどこでも自分を特定されてしまうのでは」といった懸念も見受けられますが、実際には個人情報保護法、各種ガイドラインや国際標準により運用ルールが整備されたうえで慎重に導入する環境も整ってきています。技術面でも、情報が悪用されにくくする工夫や、利用範囲の明確化など、現場ごとでも対策が進んでいます。
今岡:やはり、技術の進化や制度の整備だけでなく、「それをどう使うべきか」というエシックス(倫理)の視点もますます重要になっているように感じます。こうした新しい技術が社会に根付くには、「安心」や「納得感」を生み出すための地道な取り組みや分かりやすい説明、オープンな対話が必要ですね。今回の対談を通じて、「安心して便利に使える社会」を目指す意味や、そこに向けた課題・工夫を知ることができて、とても参考になりました。
新崎氏:ありがとうございます。「安心して便利に使える社会」を実現するためには、技術の進歩だけでなく、透明性のある運用や利用者目線での説明、そしてまさにエシックスに根差した仕組みづくりが欠かせないと感じています。現場の声や利用者のリアルな体験を踏まえながら、「どんな仕組みなら誰もが納得して使えるのか」を常に考え続けていきたいと思っています。
今岡:本当にその通りですね。今後1:N認証をはじめとした本人確認技術は、行政サービスのデジタル化や医療、教育、交通インフラなど、私たちの暮らしのさまざまな場面へとさらに広がっていくと思いますが、そのたびに技術面だけでなく制度や社会的な合意形成がセットで求められるはずです。私たち自身も、疑問や課題を社会と共有しながら、オープンな議論・発信をこれからも続けていきたいと考えていますし、技術と社会の健全な関係づくりには、こうした対話と改善の積み重ねが何より大切だとあらためて感じました。私自身も今後ますます現場の声に耳を傾けつつ、「みんなが安心して使える認証社会」の実現に向け、学びと発信を続けていきたいと思います。本日はありがとうございました。
新崎氏:ありがとうございました。
【編集後記】
今回の対談では、多人数から個人を特定する生体認証の最新動向と現場での活用事例、そして社会に技術が広がるために必要なことを新崎さんと深く掘り下げることができました。
対談を通じて改めて感じたのは、どんなに便利で高度な技術であっても、使う人が納得して受け入れられるように工夫することが大切だということです。技術的な安全性や制度の整備だけでなく、利用者の目線に立って説明し、透明なルールや運用を積み重ねることが信頼につながります。納得感づくりは、技術を広める上で欠かせないテーマだと強く思いました。
これからも、現場の声や体験から見えてくる課題に向き合いながら、安心して使える認証技術や仕組みについて考え、発信を続けていきます。この記事が、生体認証や本人確認について考えるきっかけとなれば嬉しく思います。今後も皆さんからのご意見や質問をお待ちしています。


NECフェローが語る新時代の道標




