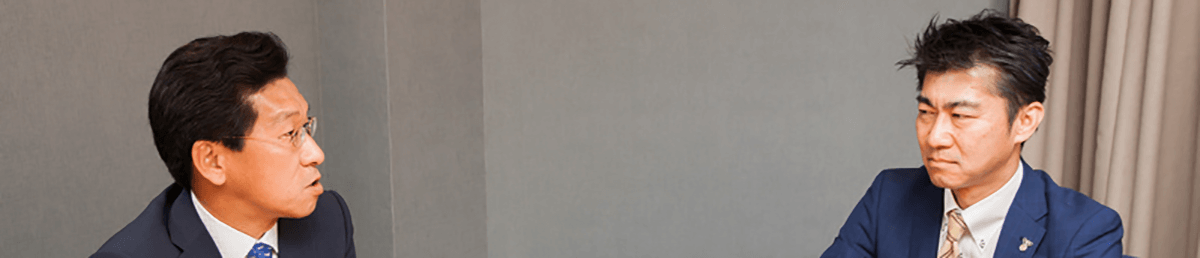2016年06月24日
インダストリー4.0最新動向、日本・ドイツ・アメリカが目指す未来とは
GEとアクセンチュアが対談、第4次産業革命がもたらす「カルチャーチェンジ」とは(前編)
製品が「利用」を起点に大きな価値を生み出す
──2016年4月には、世界最大の産業機械の展示会である「ハノーバー・メッセ」がドイツで行われ、メルケル首相とオバマ大統領が参加して世界的にも大きな注目を集めました。

清水氏:
ハノーバー・メッセはモノづくりのイベントで大きな注目を集めましたが、インダストリー4.0はモノづくりに限った話ではありません。
インダストリー4.0と言うと、大量生産から、もっとカスタマイズされたモノづくりへのシフトと捉えられがちですが、それは全体の構想のほんの一部に過ぎないのです。目指しているのは、製品が製造・販売・利用され、メンテナンスされるに至る「すべてのプロセス」におけるデータがクラウド上に集められる。つまり「ハードウェアの動きがサイバー空間上ですべてわかる」ということです。
──製品のあらゆるライフサイクルで、プロセスが記録され、データがクラウドに蓄積されて価値が生まれるということでしょうか。
清水氏:
モノづくりがデジタル化することにより、製品の「利用」を起点にして価値が生まれるというのがインダストリー4.0とインダストリアル・インターネットの本質です。背景には、製造における「プロフィット・プール(利益の塊)」の大きさが、安価な労働力を背景にスケールとスピードに左右されるものとなり、どんどん縮小しているということがあります。
今までの経済は、「資源を取り(Take)」「作って(Make)」「捨てる(Waste)」の連環でした。しかし、今後は、「作る(Make)」「使う(Use)」「何度でも使う(Use Again)」の連環にシフトしていきます。
つまり、製品は消費されて終わりではなく、利用されてからより大きな価値を生み出す。そこが、インダストリー4.0が注目されている理由ではないかと思います。

新野氏:
GEはグローバルに約400ヶ所の工場がありますが、オートメーションがとびきり進んでいるわけではないですし、日本の工場のようにカイゼンが進んでいるわけでもありません。
ただ、製造、業務プロセス全体をEnd to Endで見て、どこかに問題があったときに、「だれが」「何を」「どう対処しているか」を見て、最も簡単で、早く効果が出るところを、デジタル化で解決しています。日本の製造現場はカイゼンが進んでおり、製造プロセスには無駄がなくリーンですが、デジタル化という意味ではまだまだかもしれません。一方でGEは、カイゼンは足りないが、デジタル化は進んでいます。
リーンであることと、IoTすなわち、「カイゼン」と「デジタル化」は両立する考え方だと思います。日本の製造業は、デジタル化によって価値を生み出す余地がまだまだあると考えます。