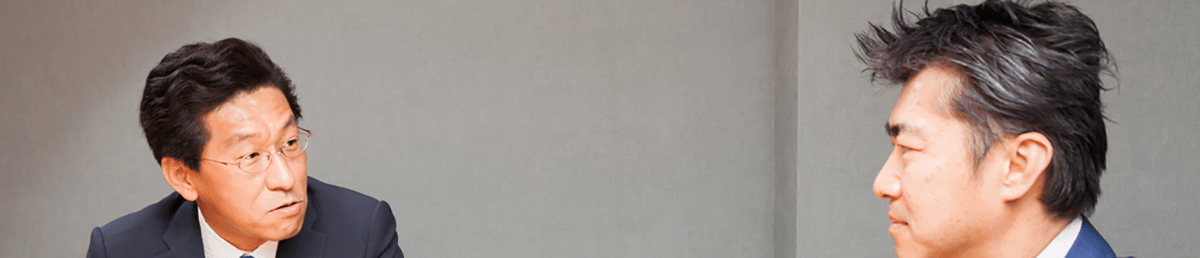2016年07月15日
インダストリー4.0最新動向、日本・ドイツ・アメリカが目指す未来とは
「モノ発想」から「アウトカム発想」へ、第4次産業革命では「実行力」が欠かせない(後編)
デジタル化によって、製品の「利用」を起点に価値を生むというのが「インダストリー4.0」や「インダストリアル・インターネット」の本質だ。それは、あらゆる企業にとって、「モノ発想」から「アウトカム発想」への転換が急務であることを意味する。前編に続き、後編では、GEデジタル インダストリアル・インターネット推進本部長の新野 昭夫 氏と、アクセンチュア 執行役員 戦略コンサルティング本部 統括本部長の清水 新 氏に、インダストリー4.0、インダストリアル・インターネットがもたらす未来や、日本企業がどのように戦っていくべきかについて伺った。

現場力、すなわちホワイトとブルーが融合した「水色ワーカー」が日本独自の強み
──「アウトカムプロバイダへの転身」について詳しく聞かせてください。既存の技術の「積み重ねの発想」ではなかなか難しいと思いますが、このあたりをどう見ますか。
清水氏:
これまで、製品の機能や性能、品質を売ってきたGEが、今までの価値観を変えて、アウトカムに事業のポジショニングを変えようとしています。産みの苦しみもありますが、カルチャーも考え方も行動も変えようと実践しているところがGEのすごさだと言えます。取り組みを始めている日本企業もありますが、ここから先は行動の「スピード感」がものを言います。
──マニュファクチャリングの改善では、日本にも独自の強みがあります。日本ならではの強みを生かす方法はないのでしょうか?
清水氏:
たとえば、海外ではホワイトカラーとブルーカラーの職能が明確に分かれていますが、日本の「カイゼン」は、データを見ながら、現場がその場で改善しています。これはいわば、ホワイトとブルーの部分が融合した「水色」で勝負してきたと言えます。
需要から生産までのプロセスがEnd to Endでつながって、製品を利用する側にプロフィットが移っていく中で、「水色ワーカー」が製造業の変革を主導していくことに注目すべきです。そこが日本の勝つチャンスです。
──海外を追随するのではなく、日本独自の強み、価値を生かす産業革命のアプローチがあるということですか。

清水氏:
どこが独自かを見極めることは重要ですが、最終的にはデータを持ち得た者が勝ちます。つまり、インダストリー4.0やインダストリアル・インターネットは、データからインサイトを得て価値を作るため、「データをより多く集める」ための戦いとも言えるでしょう。データを集めるプラットフォームは必ずしも自前である必要はなく、オープンなプラットフォームを活用してスピーディに価値を生み出すことが重要です。
新野氏:
GEは、クラウドベースのプラットフォーム「Predix(プレディクス)」を提供していますが、最初から「ハードウェアをネットワーク化するためのプラットフォーム」という構想があったわけではありません。
最初は、単純に自社のハードウェアを売るための仕組みと考えていました。そのうちに、「自社の製品でなくても使える、産業界に特化したクラウドベースのシステム」として提供したほうが価値を生み出せるのではないかと、コンセプトを固めていったのです。
──GEは、オープンの重要さ、オープンであることが競争力を生むことにいつ頃から気づいたのですか。
新野氏:
世の中に必要とされるものは、何かが起点となっています。GEも、以前はすべてを自前主義で作る思想がありました。それが20~30年くらい前から、だんだん自前主義の限界を感じ始め、研究所をドイツやインド、中国などの海外に設立し、グローバルの技術を集め、日本企業の技術も継続的にウォッチしながら「オープンイノベーション」にシフトしてきました。