

私たちは創造性を育んだことがあるか
学校だけど「教えない」理由
福島県の富岡第一小中学校を舞台に「PinS(プロフェッショナル・イン・スクール)」というプロジェクトが行われている。大工や芸術家、画家が転校生となり、学校に滞在。子どもたちと一緒に過ごすという新しい教育の試みだ。ただし、プロが教壇に立つわけではない。基本的には「教えない教育」なのだという。実際に現地を訪問し話を聞くと、この取り組みが大人である私たちや、ビジネスにも関係深い取り組みであることがわかった。
イノベーション、クリエイティブとはいうけれど
「イノベーション」「クリエイティブ」「創造」──。近年、ビジネスの世界では、新たな価値を創出する「力」が重視されている。だが、私たちは、その力を発揮するためのスキルをどこかで学んできただろうか──。
福島県浜通り、双葉郡のほぼ中央に位置する富岡町。2011年の東京電力福島第一原発事故以来、閉鎖されていた町内の小学校、中学校が、昨年の4月に再開した。
震災前、富岡町には小学校と中学校が2校ずつあり、合計で1500人近くの子どもたちがいたという。再開後は、4校が「富岡校」として1つの校舎に集約され、子どもの数は小中学校合わせても30人ほど。数字は厳しい現実を物語るが、子どもたちの笑い声が響く校舎が、地域にとって希望の光なのは間違いない。
再開された富岡校は、外に向けて開かれ、多くの町民が訪れる地域コミュニティ創造の拠点ともなっている。教師以外の大人たちと接することができる機会もまた、子どもたちの成長に資するという考え方が背景にある。
その道のプロが「転校生」として学校に滞在し、作品づくりを行う
このような富岡校における新しい教育を象徴するプログラムの1つが「PinS(プロフェッショナル・イン・スクール)」プロジェクトである。これは、芸術家が、ある土地や施設に滞在しながら創作活動を行う「アーティスト・イン・レジデンス」の学校版ともいえるが、いわゆる「芸術家」に限らないところが特徴でもある。
「アーティストはもちろん、建築家、音楽家、伝統工芸の職人など、クリエイティブな職種の方々を“プロフェッショナル”と位置付けています。一定期間滞在し、校内で仕事をするだけでなく、子どもたちと同じ時間に当校し、給食を食べ、授業にも参加する。期間限定の“転校生”だと子どもたちには紹介しています」とプロジェクトの運営に携わる、NPO法人インビジブルの林 曉甫氏は語る。

理事長
マネージング・ディレクター
林 曉甫 氏(あきお)
プロジェクトの初年度となった2018年度は、岡山県を拠点に活動する大工の林 敬庸(たかつね)氏が転校生となり、毎月数日ずつ滞在。子どもたちと学校生活を送りながら作品の制作を行なった。
制作したのは、新しい学校のシンボルになるような大きなテーブルだ。水戸~仙台間の陸前浜街道には、以前、台風で倒れた樹齢350年の巨木があり、富岡町が伐採し、保管していた。その木材を使ったのである。

「教えない教育」で、子どもたちの自発性と柔軟な発想を育んでいく
「日常ではなかなか出会えない職能の人と出会い、子どもたちの興味や好奇心を開花させる狙いがありますが、それだけではありません」。学校の再開にあたり教育振興計画検討委員会の委員長を務めたインビジブルの菊池 宏子氏は言う。
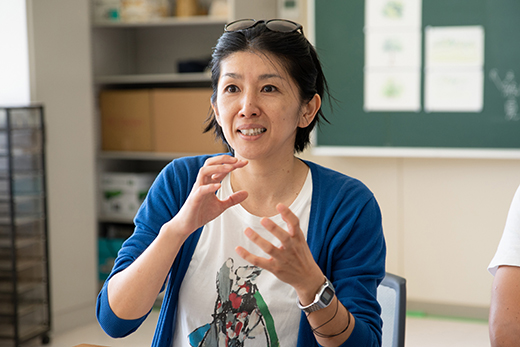
アーティスト
クリエイティブ・ディレクター
菊池 宏子 氏
滞在するプロは、学校での活動を契機に作品への向き合い方、福島に対するスタンスを見いだしていく。新しい試みが行われていることをきっかけに、地域の人々が学校に足を運ぶ。「アートを軸にした活動から、コミュニティの輪をつくり、それを広げていきたい」と菊池氏は言う。
学校に滞在するプロと子どもたちの関係性も、いわゆる学校教育の姿とは異なる。プロが教壇に立ち、子どもたちに何かを伝えることはない。定期的に登校するプロは、決まった場所で創作に取り組み、そのプロの仕事をすぐそばで見ることができる機会をつくることで、子どもたちの観察力、洞察力、子どもらしい柔軟な発想を見いだす。「教えない教育」で、詰込み型の教育の中で埋もれがちな個性を開花させたい。そんな思いが込められている。
実際、子どもたちの反応はどうだったのか。昨年、転校生として滞在した林 敬庸氏は、カンナやノミなど、鋭利な刃を持つ道具を使う。「危ないからさわってはいけない」と子どもたちに注意しておきたいところだが、教えない教育では、あえて何も言わない。だが、子どもたちは、自ら危険なことを肌で感じ、「勝手にさわらないこと」というルールを自らつくったという。
また、作業後には大量の木くずが出て、それを掃除するまでが大工の仕事だと林 敬庸氏は捉えている。その姿を見た子どもたちは、林 敬庸氏がいない日も作業場となっている教室や自分たちの教室など、自発的に掃除するようになったそうだ。
ビジネスと教育のギャップを埋めることができるかもしれない
インビジブルの理事を務める赤司 展子氏は、以前、経営コンサルタントとして働いていた経歴を持つ。実は冒頭の問いは赤司氏が抱えていた疑問だ。

理事
社会彫刻家
赤司 展子 氏
「ビジネスの現場では、既存の枠に縛られない新しいアイデア、イノベーションの重要さが叫ばれていますが、教育の現場は旧態依然としたまま。卒業するまでは、1つの答えを、できるだけ効率よく導く方法を教えられているのに、社会に出ると突然、イノベーションを求められる。ビジネス現場と教育現場の乖離を感じていました」と赤司氏。だが、PinSプロジェクトを通じて、教えない教育に、そのミゾを埋めるヒントがあるのではないかと感じているという。
このヒントを1つの手応えとしながら、赤司氏は、次の教育施策、プログラムについて、地元の教育委員会などと、日々、話し合いを継続している。
林 曉甫氏、菊池氏、赤司氏が所属するNPO法人インビジブルの活動指針は「見えないものを可視化する」というもの。アートを触媒にしたプロジェクトを展開し、見えないものを可視化することで、社会を動かす小さな変化を生み出し続けている。
「アートというと、絵画や彫刻など形のあるもの、目に見えるものを連想すると思いますが、それはアートの1つの側面と私たちは考えます。アートには、ある種の触媒として、人々の想像力を拡張させる機能もあるはずです。それはインビジブル、目で見ることはできないもの。ですが、子どもたちの人生観、死生観に影響を与えるし、大人たちは自分の立ち位置を再考するかもしれない。異なる価値観を持つ人同士がつながり、多様性にあふれた地域社会をつくるきっかけにもなる、大切なもの。この考えを社会に反映させるには教育とのかかわりが必要と考えたことが、PinSプロジェクトにつながっています」と菊池氏は言う。
2年目を迎えて見てきた課題をどう解決していくか
1年目を終え、2年目を迎えたPinSプロジェクトの今年度の転校生は、画家の加茂 昴氏。今回も学校のシンボルとなるような大きな油絵を描く予定だ。
また、現代芸術家の宮島 達男氏を転校生として迎え、「コミュニティの拠点となる学校づくり」も目指す。ここでは、数回にわたってワークショップを開催し、富岡町民と富岡第一小中学校の児童・生徒と共に作品づくりを行う。
取材に訪れたのは、まさにこの日。制作するのは、宮島氏が東日本大震災の犠牲者の鎮魂のために取り組んでいる「時の海‐東北」というプロジェクトの作品だ。子どもたち一人ひとりが自分の好きな数字を選び、それをLEDライトの点滅時間に設定し、全員で1つの作品づくりを試みた。
宮島氏の話を聞き、子供たちは思い思いの数字を選ぶ。数字を書いた用紙は回収され、宮島氏の手によって、その日のうちに作品として仕上げられ、子供たちの前で披露された。できあがった作品の美しさ、雰囲気だけでなく、自分たちの意思、選択が作品に反映される喜びに、子供たちは目を輝せる。


ただし、プロジェクト全体を通じては課題も見えてきている。富岡町での活動を継続しながら、次の展開を考える時、「ジレンマもある」と菊池氏は話す。
富岡町は、震災、原発事故とは切り離せないが、PinSプロジェクトは、決して復興支援ではなく、あくまでも、クリエイティブな観点からの新しい教育へのチャレンジだ。ゼロベースで新しい教育を構築できた富岡町にしかできない取り組みであってはならない。
「震災からの復興が背景にありますが、その文脈に限定すると広がりがなくなってしまう。富岡町での取り組みをベースに、地域、状況に合わせてどう転用できるかを考えなくてはいけません。また、継続してはじめて成果が見えてくる取り組みでもあり、継続させるにはビジネス、経営的な視点も必要になるでしょう」(菊池氏)
PinSプロジェクトが、教育改革や社会課題の解決に直に結びつくようになるのは、このような課題を乗り越えた先になるのかもしれない。しかし、「目に見えない」成果を積み上げることで、少なからぬインパクトを与えられるはずだ。
「教育だけではありません。私たちは、インビジブルの活動とビジネスもまた親和性が強いのではないかと感じています。教育現場、地域社会にはさまざまな課題がありますが、アート×ビジネスで、目に見えないものを感じ取りながら、さまざまな人たちと課題解決の方法を一緒に考えていきたいですね」と林 曉甫氏は話す。
創造と現代社会、そして教育。アートを新しい力に変えて社会を動かしていく。取り組みはまだ、始まったばかりだ。

「invisible to visible(見えないものを可視化する)」をコンセプトに活動するクリエイティブプレイス。見えないものを可視化し続けることで、社会を動かす小さな変化を生み出していく。アート、文化、クリエイティブの力を用いて、地域再生、都市開発、教育など、幅広い領域で新プロジェクトを企画運営している。
https://invisible.tokyo/



