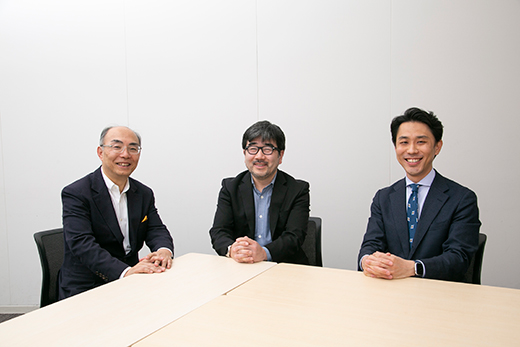米国、中国の最新デジタル化動向と日本企業が目指すべき成長戦略とは
~wisdom特別セミナー「デジタル時代の新ビジネス」講師3名による座談会~
あらゆるモノやサービスのデジタル化が進んでいる。デジタル化への対応は経営の必須命題である。世界に目を向ければ、データ活用先進国の米国、急速にデジタルサービスの普及が進む中国の存在感が際立つ。その中で、日本企業が勝機を掴むためにはどうすべきか。中国事情に詳しい亜細亜大学大学院 アジア・国際経営戦略研究科講師の田中 信彦氏、米国小売業界のマーケティング事情に詳しいデジタルメディアストラテジーズ社代表の織田 浩一氏、NEC FinTech事業開発室長の岩田 太地が語り合った(本文中敬称略)。
SPEAKER 話し手
デジタルメディアストラテジーズ社

織田 浩一 氏
代表
米シアトルを拠点とし、日本の広告・メディア企業、商社、調査会社に向けて、欧米での新広告手法・メディア・小売・AIテクノロジー調査・企業提携コンサルティングサービスを提供。著書には「テレビCM崩壊」「リッチコンテンツ・マーケティングの時代」「次世代広告テクノロジー」など。現在、日本の製造業向けEコマースプラットフォーム提供企業Aperzaの欧米市場・テクノロジー調査担当も務める。
亜細亜大学大学院

田中 信彦 氏
アジア・国際経営戦略研究科(MBA)講師(非常勤)
前リクルート ワークス研究所客員研究員
1983年早稲田大学政治経済学部卒。新聞記者を経て、90年代初頭から中国での人事マネジメント領域で執筆、コンサルティング活動 に従事。リクルート中国プロジェクト、フファーストリテイリング中国事業などに参画。上海と東京を拠点に大手企業などのコンサルタント、アドバイザーとして活躍している。
NEC

岩田 太地
FinTech事業開発室長
NECにてFinTech関連のビジネスを推進。 社内起業として三井住友銀行とジョイントベンチャー(brees corporation)を立ち上げ、現在取締役として従事。ブロックチェーンの国際的オープンソースコミュニティであるHyperledgerプロジェクトのGoverning Boardメンバー。
中国で急速にデジタル化が進行する理由とは
岩田氏:デジタル技術を活用してサービスや事業の変革を目指す「デジタルトランスフォーメーション(DX)」は世界中でホットな話題になっています。なかでも世界経済の中で大きな存在感を示す米国と中国の動向は、多くのビジネスパーソンにとって気になるポイントです。
織田氏:米国の小売業界では、ダイレクトメールに代表されるように半世紀ほど前から顧客データの利用を始めています。その後、インターネットやモバイル、CRMの普及などに伴い、データ基盤がプラットフォーム化され、現在はオンライン/オフラインのデータを統合した「CDP(カスタマーデータプラットフォーム)」の活用が進んでいます。
これは、顧客一人ひとりの属性やオンライン/オフラインの行動データを分析することで、様々な予測を可能にする手法。CDPの活用により、対前年比の売上が10%以上向上した企業もざらにある。セールスやマーケティングにおけるデータ利用が一般化しています。
田中氏:広大な中国の通信サービスはモバイルが前提です。4Gモバイル通信の利用者は10億人、アリババグループのオンライン決済サービス「アリペイ」の利用者は9億人を突破しました。
当然、Eコマースの利用が盛んです。昨年の「独身の日」のアリババのネット通販セールの取扱高は3.5兆円。たった1日でその前年の楽天のネット通販の取扱高を超えてしまいました。国土が広大なので、モノの輸送にドローンが活用され、より輸送力を高めた無人飛行機の開発も進んでいます。
岩田氏:米国ではネットでも実店舗でもクレジットカードの利用が普及していて、中国はアリペイに代表されるように電子マネーが社会に浸透しています。それに比べると、日本はまだ現金主義が根強いですね。
田中氏:日本は駅やコンビニに行けば、ATMが普通にある。金融や通信など成熟した社会インフラをベースにデジタル化を進める日本に対し、中国は社会インフラが未成熟なところにモバイルインターネットの波が押し寄せ、人々も急速に富裕化していきました。日本が歩んできたようなステップを一気に飛び越え、既存の仕組みや既得権のない領域にデジタル技術が登場したため、それが広がるスピードも段違いに速いといえます。
既存事業の延長線上から新しいものは生まれない
岩田氏:日本ではまだDXの成功例は少ないのが現状です。例えば、新規事業を始めようとしても、これまでの事業の継続でものごとを考えていたら、成功は難しいでしょう。既存のものに手を加えるのは「改善」であって「創造」ではない。新しい着眼点、新しい発想、新しい思考回路が必要だと思います。日本の経営者も従業員も変わっていかなければいけない。そんな思いをひしひしと感じています。
織田氏:リスクをどこまで受容できるかということですね。既存の意思決定プロセスに乗った時点で、それは難しくなる。今までと違うやり方が必要なのに、それが許されないからです。高度経済成長やバブル期の成功体験を知っていると、そこから抜け出せない。スタートアップで成功を収める企業が多いのは、そういうしがらみがないからでしょう。
米国では有望なスタートアップには、ベンチャーキャピタルからどんどん投資が集まります。それが新たなチャレンジを後押ししてくれる。日本でも市場から投資を募るやり方は増えてきていますが、ハードルは高い。企業の社内ベンチャーのような形で、しがらみのない若い世代をバックアップする体制がもっと増えてくれればいいと思っています。
田中氏:中国での事業展開を考えている経営者やビジネスパーソンは、日本式のものをそのまま持ち込んで売ろうと考える。そんな印象が強いですね。昔は中国と日本では技術力にも差があったので、いいモノを作ればそれだけでよく売れた。しかし、特殊な一部の分野を除き、もはやその差はほとんどないに等しい。日本製だからというだけで、中国で売れるとは限りません。

日本流の考え方が「勝ちパターン」を狭くしている
岩田氏:田中さんは著書『スッキリ中国論 スジの日本、量の中国』(日経BP社)の中で、中国社会と日本社会の「違い」を指摘されていますね。どのような「違い」があるのですか。
田中氏:まず人々の意識や行動パターンが違います。日本人は1つの仕事に打ち込んで経験を重ねていく。つまり「蓄積」を非常に重視します。中国人にとっての仕事とは「お金を得る、増やす手段」です。コツコツ働くのも、投資で儲けるのもやり方が違うだけ。そんなふうに捉えていて、常にチャンスを探し、メリット(損得)に敏感です。
また日本人は「スジが通らない」「スジを通せ」など「べき論」が好きですが、中国人は「どれだけあるのか」という「量」が判断基準です。
この違いが顕著に表れるのがリスク感覚です。日本人はリスクの「有無」を考え、徹底的にリスクを排除しようとします。中国人は「リスクはもともとあるもの」と考え、その「大小」で判断します。
日本企業は「蓄積」で勝負し、リスクのない完璧な商品を売ろうとする。だから勝ちパターンが狭くなってしまう。
岩田氏:日本の価値観や尺度で中国市場に挑んでも通用しない。まずそれを知らないと、手痛いことになりそうですね。
田中氏:中国の人口は日本の10倍、国土面積は25倍です。全土を席巻するヒット商品なんて、そうそう生まれるものではありません。成功をどう捉えるかにもよりますが、競争の軸をずらして考えてみてはどうでしょう。
中国全土をカバーするのではなく、エリアやターゲットを絞って売り込む。中国ではユニクロや無印良品、ヤクルトやグリコのカレーなどもよく売れています。勝機がないわけではない。一気にビッグビジネスを狙うのではなく、小さな成功を積み上げていくのも1つの方法だと思います。
米国で先行する顧客体験を高める新たなトレンドとは
岩田氏:データの利活用という点で、織田さんは日本企業の課題をどのように見ていますか。
織田氏:米国はクレジットカードの利用履歴に代表されるようにサードパーティが持つデータを取引する売買市場が確立されていて、自社データにそれらを組み合わせたデータ活用が行われています。日本では米国ほど自由にデータの売買はできませんが、今ある自社のデータだけでも、使い方次第で可能性は広がります。にもかかわらず、まだ一歩を踏み出せない企業が多い印象です。
例えば、CRMとデジタルマーケティング部署、カスタマーサポート部署のデータを連携させれば、電話で問い合わせがあった時点で、その顧客が誰なのか知ることができます。過去の問い合わせ履歴や購買履歴と結び付ければ、顧客が何を求めているのかも予測がつく。そうすれば、顧客との接し方も変わってくるでしょう。
また、既に購入した商品がわかっているのなら、その商品に関するターゲティングメールやリスティング広告を止める。これだけでも顧客は「自分のことをわかってくれている」と感じ、顧客体験が向上します。その企業に対して好印象を持ち、良好なリレーションシップを築けます。

岩田氏:FinTechビジネスでも顧客体験は非常に重要なテーマです。今は誰もがスマートフォンを持ち、掌の中で情報を入手したりサービスを利用したりできます。お金の借り手と貸し手のマッチングサービスを展開する米Lending Club社、専用のICカードリーダーをスマートフォンやタブレットに装着するだけでクレジットカード決済が可能になる米Square社のサービスなど、成功しているFinTechビジネスは、潜在的なニーズを捉えてスマートフォンの利便性を拡大したものが多い。
織田氏:いかに顧客体験を向上させるか。米国のデジタルサービスのトレンドは、その方向に向かっています。例えば「リアルタイム価格」は、データを駆使して競合より競争力のある販売価格を割り出し、動的に変動させる仕組み。米国では家電量販店やスーパーマーケットなどで導入が進んでいます。
またスマートスピーカーに話しかけるだけでネット通販ができる「音声コマース」のワールドワイドの利用者数は、2017年の1200万から2018年に5億2000万人に一気に急増しました。
実店舗でレジを通さず買い物ができる「AIチェックアウトフリー」は「Amazon Go」が有名ですが、これ以外にも米国ではバーコードとクレジットカードのスキャナーを内蔵したショッピングカートを使ったレジレス店舗の実証実験などが進んでいます。
このトレンドは2019年以降、必ず日本にも押し寄せてくるでしょう。セールス、マーケティングにおけるデータの重要性がますます高まっていきます。幅広い領域のデータをつなぐ「エコシステム」の構築が不可欠です。
過去の成功体験を捨て、これまでの継続性から抜け出す
田中氏:日本企業は完璧主義で確かにいいものを作りますが、単一のロジックや考え方の中で完結していてオープンではない。型にハマると強いのですが、型にハマるまでが大変です。それなのに「どうやって売るか」という、売り方ばかり考えている印象です。「売る」と「売れる」はまったく違います。
中国市場を目指すなら、まずやるべきは、中国の人が欲しいと思うモノを作ることでしょう。中国の人は常にチャンスを探し、メリットに敏感です。いいものなら黙っていても売れるし、売れるとなれば向こうから「売らせてくれ」と言ってきます。型にこだわったビジネス、売り方優先のビジネスを考え直す必要があると思います。
織田氏:田中さんは「欲しいと思うモノ」と表現されましたが、成熟しつつある米国市場では、顧客体験の向上や価値づくりをどう行うかがポイントといえるでしょう。モノに加えて、サービスや体験価値を付帯することで顧客体験を向上させる。これからはそこにこそ、大きなチャンスがあると思います。新たなトレンドに対応するとともに、二世代先を見るような未来志向で、新たな顧客体験を考えていくことが大切です。
岩田氏:過去の成功体験を捨てる。これまでの継続性から抜け出す。そうしなければ、新しいものは生まれませんね。ただし、成功体験や継続性のすべてが要らないわけではない。残し、引き継ぐべきものもある。それを自分たちで取捨選択すると手前味噌なものになってしまいます。今の取引先やお客様のその先にあるコミュニティと接点を持ち、外部の視点や意見を積極的に取り入れる。それが変革の第一歩といえそうですね。