

どうしたら健康でイキイキ過ごせる世界を創れるのか?
NEC×FiNCが挑むヘルスケアの未来
近年、日本企業でも健康経営への注目は広がっており、従業員の健康の維持・向上に取り組むケースが増えてきた。従業員の健康が、企業のパフォーマンスを左右することが認知されてきたからだ。また社会の医療コストを下げ、ウェルビーイングにもつながることから、自治体も住民の健康の維持・向上に注力しつつある。ただし、生活習慣病は健康長寿の最大の阻害要因となるだけでなく、国民医療費にも大きな影響を与えている。この状況の打開に向け、NECは日々の生活をデータとして見える化し、新たな課題の解決に挑戦している。さらに、ヘルスケア・スタートアップ企業のFiNCとも共創。一人ひとりが自分らしく生活できる社会に向けた施策を強化している。今後、NECはどのような取り組みを進め、どのような形で共創していくのか。FiNC Technologies 代表取締役CEOの南野 充則氏とNEC 執行役員の北瀬 聖光に話を聞いた。
ヘルスケア領域での価値創出を目指して NECとFiNCが共創
私たちの心身の健康は日ごろの生活習慣から大きな影響を受けている。死亡原因の上位を占める悪性新生物(がん)、心疾患、肺炎、脳血管障害(脳卒中)などは生活習慣が深く関与しているといわれている。「生活習慣病」を予防するには、運動、食生活、睡眠、喫煙、飲酒などの生活習慣の見直し・改善が重要。
これを受けて、自治体では、社会参加などを通じて、住民の運動や食事などの生活習慣の改善を目指す環境づくりが本格化。企業の間でも、健康経営やウェルビーイングの観点から、社員の健康増進に注力する動きが広まっている。
もともと日本では、労働安全衛生法で「年1回の定期健診」が義務付けられ、自治体や企業が住民・社員の健康増進に大きな役割を果たしてきた。とはいえ、心身を健康にするための具体的な取り組みは、個人の自助努力に委ねられているのが実情だ。
こうした課題を解決すべく、NECはヘルスケア領域での事業創出を目指して試行錯誤を重ねてきた。だが、AI/IoTでデータを収集・分析するのみならず、生活習慣を改善するための具体的なアドバイスまでできなければ、真の価値を利用者に届けることは難しい。そのためには専門的知見を持つパートナーとの協業が必要と考え、FiNC Technologies(以下、FiNC)と協力して実証を行った。
最大の課題は健康に向けた生活習慣を「継続できない」こと
FiNCが、「ヘルスケア×テクノロジー」に特化したベンチャーとして産声を上げたのは2012年。体重や歩数、睡眠時間などのライフログを記録し、専属のパーソナルトレーナーのサポートも受けられる健康管理アプリ「FiNC」を世に送り出し、一躍、ヘルスケアアプリの分野におけるリーディングカンパニーとなった。
「心身の健康を維持するためには、生活習慣を整えることが重要です。ところが、健康診断で問題が見つかっても、実際に何をしたらいいのかわからない。そこでジムに通い始めるわけですが、半年後には8割の方が休眠会員になってしまう。“何をすべきかわからない”“継続できない”という点に課題があるわけで、そこをサポートしていく必要があると感じていました。そのために、IoTデバイスで歩数や食事、運動を見える化し、簡単かつ自動的に記録ができ健康状態を理解できるようにする。そして、個人の趣味嗜好や生活リズムに合わせて、行動変容につながるようなプログラムやサプリメントを提案し、お客様の課題に応じたソリューションを提供していく。この2つが必要だと私たちは考えています」と同社の南野 充則氏は語る。
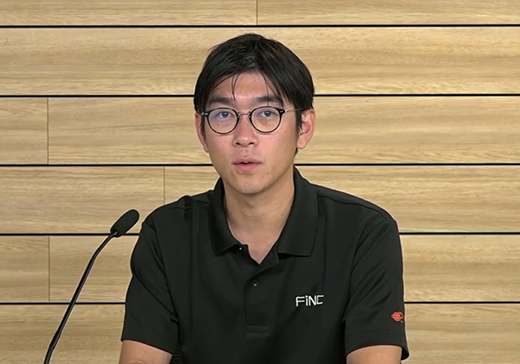
代表取締役 CEO
南野 充則 氏
他社との共創の必要性を痛感していたのは、実はNECだけではなかった。FiNCにとっても、自社のヘルスケアアプリをさらに進化させるためには、高度なセンサ技術や先進テクノロジーを持つメーカーとの連携が不可欠だと感じていたという。NECとFiNCがタッグを組めば、ビジネスのポテンシャルは一気に広がる――。両社の思いが一致したことで、2017年に業務提携と資本提携がスタート。2019年にはウェルネス・ソリューションの共同開発も始まり、NECとFiNCの共創プロジェクトが本格始動したのである。
AIとスマホアプリで自治体の生活習慣改善をサポート
現在、両社が共創プロジェクトとして取り組んでいるのが、生活習慣改善支援サービスだ。2021年10月から、AIを活用した健康見える化事業を実施。利用者一人ひとりに適した、継続性のある健康プログラムをアプリで提示し、生活習慣の改善を促す取り組みを行っている(図1)。
これは、AIを活用した「NEC健診結果予測シミュレーション」と「FiNCアプリ」を連携させることによって、健診結果をAIで分析・予測し、アプリで健康プログラムを提案するというもの。「NEC 健診結果予測シミュレーション」では、健診結果をAIが分析し、3年後までの健診検査値を将来予測し、可視化。そのうえ、対象者に効果的な生活習慣改善案を提示するとともに、それに取り組んだ場合の改善効果を予測し、可視化できる。また、「FiNCアプリ」では、歩数や食事、運動、体重、睡眠などのライフログを記録し、パーソナライズされた分析・アドバイスを表示。専門家が監修した運動・食事などの集中対策プログラムを提供し、生活習慣を改善するための行動変容を促す。
「この取り組みを行った結果、80%の人が、アプリの利用が『生活習慣の改善につながった』と回答しました。実際に効果を体験したことで、今後も引き続きアプリを使っていただけるのではないかと考えています」とNECの北瀬 聖光は期待を込める。
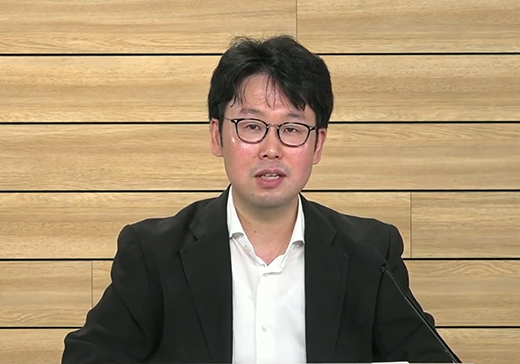
執行役員兼コーポレート事業開発部門長
北瀬 聖光
NECが独自に開発した多彩なソリューションも提供
NECのヘルスケア領域での取り組みはFiNCとの共創だけではない。これ以外にも、独自にソリューション開発を進めている。
その1つが、「歩行センシング・ウェルネスソリューション」だ。これは、小型の歩行分析センサを搭載した専用インソール(靴の中敷き)を使って、人の歩容(歩き方)を可視化し、AIによって健康状態を推定するシステム(図2)。内蔵された電池は1年間持つため、頻繁に充電する手間もなく継続しやすいことが大きな特徴だ。「第二の心臓」といわれる足からデータをセンシングして、足・脚の動きに関する時間や速度、角度、距離、身体の健康状態を見える化し、健康寿命の延伸に向けて価値を提供していく考えだ。
「まずは、Makuake(応援購入サービス)で一般ユーザに利用してもらいながら、大手・新興靴メーカーと協業して『靴のDX化』とスマートシューズの開発を推進。それと並行して、フィットネスクラブや接骨院と連携しながら、リハビリや健康増進のための検証実験も進めています。さらに、大学との共同研究の成果を靴医学会で発表するなど、アカデミックな世界との連携も進め、エビデンスの確立と実績づくりを進めているところです」(北瀬)
また、NECグループのフォーネスライフが提供するデジタルヘルスケアサービス「フォーネスビジュアス」というソリューションもある。これは、“今”と“将来”の健康状態、疾病リスクをわかりやすく可視化し、一人ひとりにフィットした生活習慣改善メニューを提供するサービスで、「疾病リスク予測」と「生活習慣改善サポート」の2つからなる。
「疾病リスク予測」では、少量の血液から約7000種のタンパク質を解析する「フォーネスビジュアス検査」により、心筋梗塞・脳卒中や肺がん、認知症などの将来の発症リスクと現在の体の状態を可視化し、医療機関を通して提供。さらに「生活習慣改善サポート」では、保健師の資格を持つコンシェルジュによるWeb健康相談に加え、スマートフォン向け専用アプリで食事や運動、睡眠、オーラルケア、メンタルケアなどさまざまな生活習慣改善メニューを提供し、受診者の健康意識を高め、日々の取り組みを支援。一人ひとりに適した改善提案と継続のためのフォローを行うことで、行動変容を後押しし、健康寿命の延伸に貢献するのが狙いだ。
NECが描く2030年のヘルスケアの未来像とは
こうしたさまざまな取り組みは、2021年の中期経営計画「NEC 2030VISION」に基づいている。ここでは「意識せずに健康でいられる」「あなたのデータが誰かのためになる」「あなたに最適な医療が受けられる」の3つを実現したい社会として掲げ、2030年の未来像を描いている。
その未来像に向けた、注力する事業領域として、「Medical Care」「Lifestyle Support」「Life Science」の3つを設定。それぞれの領域で社会課題を抽出し、ソリューションの開発を進めてきた。今回紹介したヘルスケアでの取り組みは「Lifestyle Support」にあたる(図3)。

NECは2030年のゴールに向けて、「Medical Care」「Lifestyle Support」「Life Science」の3つの事業領域に注力。社会課題の解決と新しいサービスの提供に取り組んでいく。
「NECでは、各事業の中で日々生まれるデータを、価値のあるものに変えていくことが可能です。蓄積したデータを活用して、3つの事業領域間で連携したり、他企業や自治体、国と連携したりしながら、世代を超えて医療の質の改善に取り組み、社会に貢献していきたいと考えています」と北瀬は抱負を語る。
誰もがあなたらしく生きることのできる社会。このような未来を実現するため、NECはさらなる挑戦を続けていく。
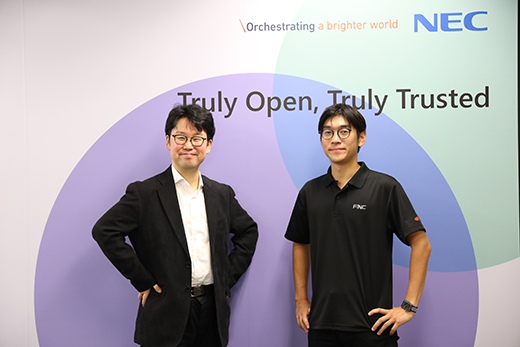

NECヘルスケア・ライフサイエンス ホワイトペーパー 「一人ひとりの日常生活に寄り添う」





