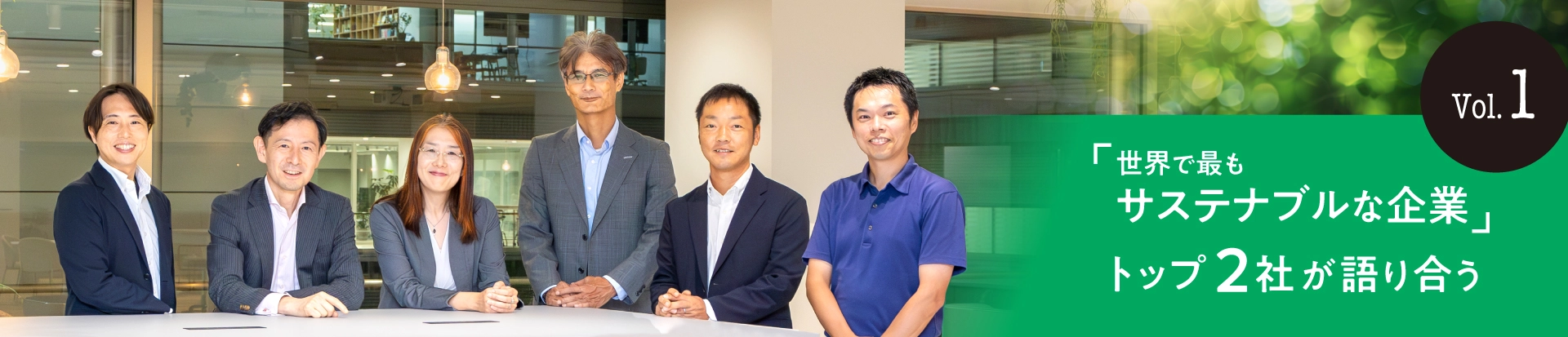
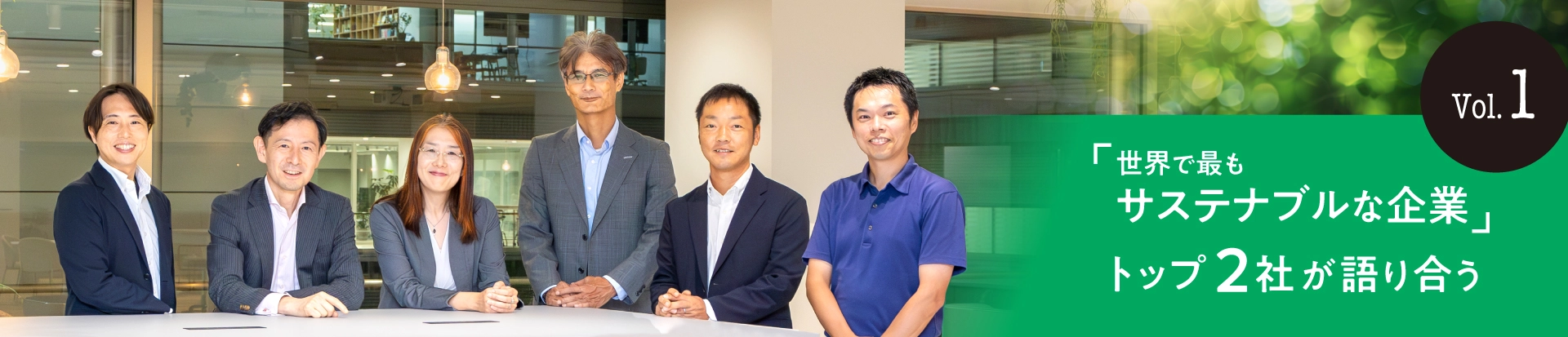
製品戦略から人材、デジタル活用まで、日本企業のサステナビリティの現在地と課題は?
国や企業、個人まで、それぞれの立場で課題意識を持っている「サステナビリティ」の推進。この言葉は日本語で「持続可能性」と訳されるが、多くの人がイメージするのは気候変動に代表される地球環境への負荷をどう軽減するかというものだろう。多岐にわたる取り組みを実り多いものとし、進化させていくためには何が必要なのか?また、日本の組織が直面している課題や、グローバルとの差とは?サステナビリティの領域で世界的に高い評価を受けるシュナイダーエレクトリックとNECのキーパーソンが語り合った(全3回の1回目)。
SPEAKER 話し手

白幡 晶彦氏
シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社
日本統括代表
代表取締役社長(取材当時)

原田 俊輔氏
シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社
マーケティング・事業開発本部
事業開発部部長

蛭田 貴子氏
シュナイダーエレクトリック株式会社
CS&Q本部長

坪井 壘
NEC
コンサルティングサービス事業部門
戦略・デザインコンサルティング統括部
ディレクター

井出 昌浩
NEC
コンサルティングサービス事業部門長
マネージングディレクター

岡野 豊
NEC
環境経営統括部
兼 カーボンニュートラルビジネス推進PMOグループ
シニアプロフェッショナル
TIME誌「世界で最もサステナブルな企業2024」に選出
――初めに、今回の対話が実現した経緯を教えてください。
原田氏:そもそもは、私とNECの坪井さんが前職の某外資系企業で同期だったことがきっかけです。私は窓用の断熱フィルムなど建物の省エネに関する製品を、坪井さんは再生紙やカーボンオフセット製品を担当していました。もう20年くらい前の話ですが、お互い当時から環境問題、サステナビリティに興味を持っており、別々の会社になってからも連絡を取り合ってきました。

マーケティング・事業開発本部
事業開発部部長
原田 俊輔氏
坪井:「いつか面白いことができたらいいね」と話していたのですが、そんな折、米国のTIME誌が選定する「世界で最もサステナブルな企業2024」の1位にシュナイダーエレクトリック、2位にNECが選ばれました※1。これは良いタイミングだと、2人で両社のいろいろな人にお声掛けしていきました。「日本のサステナビリティを加速させる1つのきっかけをつくりたい」と考えたのです。
「NEC、米国TIME誌『世界で最もサステナブルな企業2024』 第2位に選出」

コンサルティングサービス事業部門
戦略・デザインコンサルティング統括部
ディレクター
坪井 壘
原田氏:NECは日本発のグローバル企業、一方のシュナイダーは、もはや本社がどこかもはっきりしない、本質的な意味でのグローバル企業だと自負しています。両社がそれぞれ日本代表、外資系代表のような立場で、サステナビリティへの考え方の違いや共通点を発信すれば、微力ながら日本の皆さんのお役に立てるのではと考えました。
- ※1 「World's Most Sustainable Companies of 2024」
カーボンニュートラル達成が市場参加の条件になる
――TIME誌の評価に表れている通り、両社はサステナブルな企業として広く認知されています。そんな2社から見て、なぜ今サステナビリティが重要なのでしょうか。これまでの経緯とあわせて教えてください。
蛭田氏:環境問題を社会課題ととらえる動きは昔からあります。例えば、2000年にも国連によってMDGs(ミレニアム開発目標)が掲げられましたが、あまり浸透しませんでした。サステナビリティが大きく注目されるようになったのは、2015年の国連総会でのSDGs採択だと思います。サステナビリティは地球全体の問題であると同時に、経済活動にもインパクトがあるものだと、皆さんが気付き始めた。サステナビリティ向上への取り組みはNice to have(あるとよい)ではなく、Must(なくてはならない)なのだという方向に、世の中が動き出したのだと思います。

CS&Q本部長
蛭田 貴子氏
岡野:おっしゃる通りですね。2015年の国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)で初めて、2℃目標(努力目標1.5℃)やカーボンニュートラルが人類共通の目標になりました。この「パリ協定」が大きなきっかけになった認識です。
蛭田氏:また、グレタ・トゥーンベリさんのようなアイコンが登場し、さまざまなメディアを通じてClimate Action(気候変動に対するアクション)が発信されたことも世界中に広まった要因だと思います。若い世代を中心に、SNSなどで情報を入手して「このままではいけない」と考える人が増えました。
その結果として企業には、自社のCO2排出量を減らすだけでなく、技術や事業によって社会課題解決に貢献することが期待されるようになっています。国際会計基準でも、気候変動や自然資本にかかわる事業リスクと機会、両面の開示が求められるようになっています。
井出:私はコンサルタント時代、お客様が新たに工場を建てる際などに「サステナビリティのベンチマークを使いましょう」という提案をしていました。しかし、当時は積極的なお客様はまだ少なく、投資対効果を見据えた議論まではなかなか進みませんでした。それがここ数年で変わった印象です。やはり、皆さんが自分ごととして認識し始めたのだと思います。
岡野:本当にそう思います。私も以前いた会社で、グローバルの再生可能エネルギー活用戦略を決定する責任者を務めていたのですが、取り組みを進めようにも、会社の投資回収の基準になかなか届かず苦労した経験があります。それが今では、取引の要件になるなど、大きく時流が変わってきたと感じます。
白幡氏:国連は、世界の平均気温が2100年までに最大5.7℃上昇するという予測を発表しています※2。これを1.5℃以内に抑えるには、2030年までにカーボンエミッションを現在の半分にしなければいけません。この夏、日本に強力な台風がいくつも来たように、既に気候変動の影響はさまざまなところに出ています。状況はもはや“待ったなし”なのです。
サステナビリティに関する企業への要請も強まっており、既に「ある時点でカーボンニュートラルを達成していないサプライヤーからは調達しない」旨を宣言している大手企業も登場しています。こうなると、サプライヤー各社はきれいごとばかり言っていられません。販売する製品はもちろん、その生産を支える設備から自社ビルのファシリティ、データセンターまで、あらゆる事業活動の炭素排出量を把握し、ゼロにしていく必要が出てきます。将来的には、サステナビリティ指標を達成していることが市場参加の前提条件になることさえあるかもしれません。

日本統括代表
代表取締役社長(取材当時)
白幡 晶彦氏
- ※2 IPCC Sixth Assessment Report
サステナブルの価値を製品価格に転嫁することが不可欠
――このような状況ですが、日本とグローバルで企業・組織のサステナビリティへの向き合い方に温度差はあるのでしょうか。
白幡氏:「サステナビリティに関する取り組みは費用対効果で考えるものではなく、必要な投資である」。そのような意識がより強いのは欧米や中国などのお客様だと思います。
例えば数年前は、当社がさまざまな節電系のソリューションのパイロットプロジェクトを行うと、必ず「何年で投資回収ができるのか」という質問をいただきました。しかし現在は、その質問をしないお客様が増えています。まさに、先ほどのNice to haveからMustへという話につながると思います。
また、状況に対する危機感・切迫感は、お客様の戦略にも影響を及ぼしています。海外の企業の多くはサステナビリティを新たな付加価値と位置付けて、製品の魅力に転換していますが、日本企業ではそのような動きは少ないのではないでしょうか。
井出:そう思います。加えて、消費者の価値選択基準もグローバルでは大きく変化していますね。海外には「価格は多少高くてもサステナブルな製品を選ぶ」という人が大勢います。消費行動の新しい基準が確立されつつある印象です。

コンサルティングサービス事業部門長
マネージングディレクター
井出 昌浩
白幡氏:確実にあります。お客様企業や消費者の意識が、「サステナビリティに前向きに取り組んでいない企業とは付き合いたくない」「そのような企業の製品は購入したくない」というところまで変わってきています。
井出:日本はまだそこまで行けていないですね。
岡野:そうした消費者の意識と企業の戦略は依存関係にあると思います。企業の側から見れば「売れなくなるので、価格に転嫁できない」ということです。
例えば、これは私の実体験ですが、アンケートをとると「価格が高くてもサステナブルな製品を選択するか」という問いに、多くの方が「選択する」と答えます。ところが、実際にサステナブルな商品を小売店に並べると、売れない。こうしたことがまだ往々にしてあります。
現在、私が担当する日本のお客様企業の多くが「サステナビリティの取り組みを製品価格に乗せられない」と苦慮しています。カーボンフットプリントをやるにせよ、サーキュラリティをやるにせよ、製品価格に転嫁できないのでサプライチェーンが苦しくなってしまう。特にB to Cビジネスのお客様は本当に難しいようです。

環境経営統括部
兼 カーボンニュートラルビジネス推進PMOグループ
シニアプロフェッショナル
岡野 豊
蛭田氏:“サステナブル”のための取り組みなのに、サステナブル、つまり持続可能な形で実行できない、というジレンマに陥るわけですね。とはいえ、営利目的の組織である以上、資金が尽きれば取り組みを続けられなくなります。この状態を回避できるよう、社会全体が意識を変えなくてはいけないと強く思います。
井出:おっしゃる通りですね。個社の取り組みにはどうしても限界があるので、ルールメイキングを含めた産業全体のリデザインが必要だと思います。
――もう1つ、取り組みを推進する人材の観点ではいかがですか。
井出:日本企業には優秀な方が非常に多くいます。ただ、サステナビリティの取り組みで求められる、俯瞰した視点を持つ方は少ないのではないでしょうか。全体傾向として「既存のものを詳細化する」「具体化する」ということに長けている印象があります。
白幡氏:また、「正しいのか、正しくないのか」にとらわれがちで、その答えがない限り行動に移せない傾向もあると思います。サステナビリティの取り組みでは、常に「あなたはどう思うのか」を問われます。欧米の人は、子どものころからそのような考え方の訓練を受けてきているので、一歩を踏み出すのが早いのだと思います。
岡野:同感です。「どう思うのか」「どうあるべきか」を突き詰めることが大切ですね。
「データなくしてサステナビリティなし」は世界共通
――また、サステナビリティ強化に向けて不可欠なのがデジタル技術です。データの活用や情報発信の仕方など、デジタル技術の活用に関して日本とグローバルの違いはありますか。
蛭田氏:前提として、「データなくしてサステナビリティなし」というのは世界共通だと思います。デジタルツイン環境でシミュレーションを行うにしても、データがなければ何も始まらないからです。
白幡氏:ところが、データを活用する以前に、そもそもデータが取れていないケースがまだ多くあります。当社は製造業のお客様を多く抱えていますが、特に日本では、ソフトウェアを提供するITレイヤーと工場などの機器を提供するOTレイヤーが構造的に分かれています。これが、データ活用を阻む高いハードルになっています。
また例えば、一部の大手企業は高度なデータ利活用の仕組みを整えていますが、その一方で、工場設備にセンサーさえ設置していないサプライヤー企業が無数にあります。サステナビリティの取り組みにおいては、サプライチェーン全体の現状可視化が重要になりますが、それにはまずこの状況を打開する必要があるでしょう。
岡野:難しいのは、「それではすべての機器にセンサーを付ければいいのか」というと、必ずしもそうではないことだと思います。
例えば、カーボンニュートラルの取り組みでは、可視化したCO2排出量データを基に設計、調達、生産管理など、業務全体の改善や効率化を図ることが目的になります。そのような目的やプロセス、そして「だからこのデータが必要なのだ」ということを伝えて初めて、センサーを設置するべき機器が見えてきます。これは、我々のようなお客様を支援する会社が、強く意識すべきことだと考えています。
NECはサプライチェーンで部品表を管理するProduct Lifecycle Managementで国内シェアトップの「Obbligato」をさまざまなお客様に提供していますが、この分野も日本ではまだアナログ運用が残っています。原価情報などと合わせて、環境情報をこの様なシステムで見える化することが企業の変革につながります。
井出:やはり、DXでよく言われるのと同様に、サステナビリティの取り組みもビジネスプロセスの変革だということではないでしょうか。仕事の仕方やマネジメントの仕方を変えないままデジタル技術を適用しても、どこかでアナログが残ってしまってサステナブルではなくなります。プロセスの全体設計も含めて行うことが肝心だと思います。






