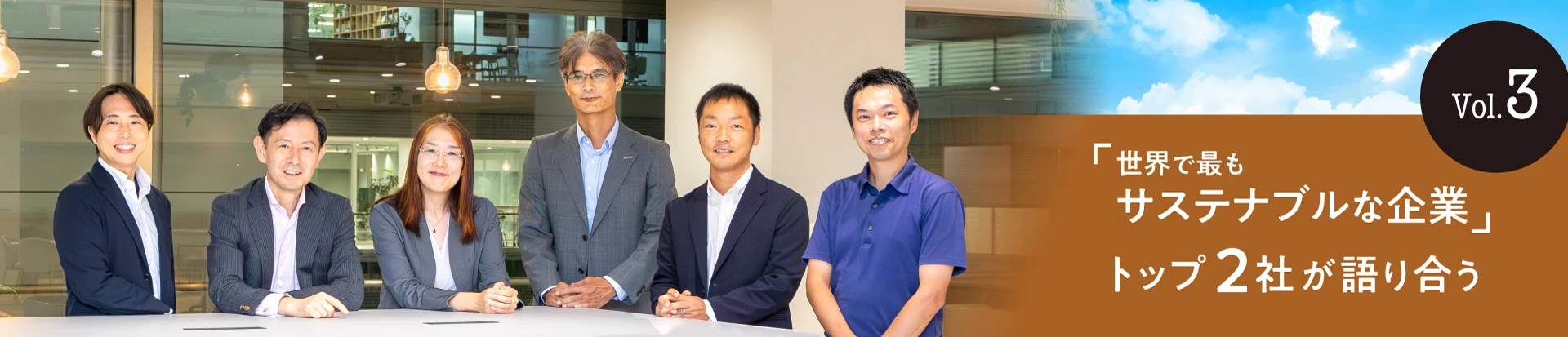
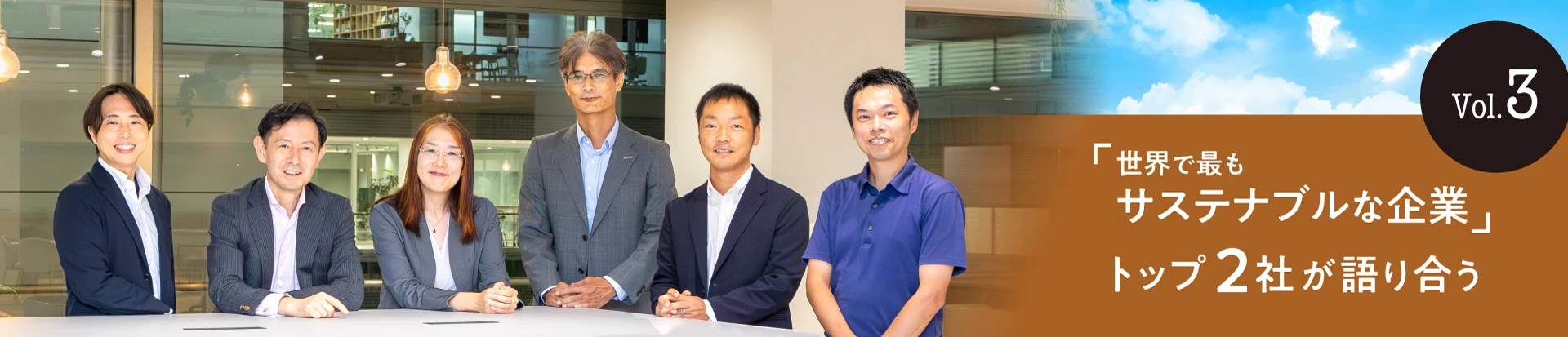
デジタル技術を軸にして描く、「サステナブルな日本社会」の未来像は?
欧米の先進企業と比較すると、日本企業のサステナビリティへの取り組みは遅れているといわれる。ただ一方で、日本には優れたテクノロジーを持つ企業や、優秀な人材が多く存在するのも事実だ。それらのテクノロジーや、感度・能力の高い人材のポテンシャルを引き出すためにはどうすればよいのか。サステナビリティの領域で日本がプレゼンスを高め、飛躍するための方法を考える(全3回の3回目)。
SPEAKER 話し手
シュナイダーエレクトリック
ホールディングス株式会社

白幡 晶彦氏
日本統括代表
代表取締役社長(取材当時)
シュナイダーエレクトリック株式会社

蛭田 貴子氏
CS&Q本部長
NEC

井出 昌浩
コンサルティングサービス事業部門長
マネージングディレクター

岡野 豊
環境経営統括部
兼 カーボンニュートラルビジネス推進PMOグループ
シニアプロフェッショナル
「サステナビリティで儲ける」への意識転換が必要
――今回は、日本のサステナビリティに対しての提言をいただければと思います。VOL.1でお聞きしたような課題は、どのようにすれば解決できるのでしょうか。
蛭田氏:まずはマインドセットを変えることが必要ではないでしょうか。例えばSDGsが日本でも浸透した要因の1つに、企業が「自らの事業活動とSDGsで提示されたゴールをリンクさせると、社会貢献している会社と認知される」ことに気付いたというのがあったと思うんです。サステナビリティと事業が明確につながっているという発想の切り替えは大事だと思います。
白幡氏:そうですね。前回も話しましたが、日本企業は欧米企業と比べてサステナビリティで「儲ける」意識が弱いと思います。
井出:確かにそう思います。むしろ「儲けたい」と言うことに対するアレルギーというか、言うと下品だという風潮がありますね。

コンサルティングサービス事業部門長
マネージングディレクター
井出 昌浩
白幡氏:これは非常にもったいないと思います。世界に類を見ないほど勤勉で、素晴らしいソリューションをつくれるのに、それを相応の金額で売る、価値付けるということがなかなか実現されていない。反対に「もっと安くつくれます」というような、コスト目線で語ってしまうんです。だから製品に価格転嫁できないという、VOL.1の話にもつながるのですが。
そうではなく、「これは素晴らしいものだから、相応の価格で提供する」という流れをつくれたらいいですね。それこそ、「相応の価格で提供されるサステナブルなもの以外は、買ってはいけないんだ」と社会全体が自然に思えるようなムードをつくっていきたいと思います。
蛭田氏:CSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)からCSV(Creating Shared Value:共通価値の創造)へ、ということですね。本業の周辺で、余力があればやるCSR活動ではなく、サステナビリティをはじめとする社会課題の解決そのものを本業にして成長の源泉にする。この状態になると、その会社が儲かれば儲かるほど社会が良くなることになります。
岡野:シュナイダーエレクトリックさんは、まさにそれを体現した会社ですね。

環境経営統括部
兼 カーボンニュートラルビジネス推進PMOグループ
シニアプロフェッショナル
岡野 豊
白幡氏:ありがとうございます。当社は、「いかにエネルギー効率を上げるか」ということをある時点で本業にしました。事業売却やM&Aによって組織の再編にも取り組み、成果につなげてきたのです。CSR観点のお飾り的なサステナビリティではなく、CSVの観点でビジネス成長のドライバーに位置付ける。日本企業も、このような意識と戦略の転換を行うべき時に来ていると思います。
デジタル技術で「見える化」することが大前提
――また、デジタルの力はサステナビリティの進展にどう貢献できるのでしょうか。
岡野:私は以前、大手自動車メーカーの環境部門にいて、その後はスタートアップで10億円規模の環境プロジェクトを担当していました。
ただ、40歳を過ぎて、やっぱり環境問題の解決はデジタル技術を使わない限り不可能だと感じるようになりました。環境負荷の実態や、環境価値をデジタルで見える化し、環境にいいことをやる人がきちんと収益を得る。そして、儲かれば儲かるほど環境がよくなる仕組みをつくりたいと考えて、NECに入社しました。
我々のような会社は、デジタル活用のテコになるべき存在です。そのため、自らが率先してデジタル技術の活用に取り組んでいます。現在は、カーボンニュートラルのほかにも水や資源、土地、森などの価値をサプライチェーン全体で見える化する取り組みを進めています。それをまとめたものが、VOL.2で紹介したTNFDレポートです。
このレポートの中で私は、NECが目指すことを書いています。そこでは、シュナイダーエレクトリックさんの「Life is On」同様、「デジタルで実態を見える化して、経済価値と環境価値をつなげるのがNECの存在意義だ」ということを宣言しているのです。
もちろん、これが全社員に浸透するまでには時間がかかると思いますが、目標にして取り組んでいく予定です。
白幡氏:デジタル技術がなければ、サステナビリティの進展や持続可能な社会の実現はない。これは大前提です。デジタル化が進むとDXも進むので、それがさらなるサステナブルへの推進力になります。

日本統括代表
代表取締役社長(取材当時)
白幡 晶彦氏
井出:完全に同意します。環境への影響、環境貢献の価値を経済に織り込む上で、デジタル技術は必須です。もっといえば、AIや量子コンピュータのような最新技術が必須だと感じています。データ取得の目的や制約条件、そして環境そのものが目まぐるしく変わっていく中では、その時々の状況をスピード感を持って見える化する必要があるからです。
蛭田氏:とはいえ、何から手を付ければいいかわからない企業は多いと思います。そんなときは「まず計測する」、これが大事です。
リサイクル資源の使用割合を検討するにせよ、カーボンフットプリントのトレードオフを考えるにせよ、測定できていないものは改善できません。まずやってみる。この姿勢がとても大切だと思います。

CS&Q本部長
蛭田 貴子氏
岡野:環境保全はつまるところ「許容量」の話です。例えば、人口100人の村なら、誰かが川の魚をたくさん獲ってしまうとほかの住民にすぐ影響が及ぶでしょう。しかし、私たちが暮らす現代社会はグローバルに経済が広がっているので、誰かが魚を1000匹獲ったとしても、その影響はすぐにはわかりません。
デジタル技術を用いることで、このようなことを正確に計測できるようになります。そのために必要な仕組みをつくるのが、私たちの務めだと考えています。
まずやってみて、成功例が出たらそこから学び、改善する
――VOL.1では人材面の課題の話も出ました。これについてはどのような解決策が考えられますか。
井出:日本にはサステナビリティに資する技術を生み出す、優秀な人材がたくさんいます。そのポテンシャルは世界にも負けないはずです。ただ、俯瞰的、構造的な視点でとらえ、ビジネスをリデザインできる人材を増やすためには、新たな視点でのトレーニングが必要です。
その点、VOL.2で話が出たシュナイダーエレクトリックさんのサステナビリティ・アンバサダーのような取り組みは、知識を得るだけでなく社内外に情報発信できるリーダーの育成に有効だと思います。人材育成の面で、日本企業も参考にすべきではないでしょうか。
蛭田氏:確かに、日本には優れた技術と人材があるのに、海外の後追いになってしまうのはもったいないと感じます。既存のルールに合わせるだけでなく、自らルールをつくるのだという気概を持っていきたいですね。
井出:日本企業は、ルールが変わったときの対応は速いです。この強みを活かして、自らルールをつくって変わっていくことが必要かもしれません。

――取り組みの具体的な進め方についても教えてください。例えば、シュナイダーエレクトリックでは、The Zero Carbon Projectとして製薬業界、半導体業界、鉄鋼業界などの産業に特化したサステナビリティソリューションを展開しています(詳細はVOL.2)。そのような仕組みは、はじめから複数業界への横展開を見据えていたのでしょうか。
白幡氏:いえ、最初からすべてを見据えてというよりは、まずはじめてみて、成功例が出てきたらそこから学ぶというスタイルで進めてきたものです。ある意味、行き当たりばったりともいえるかもしれません。「どうやればもっとよくなるだろうか」「事業として儲けるにはどうするべきなのか」ということを考え、手探りで改善しながら現在の形にたどり着いたのです。
私も、日本でのマネジメントにおいて、はじめから「完成形のプランを見せろ」とは言いません。そのようなカルチャーがある企業だからこそ、多くの成功事例を生み出せているのだと考えています。
井出:なるほど。これは新しい取り組みを進める上で、非常に大事なことだと思います。
岡野:大事ですね。

――走りながら考える、いわゆる「アジャイル」な進め方をするために重要なことは何ですか。
白幡氏:組織としての揺るぎないビジョンや軸がまずあって、その方向に走ってさえいれば、誰にも怒られない。このような心理的安全性のある環境が大事ではないでしょうか。
蛭田氏:私もそう思います。正解が見えない取り組みの場合、「うまくいかなかったらやめればいい」という共通認識があるのは、ありがたいです。例えば、SSI(シュナイダー・サステナビリティ・インパクト:詳細はVOL.2)も、指標自体はかなり何度も変更しながら現在に至っています。
サステナビリティの問題はエコシステムでしか解決できない
――また、お話を聞いていて思ったのは、2社ともサステナブルなソリューションやサービスの提供先が特定のクライアント企業ではなく、常に産業全体、社会全体であるということです。これがサステナビリティの基本ということでしょうか。
岡野:その通りだと思います。
白幡氏:結局、サステナビリティにかかわる問題はエコシステムでしか解決できません。カーボンニュートラルでいえば、当社のScope3は、パートナー企業やお客様企業のScope1、2であるということですね。常に「みんなで」という思想がベースにあります。
――最後に、サステナビリティに取り組む日本のビジネスパーソンにメッセージをお願いします。
蛭田氏:サステナビリティを軸にして活動していると、不思議とまわりに人が集まってきます。やはり皆さん、目指すことややりたいことは一緒なんですね。「一緒にやりましょう」とお声掛けすると賛同してもらえるケースが多々ありますが、我々のエコシステムを最大限活用すれば、必ずよい成果を出せると信じています。
ここにデータを連携し、エコシステム全体で変わっていくことができれば、日本流のサステナビリティが確立でき、新しいルールもつくっていけるかもしれません。そんな未来を描きながら、今後も皆さんと共に取り組んでいきたいと思います。
白幡氏:もちろん、エコシステムは非常に複雑なので、シンプルにいかないところもあるでしょう。でも、難しいからこそとりあえずやってみて、結果を踏まえて改善するアプローチが有効だと思います。徐々に効果を高めて、広く共有する。このような進め方を取り入れていただきたいと思います。
井出:NECが提供する新しい価値創造モデル「BluStellar(ブルーステラ)」では、上流コンサルティングから開発、デリバリー、運用、保守まで、戦略策定と実装をDX人材が支援していきます。ここでもサステナビリティは重要テーマの1つです。お客様と共に、未来を切り拓いていきたいと思います。
岡野:ICT基盤だけ用意しても変革は起こせません。広く情報を共有しながら、みんなで力を合わせて、持続可能な社会を実現していきましょう。






