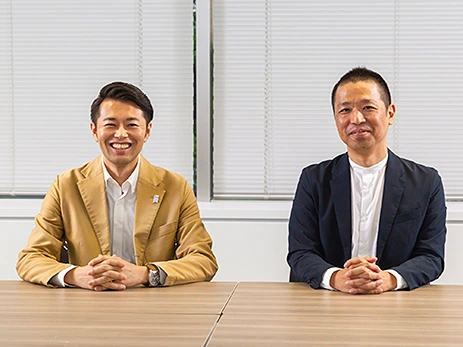フェーズフリーが握る今後のまちづくりのカギ。備えない防災とは
コロナ禍でNew Normal時代を迎えた今、ある言葉が注目を集めている。「日常時」と「非常時」という2つのフェーズの制約から自由であることを目指す、「フェーズフリー」という概念だ。フェーズフリーとは、災害の被害から大切な人を守り、安全・安心な社会をつくることを目的とした、新しい防災の考え方。行政や民間企業の間では、この概念を取り入れた商品開発やまちづくりが本格化している。フェーズフリーは、New Normalのものづくりやまちづくりをどう変えるのか。その提唱者であるフェーズフリー協会の佐藤 唯行氏にNECの山本 啓一朗が話を聞いた。
SPEAKER 話し手
一般社団法人フェーズフリー協会

佐藤 唯行 氏
代表理事
NEC

山本 啓一朗
東京オリンピック・パラリンピック推進本部
集まろうぜ。グループ 部長
(兼)IMC本部(兼)エンゲージメント推進室
「備えてくれない」人たちを守るにはどうしたらいいのか
山本:佐藤さんは大学4年の時に「災害軽減(防災)工学」の研究をスタートし、阪神・淡路大震災や東日本大震災など、数多くの災害現場を調査されたそうですね。2014年に「フェーズフリー」というコンセプトを提唱されたのも、災害現場での経験と研究がベースになっていると伺いました。
佐藤氏:「フェーズフリー」とは、「防災」にかかわる新しい概念です。私がこの概念にたどり着いたのは、大学院時代の経験がきっかけです。大学院1年の時に阪神・淡路大震災があり、その後も、さまざまな災害現場で調査を行いました。ところが、災害現場を見るたびに、デジャヴ(初めての体験なのに、既にどこかで体験したことのように感じる現象)に苛まれるわけです。時間と場所こそ違え、同じことが繰り返し起きている。それが不思議でしたし、無力感も感じました。
悲惨な現場での体験を基に、私も災害に備えることの大切さを訴え続けてきました。ところが、多くの人は「確かに必要だ」とその場では深く共感してくれるものの、結果として備えることができないまま、災害で大きな被害が出てしまう。そういう経験を繰り返して、「なぜ、備えてくれないのか。備えてくれない人たちを守るためにはどうしたらいいのか」と考え続け、ある答えにたどり着いたのです。
それは、災害用の特別なものを用意して「備える」のではなく、普段から便利に使えて、災害時には身を守れるようなものを提供すればいいのではないか。日常時のフェーズと非常時のフェーズを分けるのではなく、日常時にも非常時にも役に立つ「フェーズフリー」な概念が世の中に広がれば、備えられない人たちを守ることができるのではないか、と考えたわけです。
例えば、普段から速乾性に優れた服を着ていれば、台風で雨に濡れても、体温を失わずにすむ。日常時の快適性を追求することが、結果として、非常時に私たちや、私たちの子どもを守ることにつながる。そんな商品やサービスを皆さんに考えてもらおう、というのがフェーズフリーのもともとの発想でした。
山本:これだけ文明が発達しても、災害の問題はなかなか解決することができません。NECでもICTを活用した防災への取り組みを自治体などと行ってきましたが、災害の脅威を取り除くには至っていないのが現状です。なぜ、災害の問題は解決できないのでしょうか。
佐藤氏:今、防災を担っているのは、行政や市民のボランティアです。行政は限られた予算の中で、ボランティアは生活の中のゆとりの時間を使って防災に取り組んでいます。しかし、限りある予算と時間の中で防災に取り組んでも、持続可能な価値を提供することは残念ながら難しい。防災が「ビジネス」にならない限り、きっとこの問題は解決しない。だからこそ、「防災をビジネスにすることが必要だ」というのが、私が2年間の修士課程でたどり着いた結論でした。
山本:災害が発生すれば大変なことになるのに、日常的な優先度は低いから、「また今度でいいね」となりがちで、生活者も防災への備えに対する意識や防災商品への購買意欲がなかなか高まらない。防災をビジネスにする上では、必要性と生活者ニーズとの間の乖離を埋める必要があるわけですね。
「コスト」の提案を「バリュー」の提案に変えることが必要
佐藤氏:なぜ、防災がビジネスにならないかというと、それが「コスト」の提案だったからです。ビジネスとして防災のマーケットを広げるためには、「コスト」の提案から「バリュー」の提案に変えていかないといけない。例えば、トヨタ自動車の「プリウス」は、環境にもお財布にも優しいライフスタイルで多くのユーザに支持されています。しかも、災害時にはプリウスのバッテリーから、平均的な家庭であれば、4日分の電源を供給できる。防災用の車ではないが非常時に役立つというので、昨年の千葉の停電や、一昨年の北海道の停電の時には大きな話題になりました。
ところが、防災という観点で停電対策をしようとすると、「非常用発電機(蓄電池)を備えましょう」という話になってしまう。それで非常用発電機が普及するかというと、しないわけです。一方で、プリウスは大変普及した。エコロジー、エコノミーという日常的な「バリュー」が、災害時にも役立つからです。
山本:フェーズフリーな商品を提供することによって、はじめて防災がビジネスになる可能性が出てきたということですね。必要であればコストをかけるべきですが、防災のため(だけ)の商品が普及しないのはなぜでしょうか。
佐藤氏:それは、日常時と非常時には分厚い「想像の壁」があるためです。「東日本大震災で起こったことを忘れないで!」「首都直下地震ではこんなことが起こると想定されています。だから、その時のために備えてください!」――と、どんなに口を酸っぱくして言ったとしても、結局は「備えられない」人が後を絶ちません。「想像の壁」が分厚すぎるからです。
価値提供のマーケットを考える時、「私たちは、日常時には非常時のことなど考えられない」ということを大前提にする必要がある。つまり、サービスが「想像の壁」を超えて、勝手に災害時に備えてくれるようなものを提供する必要があるわけです。
例えば、ある紙コップは、今、大変売れているフェーズフリー商品です。避難所に来て赤ちゃんの粉ミルクやご飯を作ろうとしても、計量カップがないので材料の分量を測ることができません。そこで、模様と一体化した目盛りを入れ、計量カップとして使えるようにしたのがこの紙コップです。要は、災害時の悩みを解決できるフェーズフリーな商品を提案すれば、お客さんに選ばれる商品になるわけです。

日常時には便利に使えて、非常時にも役立つまちづくり
山本:フェーズフリー自体が付加価値になる、ということですね。最近は、商品、製品といった単位だけでなく、まちづくりにおいても、新しい防災の考え方として、フェーズフリーという考え方が浸透しつつありますね。
佐藤氏:はい。今、自治体や行政が新しいまちづくりをする際の仕様として、フェーズフリーという概念が採用されるケースが増えています。防災に強いまちを作ろうとすると、日常時には利用しにくかったり防災コストがかさんだりと、さまざまな問題が顕在化しがちです。ところが、普段は住民が楽しく施設を利用できて、非常時にも役立つとなると、維持管理もしやすいし、住民価値が上がって政策も進めやすくなります。
今治市のごみ焼却施設、今治クリーンセンターはその1つです。通常、ごみ焼却施設を作ろうとすると、反対運動が起きます。今治市さんでも、「災害時の避難場所としても役立つ」という説明を地域住民に繰り返したのですが、なかなか進まなかった。半ば諦めかけていた時に知ったのが、フェーズフリーという概念です。そこで、今治市さんは発想を転換し、「いつも楽しく住民が活用でき、賑わいを生み出すものになる上に、避難所や省エネにつながったり、非常時の電源にもなりますよ」という提案をしたのです。
普段はスポーツやイベントを楽しめる施設、あるいは広大な緑地を開放する。このように、近隣住民のコミュニティに対する付加価値(バリュー)を上げながら、非常時には発電機を備えた避難所兼備蓄センターとして活用されることで非常時にも役立つ、ということでプロジェクトが進むことができたわけです。



東京の豊島区でも南池袋公園をリニューアルしました。こちらは帰宅困難者の一時退避や物資の備蓄、災害トイレ、カフェレストランによる炊き出しなど、災害対応の機能を持つ公園としてあらかじめデザインされています。
こうした事例に共通するのは、今まで行政が「コスト」として行っていた防災を、近隣住民に「バリュー」として提供している点です。
山本:それは大変興味深いですね。NECでも「防災×観光」というキーワードで、高松市のスマートシティのプラットフォーム構築に取り組んでいます。これは、観光と防災を両立させるためのIoT共通プラットフォームで、観光面では、レンタサイクルにGPSを搭載し、観光客の動きを国籍などの属性別に把握することで、多言語対応などに活用しています。また、防災面では、沿岸や水路に設置した潮位センサーや水位センサーの情報を市がモニタリングし、災害発生時に警報を出す仕組みづくりを行っています。これら2つのソリューションを相互に活用することによって、将来的には、観光客に災害情報をいち早く提供することも可能になると考えています。

佐藤氏:それはコストをバリューに転換させるという点で、まさにフェーズフリーなまちづくりといえますね。ほかにはどんな取り組みを進めているのでしょうか。
山本:池袋駅東口では、防災も兼ねた「人の移動の見える化」を行っています。これは、防災カメラで撮影された群衆映像から、混雑状況の把握や異常の検知を行うというものです。当初は東日本大震災の経験を踏まえ、防災視点で導入したものですが、今は新型コロナウイルス対策の一環として、駅の混雑状況を把握するための利活用が始まっています。
このほか、AIとドローンを活用して、阿蘇山の火口を監視する取り組みも行っています。これは、阿蘇山の噴火の兆候をいち早く検知して、住民の避難を促すためのシステムですが、ドローンの撮影映像はVR化され、観光にも役立てられています。直近の事例としては、六本木のスマート街路灯があります。これは、AIを活用した画像解析技術により、人の流れや属性、人数を24時間リアルタイムに把握する仕組みで、防犯とマーケティングというマルチユースを想定したもの。こうした見える化のソリューションには、個人情報保護への配慮など運用面で整備することが多々ありますが、この「マルチユースの壁」を超えるきっかけとなったのが、六本木商店街のスマート街路灯の事業でした。
これらの事例は、いずれも1つのソリューション・サービスで複数ニーズに応えることによって、日常時と非常時への活用を目指したものです。

「人・空間・時間」の多様性を実現するまちづくりへ
佐藤氏:今、新型コロナウイルスのお話が出てきたので、その件についてもちょっと触れたいと思います。
「災害」とは、ハザード(予測できない危険)と社会の脆弱性が重なった時に発生するものです。仮に震度7の地震がサハラ砂漠の真ん中で起きても「災害」にはなりませんが、東京の港区で震度7の地震が起これば、それは大変な「災害」になります。震度は同じでも、地震発生の現場となった社会がどれだけ脆弱かによって、「災害」かどうかが決まってくるわけです。その文脈で考えれば、新型コロナウイルスとはハザードであり、都市の脆弱性によって「災害」が発生したということができます。
山本:都市とは、多様な人々が特定の空間と特定の時間に集まることによって、価値を生み出す場です。このため、新型コロナウイルスに感染しやすい「3密」の状態になりがちで、それがコロナ禍における都市の脆弱性につながっていたわけですね。
佐藤氏:今回のコロナ禍によって、「防災・防疫」と「フェーズフリー」という2つの方法が注目を集めたと思っています。防災・防疫は、都市の機能を犠牲にしてでも「多様な人々が、特定の空間、特定の時間に集まることを避け、感染を広げないようにする」方法です。一方、デジタルの力で「多様な人々が、多様な空間、多様な時間に集まり、イノベーションを起こす」方法は、フェーズフリーといえます。
フレキシブルなワークスタイルが時間の多様性を生み出し、リモートワークが空間の多様性を生み出し、オンラインでつながることが人の多様性を生み出す。時間・空間・人間の多様性を高めることによって、都市の脆弱性を小さくし、新しい都市の価値を生み出していく。それが、フェーズフリーの大きな流れになっています。
「多様な人が、多様な空間、多様な時間に集まる」環境をデザインすることで、災害に強いまちをつくることができる。NECさんのようなICT企業がデジタルでまちづくりにかかわることで、それが実現できるのではないでしょうか。

山本:NECのまちづくりにおいては、人の営みが常にセットでないといけないと思っています。緊急事態宣言が出た2カ月間で、普段なら年に1度会えるか会えないかという人たちと、オンラインで色々な相談をすることができました。
当社がICT企業として、人の流れに着目しながら、まちづくりをデジタルで支えていくに当たって、フェーズフリーの考え方はとても重要だと思っています。日常時と非常時、都市と地方を問わず、人の営みを守り続けられるプラットフォームをNECとして追求していく必要があると感じています。
佐藤氏:今回のことで、デジタルの重要性をあらためて実感させられました。デジタルを活用すれば、都市の機能を損なうことなく、新型コロナウイルスの対策や防災を行うことができる、という気付きを得ることができたわけです。
多様な人々が多様な空間、多様な時間に集まり、イノベーションを生み出す――そんな新しいまちづくりを、ぜひ考えていただきたい。日本のICTの根源的な部分を担う企業として、より一層大きなミッションを掲げ、新しい社会づくりを追求していただきたいと思います。