

市民の創造性を発揮させる「シビック・クリエイティブ・ベース東京」が誕生
~アート×デザイン×デジタルは、どんなイノベーションを生むのか~
2022年10月、東京・渋谷に「シビック・クリエイティブ・ベース東京(CCBT)」がオープンした。これは、デジタル技術を活用した新たな創造と交流の拠点として、東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団が開設したもの。CCBTが目指すものとは何か。それは、テクノロジーを通じてどのようにイノベーションを創出し、社会にインパクトをもたらそうとしているのか。コラボレーションメンバーとしてシビック・クリエイティブ・ベース東京(CCBT)の創設にかかわった、パノラマティクスの齋藤 精一氏に話を聞いた。

齋藤 精一 氏
パノラマティクス(旧 ライゾマティクス・アーキテクチャー)主宰
1975年神奈川県生まれ。建築デザインをコロンビア大学建築学科(MSAAD)で学び、2000年からニューヨークで活動を開始。
03年の越後妻有アートトリエンナーレでアーティストに選出されたのを機に帰国。
フリーランスとして活動後、06年株式会社ライゾマティクスを設立。
16年から社内の3部門のひとつ「アーキテクチャー部門」を率い、2020年社内組織変更では「パノラマティクス」へと改める。
2018-2022年グッドデザイン賞審査委員副委員長。2020年ドバイ万博 日本館クリエイティブ・アドバイザー。2025年大阪・関西万博 EXPO共創プログラムディレクター。
一人ひとりがコンピテンシーを持ち寄り、地域課題を解決する
新型コロナウイルスとの闘いが地球規模で繰り広げられる中、「シビックテック(civic tech)」が注目を集めた。これは地域の課題を解決するため、市民(civic)自らがテクノロジー(tech)を活用してソリューションを生み出す取り組みである。
デジタル人材が結集して、新型コロナウイルス関連のWebサイトやアプリを開発する動きは世界各地で見られ、日本では一般社団法人Code for Japanが、東京都の感染症対策サイトや接触確認アプリを開発。東京都の感染情報は、誰もが分析に活用できるようオープンデータとして公開され、新型コロナウイルス対策に大きく寄与したことは記憶に新しい。
「課題の解決に向けて多くの人の力を持ち寄る。これは何もプログラミングに限ったことではありません。多くの方々は料理にせよ折り紙にせよ、何かしら“ものづくり”をしているわけです。『私はペンキを塗るのが得意』『私はパンク修理ができる』といったコンピテンシーを一人ひとりが持ち寄れば、草の根で地域の課題解決に寄与できるかもしれない。それこそが『シビック・クリエイティブ』であり、シビックテックとシビック・クリエイティブが両輪で回れば、社会参加できる人たちがもっと増えていくのではないか。そんな思いを込めて、今回『シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]』(以下、CCBT)と名づけたわけです」とパノラマティクスの齋藤 精一氏は語る。

齋藤 精一氏
アーティストが創作プロセスやツールの使い方を公開
現在、東京都は「未来の東京戦略」を策定し、戦略の1つとして「文化・エンターテインメント都市戦略」を掲げている。これは、芸術文化の領域でもデジタルの活用を進めることで、東京の魅力を高め、「世界から選ばれる都市」へと進化させることを目指したもの。その取り組みの一環として、「TOKYOスマート・カルチャー・プロジェクト」を立ち上げ、都立文化施設の通信インフラ整備や収蔵品のデジタル化、データベース拡充などを進めてきた。
そんな中、企業やスタートアップ、大学・研究機関が集積する地の利を活かし、イノベーションを生み出すプラットフォームとして、「東京にデジタルクリエイティブの拠点をつくる」というアイデアが新たに浮上。半年間の準備期間を経て、CCBTがオープンしたのは2022年の10月23日のことだ。
CCBTは、「デジタルテクノロジーの活用を通じて、人々の創造性を社会に向けて発揮する、シビック・クリエイティブのための創造拠点」と定義されている。ここで重要なのは、創造性を発揮する主体とは、あくまでも「人々」であって、CCBTはアーティストがつくった作品やデザインを鑑賞するだけの場所ではない、ということだ。
「ここでは、アーティストにワークショップやレクチャーも担当してもらい、創作プロセスをできるだけ公開していきたいと考えています。アーティストからツールの使い方や制作の方法を学ぶだけでなく、アーティストが作品制作に使ったツールを、皆さんにも自由に使ってもらう。そこにCCBTの醍醐味があると考えています。今までアートの世界では、創作のプロセスをあまり共有しないのが一般的でした。しかし、最近はアーティストも変わってきて、単に自分のつくりたい作品をつくるというだけでなく、『社会に対して自分は何ができるのか』『もっと社会実装のお手伝いをしたい』と考えるアーティストも増えています。その傾向はメディアアートの領域では特に顕著で、『今まで見えなかったものを可視化できるような作品をつくりたい』と考えるアーティストが増えてきたように思います」(齋藤氏)
XR、3Dプリンタなど先端技術やツールの使い方も学べる
現在、CCBTでは、アート、テクノロジー、デザインをテーマにしたトークイベントやレクチャー、ワークショップ、社会課題に取り組むキャンプなど、さまざまなプログラムが行われている。なかでも、コアなプログラムの1つとして位置付けられるのが、「アート・インキュベーション」だ。

クレジット:「未来の東京の運動会」(主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団)
写真:佐藤基
これは、企画を公募して「アーティスト・フェロー」を採択し、CCBTを拠点に活動してもらう制度。フェローは1000万円を上限に制作費の支援を受け、スペースや機材の提供、テクニカルサポート、メンターや専門家のアドバイスを受けながら、企画の実現と社会実装を目指す。現在、5組のクリエイターがフェローとして活動しており、今年3月には成果発表が行われる予定だ。
だが、CCBTが対象とする「創造」の定義とは、狭義のアート作品の制作だけではない。デジタルの力も援用しながら、身の回りの課題を解決していくことも「創造」に含まれる、と齋藤氏は話す。
「たとえば、小学生の子どもが習字のコンテストで金賞を取り、作品が校舎の中に展示されている。それを見に行きたいけれど、感染対策で校内に入れてもらえない。それなら校舎の壁に作品を飾るのではなく、作品をARで空中に浮かべて見られるようにすればいい、といった具合に、さまざまな道具や手法を学びながら、身の回りの課題を解決していくわけです。CCBTではワークショップをはじめ、多様な人たちが集う交流の機会が設けられています。また、テクノロジーのリテラシーが高い人材が集まる場所なので、XRや3Dプリンタ、音響装置も含めた先端技術の使い方を学ぶこともできる。皆さんが身近で『はてな?』と思っていることを、CCBTでやり方を学び、自らつくり出していく。そんな場所にしていけるのではないかと考えています」
企業の中でできないことを、個人として表現する
それでは、ビジネスという観点から見た場合、CCBTはどのように活用できるのか。齋藤氏はこう話す。
「ビジネスにデザイン思考やアート思考を取り入れることが必要だといわれますが、都民一人ひとりがその方法を学び、自分のコンピテンシー・スイッチを押す。CCBTとはそんな場所だと思っています。課題と感じていることがあるなら、問題をとらえて自分なりに咀嚼し、コンピテンシーを活かして解決策を考える。あるいは、自分が表現したいことが企業の中でできないなら、一個人としてここのプログラムに参加し、自分にできる形で表現していく。それは社会課題の解決に限らず、『楽しいまちをつくろう』ということでもいい。その意味で、CCBTはアートやデザインだけでなく、ビジネスやまちづくりにも刺激を与えてくれる場所になると思うのです」
さらに今後は、デザイン思考やアート思考を学び、ビジネスのヒントやイノベーションの種を生み出すようなプログラムも検討しているという。
「CCBTは『東京にイノベーションを生み出していくプラットフォームとして機能する』ことを目指しています。しかし、『プラットフォームの中で起きている経済効果』が『プラットフォームへの投資』を凌駕しない限り、それはプラットフォームとはいえない。“シビック”といえども熱量だけでは成り立たないわけで、今後はシビック・クリエイティブが事業性を持つことが必要だと考えています。今は大量につくって大量消費する時代ではなく、必要なものを自分たちでつくっていく時代。小さなチームをつくって解像度を高めない限り、ものはつくれないと僕は思っています。CCBTという場で、消費者と生産者が手を取り合い、一緒にものをつくりながら、『今、何が必要なのか』『人々は何を思っているのか』と考える。従来のマーケティングでは得られない気付きやアイデアが、CCBTから生まれてくるのではないかと期待しています」

CCBTとは思考の筋肉を鍛える場所
2023年には、CCBTや都内各所で、アーティスト・フェローによる作品発表や展覧会が順次開催されている。3月4日~3月21日に開催される展覧会「Deviation Game ver1.0」(Tomo Kihara + Playfool)は、AIと人間が競争/共創するゲームを活用して、人間がまだ探索できていない表現領域の開拓に挑むというもの。また、3月10日~3月21日には、浅見和彦+ゴッドスコーピオン+吉田山による展覧会「Augmented Situation D」が行われる。これは、作品や渋谷の町中にあるARマーカーをスマートフォンで読み込むと、リアルな空間と仮想空間が融合した作品が立ち現れるという趣向だ。
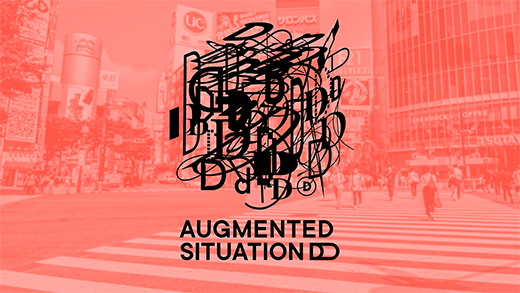
3月18日~3月26日には、SIDE COREによるインスタレーション展示、「rode work ver. under city」を開催。「都市の地下空間」をテーマにしたこの展示は、普段目にすることのない野外空間や地下空間を舞台とし、「東京」という都市に対する新たな視点を切り拓く試みである。
まだ発足して半年ということもあって、今後の課題は「地域での認知度をいかに高めるか」。「いずれはランドセルを背負った小学生が学校帰りに立ち寄り、週末には親子でものづくりを楽しむような場にしていきたい」と齋藤氏は抱負を語る。
「CCBTは、都民の皆さんにノウハウやメソッドをシェアしていく場所。『工作ができる場所』というより、『思考とスキルセットをお渡しできる場所』になっていくべきだと考えています。ある意味“訓練場”のようなもので、コロナや災害のような社会問題が起きた時に、ここで鍛えた筋肉をどれだけ使えるかが試される。だから、少しでも多くのツールをお渡しできるように、滞留する人の数も増やしていきたいし、さまざまな分野のアーティストやデザイナーに参画してもらいたい。僕が個人的に目標としているのは、ここを起点にして、いかに多くのものを生み出すかということです。それができれば、都民の皆さんから『こういうことはできないのか』『こんなことをしてみたいので、やり方を教えてほしい』という相談やリクエストをいただけるはず。それを目指して、試行錯誤を続けていきたいと思います」


クリエイター


