

次世代中国 一歩先の大市場を読む
中国で進む「クルマのスマホ化」
自動車業界に「メディアテック・モーメント」は来るか
Text:田中 信彦
中国に「メディアテック・モーメント(聯發科時刻)」という言葉がある。メディアテック(聯發科技、MediaTek Inc.)」という企業の登場で、その時点からスマートフォン(以下スマホ)のつくり方が根底から変化してしまった状況を言い表した表現だ。
EVの普及が急速に進む中国で、この「メディアテック・モーメント」に相当する動きが、クルマの世界にも起きる(起きつつある?)のではないか、との見方が出ている。今回はこの話をしたい。

田中 信彦 氏
ブライトンヒューマン(BRH)パートナー。亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科(MBA)講師(非常勤)。前リクルート ワークス研究所客員研究員
1983年早稲田大学政治経済学部卒。新聞社を経て、90年代初頭から中国での人事マネジメント領域で執筆、コンサルティング活動に従事。(株)リクルート中国プロジェクト、ファーストリテイリング中国事業などに参画。上海と東京を拠点に大手企業等のコンサルタント、アドバイザーとして活躍している。近著に「スッキリ中国論 スジの日本、量の中国」(日経BP社)。
スマホが「誰でも参入できる産業」に
メディアテックとは台湾の半導体製造およびファブレスIC設計企業の社名だ。本社は台湾・新竹市新竹科学工業園区にある。同社は2000年代頃から、携帯電話メーカー会社向けの半導体の製造、販売を手がける一方、そのまま組み込むだけで正常に動作する、いわば「出来合い」のチップセットとソフトウェアを組み合わせて販売するサービスを始めた。
この流れが進化し、メディアテックに注文さえすれば、高性能のチップセットやOS(基本ソフト)などを組み込んで、お好みのデザインで製品をつくってもらえるようになった。つまり、誰でも資金さえあれば、自分のブランドのスマホを商品化し、世に出せる状況が出現した。これが「メディアテック・モーメント」である。
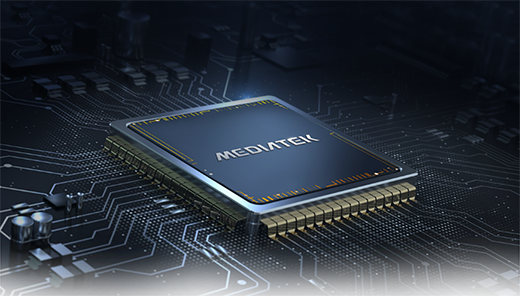
そのインパクトは絶大だった。それまで莫大な資金、とんでもない時間と人材を投入して開発するしかなかった高性能のスマホが、極論すれば、一夜にして「誰でも参入できる産業」になった。スマホの低価格化は一気に進み、スマートフォンという「高性能の手のひらコンピュータ」が、世界中で事実上1人1台といわれるまでに普及する原動力となった。
こうした動きが、クルマの世界でも果たして起きるのか。
そのことを考えるカギは、製品の「ソフトウェア化」にある。
「HUAWEI INSIDE」
昨年4月、上海モーターショーで世界的なスマホメーカー、ファーウェイ(HUAWEI、華為技術)のブースにEV(電気自動車)が展示され、話題を呼んだ。展示されたのは中国の国有大手自動車会社、北京汽車グループのEV企業「北汽能源」が発売した「ARCFOX(極狐)αS」である。
このクルマが注目を集めた理由は、そのクルマに「HI」のロゴが貼り付けられていたからだ。「HI」とは「HUAWEI INSIDE(ファーウェイ・インサイド)」の略。このクルマがファーウェイ製の半導体やモーター、各種センサー、制御用機器などからなるEVプラットフォーム全面的に採用して造られていることを意味する。

ご承知のようにパソコンの世界には「Intel Inside」という世界的に知られたロゴがある。日本では1991年から「インテル、入ってる」というコピーで一世を風靡したことをご記憶の方も多いと思う。「HUAWEI INSIDE」は、もちろん、この表現を受けたものだ。
「ブランドより中身」
この「○○ Inside」が言わんとするところは、「中身の方が大事だよ」ということである。パソコンという商品そのもの、もしくはクルマという製品自体を誰が造ったか(組み立てたか)はあまり重要な話ではなく、「中に使われているソフトウェアや中核部品を見てください」と言いたいわけだ。
パソコンという商品は、最終セットメーカーのブランドが全く意味を持たないわけではない。しかし、かなり昔から、その主要な価値は製品全体をコントロールするソフトウェア(OS)および製品を構成する中核部品が何なのかで決まる構造になっている。スマホでもそこに使われているCPUのブランドや性能を購入の目安にする人は多い。
そして「HUAWEI INSIDE」は、いまやクルマの領域でも「中身が何か」が広く顧客に向けてアピールされる時代が始まったことを意味する。「○○ Inside」の「○○」はファーウェイには限らない。EVはバッテリーが命だから、「BYD Inside」かもしれないし、「CATL Inside」や「Panasonic Inside」だってありうる。「北汽能源」には申し訳ないが、誰が組み立てて売っているかはどうでもいいのである。
「ソフトウェア化」のインパクト
このように「○○ Inside」がビジネスの表舞台に出てきた最も本質的な要因は、あらゆる製品の「ソフトウェア化」の流れにある。
パソコンやEVに共通するのは、OSでさまざまな機能を集中的に制御する仕組みになっていることだ。各種の機能を担う個々のコンポーネントはOSに従属しており、その指示に従う。その製品の「優秀さ」は、OSおよび主要な中核部品の性能に大きく支配される。その他の機能は副次的な要素にとどまる。
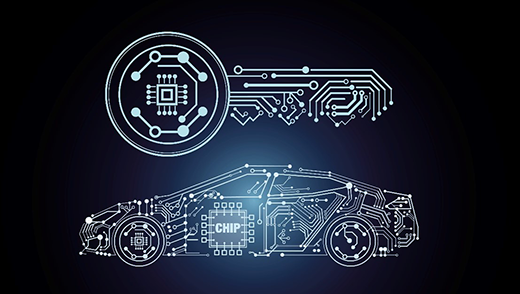
したがって、全体を統御するOSと中核部品を信頼できる専業メーカーから供給を受ければ、それを組み合わせるだけで、立派な製品ができてしまうことになる。さまざまな機能を持つ複雑なメカニズムを組み合わせ、いわゆる高度な「擦り合わせ」で高い性能を出すという「熟練の技」の重要度は相対的に低くなってくる。
ソフトウェアで走るテスラ
クルマの世界でこの流れを最も端的に表したのがテスラである。テスラは「EV」の代表格として語られるが、その本質的な新しさは動力源が電気であることより、「ソフトウェアですべての機能をコントロールして走る乗り物」である点にある。
シリコンバレーを拠点に活躍する著名なアナリスト、ベネディクト・エヴァンス(Benedict Evans)は、テスラについての自身の論考「Is Tesla disruptive?」の中で、「We will go from complex cars with simple software to simple cars with complex software(複雑なクルマを貧弱なソフトウェアで動かす(従来の)仕組みから、(テスラは)シンプルなクルマを複雑なソフトウェアで動かす方向に向かっている.[筆者訳])」と表現している。
この「シンプルなクルマ」を統御する半導体チップやソフトウェアを、テスラは自社で開発している。動力源であるモーターも、安全性を確保するブレーキも、自動運転システムも、車内のエンタテインメントも、基本的にひとつのソフトウェアで制御されており、まさに「コンピュータが運転するクルマ」になって(を目指して)いる。クルマの生産面では、テスラは非常に苦労したが、製造技術の革新を重ね、いまや世界各地に「ギガファクトリー」と呼ばれる自社工場を建設し、生産プロセスまで自社で手がけるようになっている。
テスラは非常に高いオリジナリティを持った、自動車業界のまさに「破壊的イノベーション」だった。
「テスラはクルマのiPhone」という見立て
テスラが世界に先駆けて提唱し、現実に商品化した、この「ソフトウェアで動く、シンプルなクルマ」は自動車業界に巨大なインパクトを与えた。特に大きく反応したのが、国を挙げてEV化に突き進む中国である。
ガソリン車の領域での大きなビハインドを、EVで「一発逆転」し、世界の先端に躍り出ようと目論む中国の政府や自動車産業にとって、従来のクルマとまったく異なるコンセプトでつくられたテスラは輝ける星となった。それは「EVの目指すべき形」であり、進むべき将来像を示したものと受け止められた。
そして、さまざまな企業が、「中国版テスラ」の再現を目指して走り出した。そして、そこでのテスラの持つ意味は、2010年前後、中国のスマホ黎明期にiPhoneが位置していたポジションとよく似た点がある。
iPhoneを追いかけたシャオミ
設立後わずか1年あまり、社員数百人の企業だったシャオミ(Xiaomi、小米)が2011年秋、発売したスマホ「MiOne」(第1代)は、当時のiPhone4を強く意識して開発されたものだ。デザインもスペックもほぼそっくりである。iPhone4とほぼ同等の仕様を実現しつつ、価格は1999元(当時の換算レートで約25000円)とiPhone4の半分以下。当時、「iPhoneが欲しいが、買えない」中国の若者たちの熱狂的な支持を受け、「伝説のスマホ」といわれるほどの存在となった。シャオミが現在、世界でシェア3位のスマホメーカーに躍進した原点はここにある。

当時のシャオミのような弱小企業にこれが可能だったのは、まさに冒頭に紹介した「メディアテック・モーメント」のたまものだ。そしてその背景には、Googleのアンドロイドというスマホ向けOSが、無償で誰にでも提供されるオープンソースソフトウェアとして成長したこと、加えてクアルコムや前述のメディアテックなどの半導体メーカーが高性能のチップセットを開発、外販したことなどがある。つまりここで「自社開発で閉じたiPhone対オープンな水平分業のアンドロイド勢」という構図ができあがった。
いま中国のEV市場でも似たような構図ができつつある。独自の技術で孤高の路線をひた走るテスラ、そこにさまざまな企業が合従連衡を試みつつ、テスラの「破壊的イノベーション」に追随しようとしている。それはかつてシャオミがiPhoneという「破壊的イノベーション」を必死で追いかけた姿を彷彿とさせる。
そこで次に出てくる問題は、アンドロイドOSを提供したGoogleや、高品質なスマホを安く、大量に生産し、革命を起こしたメディアテックなどの役割を、クルマの世界では誰が果すのか――である。
最有力候補はファーウェイ
その中でも、最も参入のインパクトが大きく、EVの「メディアテック・モーメント」が生まれるとすれば、現時点でその最有力候補と目されているのがファーウェイである。
ファーウェイはコンシューマー向け商品の主力だったハイスペックのスマホが、米国による制裁で造れなくなり、それに変わる成長のエンジンを必要としている。自動車市場は規模が大きく、魅力的だ。「HarmonyOS」という独自開発のソフトウェアも擁しており、グループには強力な半導体開発、製造の能力もある。自動運転の研究の蓄積も豊富だ。研究開発人員の豊富さ、圧倒的な資金量など、何をとってもその実力は飛び抜けている。
一方でファーウェイは再三、「自分ではクルマは造らない」と明言し、クルマを生産するメーカーをさまざまな形でサポートするとの姿勢を明確にしている。この点でも「メディアテック的」なスタンスと見ることもできる。現時点では、ファーウェイがEVメーカーと協業を進めているやり方は以下の3つだ。
①通常の部品のサプライヤーとして、表には出ず、いわば裏方的な立ち位置でEVメーカーに協力する
②前述の「HUAWEI INSIDE」として、ソフトウェアや中核部品のサプライヤーとして、表に出る形でEVメーカーのクルマづくりをサポートする
③EVメーカーと共同開発で、「ファーウェイの手がけたEV」として完成車を生産、販売する
現在はこれらを並行して進めている状況で、「自社でクルマはつくらない」というスタンスは変えていないが、③の「実質的にはファーウェイのEV」と目される共同開発の小型EVセダン「SERES(賽力斯)」が今年9月単月で1万7596台、前年同期比3.4倍の販売を記録、今年1~9月の9カ月間でも9万4600台、同2.7倍と好調が続いていることから、自社ブランドのEVを発売すべきとの声もある。
中国企業の「旺盛な参入」
自動車業界にもこれまで、製品の設計からデザイン、製造までを受託するODM(Original Design Manufacturing)の企業がなかったわけではない。例えば、オーストリアのマグナ・シュタイヤー(Magna Steyr)は、代表的な自動車ODM企業で、トヨタ自動車をはじめ、メルセデス・ベンツ、BMWなどを顧客に多くのクルマの受託開発および生産で、豊富な実績がある。
しかし、中国での今回の動きが過去と違うのは、世界一の規模を持つ中国の自動車市場で起きている怒涛のようなEV化という底流があることだ。そこに、これは中国経済の特徴ともいえるが、良し悪しは別として、さまざまな業界からの、あらゆる形での「旺盛な参入」が起こっている。
例えば、中国大陸の企業で初めてiPhoneの生産を一部受託したしたことで知られる電子機器受託製造サービス(EMS)大手、ラックスシェア(立訊精密、Luxshare Precision Industry)は、今年2月、中国政府傘下の大手自動車メーカー、奇瑞汽車(Chery Automobile)のグループ企業と合弁会社を設立、EVの開発と製造に乗り出した。またiPhoneの最大の受託生産先であり、中国国内で100万人近くを雇用している巨大EMS、フォックスコン(富士康科技集団)もEV生産に参入するとの観測もある。
また既存の自動車メーカーも、IT企業などと組んで、自社の生産力をEVの生産に活用しようという動きがある。例えば、中国の新興EV企業、NIO(ニオ、上海蔚来汽車)のEVは、安徽省の老舗自動車メーカー、江淮汽車集団が受託し、生産している。少し異質のパターンだが、中国最大のタクシー/配車アプリ企業である滴滴出行(Didi Chuxing)は、タクシー仕様のEV車両を、中国最大のEVメーカー、BYD(比亜迪)に発注。同社が受託生産したEV「D1」はその後、一般向けに市販もされている。これはいわば立派な完成車メーカーであるBYDがODMの役割を担ったことになる。
巨大な中国の生産力
クルマの領域で「メディアテック・モーメント」が大きなインパクトを与えるには、当然ながら、その能力を持つ製造会社が不可欠である。どんなに高性能なソフトウェアや中核部品が使われたクルマであっても、それを高品質で、安く、大量に生産することができなければ、産業として成り立たない。売れるクルマを構想し、企画することと、それを市場で競争力のある価格、品質、量、スピードで生産することは別の話である。クルマの生産には莫大な投資、長い製造現場のノウハウの蓄積が必要で、決して簡単なことではない。
その点で中国には、さまざまな業界のODM企業が存在し、巨大な生産力がある。この点は中国の大きな特徴であり、国策としてのEVの普及という大波に乗って、クルマのつくり方そのものを大きく変える可能性が存在する。このことは「自動車立国」を自認してきた日本社会にとって、大きな影響を与えるだろう。
変革の波はもう来ている?
先日、日本経済新聞電子版に「中国商用EV、日本向け専用車 広西汽車が150万円軽バン
中国の地方都市の地味な自動車メーカーが、日本のEV設計企業と組んで、1台150万円の軽自動車のバンを生産し、宅配便などの物流企業に売り込む――という筋書きである。これも典型的なODMだ。
営業所などを拠点に近隣を巡回する配送用車両は、EVの機能には最適である。使用目的が明確なクルマは開発しやすい。要は便利で安全に使えさえすればいい。まさに「シンプルなクルマを複雑なソフトウェアで動かす」の典型例で、このような活用例はどんどん広がっていくだろう。少なくとも日本の軽自動車とか、商用車の多くは遠からずこういう構図になるのではないかと思う。
もちろんスマホとクルマは違うので、「メディアテック・モーメント」で、瞬時にクルマのつくり方が変わるとは思わない。クルマは大きくて、複雑で、人が乗って高速で動くものだから安全性が重要だ。誰にでも気軽に生産できるものではない。
しかし、クルマの「ソフトウェア化」という趨勢は不可避であり、そしてソフトウェア化には、ガソリンエンジン車よりEVのほうが明らかに向いている。そのことが否定できない以上、クルマのつくり方の大変革は避けられそうにない。その震源地はおそらく中国になる。中国発の「破壊的なイノベーション」の波はもう到達しているのかもしれない。

次世代中国


