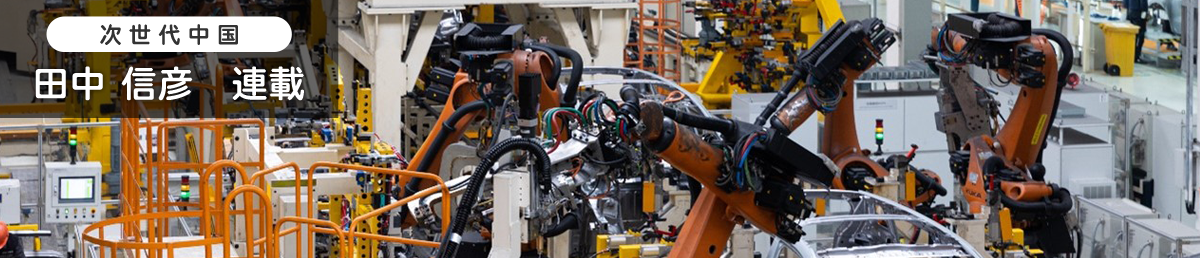
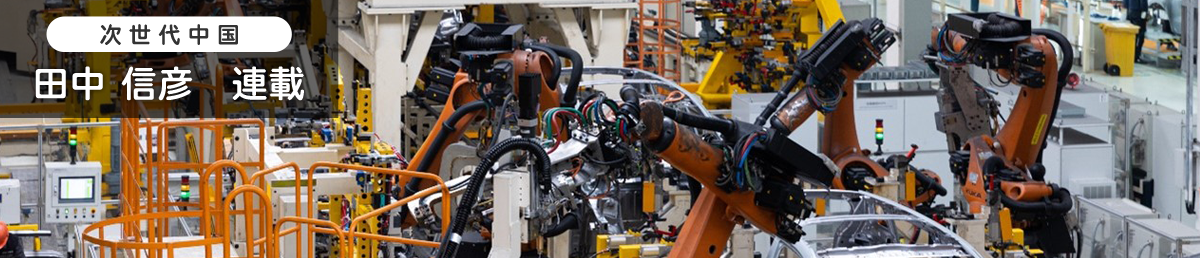
EVバッテリーの覇者、中国CATLが急成長した理由
国策と民営企業、鮮やかな連携の功罪
Text:田中 信彦
車載バッテリーの世界市場でトップのシェアを握り、昨年度の純利益は対前年比9割増と急成長する中国企業、CATL(寧徳時代新能源科技、福建省寧徳市)に注目が集まっている。時価総額でも一時、アリババや国有銀行などを追い抜いて中国最大に上り詰め、「どこまで成長するか見当もつかない」との声が上がるほどの圧倒的な存在感を示している。
しかし、基本的にB to B(企業間取引)の業態であること、表舞台で脚光を浴びることを好まない社風もあって、その成り立ちや成長の背景はあまり広く知られていない。EV車載電池の主戦場が中国国内からグローバルに広がる中、政府との関係を明確にする必要にも迫られている。
CATLの成長プロセスは、実は日本企業との因縁も深い。今回はCATLの成長にまつわるストーリーから企業と国家との関係などについて考えてみたい。

田中 信彦 氏
ブライトンヒューマン(BRH)パートナー。亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科(MBA)講師(非常勤)。前リクルート ワークス研究所客員研究員
1983年早稲田大学政治経済学部卒。新聞社を経て、90年代初頭から中国での人事マネジメント領域で執筆、コンサルティング活動に従事。(株)リクルート中国プロジェクト、ファーストリテイリング中国事業などに参画。上海と東京を拠点に大手企業等のコンサルタント、アドバイザーとして活躍している。近著に「スッキリ中国論 スジの日本、量の中国」(日経BP社)。
創業わずか6年で車載電池世界No.1に
CATLは2011年創業の新しい企業だ。中国でEVに対する補助金の支給が始まったのは2010年。EVに加え、プラグインハイブリッドカー(PHV)、燃料電池車(FCV)などを振興する「新エネルギー車」政策が本格化したのが2012年のことだ。CATLはまさに中国のEV化と共に歩んできた企業といえる。

創業わずか6年後の2017年にはパナソニックを抜いてEV用車載電池の出荷量で世界トップに躍進。翌2018年には株式を上場し、米経済紙「Forbes(フォーブス)」によれば、2021年、創業者で董事長(会長に相当)の曽毓群(Robin Zeng)の保有資産は345億ドルに達し、世界富豪ランキングの42位に躍り出た。車載バッテリーの世界シェアは37%(2022年)に達する。
しかし、いかに成長スピードの速い中国とはいえ、ゼロから6年で世界No.1になれるはずはない。当然そこには曽がCATLを創業する以前のストーリーがある。
「わかりにくい社名」の意味とは?
CATLが一般人にその実態が伝わりにくい一つの原因は、その社名にもある。CATLの正式名称は「寧徳時代新能源科技」。中国では通常「寧徳時代」と呼ばれる。「寧徳」は地名で、福建省北部の海沿いの街だ。創業者、曽の出身地である。社名の「時代」には「時流に合った」「最新の」といった意味が込められている。「新能源」は「新エネルギー」、「科技」は「サイエンス&テクノロジー」の略である。

英文社名のCATLは「Contemporary Amperex Technology Co., Ltd」の略。「Contemporary」が「時代」に相当するが、「Amperex」は英和辞典を引いても出てこない。Google検索でも同社の社名以外には、真空管のブランドやミュージシャンの名前に使われている例がみつかるぐらいで、類例はほとんどない。電流を表す単位のアンペア(ampere)に因んだ造語との説もあるが、実際のところはよくわからない。
なぜ社名にこだわるかといえば、この社名にCATLの誕生に至る歴史がそのまま反映されているからだ。
ATLとCATL
CATLの名は今や世界No.1の車載バッテリー企業として広く世界に知れ渡っている。しかし中国にはもう一つ、iPhoneをはじめとするスマホ向けの民生用電池の領域で世界No.1のシェアを持つ、グローバルなバッテリー企業がある。社名をATLという。実はこの中国企業の親会社は日本の企業なのだが、そのことは後で触れる。
ATLとは「Amperex Technology Co., Ltd」の略である。中国語の正式社名は「新能源科技」で、本社は香港だが、実質的な本部と開発・生産拠点はCATLと同じ福建省寧徳市にある。その法人名は「寧徳新能源科技」である。
要するに「ATL」に「Contemporary(時代)」が加わったのが「CATL」だ。しかも地味な地方都市の寧徳に両社とも中核拠点があり、一方は車載バッテリー、一方はスマホのバッテリーで共に世界No.1。このようなことが偶然であるはずがないことは誰でもわかるだろう。
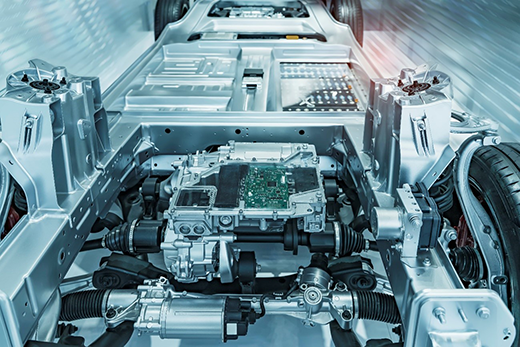
タネ明かしをしてしまえば、ATLもCATLと同じく前述の曽毓群らが創業した企業である。曽らは1990年代末、先にATLを創業、民生用バッテリーで世界的な地位を得た。そして2011年、その基盤をもとにCATLを創業した――という流れになる。CATLが創業わずか6年で車載バッテリー世界No.1に躍進できた最大の理由はここにある。
ではなぜ同じバッテリー企業であるATLを基盤に生まれたCATLが、ATLとはまったく別の企業として成長し、世界に飛躍することになったのか。そこにはATLという企業の「出自」と中国の「国策」としてのEV普及政策が決定的な影響を与えている。
福建省の農村から改革開放の最前線へ
ではCATLを生み出す基盤となったATLとはどのような会社なのか。
曽は1968年、福建省寧徳県(現寧徳市)の貧しい農村に生まれた。子供の頃から成績が良く、地元で一番の中学を経て名門の上海交通大学船舶工程学部に合格。卒業後の1989年、福建省の省都・福州市の国有企業に就職したものの、3ヶ月で辞め、改革開放の最前線、広東省東莞市に向かう。そこで磁気ヘッドを生産する日系電子部品企業に新たな職を得た。
後に振り返れば、このことが曽を世界一のバッテリーメーカーの創業オーナーの地位に押し上げる出発点となる。
この企業はもともと香港資本だったが、曽が就職する以前、日本の大手電子部品メーカー、TDKに買収され、100%子会社となっていた。ここで曽は有能な上司に恵まれてその力を発揮、若くして幹部に昇進する。1990年代後半、市場では携帯電話が急速に普及、mp3プレーヤーが人気を呼んで民生用バッテリーの需要が急増し始めていた。この機を逃すまいと、上司らと共に曽は会社を辞めて独立、1999年、小型バッテリーを設計・開発・生産する企業を立ち上げる。これがATLの始まりである。
「iPod」への電池供給で成長。競争激化で一転、苦境に
曽らは最先端のバッテリー製造特許を米国のベル研究所から100万米ドルで購入、生産に着手した。当時の資本金の4割に相当する思い切った投資だった。しかし、バッテリーが膨張してしまう問題が発生、どうしても解決できない。ベル研に問い合わせても埒があかない。曽らは覚悟を決め、不眠不休でこの問題に取り組み、ついに膨張を防ぐ新たな技術を開発。これがATL躍進の基礎になった。
当時、基本的に供給不足だった民生用バッテリーはよく売れた。ATLの将来性に着目した投資家から数千万米ドルの資金調達もできた。2004年にはアップルの「iPod」のサプライヤーの1社に認定され、1800万個のバッテリーを供給するまでになった。
しかし、この頃から競合の参入が増え、競争が激化。ATLの技術の優位性は徐々に失われ、競争力が低下し始める。2005年、資金を提供していた有力ベンチャーキャピタルがATLの将来性に不安を感じ、資金の引き上げを決め、他の投資家も追随する動きを見せた。
この時、曽ら創業者グループは自らの持ち株の大半を譲渡してしまっており、少数株主の立場だった。手元には株式を買い戻すほどの資金もない。そこで新たな資金提供者としてATLの株式を引き受けたのが、曽らのかつての勤務先の親会社、TDKだった。
大きな果実を生んだTDKの投資
この当時の状況について、TDKの石黒成直社長(当時)は「日経ビジネス」(2021年8月6日付「編集長インタビュー」)で次のように語っている。
ATL買収の際も「どこの馬の骨か分からない香港の会社を買っていいのか」という空気があったと聞いています。ATLの当時の中心メンバーがロビン・ゼン氏(曽毓群、筆者注)。今のCATLの董事長です。もともとはTDKグループの磁気ヘッドメーカーのエンジニアだったのですが、そこを辞めてATLをつくっていた。
ATLを大きくしたいのでTDKに協力を求めてきました。中身を調べたら技術が素晴らしく、高邁(こうまい)な精神もある。グループに入ってもらえば新たなチャレンジができると判断し、分かった、やろうと買収に踏み切りました。後に彼はATLから独立してCATLを設立しました。
この文面からは、TDK側は、かつて縁のあった人たちだとの認識はあったが、特に親密だったわけではなく、当初は買収にさほど積極的ではなかったことがうかがえる。
買収金額は107億円と伝えられる。「どこの馬の骨かわからない」企業の買収としては大金だったかもしれないが、この投資はTDKに後々、巨大な果実を産むことになる。
100億円の投資が1兆億円超の売上高に
ATLはその後、再び成長軌道に乗り、2007年には売上高が23億元(現在のレートで400億円強)に達し、経済紙「Forbes」で「中国で最も潜在力のある企業100社」の13位にランクイン。2012年には累計で10億個のバッテリーを出荷、「ラミネート型」と呼ばれるスマホ向けの薄型リチウムイオン電池で世界No.1の供給企業となった。もともとiPodの実績でアップルとの信頼関係があったことが、その後、iPhone向けの電池としても採用され、業績を大きく伸ばすうえで有利に作用した。
TDKの2022年3月期有価証券報告書によれば、Ningde Amperex Technology Ltd.(寧徳新能源科技=福建省寧徳市)の売上高は6945億2400万円、税引前利益は 943億9000円、Amperex Technology Ltd.(新能源科技=香港)が売上高4178億8100万円、税引前利益867億3000万円。TDKの連結売上高は1兆9021億2400万円、税引前利益1724億9000万円なので、この中国2社の貢献度の大きさがわかる。
車載バッテリー生産に外資は「資格なし」
前述したように、ATLを基盤に曽らがCATLを創業したのは2011年。その背景には中国政府のEV普及政策があった。EVを中核とする「新エネルギー車」を政府主導で普及させ、ガソリン車では先進国に追いつけない自動車産業で「一発逆転」を狙うという「国策」ついては、wisdomの連載「中国のEV(電気自動車)は「市場化」できるか~補助金終了後の「新エネルギー車」のゆくえ(2022年4月27日)」で紹介したので、ご参照いただければと思う。

その中国政府の「新エネルギー車」優遇政策の対象となるには、EVの中核部品であるバッテリーが中国企業の製品であることが条件になる。中国政府の工業情報化部(省に相当する中央官庁)は2015年3月、車載バッテリー生産企業の条件を定めた「規範条件」を策定した。これに適合する企業が生産したバッテリーを使わなければ補助金の受給資格は得られない。しかし政府の発表した「規範条件」の適合企業リストには外資系企業は1社も含まれていない(この規制は2019年、廃止されている)。
CATL設立の段階ではATLの子会社である「寧徳新能源科技」がCATLに15%を出資し、資本関係を保持していた。しかし上記の「規範条件」が明確化された2015年、この部分の株式はある中国企業に譲渡され、CATLは100%中国資本となっている。
EV向けの車載電池市場が急成長することは当時から確実だった。しかし100%外資のATLの系列企業が政府の優遇策の対象となることは難しい。CATLがATLとは完全に切り離され、100%中国資本の企業となったのはここに理由がある。その後、中国でのEVの急速な普及を受け、CATLが爆発的な成長を遂げたことはすでに紹介した通りだ。
後日談になるが、ATLの子会社からCATLの株式の譲渡を受けた中国企業は、その後のCATLの業績拡大、2018年の株式上場によって保有株式の時価が数百倍になったとされる。この結果に対して、ATLの親会社であるTDKは「大魚を逸した」との見方もある。しかし、その中国企業への株式譲渡価格が適正なものであったかは議論の余地があるとしても、政府の明確な規制がある以上、最終的には他に選択肢はなかったというべきだろう。
「自国産業育成」の鮮やかな成功
こうした経緯からもわかるように、CATLが「中国企業」として驚異的な成長を遂げた背景に外資に対する政府の規制があったことは明らかだ。中国でEVが急成長した2010年代の数年間、少なくとも中国国内で販売されるEVには100%中国企業の生産したバッテリーを搭載するしか、事実上選択肢はなかった。このことが設立当初、車載バッテリーでは決して世界の最先端とはいえなかったCATLに決定的な「成長のための時間と資金」を提供した。
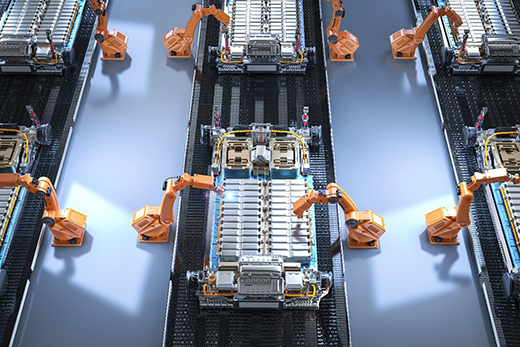
中国政府は、社会的にさまざまな無理や難題があることを承知のうえで、半ば力ずくでEVを普及させる政策を取った。そして、CATLに代表されるEV関連の中国企業を政策的に外資との競争から保護し、世界のトップ水準に育て上げた。そのやり方の是非はともかく、「自国産業の育成」という政府の職責からみれば、CATLはその鮮やかな成功例といっていい。
米国の優遇政策から「外された」CATL
今年2月、CATLは米国の自動車会社フォードと協力し、米国内のフォードの工場で車載用のリン酸鉄リチウム(LFP)電池セルを生産する計画を発表した。35億米ドルの資金を出して工場を建設し、電池を生産するのはフォードで、CATLは契約に基づき技術を提供する。CATLが持つ特許技術の使用も認める内容とされる。
車載電池の完成品供給ではなく、CATLの技術供与でフォードが電池を生産する形になったのは、米国で2022年8月に成立した「歳出・歳入法(インフレ抑制法)」が背景にある。同法には米国内のEV購入者は1台当たり最大7500米ドルの税額控除を受けられる優遇措置がある。しかし、そのためには車載電池が米国本土で製造され、原材料の一定比率を米国ないしは米国が自由貿易協定を結ぶ国から調達するなどの条件が設けられた。
これは明らかに世界のバッテリー市場で圧倒的な力を持つ中国企業を念頭に置いたものだ。同法への抵触を避け、米国内での政治的な反発を避けるために、両社の協力関係はこのような形式になったとの見方が強い。中国政府の優遇策の恩恵を受けて成長したCATLが、米国市場では米国政府の政策によって縛られる。時代の大きな変化を印象づける出来事だった。
政府と民間、広がるギャップ
モバイル通信関連設備やスマホで世界をリードする技術力を持ったファーウェイ(華為技術)、ショート動画で米国をはじめ世界を席巻したTikTok(抖音)、ITを駆使して「売れる商品」を素早く特定し、安く、速く提供する仕組みを確立して人気爆発した中国発EC「Shein(シーイン)」、米国を皮切りに世界市場に打って出た中国の低価格EC「ピンドゥオドゥオ(拼多多)」など、昨今、中国で成功した企業による米国を中心とするグローバル市場への展開が目立っている。その背景には、中国市場の成熟化と将来への不透明感、そして中国民営企業経営者の意識の変化が存在する。
中国国内では今でもGoogleやFacebook、Twitterなどが使えないことに象徴されるように、業界によって程度の差はあれ、政府の政策によって海外の先進企業から国内企業を守ることで中国の産業は成長してきた側面を持つ。CATLの例で明らかなように、その手法は中国の見方に立てば大きな成功を収めてきた。
しかし、中国企業の力が弱かった時代には大きな支えとなった政府の保護は、企業が成長し、世界市場で通用する実力を身に付ければ、それは逆に足かせになる。企業の背後に「国家」の影がちらついてしまうからだ。CATLをはじめ、ここに挙げたような中国発の企業たちは、本音を言えば政府の「保護」を煩わしく感じ始めている。
中国発の企業を通じて「中国の」メリットを追求しようとする政府、グローバルに活躍の場を広げ、世界中のより多くの人々の支持を得たいと望む企業家たち。その感覚のギャップは次第に広がりつつある。

次世代中国


