

次世代中国 一歩先の大市場を読む
欧米のDNAを持つ中国発の最先端技術
「EVのアンドロイド」を目指す吉利汽車のオープン・プラットフォーム戦略
Text:田中 信彦
中国の自動車メーカー「吉利汽車」(Geely Auto、ジーリー、浙江省杭州市)をご存知だろうか。社名は知らなくても、「スウェーデンのボルボを買収した中国企業」といえば、思い当たる方も多いかもしれない。
いま中国の自動車業界で、このジーリーが、にわかに注目を集めている。EV販売台数で一時は独走体制かと思われたBYD(比亜迪、広東省深圳市)を急追。株価もこの1年で2倍以上になった。
しかし、ジーリーが注目される最大の理由は直近の業績ではない。同社が掲げる、業界の常識を覆すクルマの造り方、「オープン・プラットフォーム戦略」にある。
EVの先行者であるBYDやテスラはサプライチェーンの多くを内製化し、垂直統合的なモデルで成長してきた。それに対してジーリーは、汎用性の極めて高いEV専用プラットフォームを他企業に公開、世界中の企業と組んで、水平分業的なクルマづくりを志向する。自らはいわば「プラットフォーム・プロバイダー」となり、スマートフォンにおけるアンドロイドのようなポジションを目指す。そして、その動きにメルセデス・ベンツやGoogleの自動運転Waymo(ウェイモ)など、世界の有力なプレーヤーが次々と参画している。
AIの飛躍的な進化で、ソフトウェアの重要性が高まり、クルマの基本構造は大きく変わりつつある。独自技術を持つ多様な企業が参画しやすいオープンなプラットフォームの有効性は高まっている。ジーリーの提示するオープンな開発モデルが、業界に地殻変動を起こすのではないかとの見方も出ている。
今回は中国の一地方企業から世界の主要なプレーヤーに成長したジーリーを切り口に、クルマの世界のオープン化、世界市場での中国企業の生き方などについて考えてみた。

田中 信彦 氏
ブライトンヒューマン(BRH)パートナー。亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科(MBA)講師(非常勤)。前リクルート ワークス研究所客員研究員
1983年早稲田大学政治経済学部卒。新聞社を経て、90年代初頭から中国での人事マネジメント領域で執筆、コンサルティング活動に従事。(株)リクルート中国プロジェクト、ファーストリテイリング中国事業などに参画。上海と東京を拠点に大手企業等のコンサルタント、アドバイザーとして活躍している。近著に「スッキリ中国論 スジの日本、量の中国」(日経BP社)。
販売台数で一時、BYDを抜き、国内首位に
2025年上半期、ジーリーの販売台数は140万9000台。前年同期比で47%増加し、EVに限ってみれば同2.7倍に伸びた。今年1月には中国国内販売台数でBYDを抜いて一時的だが首位に立つ「快挙」を見せた。今年上半期の中国での市場シェアは10.4%となり、首位のBYD(同14.8%)に手が届く位置に来た。中国におけるEVの競争環境が変わりつつあることを印象付けた。

 )
)その原動力がジーリーの柔軟な「マルチブランド戦略」だ。BYDが自社単一のブランドで市場を広くカバーするのとは対照的に、ジーリーは、異なる顧客層を狙う多数のブランドが、異なる市場で、それぞれ個別に展開する「狼の群れ(狼群)戦略」を取っている。
EV時代の新たなプレミアムカーを掲げる「Zeekr(ジーカー、極氪)」、中国のメインストリーム市場を狙う「吉利銀河(Geely Galaxy)」、ボルボとの共同出資で立ち上げ、若者やグローバル市場をターゲットにした「Lynk & Co」、同じくEV専用ブランドの「Polestar」、メルセデス・ベンツとの合弁事業のマイクロカー「Smart」、そして信頼性の高いグローバルブランドとして日本でも根強い人気を維持する「Volvo」など、高級車から大衆車に至るまで国を超えた広範な地域、幅広い価格帯、多様なニーズに対応している。
ボルボと共同で拡張性の高いプラットフォームを開発
この体制を支えるのが、汎用性の高い独自のプラットフォームだ。2010年のボルボ買収後、ジーリーは2013年、スウェーデン第2の都市、ヨーテボリ市にボルボと共同で研究開発センター「CEVT(China Euro Vehicle Technology)」を設立。そこにスウェーデンや英国、ドイツ、中国などの技術者が集まり、幅広い車種に応用できる拡張性の高いプラットフォームの開発が始まった。
2017年、最初の共同開発プラットフォームである「CMA(Compact Modular Architecture)」が誕生。同年に発表された新ブランド「Lynk & Co」の第1弾モデル「01」で初めて採用された。CMAは乗用車のC~Dセグメント(おおむねコンパクトからミドルサイズ)に対応可能で、内燃エンジン(ICE)、ハイブリッド(HEV)、純電気自動車(EV)などあらゆる動力源をカバー。中国国内に加え、世界市場向けブランドでも多様な要求を満たせるように作られた、同社初めての本格的な柔軟性と拡張性を有するプラットフォームだった。

 )
)このCMAの成功で、ジーリーは「オープン性」の重要さを再認識した。バックグラウンドの異なる多数の技術者が集まって開発する、柔軟で拡張性の高いアーキテクチャは、グローバル市場の多様な顧客のニーズにフィットする。異様なまでに激しい中国国内市場の競争に飲み込まれることなく、世界に飛躍するためには「オープン性」がカギであることを同社は学んだ。
ミニカーからトラックまで対応の拡張性
この成功を基礎に、従来のエンジン車の制約を離れ、ゼロベースで設計するEV専用プラットフォームとして開発されたのが「SEA(Sustainable Experience Architecture)」である。CEVTを中心に、3年の年月、180億元(約26億米ドル)の資金を投じて2020年に最初のバージョンが完成、翌2021年から投入された。その後、随時バージョンアップされている。
最大の特徴は、その驚異的な拡張性だ。ホイールベースは1800~3300mmの範囲で自在に調整可能。AセグメントのミニカークラスからEセグメントの高級セダンや大型SUV、さらには小型トラックなどの商用車まで、あらゆるタイプの車両をこのアーキテクチャから生み出せる(SEAのスペックはジーリー自身の発表による。以下同)。
三電システム(バッテリー・モーター・制御システム)も先端水準にある。最新版の「SEA-S」は業界初のフルスタック900Vハイブリッドアーキテクチャを採用、電動駆動の最高出力は1000kWを超える。このアーキテクチャを搭載したSUV「Zeekr 9X」は、プラグインハイブリッド(PHV)車ながら電気のみによる走行距離が380kmに達する。バッテリーは10分間で完全充電可能な「6C」急速充電をサポート。20%→80%の充電は9分で済む。車両重量3000kg近いフルサイズのSUVながら、0-100km/h加速は約3秒で、スポーツカー並みの動力性能を持つ。

全ての車種、全ての価格帯で先端プラットフォームを導入
インテリジェント化も高水準だ。AIはエンドツーエンドやVLM(Vision-Language Model、視覚言語モデル)などの先端技術をカバーし、「レベル5」の完全自動運転時代にも対応できる。スタンダードなバージョンでも100TOPS以上の演算能力を標準装備、上位バージョンでは都市部での地図不要NOA(高速ナビゲーション支援運転)、将来的にはVLA(Virtual Lane Assist、仮想車線アシスト)への進化も予定されている。
また「SEA OS」と呼ぶインテリジェント開発システムを内包し、ソフトの開発時間を従来比で50%以上短縮。クルマのライフサイクル全体を通じて、随時機能を追加・更新できるファームウェアOTA(Firmware Over-the-Air)を搭載し、「購入後も性能がアップし続けるクルマ」として、SDV時代の車両開発に対応している。
ジーリーは価格帯を問わず、グループの全ブランド、全車種をこのSEAでカバーすることをすでに表明している。
先端のプラットフォームを他社に公開
こうした高い仕様もさることながら、SEAの最も際立った特徴はその「哲学」にある。ジーリーはSEAの開発当初から「オープンであること」を自社の姿勢として強く打ち出している。そこには強い戦略性が感じられる。
前述したように、BYDやテスラをはじめ、エンジン車を含む既存の大手自動車メーカーは、垂直統合的な生産方式を強みに成長してきた。それに対してジーリーは、高い競争力を持つSEAをグループ内での利用に限定せず、他の自動車メーカーやサードパーティにも提供することを当初から公言し、実行している。
これは従来の自動車業界の常識を覆す戦略といえる。
2020年9月、SEA完成の際、同社の創業者であり董事長(会長に相当)の李書福(敬称略、以下同)は、このSEAを「オープンソース・アーキテクチャ」と表現し、「気候変動問題への対応という自動車業界共通の利益に鑑み、この技術革新の恩恵を他メーカーにも提供する」(訳は筆者、以下同)と高らかに語った。これはジーリーが、既存の自動車メーカーと同じやり方で競争するのではなく、根本から異なる発想で勝負しようとしていることを意味する。
ここで李が言うジーリーの「オープンソース」(中国語で「開源」)は、ソフトウェアの開発モデルで使用されるオープンソースの定義とは明らかに異なる。どちらかといえば「ライセンス供与」に近いものだ。しかし李は、それを承知のうえで、あえて今日性の高い「オープンソース」という単語を使うことで、自社の哲学の独自性、グローバル戦略の開放性を強調してみせたと思われる。
自動車業界を支える「プラットフォーム・プロバイダー」
ジーリーが発表した経営戦略「Smart Geely 2025」プランでは、「Smart Geely Technology Ecological Network」と呼ぶエコシステムを構築すると宣言。「先端的なチップやソフトウェア、OS、インテリジェント・コネクティビティ、衛星ネットワークなどを中核としたエコシステムを形成し、技術主導型のグローバルな自動車グループとなり、未来のコア競争力を確立する」とうたっている。
その目的達成のために、同プランは「統合された車両ソフトウェアユーザー体験を創出するため、ソフトウェアアーキテクチャを開放する。1000以上のAPIインターフェース(API)およびソフトウェアツール・プラットフォーム、1000社以上のデジタルパートナーとのサービス提携を世界中の開発者に提供する」と表明している。
ここから読み取れるのは、ジーリーは、従来型の垂直統合的な囲い込みで勝とうとは考えていないことだ。より高性能なクルマを、より効率的につくるためのプラットフォームを他社に提供し、オープンなエコシステムを形成する。自らはそこで業界全体のEV化を支える「プラットフォーム・プロバイダー」になる。そのような戦略を進めつつある。
「EVのアンドロイド」を目指す
このアプローチは、スマートフォンにおけるアンドロイドOSや、クラウドコンピューティングにおけるAmazon Web Services(AWS)などの戦略と共通性がある。
自らは他社の事業基盤となるプラットフォームそのものを提供する。そのプラットフォーム上で世界各地の多様なプレーヤーが製品やサービスを開発する。そして、自力では高度なプラットフォーム開発力を持たない、もしくはコスト削減、開発期間の短縮を狙う各地の自動車メーカー、さらにはIT業界など他業種の企業をも自陣営に引き込む。それによって今後、大きな成長が見込まれるEVやSDVの領域で、業界全体の進化をリードし、その中核部分で利益を得るという壮大な構想である。
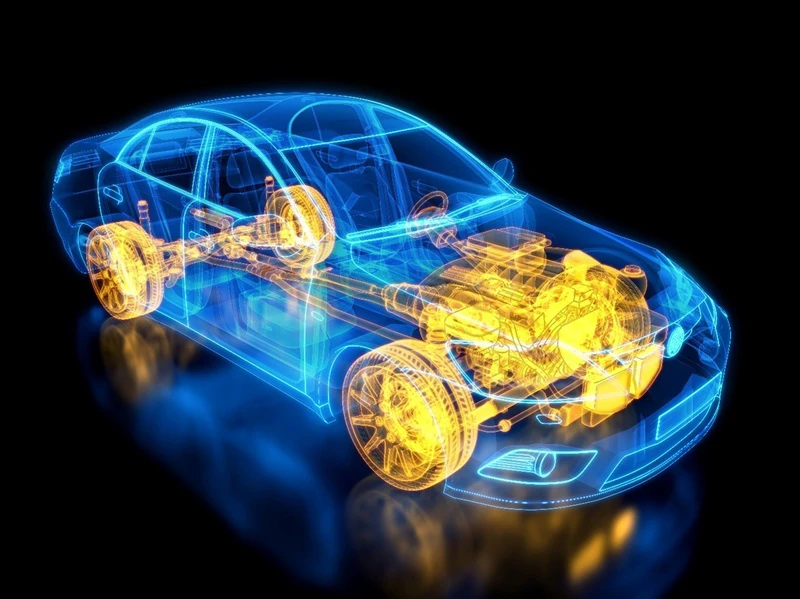
もちろんこれはそのような「目論見」の話であって、実現するかどうかはわからない。しかし、この「オープン・プラットフォーム戦略」はすでに具体的な成果を生み始めている。
Googleのロボタクシーがプラットフォームに参画
象徴的な事例が、Google傘下で、自動運転技術で世界をリードする存在の「Waymo(ウェイモ)」との提携だ。Waymoは自社の自動運転システムを搭載する次世代ロボタクシーの専用車両として、SEAをベースに特別に設計された「SEA-M」アーキテクチャを採用した。
ジーリーグループの「Zeekr」と共同開発したタクシー専用ミニバン「Zeekr RT」は、今年1月の「CES」で量産モデルがお目見え。ハンドルやペダルを省き、広い室内空間を確保。Waymoの第6世代センサー群(LiDAR、カメラ、超音波レーダー)を最初から搭載の上で量産されると発表されている。自動運転の領域では、中国のIT大手Baidu(百度)もジーリーと合弁企業を設立。Baiduの自動運転システム「Apollo」をSEAと融合させた車両開発を進めている。
またメルセデス・ベンツとジーリーの合弁企業「スマート・オートモービル」が生産するマイクロカー「smart」は、SEAを基盤に開発されている。「smart」ブランドは全モデルが完全電動化される計画で、そこではこのプラットフォームが全面的に活用されることになる。
その他、グループ内の「Zeekr」「Volvo(EX30, EM90)」「Polestar」「Lynk & Co(Z10, Z20)」などもSEAを使用し、すでに世界各国で販売されている。グループ外でも、ポーランド政府が支援する「Electro Mobility Poland」のEVブランド「Izera」がSEAの採用を決定したと伝えられる。
これらの事例は、SEAが世界の先端レベルのニーズに適応可能なプラットフォームであり、ジーリーの戦略が世界的なプレーヤーを惹きつける力を持ち始めたことを示している。
ボルボの技術・文化と「Geely speed」の融合
2010年、経営危機に陥った米フォードからボルボを買収した当時のジーリーは、中国の低価格自動車メーカーの一社にすぎなかった。「格下」の中国企業に買収され、ボルボの将来を悲観する声が強かった。
しかしジーリーは、自らの立ち位置を冷静に理解し、李書福の強烈なリーダーシップの下、ボルボの技術やブランド力、企業文化を尊重し、真摯に学ぶ姿勢を貫いた。そして、急拡大を続けた中国のEV市場、豊富な開発人材、強力な生産力をそこに結びつけた。それがSDV時代に幅広く適用可能な新たなプラットフォームの開発に結実した。
そこにあったのは「謙虚に学ばなければ、世界で勝てない。世界で勝てなければ滅びる」という強い危機感だ。そして、自国の殻に閉じこもらないオープン性、多様性こそが競争力を生む。前述した研究機関のCEVTでは、「ボルボの体系的で品質を重視するアプローチと『Geely speed』が融合した独自のハイブリッドな研究開発文化が生まれた」とジーリーの公式ホームページは誇らしげに記している。
オープン性、多様性を重視し、自らの成長に貪欲に活用しようとしたジーリーの姿勢が、「欧米のDNAを持つ中国発の最先端技術」を世界に広める成果につながった。
「クルマのスマホ化」は本当に起きるか
ジーリーの「オープン・プラットフォーム戦略」は、国家間の政治的対立が世界経済の大きな障害となりつつある現在、中国の民間企業が成長するための強力なツールとなりうる。李書福が「オープンソース」をあえて強調したのも、そのあたりの思惑あってのことだろう。

他社にとって不可欠な技術基盤のサプライヤーとなることで、ジーリーは他企業のバリューチェーンに組み込まれる。深い相互依存関係と長期的なパートナーシップを形成することになる。より多くの相手を引き込むことで、技術開発はより加速し、プラットフォームの価値がより高まる「ネットワーク効果」を生み出す。それによってジーリーは他企業にとって競争相手からパートナーに変わり、いわば「EV産業のインフラ」へと格上げされる。
ビジネスとしての収益性と同時に、企業グループの世界的地位を大きく引き上げる可能性のある、非常に優れた戦略だと思う。ちなみに、ジーリーは2024年末時点で、実は販売台数の約60%が既存のエンジン車である。そのような旧来型の収益構造を持ちながら、かくも大胆な戦略実行に踏み込む。これはなかなかできることではない。
もちろんハードルは低くない。グローバルなプラットフォームになるために必須の条件は、ジーリーが「政治的に安心できる相手」であることだ。昨今の中国の政治状況を考えると、これは決して容易なことではない。ここが揺らげば、世界市場で信用は得られない。
ITの進化で、誰でも資金さえあれば、ジーリーにお願いするだけで自分ブランドの、世界最高スペックのクルマをあっという間に発売できる。そういう時代が来た。「クルマのスマホ化」は本当に起きるかもしれない。既存の自動車産業は大きく変わるだろう。「EVか、エンジン車か」といった議論の段階はとうに過ぎ去っている。

次世代中国



