

次世代中国 一歩先の大市場を読む
中国の「996 問題」とは?労働問題から見える遠ざかるチャイナドリーム
Text:田中 信彦

田中 信彦 氏
BHCC(Brighton Human Capital Consulting Co, Ltd. Beijing)パートナー。亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科(MBA)講師(非常勤)。前リクルート ワークス研究所客員研究員
1983年早稲田大学政治経済学部卒。新聞社を経て、90年代初頭から中国での人事マネジメント領域で執筆、コンサルティング活動に従事。(株)リクルート中国プロジェクト、ファーストリテイリング中国事業などに参画。上海と東京を拠点に大手企業等のコンサルタント、アドバイザーとして活躍している。近著に「スッキリ中国論 スジの日本、量の中国」(日経BP社)。
カリスマ経営者も「炎上」
中国でいま「996問題」が論議を呼んでいる。「996」とは「朝9時から夜9時まで、週に6日間働く」の意味で、つまり1日12時間労働、休みは週1日、日曜日だけという勤務状況を指す。この表現自体は2016年に生まれたものだが、今年3月、若いプログラマーたちがこの問題を告発する自主サイトを立ち上げ、一気に注目が集まった。
アリババグループの総帥、ジャック・マー(馬雲)や、中国のEコマース第2位の京東(JD)の創業者、劉強東らが、みずからの成功体験をもとに「若いうちはがむしゃらに仕事に打ち込むことも必要だ」といった趣旨の「996擁護論」を語るや、これらカリスマ経営者に若い世代の批判が殺到、いわゆる「炎上」状態となる前代未聞の事態が出現した。
このことは中国の若い世代から見た「成功の意味」が大きく変わったことを意味している。ジャック・マーらに代表される中国の「IT企業家第一世代」は、1990年代後半、事実上、白紙に近い状況だった中国IT領域で、まさに無人の野を駆け抜けて今の地位を築いた。そこにはむろんその時代固有の困難さや競争もあったが、市場の空白はあまりにも大きく、才覚と努力次第で成果はつかみ放題──という面があったのは事実だ。
ところが今の若い世代に、もはやそれはない。同じ戦法で戦えと言われても無理だ。無駄な討ち死にはしたくない──。1980年代、90年代以降生まれの世代にはそんな思いがある。今回の「996問題」の推移を見ていると、中国の「野蛮な成長」の時代は終わったのだと実感せざるを得ない。これからの中国は、まさに日本の社会がたどったように、安定成長の下、緩やかに「低欲望社会」に向かっていくだろう。今回はそんな話をしたい。
「996」は労働法違反
「996」という言い方が世に出たのは2016年10月、中国のある大手IT企業が「996工作制」と呼ぶ働き方を定めたのが最初とされる。当時の報道によれば、会社側は「毎年10月、11月の繁忙期に社員に心構えとして呼びかけたもので、強制でもなく、制度的なものでもない」と説明しているが、社員の強い反発を呼び、メディアでも批判的に報道された。
仮に「996」で1日12時間、週に6日働けば1週間の労働時間は72時間となる。中国労働法では「労働者の毎日の労働時間は八時間を超えてはならず、毎週の平均労働時間は四十四時間を超えてはならない」(訳は筆者、以下同)と規定されている。また残業については「残業時間は一般に一日一時間を超えてはならず、特殊な事情で残業する場合でも、労働者の健康を十分保障したうえで、一日三時間を超えてはならない。ただし毎月の残業時間は三十六時間を超えてはならない」とされている。
1日の法定労働時間は8時間、仮に12時間労働すれば4時間の残業、それだけで即、違法である。また同法では残業に対しては通常の給与の50%増しの賃金を支払うことと定められているが、IT技術者に関しては「フレキシブルな勤務体制」「成果に応じた報酬」という名目の下、割増賃金が支払われない例が少なくない。このような問題は以前から存在したが、「996問題」が社会的に特に大きな注目を集めることはなかった。
プログラマーたちが「996」を告発
状況が変わったのは今年3月のことだ。米国サンフランシスコに拠点を置く世界的なソフトウェア開発のプラットフォーム「Github(ギットハブ)」上に中国のプログラマーの有志が「996.ICU」と称するプロジェクトのページを開設。「ICU」とは病院の「集中治療室 Intensive Care Unit」の略で、「996の体制で勤務を続けた結果、病気になって集中治療室に運び込まれる」との意味を持たせている。現場のプログラマーたちから寄せられる情報をもとに、企業のブラックリストを実名で公表するなど、「反996」の活動を展開した。
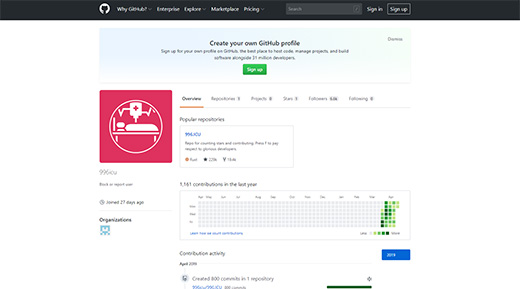
この告発ページは強い支持を集めた。プログラマーたちからは「現実には996なんてものじゃない。807、あるいは716だ」といった声が続々と寄せられた。「807」とは午前8時から午前零時まで働き、週7日労働、土日も休みなし」を意味し、「716」とは「午前7時出勤、深夜1時まで働いて、休みは日曜日だけ」の意味である。
動きを知った中国共産党中央機関紙「人民日報」が4月11日、「強制的な残業を企業文化にすべきではない」と題する論評を掲載。これをきっかけにその他メディアも続々と「996問題」を批判する記事を掲載、「996」は社会のホットなテーマに躍り出ることになった。


企業のブラックリスト、ホワイトリストを公開
「996.ICU」のページを見てみると、まずページ開設の目的や趣旨などが書いてある。「原則と目的」の項目には「これは政治運動ではないことをまず明らかにしておく。我々個人が労働法を固く遵守し、あわせて雇用主に従業員の合法的な権益を尊重するよう求めるものである。996.ICUは中国の多くのIT産業従事者が集まって(権益の尊重を)発起するものであり、IT領域以外、中国以外の人々の参加を歓迎する」と設立の趣旨がうたわれている。
それと並んで、プログラマーたちからの情報提供に基づく「996企業」のブラックリスト、さらにはホワイトリストに相当する「955企業」も共に実名で公表されている。「955」とは「午前9時から午後5時までの労働、週5日の勤務(週休二日)」を意味し、生活と仕事のバランスのとれた企業として称賛の対象になっている。
ブラックリストの中にはアリババグループ、検索No.1の百度(Baidu)、スマートフォンの華為(Huawei)や小米(Xiaomi)、Eコマースの京東(JD) 、アリペイを運営するアリババグループのアントフィナンシャル、WeChatを運営する騰迅(Tencent)といった中国を代表するIT企業の名前が並ぶ。一方、ホワイトリストにはGoogleやIBM、インテル、マイクロソフト、SAPといった外国企業の名前が目立つ。
ジャック・マーの発言が「炎上」
「996」の議論をさらに加熱したのがジャック・マーの発言だ。「人民日報」が評論を掲載した同じ日、ジャック・マーはアリババ社内の講話で「996で働けることは幸せなことだ。多くの企業や個人は、そんなことができる機会すらない。むしろ誇りに思うべきだ。若い時に996をやらなかったら、一体いつできるのか? 他人を上回る努力と時間の代償を払わなければ、どうして自分が望む成功を手にできるのか」などと語った。

さらに「アリババグループの使命は”世界から不可能な商売をなくす”ことにある。そのために我々は努力している」と強調したうえで、「使命の実現のためには代価を払わなくてはならない。この会社に入るなら1日12時間働くことを覚悟してほしい。1日8時間働きたい人、きれいなオフィス、食堂、名前の通った会社で満足を感じる人はいらない。もし自分が嫌な仕事なら8時間でも苦痛だろう。仕事を愛していれば12時間でも長く感じないはずだ」などと語り、「996擁護」の姿勢を見せた。
この内容が伝えられると、ネット上では「まったく経営者の論理だ」「企業に命を捧げることを幸福と思えというのか」「論理のすり替え。使命のために働くことと996はまったく別の話だ」「996を認めるなら、相応の賃金を払え」といった反発、批判が噴出。「ジャック・マーがこんなに叩かれるのは初めて見た」というコメントがつくほどの異例の状況が現出した。
弁明も逆効果、高まる批判
この騒ぎを受けて翌4月12日、ジャック・マーはSNS「Weibo(微博)」上のみずからのアカウントでコメントを発し、「どのような企業も996を従業員に強制すべきでないし、強制することはできない」と語り、批判に一定の配慮をする姿勢を見せた。しかしその一方で「996の弁護をする気はないが、奮闘して働く人には敬意を表する」「対価を払わなければリターンは得られない」などと述べ、引き続き「996的なもの」に対する肯定的な姿勢をにじませた。
しかしこの「弁明」はむしろ世論の反発を強め、批判的なコメントは増える一方。4月20日現在、4万を超えるコメントが寄せられているが、確認できる限り、そのほとんどが996に対する彼の姿勢を批判し、失望感を表明したものになっている。
こうした状況を受けてジャック・マーは4月14日、改めて長文のメッセージを発信、「喜んで996で働く人は誰もいない。人道的にも問題であり、不健康で、長く継続することはできない。法律にも違反している。996を通じて利益をあげようという企業は愚かであり、いくら高い賃金を払っても人材は逃げてしまう」などと語り、996を否定する姿勢を示さざるを得なくなった。


