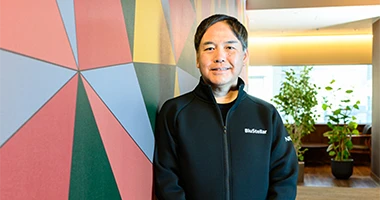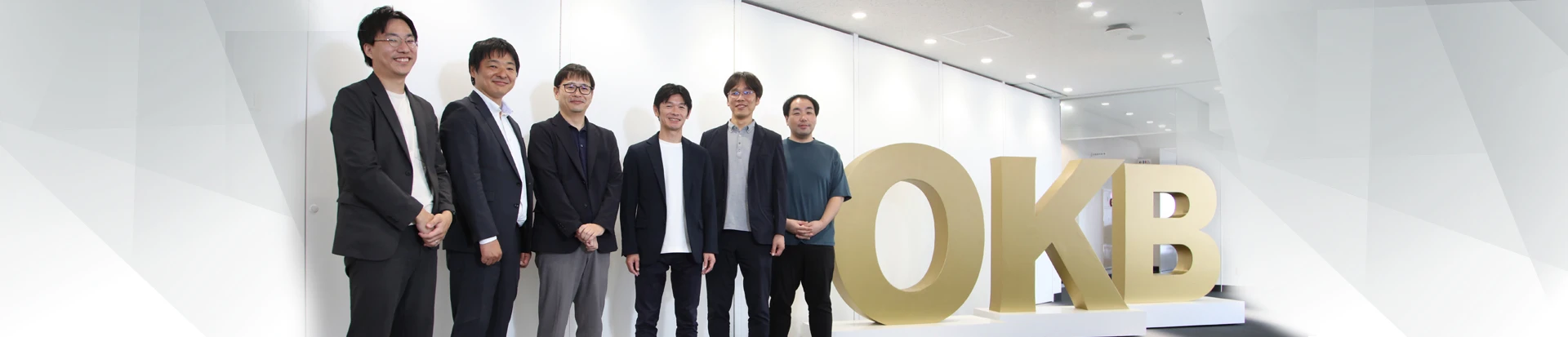
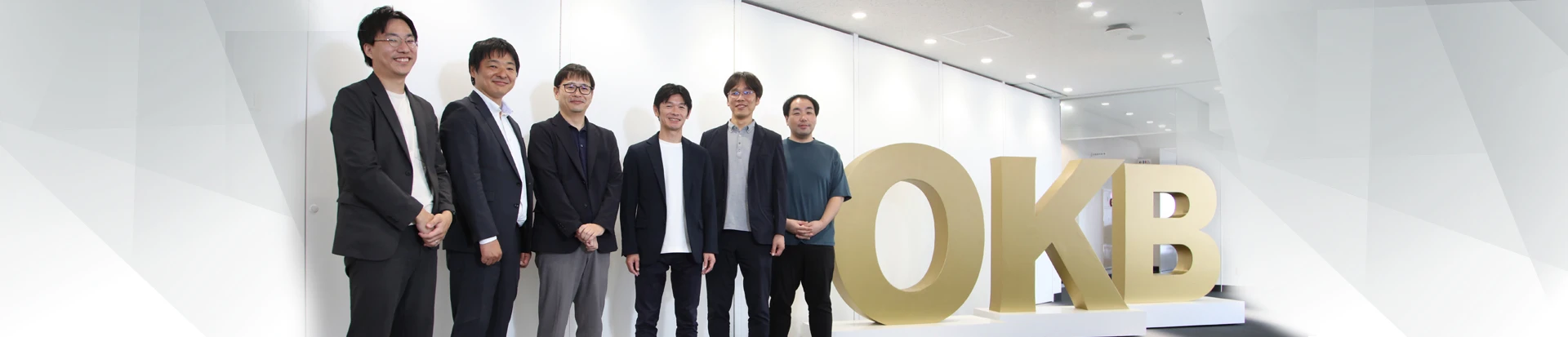
お客様を理解して、地域密着型金融を実践
変革を支える大垣共立銀行のデータドリブン経営とは
お客様に寄り添い最適な価値を届けるためには、データ活用が不可欠。しかし、データが複数のシステムや媒体に散在している状態では、その価値を十分に引き出すことが難しい。そこで大垣共立銀行は、蓄積した多様なデータを目的に応じて加工し、データ活用を支えるデータ活用基盤を構築した。構築においては数年後の活用状況を見据えたアーキテクチャを採用するなど、さまざまな工夫を行っている。この基盤のもと、同社は「顧客接点の変革」や「プロセス改革」に取り組み、これまで以上に地域社会の発展に貢献している。その取り組みは、同様にデータドリブン経営を推進したいと考えている企業にとって大いに参考になるはずだ。
顧客接点の変革、プロセス改革のためにはデータが不可欠
岐阜県大垣市に本店を構え、岐阜県と愛知県を中心に店舗網を展開している大垣共立銀行。「地域に愛され、親しまれ、信頼される銀行」という経営理念を掲げて「地域密着型金融」に取り組んでいる。
「当社は、全国で初めてATMの年中無休営業を開始したり、地銀で初めてインターネットバンキングを開始したりするなど、さまざまなチャレンジを行ってきました。ただし、変化や多様化がさらに進むお客様のニーズに応えるには、これまでのプロダクトアウト型の発想から、マーケットイン型の考え方や取り組みに転換していく必要があります」と同社の小坂井 智浩氏は言う。

デジタル統括部長
小坂井 智浩氏
例えば、法人に対しては、コンサルティング型の営業を通じて、お客様の事業の“川上”から深い関係を構築し、多様な経営課題にワンストップでの対応を計画している。また個人向けでは、お客様のライフスタイルを理解し、資産形成・資産運用の支援を行うだけでなく、シニア世代の健康な暮らしに貢献するなど、非金融分野におけるサービス拡充にも注力している。
このように同社の地域貢献は深い顧客理解が前提となっている。そのために欠かせないのがデータだ。実際、同社のDX戦略は、あらゆる接点でデータを利活用したパーソナライズなコミュニケーションを行う「顧客接点の変革」、データドリブンな意思決定を中心とする「プロセス改革」を柱に据えるなど、データが大きなカギを握っている。
データ活用の促進を阻む散在などの課題
しかし、これまで以上にデータを有効活用するには解決しなければならない課題があった。同社の既存の環境ではデータの価値を十分に引き出すことが難しかったのである。
「過去データは既に本番環境にはなく、場合によってはディスクではなく磁気テープに保存されているなど複数の場所に散在しており、データを活用するとなるとまずデータを集めることから始めなければなりませんでした」と同社の窪田 成臣氏が言う。

デジタル統括部 課長
窪田 成臣氏
過去データの中には、散在しているだけでなく、システムの更改を繰り返すなかで消失したものもある。これがビジネスにどのような影響を与えていたのかについて、同社の伊藤 啓氏は住宅ローンを例に次のように説明する。「住宅ローンは銀行の主力商品です。返済については、住宅ローン減税の適用期間が終了した後に繰り上げ返済をされるお客様が多いのですが、どれくらいで完済される方が多いのかを知りたくても、データが十分に残っておらず、傾向を正確に把握できませんでした」。
システムごとにデータの形式がバラバラという問題もあった。「例えば、顧客属性別リストを作成するシステムでは、異なるシステム間のデータの統合や活用の際に手作業で標準化やクレンジングを行わなければなりません。その加工に工数がかかっていました」と伊藤氏は続ける。
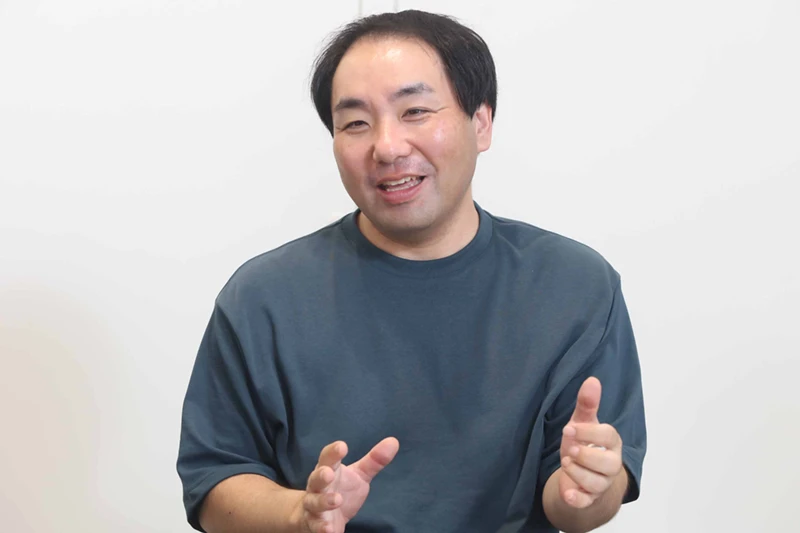
デジタル統括部 調査役
伊藤 啓氏
数年後のデータ活用を見据えたアーキテクチャ設計
データの散在や消失、形式の違いなどの課題を解決し、データ活用を促進するには、新しいデータ活用基盤が必要。そう考えた同社は、NECをパートナーに選定し、データ活用基盤プロジェクトを立ち上げた。ただし、NECは単にシステムインテグレーターとしてシステムを構築したのではない。「データ活用基盤コンサルティング」を通じて、データ活用基盤プロジェクトの上流からの支援を行った。
「さまざまなデータを1カ所に蓄積し、用途に合わせて加工する機能を持つ基盤が必要。そのことはわかっても、それをどのような仕組みで実現するか、私たちだけで判断するのはリスクが高いと考えました。場合によっては、トレンドに惑わされて、回り道をしてしまうかもしれません。NECは、当社のやりたいことやシステム環境の制約などを理解した上で、最適なデータ活用基盤を共に考えることを提案してくれました。特定の製品の導入を前提とする提案を行うほかのベンダーとは、スタンスが全く異なりました」と同社の粟野 修司氏は話します。

デジタル統括部 調査役
粟野 修司氏
NECは、さまざまなお客様における導入支援の経験を通じ、データ活用基盤に求める要件は企業ごとに大きく異なることを体感してきた。また、NEC自身もクライアントゼロ(※1)としてデータマネジメントの高度化に取り組み、その一環としてOne Data Platformという全社的なデータ活用基盤を構築。その過程でさまざまな試行錯誤をし、壁を乗り越えてきた経験を持つ。データドリブン経営の伴走支援やデータ活用基盤コンサルティングには、その豊富な経験を通じて得た知見が反映されている。
「お客様は、現状どのようなシステムを利用しているか。その中でデータがどのように連携・蓄積されているか。また、データを活用して短期、もしくは中長期で何を実現したいのか。そのユースケースはどこまで具体化されているのかなど、システム環境の制約やデータ活用の目的、進捗といったお客様ごとの事情を理解した上でお客様にとって最適なアーキテクチャを共に策定し、データ活用基盤の構築を支援します」とNECの福山 雄斗は話す。

第四金融ソリューション統括部 ソリューション推進グループ プロフェッショナル
福山 雄斗
例えば、今回大垣共立銀行のデータ活用基盤においては、クラウドとオンプレミス、どちらで構築するかが設計のポイントとなった。
「データレイクやDWH(Data Warehouse)、ETL(Extract/Transform/Load)など、データ活用基盤を構成するシステムには、豊富かつ魅力的な機能を持つクラウドサービスが多数登場しています。ぜひ利用してみたいと考えるお客様は多いのですが、クラウドサービスは運用の容易さや拡張性といったメリットがある一方、データ量や処理量、ユーザ数によってコストが増減するため、どのように利用するか、数年後の利用状況も見据えた見極めが必要です。そこで大垣共立銀行様に向けて、各製品・サービスの特徴や分類分け、機能や課金体系などを整理して有力な候補を示すと同時に、データ量やユーザ数の変化を想定するための活用ロードマップも提示しながら、6パターンのシステム構成を提案しました」とNECの川畠 輝聖は言う。

データ基盤サービス統括部 データドリブン事業グループ シニアマネージャー
川畠 輝聖
このような考え方のもとで議論を重ね、NECと共に構築した大垣共立銀行のデータ活用基盤は、オンプレミス、クラウドのどちらかに絞るのではなく、その両方を適材適所に組み合わせたハイブリッドな構成となっている。
「過去データも取り込んだり、対象システムを追加したり、これからデータ量が増えていくことを考慮して、データレイクと多くのユーザが利用するDWHはオンプレミスに置いています。一方、データサイエンティストなどの限られたユーザが利用するDWHは、拡張性より高度な機能などを優先してクラウドサービスを採用しました。またETLについては、既存資産も有効活用しつつ、ハイブリッド構成に合わせた複数の製品を使い分けています」と粟野氏は説明する。
現場を動かすことが次のテーマ。それを継続的な支援に期待
同社は新たに構築したデータ活用基盤のもとデータ活用の促進を図っていく。「例えば、さまざまな情報を一目で把握できるダッシュボードを実現して、データドリブンで意思決定を行う文化を醸成。そうすれば会議の度にデータを集計して資料を作成する工数も削減できます」と窪田氏は述べる。
データサイエンティストを中心としたAI活用にも期待している。「データの準備にかかる工数を削減し、AI活用に挑戦しやすい環境が整いました。AIによる予測結果などを実際の業務に落とし込むには、さらなるシステムインテグレーションが必要ですが、当社のデータ活用基盤を熟知し、AIにも精通しているNECの支援に期待しています」と伊藤氏は言う。もちろんNECは、その期待に応える構えだ。「AI やガバナンス、セキュリティなど、データ活用の幅が広がると課題も複雑になります。継続的な支援を通じて、共に課題を解決していきます」と川畠は話す。
このように積極的にデータ活用に取り組んでいける環境を整えた同社が次のテーマに見据えているのが「現場」である。小坂井氏たちが所属するデジタル統括部は、従来、同社のIT分野を担っていたIT統轄部とシステム部を統合して新たに設置したDX専門組織だが、部内には実行力を高めるために現場との連携を強化する「DXセンター」が併設されている。「どのように現場を動かすかは、これからの重要テーマの1つ。NECには現場主導のDXを支える提案を期待しています」と小坂井氏は言う。
その思いはNECも共有している。「『使える基盤』を『使いこなせる環境』へと進化させることが次に求められる支援だと考えています。現場の職員様が自律的にデータを活用できるよう、データカタログなどの仕組みを提案していきます」と福山は言う。
今後もNECは大垣共立銀行のDXに伴走し、価値創造モデルBluStellar(ブルーステラ※2)を基軸とする支援で同社の変革に貢献していく考えだ。
- ※1 クライアントゼロ:NEC自身をゼロ番目のクライアントとして最先端のテクノロジーを実践する取り組み
-
※2

「BluStellar(ブルーステラ)」は実績に裏打ちされた業種横断の先進的な知見と長年の開発・運用で研ぎ澄まされた NEC の最先端テクノロジーにより、ビジネスモデルの変革を実現し、社会課題とお客さまの経営課題を解決に導き、お客さまを未来へ導く価値創造モデルです。
https://jpn.nec.com/dx/index.html