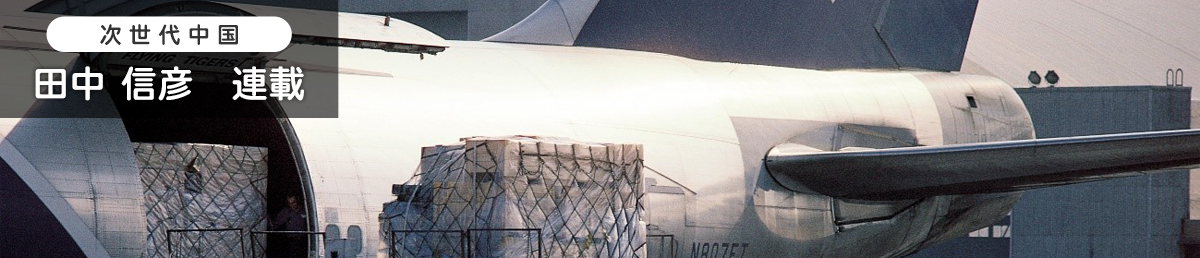
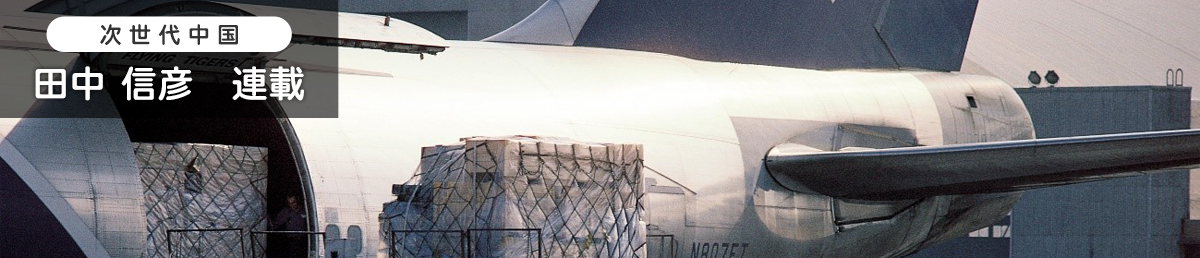
次世代中国 一歩先の大市場を読む
世界市場を席巻する中国発、越境EC
TemuやSHEINはなぜ急成長したのか
Text:田中 信彦
中国の工場から世界中の消費者に商品をダイレクトに届ける越境ECが急拡大している。日本でもTemuやSHEIN、AliExpressなどの存在感が急速に高まっている。
その最も直接的な理由は、「フルホスティングモデル」(Full Hosting Model、全託管服務)と呼ばれる新たなビジネスモデルの登場だ。これは旧来の「ネット上の店舗貸し」とは異なり、メーカーがEC企業に製品を納入しさえすれば、広告宣伝から物流、販売、はては苦情処理まで、すべてEC企業が引き受け、世界中で売ってくれるという方式である。
これによって中国国内の製造業者は、従来に比べて圧倒的に低い価格、短納期で世界中の消費者に商品を販売できるようになった。国内消費が低迷する中、中国のあらゆる業種のメーカーがこの新モデルに活路を見出そうとしている。
越境ECには、著作権侵害や過酷な労働環境、「造りすぎ」による資源浪費など、さまざまな問題が指摘されている。日本をはじめ、世界各国の製造業、小売業に与える影響も大きい。しかし、生産と物流、販売を一直線に極限まで効率化するそのパワーは強力で、現実に消費者の支持は強い。存在感はますます大きくなるだろう。
今回はこのモデルの持つ意味について考えてみた。

田中 信彦 氏
ブライトンヒューマン(BRH)パートナー。亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科(MBA)講師(非常勤)。前リクルート ワークス研究所客員研究員
1983年早稲田大学政治経済学部卒。新聞社を経て、90年代初頭から中国での人事マネジメント領域で執筆、コンサルティング活動に従事。(株)リクルート中国プロジェクト、ファーストリテイリング中国事業などに参画。上海と東京を拠点に大手企業等のコンサルタント、アドバイザーとして活躍している。近著に「スッキリ中国論 スジの日本、量の中国」(日経BP社)。
中国越境EC「四小龍」
中国には越境ECの「出海四小龍」(以下、「四小龍」という)という言い方がある。
中国EC最大手のピンドゥオドゥオ(拼多多)が手がけるTemu(“Tee-moo”と発音する)、アリババグループのAliExpress(全球速賣通)、女性ファッションが主力のSHEIN(希音)、ティックトックのEC部門であるTik Tok Shop――の4つだ。このうちTik Tok Shopは日本での営業はしていないが、他の3つは日本で買い物ができる。

越境ECそのものは以前からあった。AliExpressとSHEIN(当時のブランド名は「SheInside」)が本格的に海外販売を始めたのは共に2010年のことだ。2017~18年頃からSHEINが米国で本格的にブレイクし、「中国から直送」型の越境ECが注目を集めるようになった。SHEINのユニークさは、wisdomの「中国発EC『Shein(シーイン)』は『究極のビジネスか』? 『売れる商品』を特定し、速く、安くつくる仕組み」(2022年8月)で書いたので、ご参照いただきたい。
SHEINは女性衣料を中心にスタートしたが、昨今の越境EC勢の急成長は、「SHEIN的なやり方」が中国全土あらゆる業種、さまざまな商品に拡大したものとみることもできる。
Temuのユーザー数はAmazonに次ぐ世界2位に
2022年9月、ピンドゥオドゥオが、米国で越境ECのTemuをスタート。2023年7月には日本でも事業を始めた。
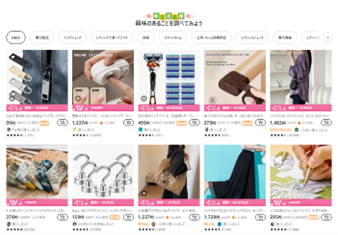
 )
)後発のTemuは苦しいのではとの見方もあったが、圧倒的な低価格を武器にまたたく間に世界市場を席巻。2023年末時点で北米、日本および東アジア、欧州、東南アジア、中東、アフリカなど47の国や地域で、登録ユーザー数は4億6700万人に達し、越境ECでAmazon(約23億人)に次ぐ世界2位に躍り出た。2023年のGMV(流通取引総額)は140億米ドルで、2024年には2倍以上の300億ドルに達すると見込まれている。
日本でもTemuは、日本経済新聞が「利用者が1月に1500万人を超えた。日本参入から約半年で、先行する大手3社平均の5割超に達した」(2024年2月19日付)と伝えており、その好調ぶりがうかがえる。
連日、100機以上のエアカーゴが世界に
その他の「四小龍」も絶好調だ。
越境EC世界の老舗ともいうべきAliexpressは、やはり4億人以上のユーザーを有し、2023年のGMVが285億米ドル、対前年比44%増、過去6四半期連続で市場予測を上回った。SHEINは業績を公開していないが、中国メディアの報道によれば、2023年のユーザー数は2億5000万人、GMV は300億米ドルに達した。Tik Tok Shopも2024年のGMVは対前年比約2.2倍、500億米ドルになると見込んでいる。
統計によると、現在、「四小龍」は中国から毎日、約1万㌧の航空貨物を全世界に向けて発送している。内訳はSHEINが5000㌧、Temu 4000㌧、AliExpressとTik Tok Shopで約1000㌧(新華社、2024年2月29日付)。この数字は大型貨物機、ボーイング777機換算で108機分の荷物が連日、中国から世界各国に飛び立っている計算だ。

「四小龍」のアプリを見ると、とにかく驚くほど安い。生産国から直接空輸するので配送にはやや時間がかかるが、送料無料の商品も多い。購入者のコメントを見ると、まさに世界中の人たちが買っている。もしまだ見たことがなければ一度覗いてみることをお勧めする。みるからに怪しげな商品もあるが、こういうビジネスモデルが世界で多くの消費者の支持を集め、急拡大している現実を知っておくのは意味がある。
越境ECを変えた「フルホスティング」
ではなぜここ1~2年、「四小龍」がここまで急速に世界市場で拡大しているのか。その背景には「フルホスティング」と呼ばれる新たなビジネスモデルの登場がある。この仕組みが越境ECの概念を大きく変えた。
フルホスティングとは、越境ECのプラットフォーム(ここで言う「四小龍」の側)が、生産工程以外のすべてのプロセスをホストし、商品を消費者に届けるモデルである。メーカーは商品を製造し、あらかじめ決めた数量を中国国内の指定の倉庫に納入するだけでよい。あとはすべてプラットフォームがやってくれる。
プラットフォームは、自社のアプリやサイトに商品を掲載し、広告宣伝をして、お客からの質問などに対応し、注文があれば迅速に発送する。商品を届け、必要な場合は組み立て、苦情があればその対応まで受け持つ。つまり、工場の側から見れば、「生産以外のすべての業務を代行してくれるグローバル直販」のシステムであり、プラットフォーム側から見れば、あたかも自分たちのプライベートブランド商品を、工場に委託して生産し、世界中で販売しているのと実質的に同じことになる。
越境ECそのものが「製造業化」の方向に進んでいるといえる。
「店舗貸し」から一気通貫の「製造小売業」へ
このモデルを他社に先駆けて始めたのがTemuだ。Temuは2022年秋、事業開始と同時にフルホスティングの実現に動いた。大きく先行するAmazonを追撃するには、異なる発想で、違う優位性を持たねばならない。
そのカギは価格とデリバリーにある。可能な限り商品を安く、しかも速く、大量に消費者の手に届けるために中間のプロセスを極限まで効率化する。製造以外、すべての工程を自分たちでやる。先に展開していたSHEINの、中国の工場から世界各地の消費者に商品を直送する仕組みは、衣料品以外の商品でも成り立ちうる。もちろん社外のリソースは活用するが、それを管理し、責任を持つのは自社である。

つまりEC企業とはいうものの、「商売の仲介者」ではすでになく、実質的には、あらゆる商品を世界中で販売する「製造小売業」化したといえる。サプライチェーンがほぼ完全に統合され、商品が生産者からダイレクトに消費者に届く。全世界をカバーする「巨大製造販売システム」の誕生である。フルホスティングの最大の変革はここにある。
新たなモデルの大成功を見て、Aliexpressなど他の越境ECも、それぞれやり方は異なるが、同様の発想で追随、一気に越境ECの概念が大きく変わった。Amazonも販売手数料の大幅引き下げなど対抗措置に動かざるを得なくなった。従来型の「店舗貸し」スタイルの越境ECは価格競争力を急速に失いつつあり、よほど特徴のある商品か、強いブランド力がある場合を除き、生き残りはますます難しくなっている。
生産地のメーカーに大きなメリット
フルホスティングのモデルは、「世界の工場」を支える無数の中国メーカーにとっては、不振が深刻な国内市場から、小企業でも世界市場に乗り出せる魅力的な仕組みだ。
中国の国内市場は大きいが、世界市場はさらに大きい。しかし、人材や資金に乏しい中小メーカーの販売力は乏しく、生産さえすれば全世界に売れる魅力は大きい。
これまでも自社のサイトなどで越境ECに取り組む企業はあった。Amazonで販売する手もある。しかし、いずれも広告宣伝や物流や顧客対応など自社で行なう作業は大きく、コストもかかる。外国語の問題もある。フルホスティングなら、それらがクリアできる。
プラットフォームは世界中の消費者と直結しているので、情報が早く、売れ筋の特定がしやすい。マーケティングや広告宣伝も強力だ。いったん火がつくと、大きなヒットにつながる可能性がある。プラットフォーム企業と一体となって製品の改良に取り組めば、世界最高クラスのコストパフォーマンスを持つメーカーに進化できる可能性がある。
自社ブランドの構築はできない
一方、デメリットもある。最も大きいのは自社ブランドの確立がしにくいことである。プラットフォームは量を売る力はあるし、生産者の相対的なリスクは低いが、反面、メーカーは生産して納品するだけなので、自社のブランドが認知されにくい。これをどう考えるかは、メーカーの経営者の判断ということになる。
また、プラットフォームに依存したビジネスだけに、メーカーは値下げ要求を拒否しにくい。他に競合メーカーがあれば、取引条件は切り下がってしまう。メーカーにとっては、営業や顧客対応などの必要がなく、生産に特化できるぶん、新たな商品や技術の開発などで、より魅力的な商品を生み出せるかがカギになる。
またプラットフォームからの納品要求に応えるために、メーカーは常に一定の在庫を確保しておかねばならない。そのためのコストがかかるという問題もある。
中国のEC大手が、こぞって「越境」に走る理由
中国の大手EC企業が今、なぜ一気に世界市場に「越境」しているのか。そこには巨大な中国国内市場で大きく成長した存在ならではの危機感がある。
最大のものは国内市場に漂う飽和感、停滞感だ。不動産、株式市況は低迷が続き、失業率も高止まりで、消費マインドは弱い。当面、国内市場に依存した成長は見込めそうにない。経営者の危機感は強い。
スケールメリットの追求も大きな狙いだ。高品質の商品をより低価格で提供するには1品目あたりの生産数量を最大化することが有効だ。中国で成長したECが国内に留まっている理由はない。世界市場に向けて押し出すのは時間の問題だったともいえる。

さらに言えば、国内市場で過去10数年、激しい競争を繰り広げてきた中国ECの蓄積したノウハウ、技術力は膨大だ。アプリの使いやすさ、支払いのスムーズさ、顧客対応の丁寧さ、デリバリーの速さなど、世界的にみてもその実力は群を抜いている。その優位性はむしろ海外のほうが活かしやすい。
「政治的」な危機感
加えて、中国国内の政治的な雰囲気の変化も、企業家の心理に微妙な影響を与えている。典型的な例がアリババグループだ。
昨年、同グループの会長に就任した蔡崇信氏は、先頃メディアのインタビューに答え「アリババは電子商取引(EC)とクラウドを中核業務とする企業に立ち戻る」という趣旨の発言をした。ここ数年、創業者のジャック・マー(馬雲)と政府の関係が微妙なものになり、アリババから派生し、Alipay(支付宝)を中核に金融事業を展開してきたアントグループには2023年7月、約1400億円の罰金が課された。株価は大きく下落し、アリババの経営は転換点にある。
そのアリババが中核事業をECとクラウドに求めたのは暗示的だ。ECの成長領域は越境取引しかない。クラウドはいわば「雲の上」の話だ。いずれも国境の概念に縛られにくい、「国家」と距離感のあるビジネスである。金融という、いわば国の本丸に近いところで政治の壁にぶち当たったアリババが、越境ECに成長の可能性を求めるあたりに現在の中国の状況が透けてみえる。
他の3社にしても、中国発祥の企業ではあるが、ECという業態は国家の枠に縛られることにメリットはない。グローバルに手広く商売したほうが得策だ。米中の政治的対立で国境の壁が高くなりつつある昨今、早いうちに海外展開して既成事実をつくっておきたい意向が働いている。
実際、Temuの運営会社の法人登記地はアイルランドのダブリンに移されており、親会社のピンドゥオドゥオとの切り離しが進んでいると中国メディアは伝える。SHEINの登記地もシンガポールで、創業者兼CEOの許仰天氏はシンガポールの市民権を取得したと報道されている。越境ECの「脱中国化」は今後も進むだろう。
TikTok Shopはインドネシアで停止に
こうした新しいタイプの越境ECは、各国の製造業、小売業に大きな影響を与えている。
2023年9月、インドネシア政府はSNS上での商品売買の規則を改定、TikTok Shopは同国での営業を停止せざるをえなくなった。新規則によれば、SNS上で商品の宣伝はできるが、販売は禁止。また国外からの一部輸入品に最低取引価格を設定、該当する商品は100米ドルを超えるものしかECでは購入できなくなった。
これは圧倒的な商品力を持つTikTok Shopに対し、国内の小売業者が衰退するとの反発が強まり、政府が対応に動いたものだ。これに対しTikTokは同年12月、同国内の大手ECサイトを買収、事業を統合し、追加で10億米ドルを超える投資も行うことで同国政府の了解を得て、再開にこぎつけた。
世界市場を直撃する「超・中国価格」
越境ECの商品の多くは、生産地から直接、航空便で個々の消費者に送られる。そのため消費国にはビジネス面での恩恵はほとんどない。仮に日常的に繰り返し購入される商品が海外生産地からのダイレクトな販売に切り替わってしまえば、各国のメーカーや小売業に甚大な影響がある。インドネシアでのTikTok Shopの一時停止は、そうした懸念から起きたものだ。
しかしながら、現実に安くて一定の質が伴った商品が消費者の前に現れれば、それを選択するのは止めようがない。そういう状況がいま世界中で起きている。

現状の越境ECには知的所有権の侵害、生産現場で過酷な労働が強制されていないか、大量の商品の造りすぎによる資源浪費の懸念など、さまざまな問題がある。これらに対する監視は世界各国が協調して、強化していかねばならない。
しかし、これまでのアパレル業界の動きを見る限り、これら諸問題に対する中国企業の現場での取り組みは着実に強化されており、状況は改善している。世界中の消費者サイドがしっかりと監視し、要求を続ければ越境ECでも状況は改善していく可能性が高い。
越境ECの破壊力
現状、日本国内では消費者の間に越境ECの商品に対する一定の警戒感はあるが、若い世代を中心にそうした抵抗心理は急速に薄れている。フルホスティングのモデルが今後より定着、進化することで、サービス体制は急速に高度化されていくだろう。
そうなれば、もともと価格競争力の強い中国の商品に、さらに強力なスケールメリットが加わり、よりコストパフォーマンスの高まった「超・中国価格」の商品が世界市場を直撃する可能性がある。国内の製造業や小売業を守るための何らかの対策を求める声は強まるだろう。
国家間の政治的対立はありつつも、現実には世界経済の一体化は確実に進んでいる。中国の越境ECが向かう製造小売業化の流れは、世界のあらゆる国の産業構造を根底から揺るがす破壊力を秘めている。

次世代中国



