

”自己理解”が学びと挑戦の本質──安心して「葛藤できる」場の重要性
~NEC未来創造会議 2019年度第4回有識者会議レポート~
シンギュラリティ以後の2050年を見据え、目指すべき未来像を構想するプロジェクト「NEC未来創造会議」。2017年度にNECが開始したこのプロジェクトでは、毎年さまざまな領域から国内外の有識者を招聘し会議を行なってきた。昨年度は世界に蔓延する分断を解消する未来像として「意志共鳴型社会」を提唱、今年度は議論を続けながらも社会実装にむけ幅広いステークホルダーとの共創活動にも積極的に取り組んでいる。
全4回にわたって行なわれた今年度の有識者会議では、これまで以上に議論を具体化すべく各回のテーマを設定。「RELATIONSHIP」「EXPERIENCE」「VALUE&TRUST」 「LEARNING/UNLEARNING」という4つのテーマに沿って毎回異なった有識者を招き、会議を行なってきた。
第4回有識者会議のテーマは「LEARNING/UNLEARNING」。美学を専門にする学者でありながら障害を捉えなおし新たな身体論を立ち上げる伊藤亜沙氏、昨年度の有識者会議にも参加してきた文化人類学者の松村圭一郎氏、NECフェローの江村克己、そしてこれまでと同じく『WIRED』日本版編集長の松島倫明氏がモデレーターを務めた。今年度最後のテーマで行なわれる有識者会議は、果たしてどこに向かっていくのだろうか。
「学び」は受動と能動を繰り返すこと
今年度の有識者会議は、「RELATIONSHIP」「EXPERIENCE」「VALUE&TRUST」「LEARNING/UNLEARNING」の4つをテーマとしながら、意志共鳴型社会の実装にむけ、人の意識に焦点を当てながら一貫した問題意識をもって議論をつづけてきた。コミュニティ、VR(仮想現実)、宗教など議論はさまざまな領域に及んでいったが、注目すべきは「身体性」や「固有性」が共通したキーワードとなっていたことだろう。
デジタルテクノロジーが新たな体験を生み生活の利便性やビジネスの効率性を上げていく一方で、身体性のように容易にはデジタル化できないものの価値が見過ごされているのも事実だ。だからこそ「LEARNING/UNLEARNING〜2050年に向けた“学び“と”挑戦”〜」と題した第4回の会議では、身体性を議論の軸としながら新たな「学び」の可能性を探るべく議論は進んでいった。
今回設定された問いは「身体性に根ざした個や社会の固有性とは何か?」と「デジタルテクノロジーは他者をいかにデータではなく固有性をもつ個人や社会として捉えることを可能にするか?」のふたつ。まず議論はこれまでの会議を振り返ることから始まった。

美学を専門としながらも、吃音など障害の研究から新たな身体論を立ち上げ近年広く注目されている。著書に『どもる身体』など
長年NECのテクノロジーを牽引してきた江村は、これまでの議論を通じてむしろテクノロジーやデジタルとは異なる方向から議論を始める必要があると感じたという。江村の発言を受け、伊藤氏も「デジタル化とは人間が恣意的な基準によって世界を操作可能にする作業ですよね」と語る。
自身の研究を通じて身体のもつ記憶やローカリティについて書いてきた伊藤氏は「身体には抽象化できない固有な部分がある」と続ける。「病気や事故など身体には絶えず偶然に与えられるものがあり、それを本人が引き受けて必然化していくことが人生だといえるでしょう。とくに障害をもたれている方は身体の固有性がもつ求心力が強いなと感じます」
他方で松村氏は伊藤氏が研究した吃音を例に挙げながら、身体性から始まる「つながり」について語る。
「吃音はその人の身体が反応しているというより状況や相手次第で出る場合と出ない場合がありますよね。つまりわたしの身体はわたしだけで完結しているわけではなく、外側の世界と連動している。それは自分と相手との固有性が溶けてしまうような関係です。人と人とのつながりには、そんな固有性の輪郭が曖昧になるつながり方と、互いの固有性を固定するつながり方があるのだと思います」
伊藤氏や松村氏が語る身体の豊かさは、テクノロジーによる効率化や抽象化によって切り捨てられてしまうことも少なくない。しかし、伊藤氏は「自分ではコントロールできないものに対する畏れをテクノロジーと結びつけていくことが重要です」と語る。余剰を切り捨てて社会や生活の利便性を高めることは、同時に想定外の物事に対する想像力を奪ってもいるのかもしれない。
「想定外のことが起きるからこそ、学びが生じるわけです。最近よく学びは受動的ではダメだと言われますが、受動的な学びの先に能動的な学びがあって、その先にもう一度受動的な学びがある。身体も事故や病気など想定外のことを引き受けることで再発見されていくのですから」
そう伊藤氏が語ると、松村氏も「学びは“できない自分”から駆動されていきますよね」とうなずき、次のように語った。「学びとは知識を獲得して蓄積していくようなアクティブラーニングではなくて、自分のできなさを引き受けること。つねにUNLEARNINGがあるからこそLEARNINGが可能となるはずです」

エチオピアの農村や中東の都市でのフィールドワークを重ね、富の所有と分配について研究を行なう。著書『うしろめたさの人類学』で毎日出版文化賞特別賞受賞
”異質”なものとの出合いが共鳴を生む
松村氏が語った固有性が溶けてしまう関係とは、過去の会議でたびたび論じられてきた「共感」と「共鳴」の差異とも深く結びついている。インターネットのような空間においては、「わたし」に揺さぶりをかける関係が生まれづらいのではと松村氏は語った。
「SNS上の“いいね”は、わたしという輪郭を再確認し強固にする作業ですよね。それが『共感』なのかもしれません。一方で、たとえばエチオピアのような生活環境がまったく異なっている国に行ってから日本に帰ると、それまであたりまえだと思っていた光景に違和感を覚えることがあります。他者との交流をとおしてわたし自身もいつの間にか変化している。それがわたしの輪郭が溶ける『共鳴』なのかもしれませんね」
江村も松村氏の発言を聞いてうなずき、「異質なものと出合ったときに初めて共鳴が起きるのだなと。共鳴は共感の対極にありますね」と語る。では、共鳴が起きて人が変わるとき、そこでは何が起きているのだろうか? ここで伊藤氏は、自身が「最強の共鳴」を経験したことがあると明かす。

「最強の共鳴」を生みだしたのは、目の見えない人が見える人と一緒にマラソンに取り組むクラブだという。目の見えない人が走るときには、目の見えない人と見える人がロープで手をつなぎ、腕の振りをシンクロさせながら走っている。この仕組みは一見シンプルすぎるように思えるが、じつは膨大な量の情報がロープによって伝えられるのだと伊藤氏は語った。
「本当に熟練したペアだと、ちょっとした情動の変化でさえ、ロープを通して伝わってくるそうです。人が意識化・言語化するまえの身体的な情動としかいえないようなもの。しかも、自分の思いが相手に伝わって、それがまた自分へと返ってくる。1+1=2ではなくて、自分の輪郭のなかに相手も含まれていくというか、相手の身体のことも感じながら走っていくわけです。その感覚をみんな『共鳴』という言葉で表現されていて。ロープがまるで神経線維のようになってすべてが伝わってくるのだと仰っていましたね」
この体験を経て、伊藤氏は「コミュニケーション」を再考する必要があることに気づかされる。しばしばコミュニケーションは情報の発信者が伝えたいメッセージを伝えるものと捉えられがちだが、その結果メッセージだけが流通し背後の文脈や身体的な状況が失われてしまうことも少なくない。メッセージだけが文脈を抜きに解釈されれば、炎上や分断が発生していく。
「そうではなくて、ロープ的な体験こそがコミュニケーションなのだなと感じました。ふたりで『走る』というひとつのできごとに取り組むように、できごとのなかでメッセージがつくられていく」
それを聞いた松島氏は「わたしがいてあなたがいるのではなく、その間にあるもののなかで受動性と能動性が混ざりあっていくわけですね」と応答する。「身体性に根ざした個や社会の固有性」を問うことで、むしろ確固たる個が揺らいでいく関係性や受動と能動が混ざりあう体験の豊かさが提示されたといえよう。
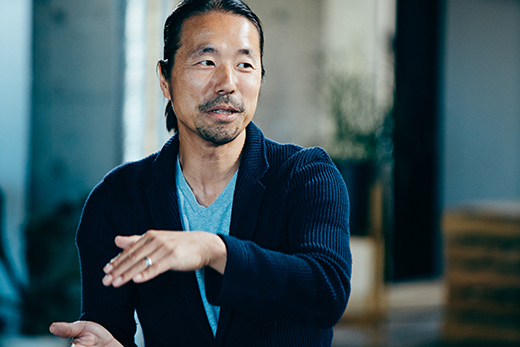
NHK出版で数々の話題書を手掛けたのち、2018年よりテックやビジネス、カルチャーを横断するメディア『WIRED』日本版編集長を務めている
答えを出さず、サポートする
ここまでの議論では、従来のテクノロジーが切り捨ててしまっていた身体性や固有性の価値に光が当てられていた。では、これからのテクノロジーはいかにその価値をエンパワーしていけるのだろうか。伊藤氏が語ったような身体のもつ「畏怖」は、どうすればテクノロジーによって回復できるのだろうか。伊藤氏は、まだ明確な答えはないとしつつも「人間がもつ身体的な知恵と外部のテクノロジーを等価に扱いたい」と語る。
「たとえば障害をもった方のなかには、自分の趣味から新たなスキルを生みだして障害に活用される方がいます。一人ひとりがいろいろな面をもっていて、何か問題が起きたらべつの面から知恵を引き出して適用できる。人間の身体がもつテクニックは非常に柔軟だけれど、テクノロジーは多くの人にとってブラックボックス化している。テクノロジーも同じくらい変形可能なものであるべきだと感じますね」
伊藤氏はそう語り、しばしばダイバーシティという言葉は集団のなかの多様性を指して使われるがむしろ「ひとりの人のなかのダイバーシティのほうが重要かもしれない」と続ける。同氏が自著で「多重身体」という概念を提示したように、人は誰しも複数の身体を生きているのだ。
伊藤氏の発言を受け「情報をたくさん与えることとは異なるテクノロジーの使い方を考えなければいけないですね」と江村も述べる。NECは限りなくリアルな体験を共有可能にする「エクスペリエンスネット」なるネットワークを構想していたが、これも単に体験を共有するのではなく「ロープ」が生んだような共鳴をつくれなければ意味はない。

1982年、光通信技術の研究者としてNECへ入社。以降、中央研究所長やCTOを経て現職
加えて、江村は「これからのテクノロジーはダイレクトに“答え”をつくるのではなく、人を“サポート”するものかもしれません」と続けた。テクノロジーそのものが問題を解決してしまうのではなく、人のなかにあるものを増幅してあげることで問題の解決へとつなげていくこと。一人ひとりのなかにある力を誘発することこそが、それぞれの身体性や固有性の価値を尊重することにつながっていくはずだ。
「伊藤さんの本を読むと、身体が非常に個別的で異なっていることに気づかされます」と松村氏は語り、一人ひとりの身体に合わせたテクノロジーの重要性を提唱する。「マスデータが一般的にはこうだからと指示してくるのではなくて、対話のなかで自分の特性に気づかされテクノロジーの動き方が変わっていくようなあり方が理想かもしれませんね」

「五感」と「文脈」をテクノロジーに実装せよ
会議が終盤に近づくにつれ、現在のテクノロジーの問題も明らかになっていった。なかでも松村氏はテクノロジーによるデータ活用から「文脈」が欠如してしまっていることを指摘する。
「データって文脈から取り出されてあちこちに適用できる情報として扱われますが、わたしたちは文脈のなかでしか生きていません。文脈のない生などありえないわけですよね」
江村も松村氏の発言を受けてうなずき、「最近はテクノロジーがなんでもレコメンドしてしまいますが、それは数値化できる情報だけ。五感に響かず、同時にほかの選択肢が失われている可能性もある気がします」と語る。松島氏も日々ウェアラブルツールで自身の身体データを計測していくなかで、データ化していくことの功罪を感じたことを明かす。
「毎日の体温や心拍数の違いを見ると自分の身体の多様性に驚かされるのですが、同時にデータによって縛られていく可能性も生まれている。自分がどこまで主体性をもっていけるか日々学んでいるといえるかもしれません」
伊藤氏も「文脈もふくめてきちんとデータ化できる方法を発明したいですね」と語るとおり、いかに文脈や体験テクノロジーによって再現するかはいまテクノロジーが問われていることでもあるだろう。松村氏は直接体験と間接体験という言葉を使い、自身が携わるフィールドワークの取り組みを振り返る。
「テクノロジーを通して実現できる体験は広がっていますが、本当にそれですべて代替できるのかという疑問はあります。わたしたちが“経験”しているとはどんなことなのかを理解しなければいけないでしょう。文化人類学のフィールドワークもいずれVR化するかもしれないけれど、直接体験できることとできないことの線引をどこでどう行なうかは難しい問いですね」

伊藤氏も障害や認知症をもつ人の体験を挙げ、「そもそもわたしたちもバーチャルに生きている部分がある」と語る。松島氏も「バーチャルとリアルの境界がひとりのなかでも混ざっているとすれば、テクノロジーが生み出すいわばバーチャルな体験も、ぼくらにとってはリアリティが何層にも重なっていくということでもあるかもしれませんね」と伊藤氏に応答する。
取りこぼされていた文脈を知ることの重要性は、意志共鳴型社会で重要な要素となる「紡がれた物語を知ること」とも直結している。いまわたしたちがテクノロジーで実現すべきことは、一見気づかない“五感”や“文脈”、そしてコントロールできない身体性、自分の判断できる余地をきちんと確保することなのだろう。
自己理解ができる、「失敗する」ためのセーフティネット
テクノロジーを更新していくために、何が必要なのか。伊藤氏は「内発性が重要だと思います」と語り、「多くの場合、人に触発されて自分のなかから湧き出てくる内発性がものすごく強いエネルギー源になりますよね」と述べた。それに応えるように「内発し、自己理解を行ない続けることが”学び”の本質であり、人がもつ本来の能力を十分に発揮することが大切なのだと思います」と江村も続ける。
その一方で、「ただ数字による評価や外部から与えられる指標は、内発性を殺してしまいがちですから。内発性は刺激されることで生じるので、安心して失敗できる環境が必要なのかもしれません」と伊藤氏は指摘する。
安心して失敗できる環境。松村氏は、自身が教育に携わるなかでも、それまでの考え方や価値観がいったん崩れてしまうような「葛藤」がなければ学びはありえないと指摘する。「失敗を恐れる学生が増えていると感じます。だからわたしがその呪縛からUNLEARNINGしてあげないといけないなと。一応安心は確保されていながらも偶然性に開かれ葛藤のなかから学びが生まれるような場をつくりたいなと思っています」
「安心」とは、これまでの有識者会議でも何度も言及されていた「セーフティネット」の構築にもつながっている。全4回の会議を通じ、たびたび話題へとなってきたこと自体が次代のセーフティネットの重要性を証明しているといえるだろう。新たな挑戦に向かうためには、自己理解にむけ知識を蓄えるLEARNINGのみを可能にするのではなく、UNLEARNINGを通じていったんそれを手放してLEARNINGへと再び立ち戻れる環境がなければいけない。2019年度の有識者会議は身体性とテクノロジーを止揚する場としてのセーフティネットという、新たな世界の土台を提示し、11月8日に行なわれる「C&Cユーザーフォーラム & iEXPO2019」NEC未来創造会議 特別講演というフィナーレへと向かっていった。







